
時代を見つめ、金沢の酒蔵の誇りと威信をかけた、当主たちの挑戦
金沢の町は遥かな霊峰・白山を南にして、グルリと東まで高い稜線に望んでいます。
その中でも、昔から金沢人に慣れ親しまれているのが医王山(いおうぜん)と呼ばれる 小高い山。標高は939m、ここを越えると、お隣りの越中富山に通じます。
そこはかつて、加賀国主・前田 利家の盟友だった悲運の武将・佐々 成政の領国でした。つまり、金沢人と越中人は、医王山の峠を越えて頻繁に往き来できたわけです。
例えば、和紙に塗った膏薬(こうやく)や反魂丹(はんごんたん)などで知られる「越中富山の薬売り」も、金沢まで八里(約32km)の道のりを、脚絆を結び直しつつ目指したことでしょう。当時の行商人たちの足運びは早く、片道5時間あれば到着できました。また、街道沿いの湯涌温泉には、のんびりと湯浴みして行く遊山客も多かったようです。
その越中富山側の玄関口は、「福光(ふくみつ)」と呼ばれています。
察する通り、「福光屋」の屋号は、この福光の地から名付けられました。
福光屋の原点となった酒蔵は寛永2年(1625)の創業ですが、その後、安永年間(1772~1780)に福光町から金沢へやって来た“塩屋 太助”が買い取っています。この人物が、現社長で十三代目の福光 松太郎 氏の御先祖です。
太助は金沢でまず質屋を始め、それを元手にして、小立野の石引(いしびき)にあった酒蔵を購入したと伝わっていますが、彼の生年は詳らかではありません。
そして享和三年(1803)頃、七代目・太助が“福光屋”を名乗っています。
株式会社福光屋の本社は、往時から変わらず石引の地に建っています。この地名は、文禄元年(1592)に前田 利家が嫡男・利長に金沢城を築かせた際、城の石積みに使う石を、町の東にある戸室山(とむろやま)の麓から掘り出し、ここを引いて通 ったことに由来しています。
その道は、今も福光屋の玄関先を通り、真っ直ぐに兼六園へと向かっています。
巨大な戸室石が延々と連なっていたかと思うと、胸が熱くなるのは筆者だけではないでしょう。



「加賀の菊酒」を天下の美酒と謳ったのは、誰よりも関白・豊臣 秀吉でした。刎頚の友である前田 利家への美辞麗句だったと言う諸氏もいますが、福光屋の建つ小立野の好環境を知れば、それは無粋な憶測と断言できます。
小立野地区は浅野川と犀川に挟まれた中洲のような土地で、現在も伏流水(地下水)が豊富です。兼六園に引き込まれている辰巳用水も、これと同じ水脈を源としています。
その昔、近隣の牛坂(うっさか/現在は、鶴間坂)には滾々と「旭用水」と呼ばれる清水が湧き出し、茶人たちが足繁く汲みに通っていたそうです。ちなみに、福光屋のかつての銘酒“旭鶴”は、この水で仕込まれていました。
今日でも、茶の湯には中硬水や軟水がすこぶるよろしいとされており、それは良質の酒造りにも最適な水です。
秀吉が京都・醍醐寺の花見で、“さすが、又佐衛門の国の酒よ!”と加賀の酒を褒めそやしたのは、酒好きの秀吉の本音であり、友の功名にさぞかし鼻を高くしたことでしょう。
そんな小立野の天恵水を授かった福光屋は、八代目・福光 太次良(たじろう)以後、酒蔵を増やし、蔵人や酒造道具も充実させ、明治初期の十代目・福光 太助の時には千石酒屋の身代を築き上げます。土蔵を備えた酒蔵の玄関には、銘酒「万歳」の大看板が掛っていました。
千石酒屋に達した理由は、小立野地区が山村への生活物資の流通拠点になったことにあります。
近郊の犀川村、湯涌村、浅川村の人々に供給する酒、味噌、醤油、干物、乾物から木炭や薪まで、さまざまな商店が小立野に軒を連ねるようになりました。すると、そこへ卸売りや、買い付け業者たちもあふれ始めました。掻き入れ時の正月ともなれば、沿道には露天がひしめき、買出し客が長蛇の列をなしたのです。
こうなると、食堂や茶屋も大わらわです。暖を取るための酒が飛ぶように売れて、福光屋の若い衆は、雪ソリに酒樽を積んで東奔西走することになったわけです。
酒造りはすべて手作業の家内工業でしたが、千石酒屋ともなれば、その設備はケタ外れの規模でした。太助の晩年頃には4つの蔵が建ち、蔵人も尋常な数ではなかったようです。彼らの出身地は白山麓の村々などで、今日では幻の酒造り衆となってしまっている「加賀杜氏」の故郷でした。

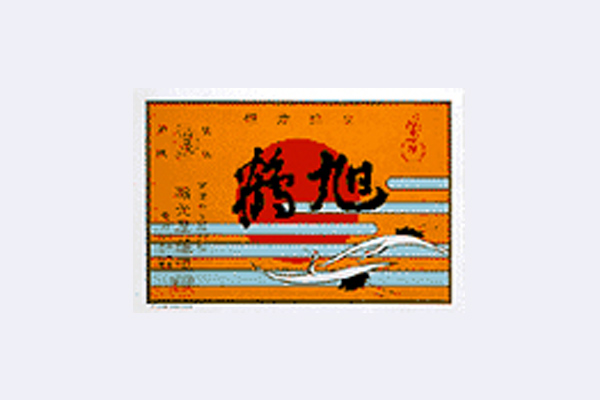

大正時代に入ると、福光屋は「福正宗」を新たに発売し、国鉄を使った貨物便で富山県の高岡へ販路を開きます。物流の近代化とともに、福光屋はその先陣を斬って他県市場を開拓しました。
しかし、大正7年(1918)第一次世界戦争が終わると、日本政府は戦需への過剰な投資から不況を招き、各地の景気は徐々に悪化していきます。さらに戦時中に停止していた金輸出禁止解除の時期を逸したため、日銀に大量の金が残り、景気対策は遅れ、これに追い討ちをかけるように昭和2年(1927)金融恐慌、その2年後に世界恐慌が発生するのです。
ところが、そんなさなかに福光屋は福蔵(五号蔵)、南蔵(六号蔵)を増設し、精米所、瓶詰め工場も新設するなど、一気呵成に飛躍していきます。
この英断を下し、みごとな経営手腕を発揮したのが、福光屋中興の祖とされている十一代目・福光 松太郎 でした。
松太郎は明治19年(1886)生まれ。「旦那さん」「おあんさん」と店員たちに敬われ、妻をとても大切にした男性でした。彼は、明治末期から昭和初期までの激動の時代に圧し潰されることなく、福光屋の経営革新と福正宗の高品質化を実現しました。
数々の功績を残し、今日の礎を築いたその人物像を探ってみると、保守的な明治の旦那気質とは異なる、大胆さと柔軟さを兼ね備えた経営者という印象が窺えます。
例えば、戦時下による酒類統制が厳しくなった昭和12年(1937)頃、多くの酒造業者が先行きに不安を抱え廃業していく中、松太郎は彼らの手放す酒造権(免許)を買い上げ始めます。
この頃は灘・伏見の酒が全国に広がり、金沢もとある灘の酒に市場を占められていましたが、松太郎は福正宗がその酒より劣っているとは思いませんでした。
灘の酒とは言え、所詮は遠距離を運ばれて来た酒。それに対し、こちらは搾り立ての蔵出し酒。それでも、福正宗を口にする人は増えません。都会で流行っている灘ブランドの口コミ人気は絶大で、松太郎には辛抱の日々が続いていたのです。
その上、清酒生産が規制されていくにもかかわらず、松太郎は次々と巨額を投じて酒造免許を手に入れます。それは、福光屋の年間売上高を越えるほどでした。
昭和14年(1939)、清酒業界は政府に全体量23%の減石決定を上申しますが、さらに48%までの下方修正を厳命されました。各地の酒蔵が生産縮小や停止となる中、福光屋は松太郎の買った権利によって減産を免れたのです。
松太郎の“先見の明”に、おそらく地元の酒造家たちの誰もが驚き、感服したことでしょう。しかし、福光屋においては、大番頭以下、丁稚や見習いまで、機を見るに敏な松太郎の決断を寸分も疑うことはなかったのです。
そんな死中に活路を見出すような勝負勘とは対照的に、福正宗の酒質については徹底してこだわり、一切の妥協を許しませんでした。
戦中から戦後にかけては、全国的に水で薄めた「金魚酒」が横行し、金沢にも出回りましたが、松太郎は紛い物の酒など見向きもしませんでした。
この十一代目・松太郎の造り続けた福正宗、彼のたゆまぬ功績と人望こそが、今日の福光屋ブランドの出発点であると言えましょう。



灘や伏見ブランドに追いつけ、追い越せをスローガンに掲げてきた松太郎の目指すところは、福正宗から田舎酒イメージを払拭し、“都酒”として北陸圏一帯に認知されることでした。
しかし、戦後復興に向けて福光屋の磐石な体制を整えた直後、昭和22年(1947)松太郎は安堵したかのように永眠します。
未曾有の嵐がやって来るのか、福光屋はどのような舵取りで時代のうねりを乗り越えて行くのだろうか……店員や蔵人がさまざまな期待と不安を交錯させる中、松太郎の意志を継いだのが、十二代目の 福光 博 でした。
博は、松太郎の妹が嫁いだ滋賀県彦根市の広野家から、福光家の養子になった人物です。余談ながら、広野家は旧・彦根藩士の家柄で、博の実父は滋賀銀行頭取も務めています。
近江商人の質素倹約、文武礼節を信条として育った博は、世界を駆けめぐる貿易商になることを夢見ていました。むろん並々ならぬ秀逸さで、広野家の血筋からしても、いずれ経済界で活躍するであろう素地素養を備えていました。 では、彼が松太郎に迎えられたのは、何故でしょう。
博は、戦前に旧制第四高等学校(現・金沢大学教養学部の前身)へ入学していました。
金沢は、母の実家・福光家のある町。機会があれば伯父夫婦を訪ね、学問の現状から貿易商の夢までを語ったはずです。
瞳を輝かせる博の卓抜した才覚に、松太郎が惚れ込んだとしても不思議はないでしょう。
もっとも、博本人は「戦争の真っ只中で、食料が乏しかった。でも、酒蔵なら米がたくさんあるから、食いっぱぐれがないと思った」と開けっぴろげな本音を残しています。


昭和24年(1949)博は福光屋を株式会社に改組すると、新たな時代に挑むべく経営戦略を展開します。貿易商を夢見ていた頃と同じフロンティアスピリッツが、その胸に滾っていました。
最新式瓶詰め設備の導入、伏見から熟練職人を登用と、博は大手メーカーに対峙できる酒質を追求しました。その一方で、福正宗のブランド化に向けて画期的な手法を使います。
ラジオ放送という新たな宣伝媒体に、博のセンスが敏感に反応したのです。昭和27年(1952)JOMR=北陸放送金沢ラジオ局が開局すると即座にスポンサーとなり、公開番組「福正宗提供 ほろ酔いクイズ」がスタートしました。
品質と広告の相乗効果によって、福正宗の引き合いは北陸一円に広がり、現金主義による強気の経営で快進撃が続きました。翌年には、「寿蔵」を新設。東京の酒販店との特約も成立し、福正宗は都酒の第一歩を踏み出そうとしていました。
鷹揚な蔵元であれば、もはや順風満帆とばかりに左団扇をあおぐのでしょうが、博はさらに熟考を重ねます。
「東京で本気で商いをやるなら、伏見で酒を造らねばならない。“伏見の酒”と言われなければ、結局は、首都圏でぶっ叩かれて安売りされている田舎酒と同じになってしまう」 そして昭和33年(1968)、博は京都伏見の深草に、製造蔵と支店を開設するのです。
この無謀とも思える投資には、若き日の博が愕然として意気消沈した体験が生かされています。
家業に就いた頃、博は福正宗をうまい酒だと実感し、金沢での人気に自信を持っていました。しかし、伏見の名酒と謳われる酒を口にした途端、あまりの格差に声を失っていたのです。
「こんなに、ちがうものなのか!?伏見の酒は、これほど美味しいのか!」
その時、本気で酒屋をやってやると博は腹を括っていました。
伏見蔵が誕生した翌年、福光屋はついに1万石を突破。東京、大阪を視野に入れたブランド戦略の第二段階へと突入していくのです。


清酒需要の追い風に乗って福光屋は躍進を続け、昭和50年代後半には、3万6千石という膨大な生産規模に到達しました。
その間、博の八面六臂のリーダーシップは休むことなく続き、彼を支える敏腕の役員たちと、意表をつくような発想や奇抜なアイデアを繰り出し続けました。
ここにすべてを紹介する紙面は残されていませんが、博のスカウトによって、福正宗を全国に知らしめたセンセーショナルな人物を紹介しましょう。
「フクちゃん」と聞いて、学生帽をかぶった可愛いキャラクターが頭に浮かぶなら、あなたは御年輩の方でしょう。漫画家・横山 隆一 氏が生み出したフクちゃんは、戦後の復興期に大ブレイクした4コマ漫画シリーズでした。
博の思うに、このフクちゃんのトーンはすこぶる福正宗にマッチしそうでした。しかし、地方の酒蔵が全国的キャラクターをコマーシャルに起用するなど、いまだかつてない暴挙と囁かれたようです。
そんな不安を、あっさりと杞憂に終わらせてしまったのが、昭和38年(1963)から北陸ネットのテレビCMで流れた「フクちゃん、フクマサもってきて」のキャッチフレーズでした。
あどけないフクちゃんが一升瓶を抱えて駆ける姿は、男性だけでなく、家庭の主婦や子どもたちにも親しまれ、“大衆のうまい酒・福正宗”のブームを迎えるのです。
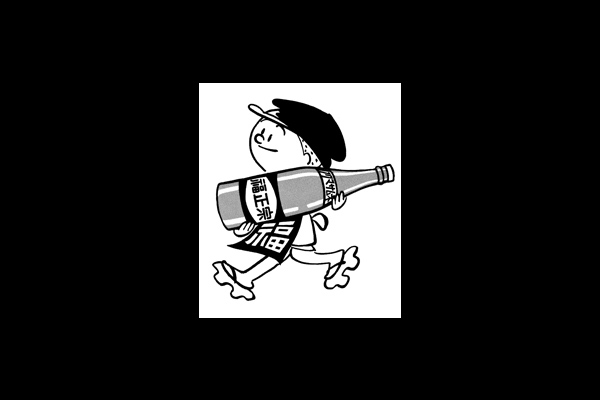
昭和60年(1985)福光屋の経営は、十二代目・博から十三代目・松太郎へ託されています。
これを機に、福光屋は「全商品を糖類無添加にする」と発表。次なる革新を歩み始めました。そして平成13年(2001)には、すべての商品を純米酒とする「純米蔵宣言」をしています。
思うに、福光屋の歴史は、金沢の酒蔵としてのアイデンティティを磨き上げながら、新しい時代の風を読むことの上に築かれてきたようです。
福光の地から金沢へ新天地を求めた六代・太助も、伏見の地に進出した十二代目・博も、その間の累代の当主たちも……彼らは、常に高邁で真摯な何物かを追い求めるかのように、新しいミッションとその達成を繰り返しています。
今、その十三代目となる 松太郎 社長は、福光家の血脈が育んできた曇りなき眼で、どんな未来を洞察しているのでしょうか。
その革新のテーマは、蔵主紹介ページでじっくりと拝聴することとしましょう。






