
米の旨味と水の素晴らしさで、「選ばれる酒」の文化を追求する
お福酒造では、近代的な事務所と瓶詰め工場が、明治時代に建てられた古い蔵に繋ぎ合わされています。所々に残る低い間口や通路からは、昔の蔵人の足音や声が聴こえてくるようです。
しかしながら、古い蔵には中越地震での傷跡がそこかしこに残っていました。
亀裂の走る地面、下地が剥き出しの漆喰壁、丸太をつっかえ棒にした棟……震度6強の縦揺れは凄まじく、酒を詰めた数百本の瓶が割れ、新酒用の大切な酒米は雪崩を打って崩れ、検査室の器具は粉微塵に砕けました。
また、社屋周辺の道路は地盤が30センチほど沈下、到るところマンホールが路面に飛び出し、翌朝には周辺住民を仰天させたのです。
「茫然自失とは、まさに、あの時の気持ちを言うのでしょうね。ただ、午後6時前の発生でしたから社員は蔵の中におらず、一人も怪我をしなかったことが不幸中の幸いでした」と当日を振り返る、岸 富雄 社長。
しかしながら、地震から一夜明けた社内は、目を覆わんばかりの惨状でした。
岸 富雄 社長、息子の岸 伸彦 専務ともガックリと肩を落とし、しばし立ち竦んでいたそうです。


「当社だけでなく、社員の自宅も相当な被害を受けてましたから、まずは皆が生活できること、ライフラインを確保することが優先でした。会社の復旧はその後だと、社長と話し合ったのです。でも有り難いことで、全員が朝は自宅を直し、昼からは会社にやって来てくれたのです」
いったい何から手を付ければいいのか、途方に暮れたと語る岸 信彦 専務。しかし、思案投げ首する蔵元に、杜氏や蔵人、社員たちから「とにかく、いい酒を造ることしかない!」と熱い声が発せられたのです。
その冬は仮修繕した社屋で一丸となって酒造りに励み、みごと全国新酒鑑評会金賞を受賞。そこには、艱難辛苦を耐えて、決してあきらめない“長岡人”気質を感じますが、何より一人一人が大切にしているお福酒造の誇りと、岸 社長の持つ人望・人徳を感じます。
岸 富雄 社長は、お福酒造株式会社の四代目。長岡の名門・松田家に誕生し、昭和38年(1963)岸家の婿に迎えられています。
「27歳の時に結婚して、東京の滝野川醸造試験場の研修を終えてから家業に就きました。父の正道 専務の下で製造から営業までを修行しましたが、昭和47年(1972)に父がクモ膜下出血で亡くなり、祖父で社長の修太を支えながら、経営全般 を担うことになりました」 岸 社長が後継した頃は長岡での販売がほぼ100%で、2級酒中心の醸造でした。
地元市場のみで充分経営が成り立っていたのですが、昭和60年(1985)以後は流通革命によって灘・伏見などの大手メーカー酒が流入し、価格破壊も起こり始めます。
また、ある越後酒がきっかけとなって、首都圏で“地酒”の人気が高まりました。これを機に、数々の蔵元が県外市場へ進出するのですが、地元優先主義に徹していたお福酒造は出遅れたのです。
「当時は地元市場のみで、全国流通や商社とのご縁はありませんでした。どうにかして東京の市場を開拓しようと思っていた矢先、当社の幹部の一人が、東京の上野界隈で手作りのキャンペーンを仕掛けたのです。これが、県外進出のチャンスに繋がりました」
岸 社長の右腕であった幹部は、山古志村出身の人物。当時、山古志村からは東京への出稼ぎ組が多く、その中に小売酒屋に勤める人たちもいました。その縁を頼んで、毎年東京で催されている“山古志出身者の会”にお福正宗を提供。これが参加者に「懐かしい!」と大好評を得て、お福正宗の銘が口コミで広がったのです。
さらには、小売酒屋の口から、お福正宗の美味しさとブランドが大手商社に伝わり、首都圏への流通が本格化したそうです。




地酒ブームが去った後も、お福酒造は地道なセールスと米の旨味を引き出した品質でファンを広げています。かつては、淡麗辛口の越後酒が大ブレイクし“新潟酒バブル”とまで謳われましたが、その時も、お福酒造は一線を隔す“旨味のある酒造り”を続けたのです。
その理由は、創業者・岸 五郎から相伝されている技術と仕込み水の良さにあるようです。
この視点から、お福酒造が掲げる企業理念について、岸 社長に訊ねてみましょう。
「やはり、創業者の哲理と長岡の文化の二つを守り続けるということではないでしょうか。当社の水は、前者の代表だと思います。岸 五郎が岸家の持っている山の懐で発見し、今も当時の横井戸から水を引いています。そして後者に繋がるのですが、地元の人々が何百年間飲んできた“大清水(おおしみず)”と呼ばれる泉に通じる水源なのです。軟水ですから、酒を仕込んでも、料理に使っても、素材の味をじっくりと引き出してくれます。つまり、何十代と馴染んできた水の味と品質は、この土地の命の源であり、文化のしずくなのです。これをずっと守って継承していくことが、お福酒造の使命。そこから生まれる酒は、誰にでも福を招く美味しさであることが、企業理念ですね」
なるほど、蔵元の真髄を語るかのような素晴らしい答え。さらに、「まずは、地元のお客様に喜んでもらえる酒でなければ、蔵元としての責任は果たせていないと思います」と付け加えてくれました。
岸 社長の言葉を要約すれば、「蔵元の文化が生き続ける酒造り」ということでしょう。
ともすれば昨今の日本酒業界では、コスト削減と利益追求を追いかける姿勢が当然のように叫ばれ“酒造業は装置産業”と叫ぶ企業も多いのですが、それも過去のものになっているような気がします。筆者も、今一度、日本酒の伝統文化を真剣に見つめ直すべきと思 いますが、この点を、次代を担う岸 専務はどう考えるのでしょうか。
「当社の酒は、新潟の中でも個性的な特長を持っています。辛口であって米の旨味もある、記憶に残る酒質だと思います。
しかし、淡麗辛口酒ブームの頃には、惨憺たる状況でした。私が入社した頃はかなり苦戦を強いられ、父は経営的に苦しかったと思いますが、それでも本来の味と品質を頑なに守り続けました。今にしてみれば、私はそれで良かったのだと思います。一貫して味のある原酒にこだわっているのも、伝統と文化を守る姿だと思います。また、これからは消費者ではなく、生活者のシーンを満たし、暮らしをハッピーにする酒の特長、蔵元の魅力が鍵となるでしょう。つまりは、酒造業は伝統産業であり、日本文化を紡ぐ嗜好品であるという原点、そこに埋もれている魅力に回帰すべきかもしれません」
長岡の郷土料理には、お福正宗の燗酒が格別合いますよ!と笑顔で語る、岸 専務。元は大手銀行のエリートと聞きましたが、やはり、蔵元の血筋ならではのオーラに溢れています。



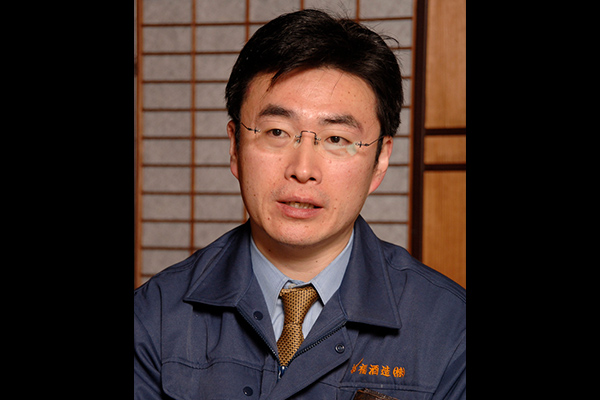

締め括りに、父と子の二代の蔵元に、今後のお福酒造のテーマについて話してもらいました。
「目前の課題としましては、震災の修繕・修復を早急に行うことですが、これも、将来的な展望も含めまして、計画をいろいろ練らねばなりません。蔵の建て直しにも、やはり文化を残していくことが大切でしょうね。そして社会が変化しても、お福正宗の原点を忘れず、時代に応じた存在価値を追求していくことですね。近年は山古志村の棚田で有機栽培された酒米“一本〆”などを使い、限定酒も造っています。農家の方々へ福を招くことも、当社の理念の一環です。残念ながら、地震後は前年の2割程度の収穫しかなく、棚田復旧への支援も検討しています。すでに、そのバトンは専務へ預けつつありますが」と、岸 社長は笑顔をほころばせます。
その言葉を受けて、岸 専務が語ってくれました。
「私は、こう思うのです。岸 五郎は、まず安全な品質の酒を造りたかったのだと。徹底した研究者の彼は合理主義者に見られがちですが、実は、その反対の心情家だった。腐造の頻発した時代でしたから、速醸酒母が完成すれば安定した酒造りが可能となり、旨い酒が庶民の食卓に並び、蔵元が潰れたり職人が路頭に迷うこともなくなる。だから、飲み手にも造り手にも幸せが生まれる。そんな五郎の酒を、多くの地元の方々が選んで下さったと思います。ですから、お福正宗とは“選ばれる酒”であるべきだと思います。私は現在、さまざまな商品開発を担当しておりますが、酒質、ラベル、名前、パッケージも含め、それぞれにお客様を惹きつける特長を考えます。いつも頭に描くのは、『長岡に、お福正宗って美味しい酒があってね!』『あっ、飲んだことある! あの酒、なかなか手に入らないけど、うまいよ』と噂されるシーン。そんな味わい、珍しさ、憧れ、個性を、これからも大事にしていきたいと思います」
今後はニッチな商品として、女性や若い人たちが好みそうな低アルコールやリキュールタイプの日本酒も視野に入れていると言う岸 専務。
そんな若々しい五代目のセンスに、岸 五郎が託してきた“福作りの酒造り”を期待しつつ、インタビューを終えることとしましょう。







