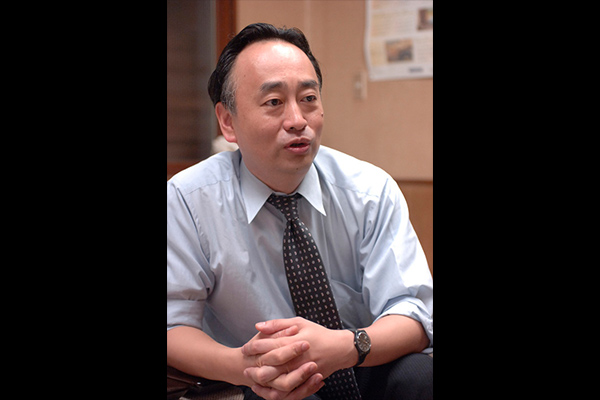酒で天下を取る!佐川酒を土佐の冠たる美酒にした、中興の祖・竹村源十郎の精神
梅雨の雲間から射す夏の光芒が、佐川町の目抜き通りを照らし始めました。
延々と続く白い蔵棟に、いよいよ土佐の銘酒・司牡丹に出逢えるのかと心が逸ります。
年輪を感じさせる土蔵は江戸末期の建造物で、佐川の町の趨勢を見つめてきたシンボルとなっていますが、どこかしら温かみのある風合いが、あたかも博学な好々爺のように思えるのです。
「この蔵は、当社で最も古い棟です。江戸時代、この界隈では領主・深尾公が入国した慶長8年(1603)以来、御用達を賜る“御酒屋”の流れとして数軒の酒屋が営んでいたようです。定かな資料は残っていませんが、当家の遠祖も遠州掛川より深尾公に従って来たのかも知れません。屋号は、黒金屋(くろがねや)と称しています。そして、幕末以後は各店が縁を結ぶなどして、明治末期には4軒の蔵元が残っていました。この4つの蔵元が大正7年(1918)に統合されて誕生したのが、佐川醸造株式会社。そして、これが司牡丹酒造株式会社へ改組したのは、昭和7年(1932)のことでした」
通称“酒蔵の道”と呼ばれる長い路地を歩きつつ解説してくれたのが、司牡丹酒造 竹村 昭彦(たけむらあきひこ)社長です。
竹村 社長によれば、司牡丹酒造の蔵元・竹村家の先祖黒金屋弥三衛門(くろがねやそうえもん)が高知城下の蔵元・才谷屋助十郎(さいたにやすけじゅうろう)から天保2年(1831)に酒造株を買ったという書状が残っているそうです。
この才谷屋とは幕末のヒーロー・坂本 龍馬の家筋で、寛文六年(1666)に高知城下の本丁筋で質屋を開業、延宝五年(1677)には酒造業も始めています。さらに元禄七年(1694)本丁筋二丁目で雑貨品を売買し、大店の商人へ発展しました。
ちなみに京都の近江屋で坂本 龍馬が襲撃された際、十津川郷士と偽った暗殺者は、龍馬に「才谷先生」と一言発して踏み込んで来たと、横死した中岡 慎太郎が言い残しています。「黒金屋と才谷屋の間では、多くの書状がやりとりされています。また竹村家の家系図には『才谷屋 女』坂本家の家系図には、『竹村氏 女』などの出自記録があり、どうやら嫁入りの形跡が窺えるのです。もしかすると、龍馬は当家と遠縁関係にあったのかも知れませんね」と竹村 社長は破顔一笑します。その風貌が、どことなく龍馬に見えてくるから不思議です。





さて明治時代に入ると、新政府が税収源として進める地租改正策が暗礁に乗り上げ、このため鰻上りになっていた酒消費に大幅な税収を見込みます。
大衆にも清酒が飲用され始めたことで全国的に酒造業は活況しますが、反面、腐造が多発し、激しい酒屋の浮き沈みが起こっていました。
そんな中、黒金屋の酒造りは安定して継承され、身代は竹村本家と竹村出店(分家)に分かれるほどになっていました。竹村本家の銘柄は「笹の露(ささのつゆ)」。竹村出店は「白梅(しらうめ)」。この後者の竹村出店が、現在の司牡丹酒造の家系です。
ちなみに当時の佐川町には、この2社以外に浜口家、井上家(牧野 富太郎 博士の売却した実家)が蔵元として操業していました。
明治中期の竹村出店の当主は竹村 寅五郎(とらごろう)で、彼には男子が生まれず、また妻と娘を残して他界しました。このため竹村出店は婿養子として、中澤 源十郎(げんじゅうろう)なる人物を迎えます。
中澤 源十郎は御免(現在の南国市御免町)の蔵元の長男でしたが、新たな商いに手を染めてはしくじる父親のために、家業は斜陽していました。ついには、その父も早逝したため、彼は教職を取って家族を養います。
ところが、源十郎が22歳となった明治35年(1902)、恩師の奨めによって竹村家への婿養子の話しが持ち上がったのです。
苦労の絶えない酒屋業に、母親は源十郎の将来を案じますが、彼の中では、すでに父の成し得なかった夢を果たすという血潮がたぎっていたようです。「酒で天下を取る。ここに私の行く道がある」と決心した源十郎は、これより竹村家の酒造りを革新し、その名と味を全国に知らしめるべく、長きに渡る中興の道を歩み始めるのです。
婿入りした源十郎は、こぢんまりとした商いでかまわないから家に落ち着いてくれと義母に諭されます。臍を噛む思いの源十郎でしたが、一面 では肝っ玉の太さ、負けん気の強さを見せ始めます。
明治36年(1903)、銘酒「白梅」の商標に対して、神戸の蔵元から「商標の無断使用だ!」と恐喝まがいの訴えがありました。
調査の結果、竹村家の商標が古いと判明しますが、居直った先方は裁判に持ち込み、源十郎もこれを受けて立ったのです。
結局14、5回も裁定に出向くほど揉めた末、五百円という大金を払って話をまとめました。決着するやいなや、源十郎は「白梅」を「若柳(わかやなぎ)」に改めます。また2年後には、牧野 富太郎の生家であった井上和之助酒店を買収し、竹村 源十郎支店として開店。酒は「日の本(ひのもと)」と命名しました。
そんな源十郎のいごっそうな人柄は評判となり、竹村出店の酒も人気を博していったのでしょう。大正元年(1912)には「若柳」を2400石製造し、県下一の醸造量へ躍進したのです。
そして、源十郎の卓抜した才は、佐川に残る4蔵を束ねることでさらに開花します。
大正7年(1918)、竹村本家、竹村出店、竹村 源十郎支店、浜口家が合併し、佐川醸造株式会社が誕生。源十郎は専務取締役に就任し、新たな銘酒「千歳鯛(ちとせだい)」は、この年の四国酒類品評会で第一位に輝いたのです。
千歳鯛の名が全国に伝播すると、またもや商標権問題が噴出し、佐川醸造は銘柄変更を余儀なくされます。そこで機を見るに敏な源十郎は、さらに古今東西に知れわたる酒銘をと、佐川出身の先達・田中 光顕 伯爵に請い願ったのです。
田中 光顕 卿は、坂本 龍馬や中岡 慎太郎の遺志を継いだ幕末の英傑であり、宮内大臣も勤めた偉人でした。郷里・佐川の酒をこよなく愛していた田中 伯爵は二の句もなく快諾し、大正8年(1919)佐川醸造に書簡が届きます。
天下の芳醸なり。今後は酒の王たるべし。
牡丹は百花の王。さらに牡丹の中の司たるべし。
ここに、銘酒「司牡丹」が呱々の声を上げました。





名実ともに四国一の酒を目指す佐川醸造にとって、“名”は完成しましたが、“実”はこれからが正念場でした。
当時、高知では軟水に薬品を加えて硬くし、短期間で旺盛にアルコール発酵させていました。源十郎はこれに疑問を抱き、難しくとも、地元ならではの軟水仕込みで優れた酒を造ろうと、昭和元年(1926)から5年間、全国の蔵元を行脚見学します。
そして、杜氏のきめ細かな仕事と観察があれば、軟水であろうとも極上の美酒が醸されることを確信し、司牡丹の品質を高めていきます。おりしも、浜口 雄幸(おさち)首相より「芳醇無比」の賞賛の書を拝受し、それを聞きつけた田中 光顕 伯爵が一筆名句を添え、改めて「芳醇無比乃巻」にしたためるほどでした。
昭和6年(1931)、源十郎は軟水仕込みを得意とする広島三津の杜氏・川西 金兵衛を蔵に迎えました。結果、翌年の全国清酒品評会で、銘酒「司牡丹」は優等賞を受賞。これを機に、佐川醸造株式会社は司牡丹酒造株式会社に社名を改め、源十郎が代表取締役社長となります。
川西 金兵衛は麹造りにこだわり、同郷の安芸津の蔵人であった植野 瞭三を見出して、昭和11年(1936)、昭和13年(1938)も優等賞を獲得。司牡丹酒造は、酒屋の王座たる名誉賞をついに獲得したのです。源十郎58歳の時でした。
この時期、酒質の向上を実感していた源十郎は、販売促進でも大車輪を演じています。
まずは司牡丹の名を大々的に宣伝すべく、昭和7年(1932)頃から、徳島市、高松市、松山市など四国他県の主要都市で販売店を集めた大酒宴を催し、アドバルーンやチンドン屋を使ったPRを打ちまくります。昭和12年(1937)に国鉄土讃線が開通すると、佐川町への販売店招待旅行を催し、親族も呆れるほどの散財を繰り広げます。
しかし、これが功を奏し、司牡丹の人気は赤丸急上昇!それなら次は地元とばかりに、佐川町から高知市まで、トラック32台に酒を積んで大行進。市街に着けば、社員全員が揃いの衣装でビラを撒きながら、練り歩いたのです。一時は呆れ返っていた社員たちも「どうせやるなら、てっぽず(とことん)やれ」とばかりに社長の奇策を応援し、結束を固めました。この効果は顕著に現れ、昭和16年(1941)の司牡丹酒造の製造量は、なんと5000石を超えたのです。
晩年の源十郎は当時を回想して、「司牡丹と心中する覚悟だった」と語っています。






米の配給が制限された太平洋戦時下、全国の蔵元は合併や廃業を強いられ、昭和19年(1944)高知県にもその命令は下り、28社の合併策が進んでいました。
しかし、司牡丹酒造はこれに断固反対し、一社での操業を決意。すでに合併の苦労を経験していた源十郎は、経営面の諍いを予測していました。戦時下の米不足のため司牡丹の醸造量はたったの600石まで急落し、県外出荷を取り止めます。源十郎は素麺やアイスクリームを製造するなどして苦境をしのぎながら、全国に「金魚酒」などの粗悪な酒が蔓延する中、酒造りでは「決して酒質を落さない」という信念を貫きます。
この決断と努力が戦後になって高い評価を受け、司牡丹には全国から注文が殺到することになるのです。
そして、昭和20年(1945)源十郎の長男・威知郎が社長に就任、今後の順風満帆を感じつつ源十郎は会長へ勇退します。
ところが、その数年後、司牡丹酒造に予期せぬ不幸が重なります。昭和24年(1949)総杜氏の川西 金兵衛が他界、その2年後にはあろうことか威知郎が急逝し、古希を迎えた源十郎は悲嘆に暮れながらも社長の席へ戻ったのでした。
断腸の日々の中、源十郎は威知郎の長男で京都の大学に学んでいた維早夫(いさお)を呼び戻し、見習い社長として教育します。そして昭和29年(1954)、維早夫は22歳で社長に就任し、司牡丹の新たな躍進が始まるのです。
源十郎は七男三女に恵まれていましたが、次男以下には継がせず、弱冠な維早夫なれども長男・威知郎の嫡流を通すあたりに、明治の男の気骨を感じます。



昭和30年代後半になると、司牡丹酒造の醸造量は10000石を突破。これを記念して、維早夫は「デラックス豊麗司牡丹」を発売します。この記念酒は、現在の大吟醸に匹敵する酒質で、やがて訪れる地酒ブームの魁として話題をさらいました。
全国的な清酒ブームの到来を予見していた維早夫は、30000石の製造を目指します。これを源十郎は「先のことばかり追って、目先を見失ってはいけない」と戒めますが、自身の夢であった10000石を達成した孫のチャレンジ精神に、本心としては目を細めていたようです。
高度経済成長による近代化の波が押し寄せる中、維早夫は製造面には最新鋭のオートメーション瓶詰設備を導入し、販売促進面ではテレビコマーシャルなどのマスコミ戦略を推進。高知の同業他社の追随を許さぬ、リーダーシップを発揮しました。
しかし、他社のマスコミ参入が白熱してくるや、維早夫はすみやかに撤退を始めます。そこには、司牡丹酒造のモットーである「品質本位」に立ち返る新たな戦略が構想されていたのです。
昭和40年(1965)から、司牡丹酒造は全国新酒鑑評会において毎年のように金賞を受賞していました。世間では三倍醸造酒がまかり通っている時代でしたが、維早夫はこの金賞受賞の成果を首都圏に浸透させ、本物志向の地酒・司牡丹への消費者ニーズを巻き起こそうと考えたのです。
こうして東京マーケットへ進出した司牡丹酒造は、昭和50年頃からの全国的な地酒ブームを牽引します。維早夫は次々に品質を向上させ、特級酒のすべてを純米酒に、一級酒も本醸造クラスに切り替えました。その徹底した品質主義は、かつて源十郎が描いた「酒で天下を取る」ことへの挑戦であり、志半ばにして逝った父・威知郎に贈る香華であったのかも知れません。
そして、この維早夫の成功を見届けるかのように、昭和53年(1978)源十郎は98歳の天寿をまっとうしたのです。
「その後も、土佐の本物の酒造りに徹底してきた当社は、平成4年(1992)新たな社是を掲げています。従来の品質至上主義の上に立つ、“源・和・創・献”という根本精神です。この最初の“源”とは、司牡丹400年の歴史における先人たちへの感謝とともに、中興の祖である源十郎本人を讃えているのです」
会長となった父親の維早夫氏から、平成11年(1999)に経営を引き継いだ竹村 昭彦 社長は、そう解説します。
小柄な曽祖父・源十郎の剛毅な面差しをよく覚えていると言う、昭彦 社長。次なる蔵主紹介ページでは、そんな社長の魅力に迫ることとしましょう。語りつくせぬ司牡丹の物語……歴史の中に秘められた美談・美酒の逸話は、ぜひ佐川の町を訪れて、読者ご自身で探りあててみてはいかがでしょう。