新人歓迎会を終えたらしき若者たちが、お揃いの黒いスーツ姿で通りを駅へ向かっていた。春のぬるい夜風に彼らの気分は上々らしく、学生気分が抜けきれないまま口さがなく騒いでいる。
その人ごみに逆らいながらポンバル太郎へ向かう右近龍二の後ろで、火野銀平がうっとおしげに眉をしかめた。
「まったく、どいつもこいつもカラスみてえな服装で、カアカアうるせえな。ちったあ、ビシッと紺色のスーツで寡黙に決めた、昔かたぎな若者はいねえのかぁ?」
どこかで一杯ひっかけて来たのか、銀平の呂律はおぼつかない。その言いぐさに苦笑しかけた龍二の肩に、人影がぶつかった。それは千鳥足になるほど酔っている老齢なサラリーマンで、通りがかりの人たちに次々と突っかかっては、よろめいていた。
「あ~あ……あの親爺さん、大丈夫ですかね」
「今どき珍しい、ぐでんぐでんだな。いくら昔かたぎっても、あんなやるせない野郎はご免蒙るぜ」
ぶつかる相手に頭を下げながら、ついでに店の看板にもお辞儀する姿に二人があきれていると、聞き覚えのある声がした。
「まるで、昭和四十年代のノンベですねぇ。まあ、その頃のサラリーマンは、みんな、あんなものでしたよ。一升瓶を抱いたまま店先に寝転がってる人も、ざらにいましたよ」
龍二が振り向くと、平 仁兵衛がポンバル太郎の扉を開けたまま、顔をほころばせていた。
「古き良き、清酒全盛の頃ですね。先生のお父さんの時代ですか」
「そうですねぇ。うちの父は漆器の職人でしたから、何かの祝い事で飲むと決めた時はあんなふうになるまでトコトンでした。でも貧乏でしたから、日頃の晩酌は水で半分以上割った酒ばかりで、泥酔することはほとんどなかったですねぇ」
龍二が平と語っている隙に、おせっかいな銀平は酩酊しかけている老齢の男に声をかけていた。そして、ふらつく男に駅への道筋を言い聞かせた後で
「先生が言ってるのは、いわゆる、玉割りって方法だろ……まあ、今どきのノンアルコールよりはマシだったんじゃねえかな」
と平の話しに加わりながら、ポンバル太郎へ三人で入った。
剣の甲高い「いらっしゃい!」の声が響くと、三人揃いの登場にカウンター席のジョージが口笛を吹いて喜んだ。手招きをするジョージの隣に平が座りながら、銀平に言った。
「うちの親父は、金魚酒って呼んでましたねぇ」
「金魚酒? 何だ、そりゃ」
カウンターの真ん中に座る銀平の声に金魚酒の語句を耳にしたジョージも小首をかしげて、純米吟醸を注文する龍二の顔をうかがった。
「大東亜戦争の頃、全国的に米不足になり、酒造量が減ってしまったんです。だから、蔵元は酒を水で薄めて増量をした。これを流通させる卸や酒屋でもさらに加水され、どんどん希釈しちゃったわけです。金魚でも泳げるような、薄い酒って例えですよ」
すると、テーブル席の客の注文をメモしている剣が、龍二の言葉を背中で聞きながら親指を立てた。
「正解だけど、江戸時代だって金魚酒はあったんだよ。稼ぎの少ない貧乏長屋の女将さんたちは、旦那の酒代をケチろうとして薄めた。それとさ、極端に薄い金魚酒は子ども向けだったそうだよ。今みたいに、お酒は二十歳からって法律はなかった。どっちかっていえば庶民よりも侍の子どもたちが大人になるための嗜みだった。十五歳で元服すると、当然、酒座に出るようになるからね」
剣の解説に、テーブル席の男たちが感心して
「マスター、こりゃポンバル二郎君だね」
とカウンターの中の太郎に向かって褒めそやした。
すると、元服の言葉に、スマートフォンで金魚酒を検索していたジョージがまた頭を捻った。太郎はお銚子を傾けてやりながら、その意味を教えた。
「おお、侍のしきたりですね。でも太郎さん、江戸時代の日本には日本酒しかなかったから、濃い原酒を売る方が儲かるじゃないですか? どうして、薄い金魚酒を許したのでしょうか?」
盃をなめる青い目のジョージの質問に、テーブル席の客たちがごもっともとばかりに耳を傾けた。
「確かに、造り酒屋は原酒を売りたかっただろうな。それも、今とちがって無濾過の生原酒ばかりだから、旨かったんじゃないかな。ただし、当時の酒造りは米の干害や飢饉の影響をモロに受けた。だから全国的に米が不作の年は、当然、薄めた金魚酒が広まった。そこは、龍ちゃんが話した戦時中の米不足と同じだな」
スマホを手帳に持ち替えてペンを走らせるジョージに、平と龍二がニンマリして純米吟醸のグラスを合わせると、ふいに剣の声が聞こえた。
「江戸時代は、全国の藩が出した酒株でその土地の蔵元の酒造りの量が決められてた。だから米不足の年は幕府が各藩に命令して、酒造りを少なくさせたりもしてるんだ。それとね……裏の話としては、質素倹約をすすめた江戸時代の中頃、ぐでんぐでんになる人たちが町に増えると庶民の生活や治安が悪くなるから酒をできるだけ造らせないとか、薄めた酒しか飲まさないって政策もあったそうだよ」
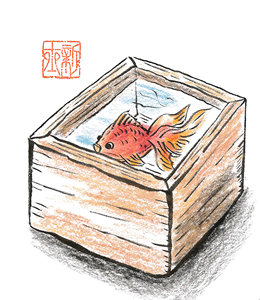
もはや客たちは剣に魅了されて、若いサラリーマンはこれからも剣のウンチクを聴きたいと太郎に頼み、年配者は孫のような剣とスマホで写真を撮っていた。
「さすが、ポンバル二郎君だね」
ハイタッチを求めた龍二に剣がはにかみながら手を合わせると、銀平が冷やかした。
「お前はまだ元服もできねえ小学生なのに、毎日、酒座に出てるなぁ? けどよ、酒は飲んじゃいけねえぞ。俺が、目を光らせてるからよ」
「まったく、しゃくにさわるオヤジだねぇ。元服をとうに過ぎてるくせに、いつまでたっても子どもみたいな銀平さんも珍しいけどさ。お子様なんだから、金魚酒を飲んでみる?」
「ぐっ! くっそう、へらず口だけはいっちょまえなガキめ」
饒舌にやり返す剣に銀平が唇を噛むと、客たちが肩を震わせながら笑いをこらえていた。
