関東の桜の名所が若葉色に様変わりすると、東京では菜種梅雨が始まっていた。もっとも篠つく雨といった風情じゃなく、どしゃ降りのゲリラ豪雨が頻繁にやって来る。
今夜も予約してないグループ客が濡れそぼった格好でポンバル太郎へ逃げ込むと、それを読んでいた剣が手回しよくバスタオルを渡してテーブル席へ案内した。激しく窓ガラスを叩く雨粒は、厨房の太郎がふるう包丁の音さえ掻き消しそうだった。
杉板の壁には「春の旬味! 富山産のほたるいか、あります」と墨字の品書きが貼られ、気になるらしい客たちは陳列ケースに目を細めた。茹でて身の盛り上がったほたるいかは、ツヤツヤとした紫色に染まっている。
雨音を聴きながらほたるいかの酢味噌和えをつまんだカウンター席の右近龍二が、グラスの富山の純米酒を口に流し込んでつぶやいた。
「日本アルプスもようやく雪解けの頃か……滑川のほたるいかミュージアムが懐かしいな」
数年前、富山の蔵元めぐりのついでに立ち寄った滑川市のほたるいかミュージアムがふと脳裏によぎった。そこで目の当たりにした青光りするほたるいかの群泳はあまりに幻想的で、言葉を忘れたかのように魅入っていた。
あの時、生きたまま水槽に飼って自室のイルミネーションにできないものかと本気で考えたほたるいかを、今夜は酒の肴にしていることに龍二は苦笑いした。その横顔に、隣に座る平 仁兵衛が話しかけた。
「その思い出し笑い、ほたるいかに関係がありそうですねぇ。それにしても、これは本当にうまい肴ですね。ほろ苦さと甘さが、キレのいい富山の酒によく合います」
純米酒のぬる燗を平が飲み干した途端、店奥のテーブルから太い声がした。
「ご主人! これは、ひょっとして滑川のほたるいかですか?」
龍二がふり向くと、自分とさほど変わらない年恰好の男が五分刈り頭を光らせながら、ほたるいかを味わっていた。飲んでいる酒は龍二たちと同じで、視線を合わせた男もそれに気づいたのか、ちらと一瞥した。
行平鍋を手にしてコンロの前に立ち回っている太郎は、「お前が代わりに答えろ」と龍二に目で伝えてきた。しかたなく口を開きかけた時、いつものべらんめい調の声が飛んで来た。
「ああ、そうでぇ。正真正銘、滑川の漁協から築地の火野屋に入った飛びっきりのほたるいかだ。おたく、ちがいが判るのかよ?」
自分よりもさらに薄く刈った青光りする面構えの火野銀平に、男は気圧されて言いよどんだ。
「あっ、いや……私、黒部一夫と言いまして、滑川の漁師です。ホタルイカの推奨販売会に上京してて、駅前のホテルに泊まってます」
田夫野人ではないが、伏せ目がちに答える黒部には朴訥とした人柄が感じられた。頑強な体躯じゃなく赤銅色にも焼けてない黒部に、龍二は彼が漁師とは、にわかに信じがたかった。厨房から現れた太郎も、不審げな面持ちで湯気の立つ鍋を持ったままだった。
「二人とも、この人が漁師に見えねえんだろ? へっ、日焼けしてねえのはよ、滑川あたりは春から夏の間もどんよりと空が低くって、蒸し暑いフェーン現象や雨の日が多いからだ」
自信ありげな銀平の口ぶりに、珍しく平が相槌を打ちながら言った。
「ほほう! それ、正解ですなぁ。私の故郷の輪島も同じですよ。『弁当忘れても、傘忘れるな』って言葉があるくらいですからねぇ」
気をよくした銀平は、嬉々としてしゃべり続けた。
「あんた、ほたるいか漁をやってんの? それじゃあ、うちの商品を獲ってくれてるようなもんじゃねえか!」
黒部はためらいながら、おじぎをした。そして、銀平が同じ富山の純米酒とほたるいかを注文するのをしばらく黙視していたが、ふいに問わず語った。
「ほたるいかは、北陸のほかの県でもたくさん獲れるようになりました。最近は、韓国でも水揚げされています。日本海の海流や海水温の変化が原因で、これには逆らえません。でも、私は滑川のほたるいかが一番だと自負しています……この季節、青く光る夜の海は私たち富山人の宝物なんですよ」
箸先でほたるいかを愛しむようにつまむ黒部に、太郎は鍋の煮物を盛りつけながら、いわくありげな笑みを浮かべていた。その時、龍二が声を高くして言った。
「僕も同じ、あれは宝物ですよ。海の中の青い花火のようで、見惚れるほど美しかった。それに、この富山の酒とはまさに地産地消ですね」
黒部と龍二のやりとりを聞いていたテーブル席の客たちが、注文したほたるいかの皿を前にしてどこが青く光るのだろうかとはしゃぎながら、純米酒を剣に注文した。
しかし、その声を耳にする黒部の表情がどことなく鬱然としていることに龍二が気づいた時、盃を飲み干した平が口を開いた。
「いや……同じじゃありませんねぇ。黒部さんのは地産池消じゃなく、身土不二(しんどふじ)です。世間一般のグルメがよく口にする地産地消よりもっと奥が深くて、切実な言葉ですよ」
聞き慣れない身土不二に、伝票を書いている剣だけでなくテーブル席の客たちも小首をかしげた。龍二だけがハッとした顔で反応した時、太郎はやけに嬉しげだった。
平は、身土不二とは仏教の教えで、人の体と生まれ育った地の風土はつながっていて二つに分けることはできない。つまり、その土地の美味しい物は、本来その土地の人にしか解らないとする考えだと説いた。
「先生、そんなこと言ってちゃ、こちとら商売上がったりだよ。今や、築地へ運ばれない食材を探す方が難しい時代なんだから」
銀平が、冷酒グラスを迎える口をとがらせた。
「いや、それを否定はしませんよ。そうではなく、どこの誰が食べても美味しい物だからこそ、その土地の人にとっての価値を再認識して、感謝することだと私は思うんですよ。いわば私たちが忘れている、“いただきます”の心ですよ」
おもむろに合掌する平の言葉に、店内がしんと静まった。少し間をおいて、カウンターに黒部の声が響いた。
「私たちの漁では、ほたるいかの青い光に見惚れている暇はありません。年々少なくなっているほたるいかに危機感と不安をつのらせていますが、全国のお客さんに美味しいと喜ばれたいし……複雑な心境です。しかし、今夜の身土不二は、ありがたかった。心情をおもんばかっていただいたような、救われる思いでした」
冷酒グラスを捧げるようにして頭を下げる黒部に、平がはにかみながら盃をかざした。
「いえいえ、大切なことを気づかせてもらった私こそ、感謝いたします」
龍二もそれに従いながら、黒部におじぎを返した。
「浅はかな意見でした。思い出のほたるいかに、あらためて勉強をさせてもらいました」
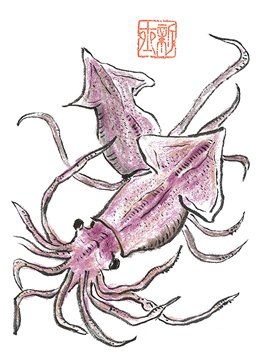
すると、顔の赤らんできた銀平がやにさがった口調で言った。
「おうっ、そうだよ。お前、地酒もウンチクばかりで、その土地の人や蔵元への感謝が足りねえんじゃねえか?」
平に賛同されて頭にのる銀平に、太郎が釘を刺そうと思った時、滑舌のいい剣の声が飛んで来た。
「銀平さんこそ、どうなの? 身土不二を一番理解しなきゃなんないのは、全国の魚を売ってる銀平さんじゃない。第一、うちに来ていただきますって手を合わせたことすらないじゃん。ダテに坊主頭してないで、仏教でも勉強したらどうなのさ」
立て板に水の剣に一言も返せない銀平へ、平がつぶやいた。
「あ~、しんど」
黒部や客たちの爆笑が、雨音を忘れさせるかのように巻き起こっていた。
