しんしんと冷え込んだ3日の朝、都内はうっすらと雪をまとい、出歩く人たちの足元をもたつかせた。
真知子も着物をあきらめ、スニーカーにジーンズの格好で店へ向かっている。
昼からは、東京に居残った常連客たちのミニ新年会である。
「寒いから、お鍋にしよっかなぁ……年末に津田さんから届いた、氷見の寒ブリがあるし。お造りとカマ焼きと、鍋はどうしようかしら」
思案しながら公園の角を曲がると、マチコの前に宅配便の軽四輪が停まっていた。玄関戸を叩いているらしく、配達員はなかなか立ち去らない。
横顔から察するには、いつも配達に来る片岡という若い青年だった。
普段は大型車に乗って上司とペアで回っているが、今日は一人のようだ。
おっとりした片岡は、ノロマだの、カスだのと怒鳴られることが多い。
「はい、は~い!今、行きま~す」
真知子は、足元の名残り雪を忘れて、店先へ小走りした。
片岡が真知子に気づいて安心した瞬間、彼女の体は宙に浮いた。しかし間一髪、片岡の腕が真知子を抱き止めていた。
「だ、大丈夫すか!?真知子さん」
「あっ、ありがとう。ビックリしたぁ~。あっ!?でも、この荷物、いい匂い~♪」
軽くめまいを覚えた真知子だったが、片岡の腕にある郵便包みに顔を押し当てたまま、ほほ笑んだ。
真知子の柔らかさと肌のぬくもりを手に感じている片岡は、頬を赤らめ、どぎまぎとしながら言った。
「そ、そうでしょう。僕もすごく気になってたんですよ。これ、何ですかね?品名は食品になってるんですけど……あっ、すみません。それって、お客様に訊いちゃいけないんだった」
「これはねぇ、冬の美味しい便り。愛情いっぱいの手造り品なの。片岡君、日本酒は好き?」
真知子は片岡の手を離れると、その包みを愛しむように抱いた。包みから漂う上品な香りは、真知子自身から匂ってくるように思えた。
「えっ、いや、あんまり飲んだことなくて。すみません」
「謝ることなんてないわ。今の若い人って、なかなか日本酒を飲む機会が少ないものね……これはね、酒粕。新潟にある酒蔵の杜氏さんが、私のために毎年贈ってくれるの。美味しいのよ~♪そこらで売ってるのと、比べられないわよ~」
自慢げに包みを開く真知子の手元に、思わず片岡は引き寄せられた。そして、銘柄と住所を見るなり「あっ!そこ、俺の出身地じゃないすか!」と口走った。
「うっ、うっそ~♪本当!?」
真知子がそう言いかけた時、片岡が軽四輪に走り寄り、その酒粕と同じような荷物を4、5個抱えて戻って来た。
「これ全部、同じ包みなんです。それに、差出人も同じなんですよ。不思議でしょう?」
首をかしげる片岡に、真知子は微笑して答えた。
「届け先って、ご町内の人ばかりでしょう?……実はね、私がご紹介してあげたの。そしたら、みんな、この酒粕が気に入っちゃったわけ」
その時、片岡の携帯電話が鳴った。
「はい!片岡です……す、すみません。すぐに向かいます……ちょっと道が混んでまして。了解しました」
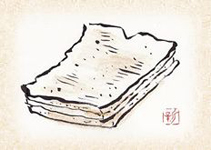 上司からの苦情らしく、受話器からは「カス!ノロマ!」と罵声が飛んでいた。
上司からの苦情らしく、受話器からは「カス!ノロマ!」と罵声が飛んでいた。
片岡は「年末だから、ノルマきつくって。マチコさん、また、ゆっくり聞かせてもらいます……俺は所詮、カスですから」と、酒粕を見つめて苦笑いした。
「何、言ってんのよ。片岡君のおかげで、美味しい粕が届いたんだもん。寒い中、大変だけど頑張ってね。良かったら仕事帰りに……あっ、そうだ!今夜の新年会は粕鍋にしようっと。ねえ、食べにいらっしゃいな。ごちそうしちゃうから」
「えっ、いいんすか……じゃあ、俺、日本酒も飲ませて下さい。真知子さんの手料理となら、きっと日本酒にハマりそうです。それじゃあ、後で」
片岡は軽四輪に飛び乗ると、通りのしじまにエンジン音を響かせて行った。
「……カスには日本酒が、つきものだもん♪」
見送る真知子のつぶやきに、酒粕の麗しい香りが漂っていた。
