日曜の昼下がり、ピンとはりつめた冬の冷気がマチコの通りを覆っていた。
閑散としている四つ角は、普段の雑踏が嘘のように消えていて、信号待ちをする車もまばらだった。
「ちっ、なんで俺だけ仕事なの。晦日まで出勤なんて、ありえねぇ~」
交差点から聞こえたぼやき声の主は、松村だった。どうやら、休日出勤の帰り道らしい。
手提げバッグの揺れ方に、ふてくされた気分がありありと分かる。投げやりな足取りは、自然とマチコに向かっているようだった。
だが、マチコもすでに年末休みに入っているはずである。
「真知子さ~ん!って呼んでも、いねえよなぁ……あれ!?」
思いがけず開いている格子戸に、松村の表情は一変。新酒の一杯を思い浮かべ、舌なめずりして玄関に飛び込んだ。
ところが先客の多さに驚いただけでなく、彼らが雑巾を手にし、作業着・マスクで完全武装した大掃除スタイルに唖然とするのだった。
「おっ、和也じゃんか。いいところに来た、もっけの幸い、手伝えよ」
ほっかむりした顔を煤で汚した男が、慣れ慣れしく言った。よく見れば、澤井ではないか。
「澤井さん?何、やってんのさ」
「何って、大掃除に決まってんでしょ。あんた、この前、晦日まで仕事だってぼやいてたから、遠慮して頼まなかったのよ。ほら、邪魔!どいてどいて」
姉さんかぶりの真知子も、汚れ水のバケツを両手に提げている。その姿に松村がしばし見惚れていると、宮部が近づいて来て「真知子さん、似合ってるでしょ」とささやいた。
格子窓の障子紙もすべて張り替えるらしく、破られた紙のすき間から冬の陽ざしがこぼれて、ほこりの渦を描き出している。そのきらめきに、どことなく懐かしさをおぼえた松村は「よっし、いっちょやるか!」とコートと背広を脱いだ。
「和也君、久しぶり。ほら、この雑巾を使いなよ」
振り向くと、数ヶ月ぶりの水野の笑顔がこぼれていた。ほかにも、馴染みの常連客たちが掃除を手伝っているのだと教えてくれた。
「ひぃ、ふぅ、みぃ……俺を入れて、8人か。夕方には、終われそうだな」
松村がそう一人ごちた時、「おい、9人だよ」としゃがれた声が聞こえた。
ふと奥座敷をみると、鉢巻をしめた老練な男が畳を上げている。腰には藍染めの道具袋を下げ、口には太くて長い針をくわえていた。
「隣町から来てもらった畳屋の仙太郎さん。八百源の大将に紹介してもらった、名人の畳職人さんよ。私、このお店で、初めて畳替えするのよ。仙太郎さん、あまり根つめずに、一服して下さいな」
真知子の出した番茶に、仙太郎は「おっ、すまないね」と手を止めると、じっと見つめている松村に、皺だらけの顔をいっそうほころばせた。
「どうした?あっしの顔に、なにか書いてあるかい?」
「いっ、いえ……ちょっと子どもの頃、思い出しちゃって。それに、畳の匂いは、久しぶりですから」
照れくさそうに、松村は鼻先を揉んだ。
「そうだろ。いいもんだろ、本物のイグサってのはよ」
仙太郎はタバコに火を点けると、さもうまそうに、ゆっくりと吸い込んだ。そして、真新しい畳をいとしむように優しく叩いた。
「大掃除ってのはよ。ただキレイにするだけじゃ、いけねえんだ。一年の暮らしを振り返って、家を守ってくれた神様やご先祖様に感謝する習わしだ。それによ、新年になるからって、古い物をポンポン捨てちゃなんねえ。御役御免の最期まで、大切に使うこと。真知子さんは、この畳をそうやって使ってきたねぇ。一目見りゃ、分かるよ。だから、ちゃんと片付けてあげないとな。物には、“つくも神”ってのが宿るんだ。ちょいとおもしろい物を、見せてやるよ」
仙太郎はタバコをもみ消すと、古い畳を一瞬で軽々とめくり上げた。
床板には茶色く古びた新聞紙が敷きつめられ、その光景も、松村に淡い思い出を描かせた。だが、仙太郎が指差したのは、畳の裏側だった。
「ここに、五円玉が挟んであるだろ。これはな、つくも神様へのお供えだよ。畳といつまでもご縁があるようにってことだ。それに五円玉には、稲穂が書いてあるから、食いっぱぐれないようにっておまじないだな。どうだ、おもしれえだろ。今の新築住宅やマンションじゃ、こんなことはもうやらねえ。この家の前の持ち主は、なかなかどうして道理の分かった人だったみてえだな」
すると、またもや松村は、鳩が豆鉄砲を食らったような顔で見入っていた。
「そ、それ……俺が子どもの頃、彦根の実家にもあったんです。でも、畳を外したってバレるのが怖いから、親父には黙ってました……そうだったんすか」
松村の言葉が終わると、「つくも神か、いいねぇ」と感心する水野の声がした。
いつの間にか、掃除を終えた男たちも仙太郎と松村を囲んで、聞き入っていた。
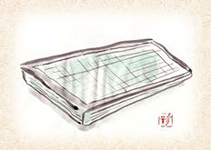 「あんた、子どもさんがいるんなら、そのご実家へ正月帰ってさ、見せてやんなよ」
「あんた、子どもさんがいるんなら、そのご実家へ正月帰ってさ、見せてやんなよ」
「はっ、はい!必ず!」
黴臭いけど、ほっとするようないぐさの匂いが、松村はやけに嬉しかった。
「ところで、和也君。あんた結局、な~んにもやってないのね?」
確かに、和也の雑巾は乾いたままで、汚れ一つさえ拭いていない。
「そんじゃぁ、仙太郎さんに授業料を払わなきゃなぁ」
冷やかす澤井に、ほかの男たちもニンマリと頷いた。
「……じゃあ、その金で、酒の神様にみんなで感謝しますかね」
松村の言葉を待っていたかのように、真知子が新酒の瓶を手にしていた。
瓶に透けて見える仙太郎の満面の笑みは、つくも神のようにも見えた。
