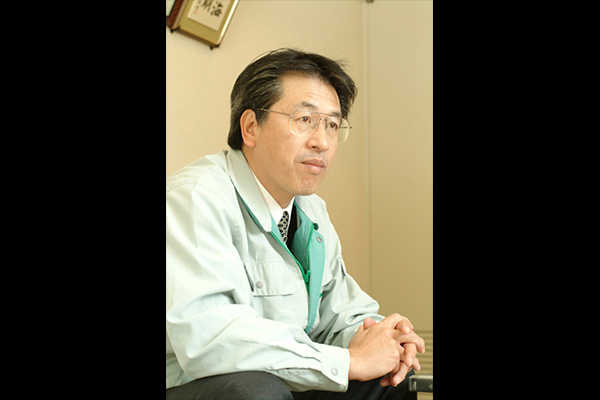たゆまぬ探究心と”土佐鶴魂”を誇りにする、蔵元と一心同体の総杜氏
林立するかのような精米機、天窓からもうもうと立ち昇る、蒸米の湯気。神聖かつ厳粛な空気が張りつめる麹室。そして、清潔でバリアフリーな作業フロア。
「圧巻のスケール……この設計と運営を、一人の杜氏に任せたのか」
千寿蔵・天平蔵の威容を前にして、筆者とカメラマンは唖然とするばかり。
施工に入る直前、廣松 社長はただ一言「請負仕事なのだから、キッチリと仕上げて下さい」と建築会社に伝えただけで、すべての采配を取締役総杜氏長の池田 健司(いけだ けんし)氏に任せたそうです。
見学後の興奮も醒めやらぬまま、池田 総杜氏長に訊ねてみました。
「あなたが造る、最高の土佐鶴の酒とは?」
即座に「それは、社長好みの酒です」の言葉が返ってきました。
廣松 社長が納得する酒を造ってこそ、杜氏冥利に尽きる。そう語る池田 総杜氏長の双眸はいぶし銀のように輝き、おだやかで明解な口元は、蔵人の束ね役としての自信に満ちています。ここにもまた、“土佐鶴魂”を矜持する人物を発見したようです。


池田 総杜氏長は、広島県豊田郡の出身。昭和17年(1942)、杜氏の里・安芸津町の農家に十人兄弟の五男として生まれました。
祖父、父親とも、農閑期には安芸津杜氏として蔵元へ出稼ぎ、一人の兄が家庭を支えるべく後を継いだのですが、病いで早逝したため、弟の健司 氏にその大役が回ってきたそうです。
「本当は、自衛隊に入りたかったのです。子どもの頃から、規律正しさや男らしさに憧れていました。部隊のジープが町を通過するたびに、思わず後を追いかけたほどでした。ですから、兄が亡くなるまではその夢を持っていました。十六歳の時に大阪で就職し、仕事のかたわら自衛隊の通信教育を受けていたのです」
兄弟に説得され自衛隊員をあきらめた健司 氏は、やる限りは杜氏の道を極めようと、酒造りをつぶさに修得できる小規模の酒蔵へ入りました。
一度は広島県竹原市の酒蔵に腰を据えたものの、昭和40年(1965)には安芸津町に発足した常備消防団に入団します。しかし、僅かな報酬しか得られず、一年後には蔵人として再出発。昭和42年(1967)広島県安芸郡の海田市(かいたいち)の酒蔵で杜氏になりました。
さらに吟醸酒を極めるため、東広島市西条で4年間、鳥取県の酒蔵で7年間を過ごし、昭和57年(1982)からは長年にわたって土佐鶴酒造の櫂棒を握っています。


高知の日本酒は一般的に「淡麗辛口」と言われますが、池田 総杜氏長は土佐鶴の酒をどう評するのでしょう。
「辛いながらも、澄んだ旨みを持つ日本酒。そして、酔い心地の良さが特長です。私はそんなに多く飲めるほうじゃないですし、粗悪な酒を口にすると頭が痛くなってしまいます。つまり、味や香りに敏感なのです。ですから清冽で味のある土佐鶴の酒は、私好みの酒でもあります」
そう語る池田 総杜氏長の酒造りのモットーは「一にも二にも“蒸し米”で決まる」とのこと。手間のかかる甑(こしき)の蒸しにこだわっています。
「ベルトコンベア式の自動蒸米機は、低精白の米を大量に扱う際には効果的なんですが、米の浸漬や吸水具合を微妙に調節する高精白の米になると納得いかない場合が多いですね。“外硬内軟(がいこうないなん)”とよく言いますが、良い蒸米を得るには、やはり甑でなければなりません。“一に麹、二に?、三に造り”とも言いますが、今はその前段階の“蒸し米”が肝心なのです」
確かに早朝の天平蔵(てんぴょうぐら)では、米が蒸し上がるたび池田 総杜氏長の「ひねり餅」が始まります。その吟味する表情に、周囲の蔵人たちは緊張を走らせていました。



麹のこだわりについては、醗酵段階の温度管理から麹蓋を使った丁寧な仕事はもちろんのこと、まずは酵母との相性にあると池田 総杜氏長は解説します。
「麹は、使う酵母によって造りを変えなければいけません。求める酒のためには、いろいろな性質の酵母から最適なものを選びますから、それと仲の良くなる麹が必要になってきます。むろん、酒母、造りも同じことです。となると、各工程ごとに集中できる環境作りも大事ですね」
なるほど、天平蔵の作業の流れは、無駄なく整備されています。酒母、初添え、仲添え、留め添えはそれぞれ別ゾーンにあるものの、その連係はスムーズ。設計段階では池田 総杜氏長自らが試行錯誤を重ね、建築家に意見・要望を述べ、頭を抱えさせたそうです。
素材と造りの素晴らしさだけでなく、蔵人へのきめ細かな配慮も、土佐鶴酒造の必須条件のようです。
仕込み水は、地元の安田川伏流水のほか、太平洋から採取する海洋深層水も使います。
海洋深層水以外は、安田町一帯をくまなく潤す水脈。つまりは魚梁瀬(やなせ)の森から下る伏流水です。おだやかな軽硬水ですが、酒質に応じて、本社と北大野に汲み上げられる7本ほどの井戸水を使い分けています。
そして酒米は、酒質にこだわるだけに山田錦が主流。地元米「吟の夢」「風鳴子(かぜなるこ)」なども早くから取り入れていますが、高知特有の暑い気候が影響し、安定した供給量が保てないそうです。それが解決すれば新たな酒質を期待できる好適米と、池田 総杜氏長は確信しています。



さて、インタビューの話題は、いよいよ「全国新酒鑑評会金賞(共催/独立行政法人酒類総合研究所・日本酒造組合中央会)」に移ります。
土佐鶴酒造の金賞36回は、昭和40年(1964)以降のレコード。それ以前の記録は行政上曖昧になっているので、実は37回以上の受賞もあり得るようです。
率直なところ大記録の秘訣は何なのでしょう? と池田 総杜氏長に訊ねてみました。
「これは、先代の杜氏が頑張られた結果です。2回、3回と続くことはよくありますが、5回以上の連続受賞となると、やはり難しいでしょうね。年々の審査も微妙に異なりますし、飛び切り斬新な酒を造るのではなく、香りと味の調和がとれた酒を造ることが肝要です。香りは優雅で、味にふくらみがあり、軽快で呑んでおいしい酒、そんなお酒なら昔からいい成績が取れたのです。言い換えれば、日頃お客様に飲んでいただく酒を出品すること。これが大変なんですよ。」
廣松 社長のポリシーは“売る酒で金賞を獲る!”こと。鑑評会用だけなら500kg前後の造りで足りるので、非常に造りやすいわけですが、土佐鶴酒造では1t仕込で30本も仕込むそうです。
この徹底した本物主義は池田 総杜氏長の望むところでもあり、社長の信念との調和が偉業を成し遂げているような気がしてなりません。
「ところで、当社には品質管理室があって、こちらの面々も高い技術を持っていますよ。仕込み水から瓶詰めした酒まで緻密に検査していますし、酒屋さんを訪問して商品管理のアドバイスもします。造った酒が、ベストの状態でお客様の口へ届くようにしているんです」
話し終えた池田 総杜氏長が視線を向けたのは、今回の取材対応を仕切る常務取締役総務部長 兼 品質管理室長の杉本 芳範 氏でした。

それでは最後に、品質管理室を覗かせていただきましょう。
プロフィール紹介が遅れましたが、杉本 品質管理室長は高知県出身の53歳。大阪大学工学部に学び、博士号を取得したプロフェッサーです。灘の大手酒造メーカーを経て、32歳の時、郷里にある土佐鶴酒造へ入社しました。先ほどの池田 総杜氏長の賛辞にもありましたが、どのような技術を誇っているのかを訊いてみました。
「プロの品質チェックは製造上の欠点を探るためのものであり、なかなか説明しにくいですから、具体的な人物を紹介しましょう。私の部下に、全国の酒造メーカーが競い合う?き酒コンテストで優勝し続け、高知県代表の審査員になった者がいます。ただ、それも仕事の延長線上の結果なのです。今は、彼が後輩たちの挑戦を応援していますよ」
そう言って、杉本 品質管理室長が紹介してくれた人物が、製造部次長の田村 隆夫 氏です。早速、インタビューを申し入れました。
田村 次長は、昭和35年(1960)土佐清水市の生まれ。
東京農業大学を卒業後、土佐鶴酒造に入社。品質管理一筋に努め、昭和63年(1988)「全国清酒協議会」の?き酒コンテストで初優勝。以来、高知県大会、四国大会進出は常連で、6度の全国大会で3度チャンピオンの座を勝ち取りました。あまりの強さに、平成6年(1994)以後は出場を遠慮してほしいとばかりに、高知県新酒鑑評会の審査員に任命されています。
その卓抜したセンスは、生まれ持ったものですか? と訊ねれば、「嗅覚は鋭い方だと思います。どこの土地へ行っても、食堂に入ると水の良し悪しがすぐに判ります。でも、味覚は先輩たちから学んだ成果です。入社当初はどれも同じ酒に思いましたが、訓練する内にまったく違うように感じ始めたのです」と、いかにも素人だったと田村 次長は答えます。 やはり、努力と修練の賜物のようです。
そして、杉本 品質管理室長は、こんな言葉で締めくくってくれました。
「ところが、廣松 社長は彼を超える感覚の持ち主なのです。『君が感じなくても、私には判るぞ』と、田村 次長と出来上がった酒を前にして問答を繰り返しています。蔵元として、少しでも納得できないところがあれば決して妥協はしてくれません。それが私たち技術屋にとって、どんなに難しい問題であっても、徹底して解決の方法を求められます」
やはりここでも、筆者は土佐鶴魂の片鱗を見ることができました。そして、廣松 社長の計り知れない力も感じたのです。
※記事中の金賞受賞年度、受賞回数、役職等は取材当時のものです。