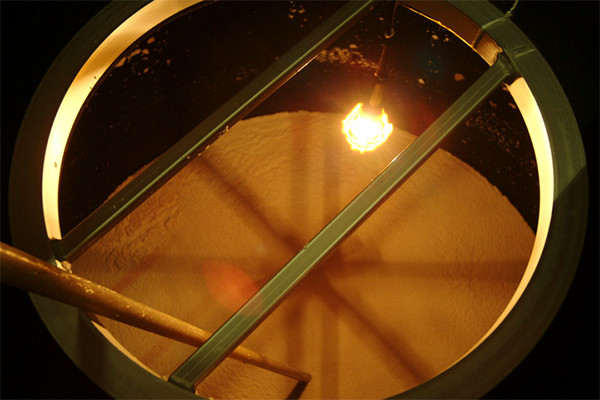小粒でもキリリとうまい!そんな北陸4醸の思いをひとつにした”革新の蔵元”
加越の銘酒“関白(かんぱく)”から思うに「これは加賀の殿様・前田 利家の僚友であった関白・豊臣 秀吉にちなんだ銘柄だろう。あの“醍醐の花見”でふるまった“加賀の菊酒”に由来するのでは」と筆者は推論していました。
「確かに、そのとおりです。でも残念ながら、その経緯を詳らかにする古い資料や文献などはまったく残っていないのです。
と申しますのも、加越は昭和36年(1961)に北陸3県の蔵元が合併し、再生した会社なのです。4つの蔵元が母体となっていて、まずは園原の“園原合資会社”。地元小松市の蔵元で、“関白”はここの銘柄でした。二つめは富山県高岡市の“開(ひらき)酒造”で、現在は卸し専門の会社になっています。さらに、私の実家である福井市の“帝関(ていせき)酒造”。そして、同じく福井市の福山酒造でした」
まだまだ酒蔵としては新しくて、伝統・文化とはかけ離れていますと“加越”の創業を語ってくれたのは、代表取締役社長の山田 英貴(やまだひでき)氏。なるほど、神武景気・岩戸景気後の清酒ブームに乗ろうと、生き残りをかけた小さな蔵元が提携したということでしょう。
さすれば、山田社長の実家には合併以前の歴史があったはず。そこで山田社長だけでなく、同郷出身の旧友と聞いた営業部長の桑嶋 睦夫(くわじま むつお)氏にも同席してもらい、二人の記憶を辿ってもらうことにしました。



山田社長の実家“帝関酒造”は、米どころ福井県北部の桑原村(現在の福井県坂井郡金津町)で創業。四代前に、庄屋の家系から起こしたものだそうです。いわゆる余剰米を使った酒造りだったのでしょう。
今年50歳を越える山田社長の曽祖父の代から始めたということは、おそらく明治時代後半の創業となります。つまりは、加越まで累すれば100年前後の歴史を紡いでいるわけです。
祖父の代には地元の村長も務めましたが、昭和26年(1951)の福井地震により蔵屋敷が崩壊。罹災した村も壊滅状態となったため、福井市内に移り、改めて蔵元を始めています。
山田社長が幼少の頃には、当時の屋敷跡が田畑となって金津町に残っていました。その規模はなかなかのもので、大正13年(1924)の国税局石高表によると200~300石規模だったそうです。
以後、昭和30年代半ばまでは順風な操業でしたが、北陸にも徐々に灘・伏見の大手メーカー酒が進出していました。
「ある日、親父たち地元の酒蔵のオーナーが全員招集されました。灘の大手メーカーから、『お宅で造っている酒を買い上げてあげるよ』と発表があったのですが、ただし価格はかなりシビアなものでした。それでも、低迷していた北陸の酒蔵のほとんどが、渡りに船だったようです」
山田社長の父親は大手との取引を調整しながら商いを続けましたが、結論的に前述の合併策へと転じたのです。



そして、話しは昭和36年の加越誕生へとつながります。
当時、国税庁の近代化政策として合併が矢継ぎ早に進められ、全国の地酒の蔵元は行政・税制上の優遇措置を利用しようと、次々に参入しました。
同様な形で、当初の加越は“園原合資会社”、“開酒造”、“帝関酒造”の3社の共同瓶詰め工場として始まったのです。
3社で造った酒を一箇所に集めて瓶詰めし、そして同時に出荷する。
効率性を高めた合併策は功を奏し、昭和38年(1963)には造りも集約。この時に福山酒造が参画し、“加越酒造有限会社”が呱呱の声を上げたのです。
この中心となったのが、園原合資会社社長の園原 忠平(そのはらちゅうべい)と帝関酒造社長の山田 英男(やまだひでお/現・山田社長の父)でした。
「当時の銘柄は、開酒造が“菊日本”、園原合資会社が“関白”、帝関酒造は“帝関”、そして福山酒造が“旭空”でした。
法人化した直後、NHKの大河ドラマで“太閤記”が放送され、“関白”が爆発的にヒットしたんです。福井県下のひと月だけで、600石も売れました。それを機に、銘柄を“関白”に統一したわけです」
北陸を中心に大ブレイクを始めた“関白”に、4社それぞれが卸会社を設立したほどでした。


そして地酒ブームとなった昭和50年代、加越は淡麗辛口の本場として“加賀吟醸”をリリースします。
切れのよい軽やかな辛口、ほのかに華やいだ香りに加え、まろみもあると好評でした。
このように特定名称酒市場においても上々のシェアーをキープし、平成元年(1988)には各自の卸会社を統合。製造販売を一貫した“株式会社加越”がここに誕生したわけです。
以来、“加賀ノ月”シリーズや低アルコール酒“レディーアクア”などを開発し、女性加越ファンの増加も顕著なようです。
その仕掛け人とも言える人物が、山田社長と縁のある桑嶋営業部長でした。
「私は、他業界のマーケッターから日本酒業界に入った“外様”なんですよ。実は、親父が山田の父親と“竹馬の友”の間柄でして、昭和58年頃に商事会社を辞めてプラプラしていた私のことを二人で話しを付けちゃって、無理やり放り込まれたんです」
そう苦笑いする桑嶋部長ですが、加越の商品企画や市場戦略については独自の見識と洞察がキラリと光っているようです。
昭和58年(1983)大手メーカーでの修行を終えた山田が加越に入社し、その翌年には桑嶋部長も入社しています。製造部門をリードする社長との息もピッタリのようで、偶然とは思えない関係を感じます。
今後の加越の躍進を握っているようです。
経営陣のフレッシュな感覚とチャレンジスピリッツに、20名ほどの社員たちの間にも明朗闊達な雰囲気があふれていました。再生と革新を繰り返してきた加越の新しい酒造りに期待が募ります。今宵は、地元の名湯「粟津温泉」にひたりつつ、“加賀の菊酒・関白”を味わうことにしましょう。