
初代・田村 勘次郎の感涙のしずく、幻の酒「嘉泉」
威風堂々たる、漆喰の白壁。こんもりとした林は鳥の囀りに満ちていて、その奥には重厚な土蔵の姿も垣間見えます。
広大な屋敷の中にめぐらされた田村分水の水際を歩けば、遥かな江戸時代の造り酒屋にタイムスリップしたような気分です。
これぞ、まさに酒蔵。惚れ惚れとしてしまう田村酒造場の佇まいに、かつての身分格式を察することは難しくありません。
「当社にいらっしゃった皆様は、一歩足を踏み入れると凜とした空気に身が引き締まる思いがするとおっしゃいます。また、手入れも行き届いてチリひとつない清潔さと、お褒めの言葉も頂きますよ。この江戸時代の当家の風情を維持していくことも、私の大事な務めです」
そう言って、筆者を案内してくれたのが、田村家十六代目の田村 半十郎(たむら はんじゅうろう)社長。精悍かつスマートな風貌に、穏やかな口調と温和な人となり。滲み出る雰囲気に、名門・田村家の血筋を実感します。
「創業者は、九代目の勘次郎(かんじろう)です。当家は、代々、福生村一帯の名主でしたので、徳川幕府から自治的な任務も仰せつかっていました。当時の福生村は天領でしてね。ここも含めまして、幕府直轄領を支配する代官所が静岡県の韮山にあったのですが、そこの代官様・江川 太郎左衛門も、当家をしばしば訪れたそうです。それと、当家の代がはっきり断言できますのは、先祖の代ごとに墓碑が別々にあるのです。通常ですと一つの墓で、お寺様の過去帳を頼るしかないのですが、田村家では、それぞれの墓がズラリと並んでいます。名前も、いまだに世襲していますよ。十兵衛と半十郎という2つの名を代々継承してきました。」
さすがに、大庄屋ならではの伝承話。田村家は、いわゆる「肝煎り庄屋」と呼ばれる身分だったようです。
聞けば、現在も田村家は福生一帯の土地を所有しているとのこと。その広さは、なんと数十キロ先にまで及んでいるそうです。


さて、蔵元初代の田村 勘次郎が酒造りを始めたのは、文政5年(1822)。それ以前の田村家はいわゆる大庄屋で、年貢取立ての元締め役を御上から任され、用水灌漑などを指導しながら新田開発に励んだようです。
つまりは、年貢の余剰米を使った酒造りを許されたわけです。おそらくは、勘次郎は代官所から酒株を買い入れ、年間50石から100石ほどの小規模な酒造りから始めたのでしょう。
創業した時代を顧みれば、まさに灘の下り酒が一世風靡した頃ですが、それは、あくまで新酒が届く春先から初夏までの風潮でした。
「蜘蛛の糸巻(くものいとまき)」という古文書を見ると、当時の江戸人口は128万人と記されています。超人口過密都市となったエリアは、今の江東区と中央区の一部、台東区・墨田区で、やはり廻船が着き、艀が行き来する隅田川の周辺に広がっていたのです。
巨大な江戸の酒消費に、灘の酒といえども底を突きます。そして、福生や多摩の地酒が江戸に運ばれるのは、灘の酒が品切れとなる初夏の頃と記されています。
つまり勘次郎の造った酒は、平常は多摩地域の需要に応えながらも、江戸庶民に「初夏の酒」や「夏越しの酒」として愛飲されたにちがいありません。
そんな彼の最初の試練は、仕込み水を探し当てることでした。
すでに田村分水を引き入れているほどですから、水には苦労しないだろうと思いきや、屋敷内のいたるところに井戸を掘っても、最適の仕込み水が見つかりません。
苦労の甲斐あってようやく掘り当てた水は、稀に見る中硬水で、穏やかな発酵を促したのでした。この水の発見を喜んだ勘次郎は「良き泉!喜ぶべき泉!」と感涙し、酒名を「嘉泉(かせん)」と命名したのです。



「大寳惠(おぼえ)と書かれた大福帳が、当家に残っています。これが、嘉泉の創業の証である古文書です。裏表紙には、田村 勘次郎の揮毫があります」
田村 専務の手にする色焼けた大福帳が、創業200年近い年輪をひしひしと感じさせます。その分厚い帳面は、往時の田村酒造場の繁盛ぶりを語るかのようです。
創業後、嘉泉によって着々と成長した田村家は、明治中期までに武州一帯(多摩地区、神奈川県、埼玉県の一部)に24の店蔵(特約蔵)を持つ大酒屋となりました。
経営面、技術面において各蔵を指導する本店的役割も担っていて、これらの蔵の中には年産4000石という蔵もあったそうですが、嘉泉は1500石前後という造り高を頑なまでに維持しました。毎年9月の決算期には、各店蔵の旦那衆が田村家の奥座敷に集い、その年の成績順に床柱を背負い、その労を田村家当主からねぎらわれたそうです。
これは初代・勘次郎からの家訓である「丁寧に造って丁寧に売る」の精神を守り通した結果です。その精神は代々の当主に受け継がれ、嘉泉の中に醸され続けたのです。
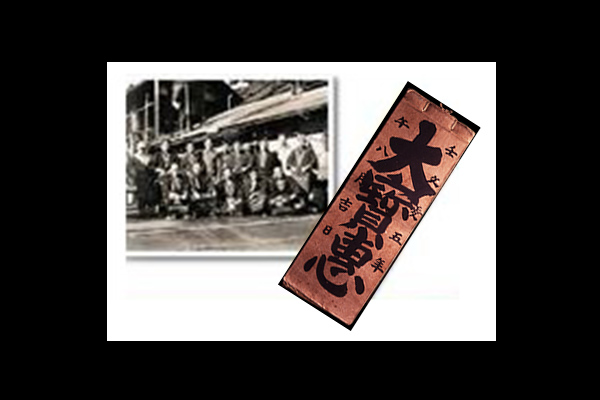
昭和の戦時統制を田村酒造場は乗り切ると、いよいよ清酒ブームを迎えます。しかし、戦中・戦後の三増酒の傾向も影響してか、当時は糖を添加した甘い酒がもてはやされ、嘉泉の特長である辛い酒は売りにくい時代でした。
そこで、杜氏は思い余って十五代目当主・田村半十郎に「いっそ、甘い酒に切り替えてみては」と進言しました。
しかし、半十郎はきっぱりと突っぱねたそうです。
「ばか、言うんじゃねえ。昔から酒呑みは、辛党と言うじゃねえか。甘党には、羊羹をやればいいや」このひと声で、嘉泉は左顧右眄することなく、初代から継承する福生の銘酒としての誉れを貫いていきます。そして昭和48年(1973)、機を見るに敏な半十郎は、清酒の大きなうねりがやって来ることを察知して、前代未聞の試みに着手しました。
「抜群の高精米を誇る、本醸造を造る。それを、二級酒として販売するんだ」
半十郎の大英断によって誕生したのが、今日、絶賛されている「特別本醸造まぼろしの酒嘉泉」でした。以降、嘉泉といえば「まぼろし」が、その代名詞として全国の日本酒ファンに伝播しているのです。
そして今、アルコール市場の大変革期を迎え、田村酒造場は新たな試みや製品を着々と開発しています。
そのリーダーとなったのが、十六代目当主・田村 半十郎なのです。
「丁寧に造って、丁寧に売る」の家訓を守りつつ、新しい嘉泉を目指すその理念と手腕を、次なる蔵主紹介で、じっくりインタビューすることとしましょう。







