鹿児島で梅のつぼみがふくらんだとニュースが流れる中、日比谷公園や新宿御苑では赤い椿がほころび、寒の戻りが続いている。東京の春はまだ遠いが、そんな花々を銘柄に使う小さな酒樽が、ポンバル太郎のカウンターに並んでいた。
色とりどりな十数種の菰かぶりに、高野あすかがウットリしている。
「桜、梅、牡丹、椿、菊……これだけ揃うと、ミニ樽でも風情があるわ」
あすかの声に、平 仁兵衛も樽酒を飲みながら目を細めている。
すべて新酒が入った四合の菰樽だが、端っこの一つには銘柄がなく、菰に鯛と桜の絵が描かれていた。樽の前には今しがたやって来た新顔の年輩客が座り、太郎にその酒を注文した。鯛の絵を嬉しげに見つめる男は、その菰樽に思い入れがあるようだった。
スマートフォンで順に菰樽を撮っていたジョージが、金色の眉をしかめた。
「ホワイ? どうして、これには銘柄が書いてないのですか? 絵だけでは商品名が分からないじゃないですか?」
「へへぇ、この絵文字が日本人の粋ってもんよ。魚は鯛だ、英語で言えばレッドスナッパーてえんだろ。そして、鯛を囲んでるのは桜の花。日本じゃ鯛は春を呼ぶ魚で、桜鯛とも呼ばれる。それでもって、この酒の銘柄は“春乃鯛”ってわけだ」
カウンター席の真ん中に座る銀平が酒の入った枡をなめながら、赤ら顔で答えた。三杯目の樽酒に、舌が回っていた。その声にテーブル席の男たちが「なるほどね」とつぶやくと、あすかが銀平をたしなめた。
「残念ながら、それだけじゃないのよねぇ。菰樽の絵は、字が読めない江戸時代の庶民たちに分かりやすい意匠だったの。昔はこの絵柄を塗るための木型を、蔵人が使ってたのよ。それに私、この春乃鯛の菰かぶりはお気に入りなの」
あすかは、今のミニサイズの菰樽は容器メーカーで一貫生産されているが、二斗や四斗といった大樽で酒を売った江戸時代は手練れの蔵人が絵を塗って素早く菰を巻き、その技を若手に引き継いだと言い足した。
ジョージだけでなく、テーブル席の客たちもあすかの解説に感心すると、銀平が負け惜しみをもらした。
「ちっ! 蔵元の娘が言うんじゃあ仕方ねえな」
銀平の声に、ふいに新顔の男は菰樽を指さした。あすかを蔵元の娘と知って、男はどことなく嬉しげだった。
「こないして絵柄や文字をつけるのを、“印菰(しるしこも)て言います」
その関西弁に全員が注目すると、男は太郎が置いた枡酒をひと口飲み、訥々と話した。
「そもそも菰かぶりは、上方の灘から樽廻船で杉の樽を運ぶのに、傷がつかへんように藁を巻いたのが始まりですわ。編み針たいな道具を使って、四つの太さの縄で菰を巻く。糊や釘はいっさい使いまへん。どの大きさの樽でも作り方は同じで、小さいからちゅうても簡単やない」
男の口の動きに、太い指が伴っていた。それを見つめるあすかが、懐かしげなまなざしで言った。
「……その手つき、菰かぶりの男結びの動きですね。ひょっとして、蔵人さんだったのですか?」
「ああ、灘の蔵元に四十年勤めましてん。実は、この春乃鯛ですわ。残念ながら、わしが退職してからは蔵が小さなってもて、教えた弟子はもういてへん。そやから菰を巻くのは、よその蔵元に頼んでる。何とも、情けない話しや」
男は十年前に蔵人を辞めてから妻に先立たれ、東京に暮らす長男夫婦に呼ばれてこの近所に暮らしていると言った。春乃鯛の絵柄を見つめる男のため息が、木枡の酒に波紋を描いた。
すると、あすかは鳩が豆鉄砲を食らったような顔で叫んだ。
「ええっ! 春乃鯛にいらしたって……じゃあ、蔵元の狩野家の娘だった美津子を御存じですか?」
「ああ、若い頃のわしには憧れのお嬢さんやった。けど何であんた、美津子さんのことを?そう言えば、あんたよう似てるな。もしや、あんた……」
「狩野美津子は、私の母です。亡くなった高野美津子です!」
興奮するあすかを藪にらみする男の表情が、大きく崩れた。
「おお! あんた、相馬の高酒造さんのあすかちゃんか。わしや、坂本元太郎や。あんた、小学生の冬休みに春乃鯛へ遊びに来てて、わしが菰かぶりを巻くのを手伝うてくれたやろ……美津子さんは残念なことやったなぁ」
坂本は驚きを露わにしながらも、東北大震災後の美津子の横死を悼んだ。偶然の出逢いに、あすかは信じられないといった顔で、まだ絶句していた。
思わぬ展開にテーブル席の客たちが顔を見合わせると、太郎が坂本に言った。
「だから、春乃鯛に思い入れがあるわけですか。坂本さん、あすかちゃんがいることで、ここのお客さんたちは幸せな気分になれるんですよ。本物の日本酒文化を知ることができるのは、蔵元の娘だった彼女のおかげです」
太郎は春乃鯛の樽から酒を柄杓ですくって、坂本の枡に注いだ。酒の中に、坂本の悲しみとも諦めともつかない表情が揺れた。
「そうでっか。美津子さんも喜んでるやろ……あすかちゃん、この春乃鯛の桜はあんたのお母ちゃんが描いたんやで。真ん中の鯛の絵は江戸時代から引き継がれてたもんやけど、あんたのお祖父さんやった蔵元の狩野光一社長は、美津子さんが高校時代に描いた桜を気に入って、その塗り型を作った。それ以来、わしはずっと美津子さんの桜を菰かぶりに塗ってたんや……ほんまに、ほころぶソメイヨシノみたいに美しい人やったなぁ」
遠い目をする坂本に、太郎は美津子への好意を感じた。
あすかは坂本の隣に席を移すと、菰かぶりの桜を指でなぞりながら言った。
「私、桜の絵のことは知りませんでした……だけど母は、高酒造の蔵に咲いてた桜が大好きだった。もうすぐ三月十一日。きっと母が、坂本さんに逢わせてくれたんじゃないかな」
気をきかせた太郎が厨房に入ると、平は木枡を手にしてテーブル席の男たちと相席した。
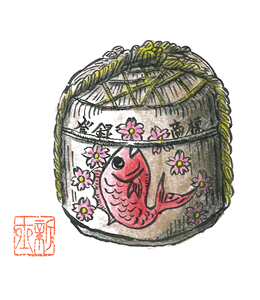
瞳を潤ませるあすかが、坂本の横顔につぶやいた。
「坂本さん、小さくなっちゃったみたい。あの時は、とっても体の大きな蔵人さんだと思ってたのに……いい思い出って、ずっと変わらないものですね」
坂本は小さく頷くと、春乃鯛の絵を指でなぞった。
「菰かぶりもこないに小そうなったけど、美津子さんの桜はキレイなまま、何も変わってへんよ」
しんみりとするカウンター席に、銀平のぼやきが響いた。
「まったくよ。あすかにゃ、かなわねえなぁ。こんな再会、小説より奇なりじゃねえかよ」
銀平の思いやりに泣き笑いするあすかが、強がりを返した。
「そうでしょ……私って、大した女でしょ。だって、蔵元の娘なんだもん」
あすかの瞳の中で、菰かぶりの鯛と桜が踊っているようだった。
