つるべ落としの言葉がふさわしくなった夕陽が、駅に向かうビジネスマンたちの顔を染めている。風もめっきり涼しくなって、ポンバル太郎の扉が開くたび、冷えた空気が茜色の光とともに洩れ入った。
ただ、客たちの動きはいつもとちがい、玄関先の本日のおすすめメニューに足を止めると、口々に「珍しいね」とつぶやいた。
“鹿肉、山鳩など、ジビエ料理あります”と書かれたホワイトボードに、今しがた入店した右近龍二もしばし目を止めていた。
「太郎さん、どうしたんすか? 去年、猪鍋はここで頂きましたけど、こんなに野趣あふれるジビエって、初めてじゃないかな」
カウンターへ座る龍二の声に、テーブル席の見知った女性グループが頷いていた。彼女たちはジビエ好きなのか、すでに太郎へ鹿肉のほうば味噌焼きを注文していた。
厨房で焼けるほうば味噌の香りが龍二の鼻先をくすぐった時、カウンターの隅に座る新顔の髭面男が口を開いた。がっしりとした体躯で、右手にぐい呑み盃を持ち、前に置いた一升瓶は岐阜の銘酒だった。
「よかったら雉肉も持って来ましたから、食べてみてください」
くたびれたジーンズに地味なブルゾンの格好は垢抜けず、いかにも山出しの印象を感じさせた。ただ、三十代後半とおぼしき男の口調に訛りはなく、ふっと笑った面差しに龍二は地方人にありがちな緊張を感じなかった。
「あなたがジビエ食材を……体つきも立派だし、マジで猟師さんですか?」
「いやいや。まあ、猟師の端くれってか、みようみまねですが、簡単な罠ぐらいは仕掛けられます」
謙遜する男のうなじを焦がした日焼けの痕が、龍二に本職の猟師らしさを伝えた。
ほうば味噌の濃い香りとともに、厨房から太郎が出て来た。
「塚田さんは、茅葺職人と農家を兼ねてるんだよ。かつてはマチコの常連さんだったけど、奥飛騨が気に入って移り住んじまったのさ。それで毎年、飛騨で狩猟解禁になると、真知子さんへジビエを届けてる。今夜の肉は、そのお裾分けってわけだ」
男が照れくさげに小さく会釈すると、鹿肉の皿を前にしたテーブル席の女性たちは「ありがとうございます」と礼を返した。
龍二は、いつか太郎とマチコを訪れた際、真知子が語った塚田らしき人物のことを思い出した。限界集落の高齢者を心配し、奥飛騨でゆっくりと生きていく道を選んだ男だった。
東京にいた頃は脆くて流されやすい人柄だったが、家族とともに里村に暮らす内、心身の隅々に山の神を宿しているみたいになったと聞いた。
「あのう……この鹿肉のほうば味噌焼きには、どんなお酒が合うのか、教えてもらえませんか?」
テーブルの女性の質問が、龍二の追憶をさえぎった。
塚田の答えに、龍二も聞き耳を立てた。
「もちろん、今飲んでいるような岐阜の地酒をすすめますけど、しいて言えば、吟醸造りや純米酒ではなく、辛口でコクのある本醸造か普通酒が僕は好きですよ。野生の獣は丁寧に血抜きして、下ごしらえをしても、匂いが若干残ります。だから、それを抑えるためにも、飛騨では味の濃いほうば味噌や八丁味噌を使います。これには、ずっと昔から、地元のドッシリとした並み酒やどぶろくを合わせていたそうです。猟師仲間には、“またぎ酒”ってのもあります」
訊ねた女性たちよりも、酒のプロである太郎に聞かせるのを意識した答えだと龍二は思った。
「それは、かなり甘辛くって濃い酒ってことか……なるほど、その酒なら、ほうば味噌にも負けねえな」
その時、扉の鳴子が高い音を響かせた。勢いよく入って来た高野あすかが、ワイン瓶を振りながら興奮していた。
「ビックリ! どうして、ポンバル太郎でジビエなのぉ~? 私、デパートでハンガリーの貴腐ワイン買っちゃったの。これって、よく言われるデザートよりも、ジビエに合うって評判なのよ」
それを聞いたテーブル席の女性たちが、顔色を変えた。彼女たちはワインつうでもあるらしく、その一人が
「ハンガリーなら、トカイワインですか?」
とあすかの右手に瞳を凝らした。そしてトカイワインは、貴腐ワインの王様と呼ばれ、濃厚なソースのジビエ料理にふさわしい一本だと言った。
途端に、あすかは頷きながら、鹿肉のほうば味噌焼きの皿に視線を止めた。
「そうなのよね。ねぇ、太郎さん。一杯だけ、彼女たちにこれを飲ませてあげていいかな? これ、鹿肉でしょ? 絶対に、トカイワインが合うと思うの」
その場の事情を知らないあすかは太郎だけでなく、カウンター席の龍二へもおもねって同意を求めた。
「悪いが、そいつぁ無理だ。てえことよりも、塚田さん……さっきの答えの続き、教えてもらえませんか」
太郎がカウンターの隅へ送った視線でようやく塚田の存在に気づいたあすかは、手にする貴腐ワインのボトルのように赤面した。
「実は、またぎ酒を持って来ました」
塚田は体をかがめて、足元に置いたリュックを開いた。
武骨な手で新聞紙にくるんだ塊りを取り出すと、その中から、レッテルを貼っていない茶色の四合瓶が現れた。
「貴腐ワインは、貴腐ブドウから作ったワインですよね。糖度が高くって、深い香りとコクのある味わいです。その味は、気象条件によってブドウ表面にボトリティスシネレア菌が繁殖し、太陽を浴びると水分が蒸発して、甘味がさらに凝縮します。その糖分が、貴腐ワインの深い甘さとコクを造るんです。このまたぎ酒も同じように甘味とコクが深くなっていますが、方法はちがって、つぎ足しによって熟成した酒です」
あすかと女性たちが不審げな顔を見合わせると、考え込んでいた龍二が顔を上げた。
「それって、貴醸酒(きじょうしゅ)ですか?」
太郎が反応して、口を開いた。
「いや、そうじゃない。貴醸酒は、酒を仕込む水の代わりに酒を使うんだ。塚田さんのまたぎ酒は熟成する酒に新たな酒を継ぎ足していくことで、深みと香りが増していく独特のブレンド酒だ。しかし、山小屋に保存してちゃ、途中でヒネちまうんじゃねえか?」
それを聞き流すかのように、塚田は四合瓶の栓を開けるとぐい?みに注いだ。薄い黄金色の酒が、おだやかな香りを漂わせた。盃に揺れる酒には、とろみもあるようだった。
塚田は、太郎の懸念にごもっともと目で答えながら
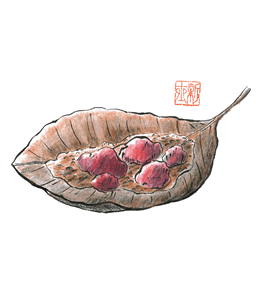 「確かに、何の変哲もないまたぎの山小屋には冷蔵庫もありませんが、奥飛騨の冬の寒さは半端じゃありません。シンシンと降る雪の中ですから、小屋の中でゆっくりと冷温で熟成します。それに、山の神様も醸してくれますしね」
「確かに、何の変哲もないまたぎの山小屋には冷蔵庫もありませんが、奥飛騨の冬の寒さは半端じゃありません。シンシンと降る雪の中ですから、小屋の中でゆっくりと冷温で熟成します。それに、山の神様も醸してくれますしね」
とぐい?みを手渡した。
「またぎは、これを囲炉裏で回し飲みします」
塚田の声に、太郎から龍二へ、そしてあすか、テーブル席の女性たちへと盃が回った。
誰もが不衛生などと嫌がらず、またぎ酒の濃厚な味わいに郷愁を感じた。
「こりゃ、ジビエってより、またぎ飯だなぁ」
カウンター席から立ち上がった太郎が、玄関のメニューを書き換えた。
それを見つめる塚田の赤らんだ笑顔に、龍二は山の神が宿っているように見えた。
