秋の気配をまとった冷たい小糠雨が、鮫皮を張った中之島 哲男の雪駄を濡らしている。
渋い海老茶色の番傘をたたんだ中之島は、和服の袂から取り出した手拭いで少し雨を吸った裾を拭くと、ポンバル太郎の玄関を静かに開けた。そして、左手に提げている籐かごを振りながら太郎に言った。
「おまっとうさん。今年も持って来たでぇ、但馬の松茸や」
その声にカウンター席で並ぶ火野銀平と手越マリが、一瞬、小躍りするように振り返った。隅の席に座っている平 仁兵衛も、純米酒をなめる口元が嬉しげだった。
「うひょう! 待ってました。この日ばかりは、中之島の師匠が神様に見えちまうぜ」
間髪入れずに叫ぶ銀平の声に太郎は呆れたが、マリも合掌して
「毎年、この日にたまたま来ている私は運がよかばい!」
とほくそ笑んだ。
松茸と聞いたテーブル席の客たちも、ほろ酔いの顔色を変えた。
「な~んや、銀ちゃん。ほなら、いつものわしは、どないやねん? さしずめ、口うるさいジジイちゅうとこか? 今年はあいにくと松茸の数が少ないもんで、あんたには当たりがないかもなぁ」
「ちょっ、ちょっと待った! ほら、剣! ボウッとしてねえで、松茸様をお預かりしろってんだよ」
「なんだよ、さっきから松茸!松茸! って……これって、そんなに旨いかなぁ?」
店を手伝う剣が、松茸と緑色の松の小枝を包んだ籐かごを中之島から受け取りながら、小首をかしげた。小学生の剣にしてみれば松茸はとりわけ美味しい物ではなく、贅沢な大人のツマミとしか思えなかった。
むしろ、あのキノコっぽい匂いが鼻について、酒の香りの邪魔をするような気がしていた。
素っ気ない態度の剣に、平が訊ねた。
「剣君、松茸は嫌いかな? 珍しいですねぇ」
「平先生は、大好きなんでしょ。去年もすごく喜んでたし、先生から頂いた器にも松茸専用があるって、父ちゃんから聞きました」
「ふむ、あれはあなたのお母さんの紹介で、但馬にある松茸山で採った土で焼いた陶器です。松茸も、さぞ喜んでくれる気がしましてね。素朴な色と焼き具合が、焼き松茸に似合うんですよ」
平が剣に語る口調は子ども相手と軽んじない、大人として扱う響きがあった。
「ふ~ん……でも今日の僕には、松茸よりも待ってたご馳走があるんです。中之島のお師匠さん、約束した“ぜいたく煮”を持って来てくれましたか?」
「はいな~! ここに、おまっせ。しかし、五年も前にハルちゃんが言うてたこと、よう覚えとったなぁ。太郎ちゃん、剣ちゃんはほんまに、居酒屋の申し子みたいなやっちゃで」
しかし、炭火で松茸を炙り始めた太郎はキョトンとしている。
事情を知らないらしい太郎が剣に問いただすような視線を投げると、中之島は苦笑いとも困り顔ともつかない表情を浮かべた。
厨房から芳わしい焼き松茸の香りが漂ったが、銀平は中之島の言葉に気を奪われていた。
「五年前? ……剣が、まだ六歳の頃じゃねえか。師匠、ぜいたく煮ってなんすか? ハルちゃんがらみの物なら、やけに気になりますよ。きっと、高っけぇ食材を使った煮物なんでしょう?」
すると、剣と中之島が視線を合わせて笑った。
「まあ、昔ながらの京都の郷土料理。おばんざいの一つや。けど、ぜいたく煮はちょっとちがうで」
中之島が、大きなタッパウェアーを風呂敷から取り出した。蓋を開けると、なんの変哲もない、薄く切った大根と刻み唐辛子の入った煮物が現れた。
眉をしかめて、銀平が言った。
「な、なんだよ。これが、ぜいたく煮かよ? ただの大根の煮物じゃねえか」
「と思うでしょ? ところが、ちがうんだよ」
今にもよだれを垂らしそうな剣のその声につられ、太郎が焼きあがった松茸を手にして、ぜいたく煮を覗き込んだ。
「太郎ちゃん。五年前にハルちゃんが剣ちゃんを連れて、大阪へ遊びに来たことがあったやろ。あの時、わしが日帰りで京都の大原へ二人を連れ出し、松茸山の持ち主の家で、これをご馳走になったんや。ハルちゃんは、いっぺんで気に入り、しつこく作り方を訊いてた。それを剣ちゃんは、しっかり憶えてたんや」
そう打ち明けた中之島が手作りのぜいたく煮を小皿に取り分けると、平が小さく手を合わせて箸を伸ばした。
そしてひと口噛んだ途端、感嘆の声を上げた。
「むうっ! こりゃあイイ! 抜群の酒の肴だ。うん、あったかいご飯にも最高でしょう」
平が剣に向かって、親指を立てた。それは、亡きハル子への称賛の気持ちでもあった。
ぜいたく煮をつまむ面々は、盃を傾けながら愉悦の表情を見せた。
ポリポリと小さな噛み音を立てる太郎の顔を見つめながら、剣が語った。
「……ぜいたく煮は古漬けになったタクアンを一晩塩抜きしてから、じっくりと炊き上げるんだ。京都では“気出し”って呼ぶって、母ちゃんは言ってた。生の大根を煮るのとは、まったくちがう食感と風味がある。名前とは反対にちっとも贅沢じゃないけど、手間ひまをかけた京のおばんざいだって……私の求める酒の肴にピッタリって、言ってたよ」
無言で噛みしめている太郎に、中之島がつぶやいた。
「京都みやげの“千枚漬け”や“すぐき”は、高級な漬物や。けど一方で、こんな家庭料理もある。見た目はピカピカの観光地の京都やけど、一歩、町の暮らしの中に入ったら、素朴で知恵のある食文化がぎょうさん残ってる。ハルちゃんは、そんな京都が大好きやったなぁ。ぜいたく煮はいつか自分で……この店が出来てから作ると言うてたのを、わしもすっかり忘れてた。けど、剣ちゃんはずっと憶えとって、先週、わしがここへ来た時、唐突に頼まれたんや」
「高級品の松茸と古漬けのたくあん、まったく対照的な存在ですねぇ。でも、表看板が本物の町には、裏側にも本物が隠れているんですねぇ」
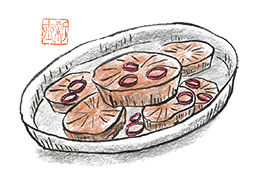
松茸とぜいたく煮を見比べる平が、穏やかな目元でつぶやいた。
カウンターに置かれた焼き松茸の香りが薄れ、冷めかけていたが、誰も口をつけなかった。
「おっ、おう。松茸も忘れちゃいけねぇだろ」
食い意地を出す銀平が箸を伸ばそうとすると、マリが口を開いた。
「銀ちゃん。この空気ば、読めんとね。あんた、人間の中身が古漬けになっとると? 一度、京都に行って、気出ししてもらえばよかよ」
とたんに張り詰めていた雰囲気がほどけて、店内に笑いが巻き起こっていた。
その隅で、ようやく目尻をほころばせた太郎が、剣の前にしゃがんで、ぜいたく煮の作り方を聞き出していた。
