雲間から覗いた満月の明かりが、東京の下町を照らしている。
ひんやりとした秋の夜気に、ポンバル太郎や周辺の居酒屋から立ち昇る湯気の白い色も日ごとに濃くなっている。
「今夜は冷えるね。こりゃ、熱燗の方がよさげだな」
杉の扉を開けて入って来た菱田祥一が肩を震わせながら、連れの男に笑った。
カウンターで高野あすかの相手をしていた太郎がその声に顔を上げると、菱田の連れは金髪の外国人男性だった。
「おっ、菱田らしいお客様だな。ウェルカム トウ ポンバル太郎」
初めて耳にする太郎の英語の上手な発音に、あすかは思わず目を丸めながら菱田に振り向くと、おぼつかない自分の英語力を呼び起こそうとして焦った。
ところが、金髪の男性の口からは流暢な日本語がすべり出た。
「今晩は。初めまして、ジョージです」
「彼は、ニューヨークで知り合った雑誌社の記者でね。日本の食文化と日本酒について、今月いっぱい取材中なんだ。ポンバル太郎の話しをしたら、与和瀬に逢いたいって頼まれてね」
菱田が紹介するとジョージは太郎だけでなく、あすかにも澄んだ青い瞳を向けてほほ笑んだ。まだ酒を飲んでいないあすかが、いつになく、恥らうように頬を赤く染めて会釈した。
「それは、光栄だな。じゃあ、まずは俺よりも日本酒の蔵元の娘さんに取材すればいいぜ」
そう言って太郎が、戸惑うあすかの隣の席にジョージと菱田を並ばせた時、玄関から聞き慣れた声が飛んで来た。
「待った、待ったぁ! 俺を忘れちゃいけねえよ、菱田さん。日本の魚のことなら俺が教えるぜ」
いい雰囲気をぶち壊す銀平に、菱田と太郎は目を見合わせて
「まったく、タイミングの悪い奴だな」
と苦笑したが、ジョージは銀平の声には反応せず、あすかの手元を凝視していた。
「そのパープルな……紫色の食べ物は、なんですか?」
ジョージの指さす先には、白磁の小鉢に盛られた紫色のおひたしがあった。
あすかはどう表現すればいいのか悩んだが、はっとした顔つきになって取材用のノートを取り出した。それがジョージを逆取材するチャンスと思った行動と太郎は気づいて、ただでは転ばないあすかに感心した。
「これ、“かきのもと”って言います。菊の花のおひたし。菊って英語で言うと……」
「クリサンセマム(chrysanthemum)。ちょっと日本人には、覚えにくい英語ですね」
ジョージがあすかをフォローすると、太郎もなるほどといった顔つきで頷いた。
「それにしてもファンタスティック(素敵)で、アメイジング(不思議)です。花を日本酒の肴にするのですか?」
ジョージの高まる声に、テーブル席の客たちがカウンター席を見つめた。そして、かきのもとの小鉢を遠目に眺めた。
「けどよ、かきのもとって東京じゃ、食べないだろ。太郎さん、どうして今夜はメニューにあるんだよ?」
ジョージの高い鼻梁に見惚れていた銀平が、ふいに太郎に訊いた。
「私が持って来て、お願いしたんです。震災で亡くなった祖母が好きだったので……子どもの頃、秋になると夕餉の膳には、かきのもとがありました」
元来、かきのもとは新潟県の食べ物で、食用菊である。お隣の福島県にその食文化が伝わって、実家のある相馬市でも食べていたとあすかは語った。
菱田と銀平がその言葉に口をつぐんだが、ジョージは真剣なまなざしでメモを取っていた。湿っぽくなりかけた雰囲気に、あすかは笑顔を見せてジョージに言った。
「あら、抜け目ないですねぇ。ジョージさん、かきのもとをお召し上がりになりませんか?」
「ありがとうございます。でも、もっとお聴きしたいです。あなたは、日本酒の蔵元のお嬢さんですね。日本酒には“菊酒”という言葉がありますが、そもそもは菊の花を入れるのですか?」
その質問に、銀平と菱田、そして太郎も耳を傾けた。気づくと店内の客たち全員が静まって、あすかの答えを待っていた。
「実際に、樽酒に入れたこともあると思います。例えば、あの豊臣秀吉が京都の醍醐の花見で、盟友の前田利家の持参した加賀の酒が一番美味しいとほめたせいで“加賀の菊酒”って言葉がはやると、庶民はこぞって日本酒に菊の花を散らしたらしいです。でも、本来の菊酒の意味はちがうと祖母から聴きました」
あすかは、古代中国の伝説に“菊慈童(きくじどう)”の伝説があると加えた。菊の花が咲き乱れる深い山があり、そこに七百歳の仙人が棲んでいた。しかし仙人は少年のままの姿で、彼の不老不死を保ったのが万朶の菊の花からこぼれる水のしずくを飲むことだった。その霊水が、菊酒として語られたと解説した。
そして九月九日は重陽の節句で、心身を癒すための菊酒として日本酒を飲む風習もあり、これも菊慈童に由来していると言った。
落ち着き払ったあすかの声が店の杉板の壁にしみるように響くと、太郎が拍手して言った。
「さすが、本物の蔵元が語ると、俺なんかよりもぐっと深イイ話しになるね」
「それで酒の銘柄に菊を使う蔵元が多いわけか……こりゃ、不勉強だったな」
つぶやく菱田はジョージにかきのもとを勧めながら、自分も頼んだ。すると、店内の客たちも次々に太郎へかきのもとを注文した。
「なんだよ、なんだよ! 日本人の悪い癖だぜ。迷信めいた話しを、すぐに信じちまうのは。それにジョージさんよ、日本の魚匠である俺にも、酒の話しをさせなよ」
にわかに菊酒の話題で店内が活気づくと、あすかに差をつけられた銀平がジョージに擦り寄った。
しかし、ジョージはそれを無視するかのように、ペンを走らせながら独りごちた。
「クリサンミスト……このキャッチコピーで、いこう」
「クリ? 栗じゃねえよ、日本酒は米なんだよ!」
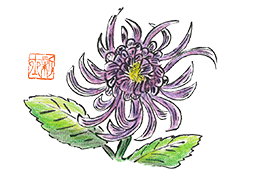
眉をしかめる銀平に、ジョージが首を横に振った。
「いいえ、ちがうのです。クリサンミストとは、菊のしずくとか霧という意味です。これは、いい菊酒のキャッチコピーができました! あすかさん、ありがとうございます!」
「なるほどねぇ、神秘的でアメリカ人にもウケそうだな」
「ジョージさん、素敵です! 私も、そのコピー使っていいですか?」
菱田とあすかが褒めそやすと、ジョージの肩を揺すってメモの邪魔をする銀平を太郎が皮肉った。
「ジョージさん。まあ、こいつの話しは眉唾だから、適当に聴いておけばいいよ」
「マユツバ? って、どういう意味ですか? 銀平さん、ぜひ、教えてください!」
「あっ、眉唾ってのはよ……ちくしょう! なんで、そんな話しを取材されなきゃなんねえの!?」
銀平のぼやきに満面の笑顔をこぼす客たちを目にしながら、今夜の酒が菊酒になるように太郎は胸の中で祈った。
