青山通りを歩く人たちのファションが秋めいても、イチョウ並木の緑は濃いままである。
銀座や赤坂の割烹には気の早い鍋料理が登場し、セレブな外国人観光客を呼び寄せていた。日本酒ツウな彼らは、旨口の冷やおろしにも舌鼓を打っている。
そんな都内に営むかつての兄弟分たちの料理店を回った中之島哲男は、いつになく重い足取りでポンバル太郎へやって来た。
「あれ、中之島の師匠。元気ありやせんね。具合でも悪いんですかい?」
カウンター席でぬる燗の純米酒とサンマの塩焼きを口にしている八百甚の誠司が訊ねると、太郎も中之島の冴えない表情に包丁の動きを止めた。
加賀と土佐の冷やおろしを飲み比べする平 仁兵衛と右近龍二も
「そのお顔は、体の具合じゃなくて、胸の中がクサクサしているようですねぇ」
「冷やおろし、うまいすよ! 気分直しにどうすか?」
とガラスの酒デキャンタを差し出した。
ソフト帽を取りつつ誠司の隣へ腰を下ろした中之島は右手を横に振って遠慮すると、長いため息を洩らした。
「東京と大阪のちがいに、ちょっとしたカルチャーショックや。飲食業の景気に、ここまで差がついとるとはなぁ。インバウンドの効果だけやない。東京はあいかわらず人口が増えとるから、店も賑わうわけやなぁ」
関西の飲食業は京都の独り勝ちで、次いで神戸、低迷する大阪はずっと3位に甘んじていると中之島は嘆きながら、辛口の本醸造を熱燗で頼んだ。確かに、京都が祇園祭ツアーなどのインバウンドで好景気なのは、誠司ですら知っている。
久しぶりに中之島のぼやきを耳にする太郎は、斟酌するように熱燗のお銚子を差し出した。
「だけど師匠、うちは変わりませんよ。下手すりゃ、ボウズに近い日だってある。銀座の景気がいいったって、近頃の料理屋は混沌としちまって、昔の銀座らしさは薄れちまった気がします。目新しい料理店ができても、早けりゃ、一年ともたずに消えちまうし」
頬杖をつく中之島の横顔を見つめる誠司も
「そうすよねぇ。何だか、居酒屋やラーメンのチェーン店とかも増えちまって、銀座と新橋の境目が分からねえや。数年前まで、俺には銀座の夜なんて聖域だったんすけどねぇ」
と相槌を打った。それを聞いて、龍二が呆れたような声をつないだ。
「その一方じゃ、目玉が飛び出そうなぐらい高級な寿司屋も人気だし。まぁ、俺たちの小遣いじゃ、大間マグロのトロなんて高嶺の花だけどね」
聞いていたテーブル席の三十歳前後とおぼしきスーツの男たちが頷いた時、ネガティブな話題を消すかのように玄関の鳴子が勢いよく弾けた。
「さぁ兄弟、入ってくれ。ここが俺のお気に入りの下町の日本酒バルだぜ!」
火野銀平の裏返ったような声音に、ご機嫌の良さが如実に分かった。兄弟と呼んだ連れの男は、店内を見渡しながら「ふうん……客の入りは、まあまあやなぁ」と関西弁でつぶやいた。薄く刈り上げた頭が、ビジネスマンには見えない。
男の関西弁に、中之島が盃を口元に止めて振り返った。男も視線を感じて、中之島を見つめている。
それに気づいた火野銀平が、男の背中を押しながら紹介した。
「中之島の師匠。こいつは、今年の春まで築地の葵屋にいた奴で、摂津 孝介って言いやす。今は、大阪の木津(きづ)市場の鮮魚商・摂津屋の四代目でさ。大阪の鮮魚卸じゃ名の通った老舗で、こいつぁ、葵屋の伝兵衛親方の仲人で婿養子に入ったんすけどね。師匠は、摂津屋をご存じじゃねえすか?」
自慢げに語る銀平へ男は謙遜し、中之島へ頭を下げると
「まだ、新米ですよって、よろしゅう頼んます」
と古臭い大阪弁でしゃべった。しかし、どことなくアクセントがおかしく、板についていない。平と龍二、誠司だけでなく、テーブル席の客たちも「ちょっと訛ってるよな」と苦笑した。摂津本人も自覚しているのか、照れ臭そうに咳払いをした。
「築地で修業したのに、大阪へ婿入りとは珍しいね。言葉だけじゃなくて、商売の流儀もちがうでしょう?」
太郎が摂津をカウンター席へ誘いながら訊ねると、中之島も理由を聞きたそうな顔で手招きした。
中之島の隣へ座る摂津は、「すんまへん」と両手を合わせた。大阪人らしい仕草だが、それもぎこちない。
平と龍二は、摂津がカウンターに置いたセカンドバッグに目を止めた。ぶら下がっている根付のような黒い塊は、二枚貝の形をしている。それが何なのかは、分からなかった。
いささか緊張気味な摂津に中之島は盃を渡し、お銚子を差し出した。
「東京の方が活気はあるのに、よっぽどええ婿入りの条件やったんかいな? 最近は、摂津屋はんとて、わしはそないに儲かってるとは思わへんで」
流暢な大阪弁がカウンターに低く響くと、心なしか客たちの表情が和んだ。銀平も中之島の察しが気になったのか、摂津の横へ腰を下ろして、耳をそばだてた。
「実は、僕の祖父もかつては築地で働き、大阪市内にある木津(きづ)市場の卸商に婿入りしたんですわ。その息子だった父は若い頃に上京して、ごく普通のサラリーマンになりましたけど、僕は祖父の血を引いたようで、婿養子になったのは、そんな御縁から覚悟を決めたんです……大阪市内の北新地や宗右衛門町の料理店が客筋の木津市場の卸商は、品物がええだけやなく、値頃な品揃えに尽きますわ。けど、どんな魚を調達したらええんか、よそ者の僕には、まだ分からん。店の職人は、何も教えてくれへんし、ええ手がないもんか、探してますねん……」
先細るような摂津の声に、切実な悩みが垣間見えた。
歯がゆげな銀平は龍二から冷やおろしのデキャンタを奪うと、大ぶりのぐい呑みへあふれんばかりに手酌した。
「そりゃ、摂津屋の奴らが、おめえを試してるってことかよ? 跡取りとして迎えたのに、ふざけんじゃねえよ!」
舌打ちして酒をあおる銀平に、摂津が即答した。
「いや銀平、そうじゃねえよ。長年、木津市場を支えてきた職人からすりゃ、築地者がナンボのモンじゃいってえのは当然だろうよ」
唾を飛ばす摂津は、生粋の江戸っ子言葉に戻っていた。粋でいなせな築地の男らしさをにじませる摂津に、龍二や平は彼の慣れない大阪での心境をおもんばかった。
静まった面々の中、摂津は口元を拭うハンカチをセカンドバッグから取り出した。貝の形をした塊が揺れて、中之島の視線を奪った。
ハッと顔色を変えた中之島は、摂津の肩をつかんだ。
「摂津はん。あんさん、本名は何ちゅうねん? もしかして、海野っちゅう姓やないか?」
すると、摂津が驚いたように目をみはった。声の出ない摂津に代わって、銀平が
「ず、図星でさぁ! 俺ぁ、奴の本名についちゃ、何にも言ってねえすよ!? どうして、知ってんですかい?」
と前のめりになった。
「今夜は、誠司じゃなくて、中之島師匠が神ってるよ」
太郎は龍二と声を重ねたが、誠司には聞こえていないのか
「これって、釣りに使うブラクリじゃねえですかい?」
と、貝のような塊を凝視した。
平だけでなく、テーブル席の客たちもブラクリを知らないのか、キョトンとしている。ただ一人、中之島が摂津に
「それを持ってたあんたのお祖父さんは、海野三郎。木津にあった海野商店の大将や。アダ名は、ガシラの海野やったな……横顔が、よう似てる。血は争えんなぁ」
と目尻をほころばせた。
「どうして、それを……けど僕は、その意味を知らんのですわ」
答えた摂津の顔は、興奮のあまりに紅潮している。
ガシラが分からず眉をしかめている誠司へ、二人のやりとりに得心した顔の太郎が冷蔵ケースの赤い小魚を目で指した。
「ブラクリ釣りで、分かったぜ。東京じゃ、カサゴだよ。根魚だけど、白身の高級魚だ。残念ながら、こいつの大物は火野屋でもめったに手に入らねえんだと」
と中腰になったままの銀平へ投げかけた。
「ああ、カサゴはよう。テトラポットの隙間や波止場の岩礁なら、ブラクリ釣りで子どもだって釣れちまう小魚だ。煮つけにすりゃ、すこぶるつきにうめえし、燗酒には最高でぇ。だけど、大物は穴場を知らなきゃ獲れねえ……てぇこたあ、孝介のお祖父さん、いやガシラの海野はカサゴの上物を、自分で釣って店に揃えてたってわけか!?」
両手を叩いた銀平に、驚きで声が出ない摂津も中之島の答えを待った。
「ああ、その通りや。わしが若い頃、“ガシラの海野”は木津市場の伝説になってたわ。お目にかかったのは、海野はんが引退された後の1回だけや。あんたと同じように、手さげ袋に、そのブラクリを吊り下げとった。わしは、どうやって、手に入りにくい大物ガシラを揃えたんか、訊いてみた。そのガシラは、海野はんが大阪の海でブラクリ釣りを続けるうちに見つけた秘密の穴場で釣り上げた。漁師に頼んでも、穴釣りなんぞ、せえへんからな。その結果、築地者と煙たがられとったのが、木津市場で一目を置かれる存在になった」
聞き入る客たちの感心するため息が、あちこちから聞こえた。しかし、摂津は神妙な表情で口を開いた。
「この貝のブラクリは、僕が子どもの頃、祖父さんを亡くしてからお守りのつもりで提げてますねん。けど、これが“ガシラの海野”を生んだとは知らんかった……僕にも、やってみいちゅうことですかね……ブラクリ釣りを」
摂津の指が、黒い二枚貝のブラクリを大事そうにつまんだ。
「小さな仕事からコツコツと。それが、なにわ商人の流儀やで。ガシラの大物が釣れたら、わしの割烹・中之島へ一番に納めてもらおうやないか」
中之島の差し出した割烹の名刺には、明石鯛や明石ダコとともに、ガシラのイラストも描かれていた。
祖父と中之島の出会い、それが銀平やポンバル太郎につながり、自身へめぐって来る不思議な縁に、摂津は目頭を潤ませた。
平が、摂津に能登の冷やおろしを注いだ。
「考えてみれば、自分で釣って調達するのは、魚屋さんの裏ワザじゃないですかねぇ」
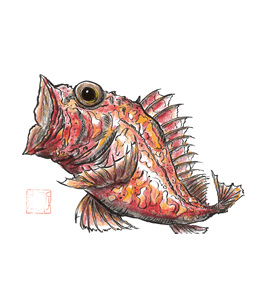 負けじと、龍二も土佐の冷やおろしのデキャンタを構えた。
負けじと、龍二も土佐の冷やおろしのデキャンタを構えた。
「それどころか、すこぶる新鮮だし、値段も安くできるじゃないですか」
言い得て妙な二人の助言に店内の客たちが頷くと、摂津は立ち上がって深く頭を下げ、謝意を示した。
ご機嫌な気分になった銀平が冷やおろしの盃を飲み干して、声を上げた。
「兄弟! 大丈夫でぇ! おめえなら、やれるよ。お祖父さんと同じ、築地者の血が流れてんだからよう。ところでよう、太郎さん。そのガシラ、煮つけにしてもろてええやろか?」
語末だけをわざとらしく大阪弁にした銀平だが、それは摂津さえ吹き出しそうなイントネーションの酷さだった。
「兄貴ぃ、相当に訛ってやすねぇ。せっかくのガシラが、まずくなりそうでさぁ」
誠司の本音に、客席はどっと笑いを吹き出した。
