残暑がぶり返した都心の夕暮れに、打ち水が撒かれている。濡れた目抜き通りには、「品川宿場まつり」の幟がはためいていた。
北品川の八ツ山口から南品川の青物横丁までを練り歩く行列の先頭は花魁道中で、角兵衛獅子やちょん髷の棒手振り男たち、日本髪に唐桟をまとった女たちが江戸時代の品川宿を髣髴とさせている。サンマやサケ、イカやカキを焼く夜店屋台の一画には地酒の弧樽も積まれ、観客に桝酒がふるまわれていた。
高野あすかと一緒に祭りを取材していたジャーナリストのジョージは、飲み食いが過ぎたのか、浴衣姿でポンバル太郎のカウンター席で伸びている。
「まったく、だらしねえヤンキーだぜ。タダだからって、いじきたなく飲むんじゃねえよ」
浴衣のはだけたジョージを火野銀平が腐すと、あすかも呆れ顔で笑った。
「しょうがないわね。あんなに美味しい物が揃ってちゃ、つい飲みすぎるわよ。北海道のホタテ焼き、秋田のキリタンポ、山形の芋煮、千葉のサザエつぼ焼きとか、目移りしちゃった」
あすかの隣でぬる燗の盃を傾ける平 仁兵衛が、銀平に訊いた。
「品川宿ねぇ……銀平さん、昔の品川宿は海が目の前でしたから、さぞかし魚は美味しかったのでしょうねぇ」
「あたぼうでさぁ! 今の品川駅の辺りは袖ケ浦つって、浜と干潟が続く海だった。だから江戸前の活きのいい魚を食うなら、品川宿が獲れ立て一番てぇわけですよ」
火野屋のTシャツの胸を張る銀平に、カウンターの端っこで上燗の本醸造を飲んでいる白髪の男が火野屋のロゴマークにくぼんだ目を見開いた。短かく刈った頭は職人然とした雰囲気だった。
テーブル席の男性客が
「じゃあ、うちのオフィスって、当時は海の中だったのか。今の品川からは、考えらんないよなぁ」
とつぶやいた。同僚らしき連れも、冷酒グラスの冷やおろしを口にしながら頷いた。
うつろな目のジョージに冷たいおしぼりを出す太郎が、冷蔵ケースの中へ手を伸ばした。
「品川は、東海道で江戸へ入る直前の宿場町だった。旅の汗と汚れを落として、身ぎれいにしてから、ご馳走を楽しんだってわけだな。だけどよ、品川宿で働く庶民が食ってたのは、イワシや小アジとかの雑魚だ。そして、定番はこいつだ!」
太郎の右手が、冷蔵ケースから何かを取り出し、ジョージの目の前に置いた。
「キャ! な、なに?」と、あすかが小さく飛び上がった。一見、不気味な形をしたシャコに、寝ぼけ眼のジョージも「ワ、ワオ! エイリアン!」と椅子からずり落ちそうになった。
「エイリアンたぁ、ご挨拶じゃねえか。おめえ、シャコも知らねえのかよ? それでも、日本の食文化を伝えるジャーナリストかよ。こいつは、木更津の盤洲干潟(ばんずひがた)で獲れた、極上のシャコだ。うちの祖父さんの頃から扱ってる、銀座の寿司屋でも御用達のシャコだぜ」
自慢げな銀平へ、ジョージをかばうかのように、あすかが水を差した。
「アメリカじゃ、チャイナタウンの中華料理じゃないとシャコは食べないわよ。見た目にグロテスクだから、私だって苦手だわ。最初にシャコを食べた人って、偉いよね」
聞き耳を立てるテーブル席の客たちが頷くと、カウンターの白髪男も「ちげえねぇや」と江戸っ子言葉で苦笑いをした。
シャコは車エビのような身のプリプリした締まりがないので、食感的にはイマイチだと、あすかは付け加えた。その隣で、ジョージは15㎝近いシャコの写真をインスタグラムにアップしている。
「確かに、エビほど人気はありませんが、シャコ獲りは簡単で、楽しいですよ。子どもの頃、能登の干潟でシャコを獲りました。習字の筆をシャコのいる泥の穴に突っ込んで、引っ張り出すんですよ。これが、おもしろいように獲れます」
相好を崩した平が身振り手振りで穴シャコ獲りを説明すると、ジョージはメモを取り始めた。銀平も思い出したように
「そうそう! 俺もガキの頃、木更津の干潟でよくやったぜ!」
と相槌を打って、1日で100尾近くを獲った時は、しばらくの間、おやつは山盛りのシャコの塩茹でだったと回想した。
「皿にテンコ盛りのシャコかぁ……ちょっと、引いてしまいそうだよなぁ」
テーブル席の男の一人が銀平の体験談に身震いすると、カウンターの隅から声が聞こえた。
「兄さんはひょっとして、火野銀次郎さんのお孫さんの銀平さんかい?」
いぶし銀のような渋い声に、客席の視線が向けられた。突然に訊かれて驚き顔の銀平は、白髪の男へ目を細めて誰何したが、記憶にないようである。
「ええ、そうですが、どちらさんで? あっしは、お客さんとお目にかかった憶えはねえんですが」
「無理もねえやな。あんたぁ、まだ3つや4つのハナタレ小僧だったからよう。銀次郎さんに連れられて、俺ん家がやってた簀立(すだて)へ遊びに来てた。潮が引くと干潟も出て、そこで穴シャコを獲ったよなぁ」
男から懐かしげに顔を覗かれて記憶の糸をたどる銀平より先に、あすかが声を上げた。
「あら! 銀座の老舗寿司店・正兵衛の板長をなさっている、磯田さんじゃないですか。私、以前にお店を取材させて頂いた高野です」
知っていたよと笑みで答える磯田に、客席からも
「あの親父さん、現代の名工に選ばれた達人だよ」
と囁く声が聞こえた。
太郎も寿司・正兵衛の名はむろん知っているが、よもや板長がポンバル太郎へ来るとは思いもよらず、いつになく手元が落ち着かない。
それを気にせず、磯田はシャコを塩茹でにしてくれと太郎へ注文すると、
「俺ぁはあん時、16歳の若僧でね。ちょうど、東京に出て寿司屋の職人になろうてぇ時だった。銀次郎さんは、うちの簀立で揚がる魚や干潟のシャコを仕入れて、そいつを銀座の料理屋に奨めてくれたんだ。そのおかげで、俺は一流店に入ることができたわけよ。いわば、あんたのお祖父さんは、俺の恩人だ」
と銀平へお銚子を差し出した。
予想だにしない再会に、うろたえるやら、恐縮するやらの銀平へ、あすかが
「だらしないわねぇ! しっかりしなさいよ、銀次郎さんに叱られるわよ」
と新しい盃を手渡した。
「う、うるせぇ! あんまり突然でビックリしてんだよ! 磯田さん、ようやく思い出しやしたよ。あんたぁ、獲ったシャコの前足に弾かれて、指の爪が割れて、絆創膏をいっぱいしてやした。とにかくシャコは華奢な体に似合わず、前足の力が尋常じゃねえ。アサリの貝殻だって一撃で割って食っちまうんだって、教えてくれやしたね。それこそ、1日100尾のシャコはおたくの干潟で獲ったんでさ。だから、火野屋は木更津のシャコしか仕入れねえ……けど、ご実家は、商売をずいぶん前にやめちまったでしょ。ありゃ、どうしたわけで?」
銀平の盃に注がれる酒が、ふいに止まった。ため息を洩らす磯田の顔を、茹で上がったシャコの湯気が隠した。
「……簀立漁を続けるのは、難しい時代になってな。今じゃ数軒しか残ってねえし、観光向けの遊び場としてのビジネスだよ……だけどよう、俺の握る寿司は生まれ育った木更津のシャコじゃねえと、いけねえんだよ。小ぶりのシャコだが、ぎゅっと身が詰まってんだ」
秋のシャコは傷みにくいし、身がしっかりしている。とりわけ、前足の肉はシャコツメと呼んで、軍艦巻きにするとすこぶるつきに美味で、1尾からわずかだけ取れる珍味だと、磯田は自慢した。ただ、シャコは死んでから時間が経つと殻の中が酸化しやすく、身を溶かしてしまうので、殻のサイズの割に中身が痩せてしまっている場合が多い。だから、新鮮な内に調理することが大事だ。つまり、木更津のシャコなら都内へ届けるのに時間的に好都合。そこに目をつけたのが、火野屋の銀次郎だと褒め称えた。
磯田の嬉しげな指先が、赤く茹で上がったシャコの皮を剥いだ。野趣あふれる磯田の食べ方は、およそ寿司の達人っぽく見えないが、千葉の地酒の上燗をうまそうにあおった。
達人の恍惚とした表情に、客席から「俺も注文します!」「こっちも頼むよ!」の声が飛び交った。平は抜け目なく別メニューの焼きシャコを頼み、ジョージもおっかな顔でそれにのった。
機嫌を良くした磯田は、こうも言った。
「江戸時代はよう。シャコをシャクナゲつってたんだよ。身を茹でると紫色に変わるだろ。ありゃあ、石楠花の花の色に似ていたからだ。どうでぇ、粋な呼び名だろ。うちの寿司屋で『シャクナゲを頼むよ』って注文されりゃ、俺はもう、嬉しくって仕方ねえよ」
破顔一笑する磯田がシャコを横目で睨むあすかに、食べてみなよと目顔で勧めた。
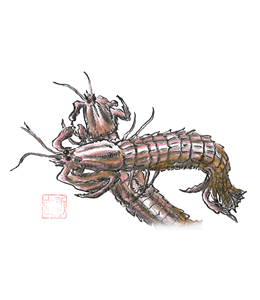 「へっへい! どうでぇ、あすか。これほどうめえって聞きゃあ、酒と食ジャーナリストのおめえも食わねえわけにゃ、いかねえよなぁ」
「へっへい! どうでぇ、あすか。これほどうめえって聞きゃあ、酒と食ジャーナリストのおめえも食わねえわけにゃ、いかねえよなぁ」
躊躇しているあすかの鼻っ面に、したり顔の銀平がシャコを近づけた。
途端に、あすかの「ギャッ!」という悲鳴とともに、往復ビンタが銀平の頬に飛んだ。
客たちが唖然とする中、磯田は頭を掻きながら念を押すように笑った。
「あのよう、銀平さん。あん時、俺はこうも言ったぜ。シャコのメスのパンチは、オスより速い。産卵前に嫌いなタイプのオスに言い寄られた時、逃げるためのビンタなんだって。今のは、まさに、そいつだなぁ」
「そ、そいつは、忘れてやしたぁ」
椅子からずり落ちそうな銀平に、店内から大爆笑が巻き起こった。
