サクサクサク……と小気味よい音が、白木のカウンター越しに聞こえている。
ちょうど今、店を開けたばかりのポンバル太郎に入った高野あすかは、その響きに包丁を振るう太郎の姿を探した。客席にまだ人影はなく、あすかの胸がときめいた。
しかし、太郎は厨房の右端に立ち、前かがみでまな板に向かっているのはガッチリとした大柄な男だった。見憶えのない男だったが、浅黒い額に巻いたバンダナとリストバンドは真っ赤な色で、ことさら存在感をアピールしていた。
「こっ、こんばんは……太郎さん、どうしたの?」
躊躇しながら厨房を覗き込んだあすかが、キャッ! と声を上げた。まな板の端には牙を剥いた血まみれの鱧の首が転がり、まだピクピクと顎を動かしていた。
男は鱧の身をさばいて、骨切りをしていたのだ。
それでも息を呑んで、スマートフォンで写真を撮ろうとするあすかへ、今は遠慮するようにと太郎が目で合図した。
その時、男が包丁を止めて視線をもたげた。日本人離れしたエキゾティックな顔立ちに、一瞬、あすかの胸が高鳴った。
あすかの表情を見て取った太郎が、したり顔で笑った。
「ドッキリするだろ。村田アキラ君といって、中之島の親父さんのお弟子さんだ。鱧きりの新しい包丁を、泉州の堺からわざわざ届けてくれてね。その試し切りも兼ねて、本場の骨切りを実演してもらっているんだ。見ての通り、ハーフの男前。それに、彼のプロフィールがスゴイ。元は実業団のバスケットボール選手で、プロも約束された男だったけど、怪我をして引退し、今は料理人だ」
太郎の紹介に村田は小さく会釈しただけで、まな板に向かうと、軽やかな骨切りの音をまた刻み始めた。
「あっ! バスケのドリブルがうまかったから、骨切りの包丁さばきもリズミカルで、上手になったとか!? ってジョークもありの村田さんの記事、書けませんか。それに鱧料理って、夏が旬でしょ。そろそろ秋、時期はずれじゃないんですか?」
あすかの問いかけに村田は動じず、しばらく単調な音を紡いでいた。だが、片身の骨切りを完成させると、手にしている鉈のような包丁をあすかの眼前に突き出した。
「うわっ、ぶ厚~い! それが、鱧の骨切り専用の包丁?」
屈託のない驚きと質問を発するあすかを、村田はあきれ顔でたしなめた。
「こいつを見たことも触ったこともない人に、鱧料理の記事なんて書けるの? それに鱧は夏のものと決まってなくて、旬は二度ある。これから肥えてくる秋鱧は脂がのって味が熟成するから、天麩羅や鍋料理にします。太郎さんも秋から鱧すき鍋を始めるため、この秋鱧用の骨切り包丁を新しく誂えたんです」
まだまだ新人のライターと見抜かれ、反論の余地もないあすかだったが、太郎は助け舟を出してくれなかった。
こんな時にこそ銀平や龍二がいてくれたらと、忸怩たる思いであすかは村田に訊き直した。
「秋鱧のためって言いましたけど、その包丁はどうちがうの?」
「脂がのって肥えるってことは身が太るわけで、当然、骨も太くなる。だから、背に厚みを持たせた重い包丁が骨切りをしやすいんです」
村田のたくましい腕がぶ厚い包丁をかざすと、刃に反射した明かりが店内に走った。その光が、開いた入り口の扉に現れた銀平と龍二の目をつぶした。
「な、何しやがる! まぶしいじゃねえかよ!」
とっさに目を手で覆った二人だったが、次の瞬間、龍二がつぶやいた。
「あの形と厚い刃は、堺の宗久庵の鱧きりだ……銀平さん、火野屋でも使ってるヤツでしょ?」
銀平は指の隙間から瞳を凝らしながら、包丁から村田へ視線を移した。
「うっ、うん!? 確かに、似てるな。おいおい! 外人が鱧をさばいてるぜ……しかも太郎さんと厨房に入るって、どうなってんだ?」
「あっ、やっと登場ね!」
ようやく援軍が来たとばかりに手招きしたあすかは、太郎に鱧の落としと純米酒を三人前注文した。
試し切りを終えた村田は、まな板の血を丁寧に洗い流し、抜かりなく磨き上げると、包丁を木製の鞘に納めて太郎に手渡した。
太郎から中之島の肝煎りである村田の素性を知った銀平と龍二は、カウンター席に座るや鱧談義を始め、俄然、会話は熱を帯びていった。それをあすかが取材しながら、酒と肴を注いで回るという按配になった。
銀平は太郎の特注した秋鱧用の骨切り包丁を手にすると、宗久庵の刻銘を確認しつつ村田に語った。
「俺がガキの頃、鱧を扱う築地の魚屋は少なかった。亡くなった親父は『鱧なんてなぁ上方のゲテ物で、江戸っ子の食う魚じゃねえ。東京湾の穴子の方が上等だ』って、見向きもしなかったよ。実際、鱧をさばける料理人はわずかだったぜ」
銀平は、宗久庵を贔屓にする者同士に合い通じるような答えを期待した。
「それには、理由があります。そもそも江戸は全国から参勤交代の武家が行き来して、侍が多く住んでいるので、地方食の渾然一体となった献立が江戸料理の原型だった。これが明治頃まで続いたのですが、大正時代の関東大震災で東京が焼けてしまったことで料理事情が変わります。焼け野原になった東京に、一攫千金を狙った京都や大阪の料理人が大勢やって来て、上方料理を広げた。これが、今の東京の日本料理の原型だ。つまり京都の懐石料理文化が、この頃から、徐々に東京へ浸透していくわけです」
口を冷酒グラスに近づけた村田は、ふと、あすかに酒の銘柄を訊ねた。それが淡路島の純米酒と知ると、大きく頷いて、ようやく笑顔を見せた。
その意味を知った龍二が、村田の彫りの深い横顔につぶやいた。
「なるほど……これは淡路の沼島(ぬしま)産の鱧ですか。身の大きさも手頃で、脂ののりもいいですね」
「嬉しいな、判ってくれて。でも淡路島産の鱧が、今じゃ韓国産に取って代わられているんだよ」
淡路島の東側にある沼島の周辺は広大な泥底で、昔から鱧の格好の棲家だったと村田は続けた。しかし、海水の温暖化や潮流の変化によって、少しずつ鱧がいなくなっていると嘆いた。
「うむ、確かに築地で扱う鱧も、韓国産の活け物が多くなっているぜ。まぁ、それを言えば、今はどんな魚介類も海外産だよ。料理人だって、あんたのようなハーフやネイティブな外国人だって、増えてるじゃねえか」
その時、尽きない話しをひと息つかせるように、白く湯引した鱧の身を太郎がカウンターに置いた。二つの小鉢に盛られた白身には、それぞれ赤い梅肉と黄色い酢味噌が添えられていた。
「まずは秋鱧のうまさってのを堪能しようじゃねえか。東京は梅肉ってのが主で、関西は酢味噌が一般的だ。それは、関東酒の辛口、関西酒の旨口に合うからだろう。なあ、村田さん」
太郎の問いに、村田は大きく頷いて、花が咲いたように盛り上がった鱧の身をうまそうに食べた。
「ちなみに、あんたの鱧きりはどんなの?」
銀平の問いかけに、村田がニンマリとして、きらびやかな西陣織りの包丁袋を厨房から取り出した。
そこから真っ赤な柄の、あたかも名刀のような輝きを持つ鱧きりが取り出されると、銀平と龍二はあんぐりとして、あすかはスマホの写真撮りを忘れたまま、目を丸めていた。
「な、な、なんでぃ、このド派手な形の包丁は!? それに、あんた、赤い物好きだね。どうしてだよ?」
「はい! 前田慶次をご存知ですか? 赤が似合う戦国のバサラ侍として名を馳せた人物で、大ファンなんです。ちなみに俺、携帯もハンカチも赤です」
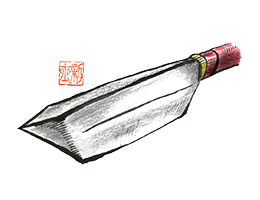
胸を張る村田に、カウンターに座る三人ともがため息をついた。
「それに今日の鱧は、赤鱧だ。こだわってるね」
赤い柄の鱧きりを手にする太郎に、あすかが訊いた。
「赤鱧って……鱧にも種類があるの?」
その答えを、淡路島の純米酒を飲み干した銀平がうばった。
「うまい秋鱧のサイズは、500gぐらいだ。体の色は赤銅色で、雌なんだよ。これに対して雄は青みを帯びていて、青ハモと呼ばれる。雌は、9月から10月頃の産卵期に向けて栄養を蓄えるから、うまくなるんだ」
あすかと龍二が感心すると、ふたたび村田は自分の鱧きりを太郎から受け取り、まな板に向かった。
赤い柄の鱧きりが白い鱧の身に映えながら、心地よい音を響かせ始めた。
