ポンバル太郎のカウンターに座る火野銀平が、カウンターの端っこで冷酒を傾けている右近龍二に突っかかるように、斜に構えながら声を荒げていた。
残暑とはいえ、ようやく異常な熱波も落ち着いて、秋上がりの熟成酒をまったりと楽しんでいるテーブル席の客たちは、銀平の着る火野屋のTシャツの背中に眉根を寄せた。
たった今、杉の扉を開けてやって来た手越マリもそのようすを目の当たりにして
「銀平! 私の龍ちゃんをいじめると承知せんけんね!」
とシワ立った富士額に浮く汗をハンカチでぬぐった。
鼻息を荒げるマリだったが、銀平の隣に腰を下ろしながらも、テーブル席に座っている男女に視線を奪われた。いつもカウンター席で独酌する平 仁兵衛が珍しく女性を同伴し、どちらも和服の装いだった。
女はシルバーグレーに染めた髪をふっくらと結い、目尻に上品な小ジワを寄せ、六十歳半ばとおぼしき面差しを覗かせている。
彼女の薄紫の正絹が、平のまとっている鈍色の蚊絣の羽織に寄り添っているようだった。
不思議なのは、いつもなら銀平たちの諍いをとがめる平が気にかけることなく、むしろ、笑みさえ浮かべていることだった。二人が飲んでいるのは、ぬる燗の伏見の純米酒だった
その時、太郎がカウンター越しに魚の干物を置いた白磁の皿を手にして、マリに見せた。
焦げた香ばしい匂いを漂わせている鱗とほのかな赤い皮の色が対照的で、一瞬、目を楽しませた。
「マリさん、銀平が“ぐじぐじ”言ってんのは、龍二の口がもどかしいわけじゃねえんだ。コイツのことなんだよ。平先生のお連れさんからの差し入れだ」
太郎はマリを宥めるようにほほ笑むと、平たちの前にその焼き魚を置いた。
「……甘鯛やなかね。それ、九州では珍しか魚たい」
マリが目を細めると、女性が平へぬる燗の純米酒を酌する手を止めて、その皿を手にした。そして、しなやかな箸使いで割いた白身と焦げた皮を平や銀平の小皿へ上手によそいながら、嫌味のないシナを作った。
年齢に関係なく艶っぽい彼女のしぐさをマリは羨ましく思い、思わず平へ訊ねた。
「平先生。こちらさん、初めての方やね。ご紹介してくれんね」
すると、銀平にからまれていたほろ酔いの龍二が口を挟んだ。
「ほら、やはり美江さんは、誰もが気になる雰囲気を持ってらっしゃいますよ。まるで、このぐじだ。甘鯛とは別格ですね」
自分の話しを折ってまで褒めそやす龍二に、マリは嫉妬のような気持ちを覚えた。その感情が先走ったのか、語気を強めて龍二に言い返した。
「龍ちゃん! ぐじと甘鯛は、同じたい!」
ふだんは龍二へおもねってばかりのマリの豹変に、銀平と太郎が思わず目を合わせた。美江と呼ばれる女性を紹介しようとした平は盃を止めたままで、苦笑いすることさえ忘れている。
その時、答えに窮している龍二に関係なく、美江の唇がゆっくり動いた。
「ぐじと甘鯛は、別物どす……確かに、同じ種類なんどすが、京都ではちがいますねん」
美江の京言葉と物腰はその場の息苦しい空気を潤わせ、マリの勢いを抑えた。テーブル席の男性客も酒を飲む手を止め、美江に注目していた。
沈黙したままのマリに、平が言った。
「この人は京都の陶芸展示会にいつも来てくださる、仁科美江さんです。祇園の『若狭』という料理屋の女将でね……若狭地方、福井県のご出身で、つまりはこの若狭ぐじを食って育ったような方ですなぁ」
「平先生、私、ぐじのお化けみたいやおへんか……マリさん、ですね。不躾に言い返して堪忍どす。けど、ほんまに、私が今日お持ちした新鮮なぐじは、甘鯛と呼んでほしくありまへん」
仁科美江は訥々としゃべり出し、マリが知っている祇園流れの銀座のホステスたちとは一線を画すような、はんなりとした、知的で論理的な話し方をした。
甘鯛は身が柔らかい魚で、漁のやり方しだいですぐに痛む。底魚だから、網で引けば獲れる量は増えるのだが、ストレスや傷によって味が悪くなる。そのため、若狭には江戸時代から伝わる底延縄(そこはえなわ)という漁法が残っている。慎重かつ丁寧にたぐり寄せるこの釣り方をして、初めて、若狭ぐじと呼ばれる一級品の甘鯛が獲れると美江は説いた。
心地よい美江の声音を、ポンバル太郎の杉板の壁が吸い込んでいた。
静まった店内に、銀平の声が響いた。
「悔しいけど、これはうちで扱ってる甘鯛より上物だ……美江さん、若狭ぐじは現地からの直接販売が主流でしょ? 築地に来るまでに痛んでしまう確立が高い。それほど、足が速いんだ」
「へえ、そうどす。鱗一枚でも取れたら、それでもう、若狭ぐじとは呼ばしまへん……贅沢なお話しどすなぁ」
ぐじをつまみながら舌を鳴らす銀平に、美江が答えると、太郎が会話をつないだ。
「甘鯛は極端な個性や主張は少ない白身ですが、繊細なので、味付けや調理方法しだいでとても変わる。今夜は細かい鱗を生かした塩焼きだけど、これもコツが必要で、当たり前に焼くと鱗が立っちまう。でも、グジに手馴れた京都の料理人が焼くとふくらんだウロコが香ばしく、身もほくほくで、格別な味になる。ちなみに、ポンバル太郎流もそれだよ」
ぐじをひと口食べて目尻をほころばせたマリに、太郎が頷いた。
テーブル席の客たちもごぞって塩焼きを注文すると、龍二が口を開いた。
「ぐじは、酒蒸しや粕漬けもいいんです。でも、忘れちゃいけない秘訣があります。下ごしらえに、伏見の酒や粕を使うこと。これ、美江さんのこだわりでもあるそうです」
かつて若狭から京都へ街道を使って届けていたぐじは、日持ちさせるために一夜干しや干物が主流だった。そして、京都の料理人は干して封じ込めたぐじの旨味を引き出すために、伏見の酒を使った。柔らかな軟水で仕込んだ伏見の酒は、別名・女酒。だから繊細なぐじにピッタリだと、龍二はその冷酒を飲み干した。
伏見の酒を美江から酌されたマリが、ぐじの皮の美味しさに目を丸めながら言った。
「私からすると、ぐじは、美江さんのような京女(きょうおんな)たい。希少な美しさと繊細さを持ってるけど、こんな人は、なかなか東京には出てこない。若狭や京都を、ずっと大切にしとるねぇ」
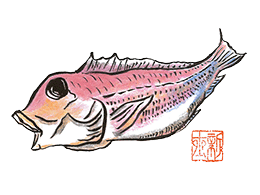
その言葉に、同感した客たちが笑顔で頷いていた。
「ところで……東男(あずまおとこ)に京女(きょうおんな)って言うじゃない。平先生、美江さんに惚れてんの? まったく、羨ましいや」
酔いの回ってきた銀平がちょっかいをかけると、美江がクスリと笑って答えた。
「そんなことを訊く無粋な男はんは、京都のおなごに嫌われまっせぇ。けど、うちと平先生の関係が気になりはりますか? いやぁ、うれしおすわぁ」
美江にサラリとかわされてしまった銀平を、太郎がいじくった。
「考えてみりゃ、人生をグジグジぼやくことにかけては、お前は希少な男だよなぁ」
それをきっかけに、どことなく落ち着いた雰囲気だった店内に、にぎやかな笑い声が聞こえ始めた。
