神宮外苑の銀杏並木が今年は早めに色づき、そぞろ歩く人たちの背中に黄昏を色濃く映している。
青山通りの雑踏の中では吐く息の白さに気づかなかった高野あすかだが、ポンバル太郎の通りに入ると、店の換気扇から立ち昇る湯気に目と鼻も奪われた。
「美味しそうな匂い。蟹だ、それも蒸したズワイ蟹!」
足早に扉を押し開けると、店内に満面の笑みが並んでいた。それもそのはず、今夜の突き出しには、大ぶりの蟹の足が二本も添えてある。
カウンター席の右近龍ニが目を凝らす本日のおすすめメニューには、蟹刺し、蟹しゃぶ、焼き蟹などが連なり、二つ隣の席で飛び切り燗の本醸造を飲む誠司は物欲しげに冷蔵ケースの蟹ミソを見つめている。
「どうしたい、誠司。遠慮しねえで食ってみな。こいつは初物でも、新潟沖で獲れたベニズワイ蟹だから、さほど高くはねえ。兵庫県の間人(たいざ)で揚がる本ズワイ蟹なら、浜値で3万円は下らねえが、ベニならその半値だ」
蟹を納めた火野銀平が、純米のぬる燗の盃をなめながら勧めた。
それを耳にして、本日のおすすめメニューを遠巻きにしていたテーブル席の客たちが「おっ、そんなに安いの」と食い気を見せた。
「バラしちゃ困るな、銀平。だけど身の詰まりは上々だし、甘みも濃いぜ」
太郎が持ち上げた一杯のベニズワイ蟹は、重かった。
「いけねえ、つい築地の口癖が出ちまった。お客さん、そう言うわけだからよう、腹いっぱい食ってくんな」
苦笑いする銀平が振り返ると、テーブルの客が舌なめずりして手を挙げた。
高野あすかも「初物、頂きまーす!」と龍二の横に座り、蟹の甲羅蒸しと新潟の大吟醸を注文した。本ズワイ蟹よりも淡白であっさりしているベニズワイ蟹と大吟醸は、あすかの定番である。
すると、カウンターの隅にいた初老の男が、ふいに口を開いた。
「お姉さん。大吟醸じゃ香りが強くって、初物の甲羅蒸しの旨さが分からねえべ」
黒い厚手のブルゾンにジーンズ姿の男は、訛った口端をゆがめた。ブルゾンの肩口には、"中越水産 佐渡”」とオレンジ色の刺繍がほどこされ、魚臭さを漂わせていた。
不審顔のあすかは、築地の同業者かと銀平に視線を送ったが、いつになく口ごもり、文句一つも返さないでいる。
妙だなと龍二も感じた途端、拙速な誠司は啖呵を切った。
「おう、うちのアネさんにあやつけようってのかよ。このお方は、日本酒ジャーナリストなんでぇ! あんたみてえなトウシロウに、文句つけられる筋はねえよ」
酔いが回って前のめりになる誠司を、あすかが「ちょっと、やめてよ!」と制した時、押し黙っている銀平の手が誠司の襟首をつかんで、席に引き戻した。甲羅蒸しを手にした太郎が厨房からしかめっ面で現れても、銀平は無表情だった。
「銀平の兄貴、ガツンと言って下せえよ」
歯がゆげな誠司の声を、男が遮った。
「言えねえわけがあるんだよ。そうだべ、火野屋さん・・・・・・あんた、築地の火野屋だろ?」
銀平のジャンパーにある白いロゴマークに、男の目つきが鋭くなった。
動けずにいる誠司とあすかの前に、太郎は甲羅蒸しを置いて男と向き合った。
「お客さん。銀平を捜して、ここへ来たんでしょう。うちに入って来た時、銀平をじっと睨んでましたね」
対峙するかのような太郎に、男は皮肉げに「ふん」と鼻息で返事をした。
「何だってぇ! それじゃ、はなっから兄貴をつけてたってことかよ!」
いきり立つ誠司を、あすかと龍二が二人して抑えた。荒ぶる誠司を、ようやく口を開いた銀平が止めた。
「佐渡さんのお祖父さんのことは、うちの銀次郎から聞いてたよ」
冷めてしまっている盃の酒を飲み干して、銀平が一気にしゃべった。
昭和の半ば、火野銀次郎は初めて佐渡の水産会社からベニズワイを仕入れたが、火野屋の若い職人が横流しをして、大迷惑をかけた。それが尾を引いて佐渡の会社は傾き、今の中越水産に吸収される羽目になった。火野銀次郎は、一生の不覚だったと死ぬまで悔いてたと、吐き出した。
店内が静まり、テーブル席の客は焼き蟹を頼みそびれた。
「だかよう、佐渡さん。あんたとこのベニズワイ、うちの祖父さんは大好きだった。安くって、旨くて、越前産のズワイにも引けを取らねえてよう」
真顔を上気させる銀平に、今夜は酒をほとんど口にしない理由が佐渡に気づいていたからだと太郎は悟った。その斟酌を、佐渡の強い新潟訛りが跳ね飛ばした。
「今さら、言いわけこくでねえ! 誰が横流ししようが、つまるとこ、おめさんの祖父さんがやったことにちがいねんだ! 俺は家業を奪われて、今は中越水産の営業マンとして、また築地にベニズワイを売り込みに来てんだ」
佐渡は言葉に詰まると、太郎の作った甲羅蒸しに手を伸ばしてつぶやいた。
「嫌でも、憎い築地によう」
取りつく島もないと、あすかと龍二の顔は色を失くしていた。太郎も腕をくんだまま、黙るしかなかった。
ふいに立ち上がった銀平は佐渡に頭を下げると、沈黙の糸をほぐすように口を開いた。
「じゃあ、うちでどうなんで。もう一度、火野屋にやらしてくんねえか」
「バカこくでねえ! 二度とだまされてたまるか」
佐渡が唾を飛ばして言い放った時、玄関の鳴子が音を立てた。
「ちょいと邪魔するぜえ。今日、築地で会った中越の佐渡さんだったな。ちょうどいいや、あんたに頼まれた仕入れ先の紹介、こいつの火野屋でどうでえ」
築地の親方である葵屋の伝兵衛が、作務衣姿で立っていた。
唖然とする太郎たちの脇で、銀平はうなだれたままだった。
「冗談じゃねえ! 葵屋の元締めさんは知らねえだろうが……」
言いかけた佐渡を、伝兵衛のしゃがれた声が差し止めた。
「おめえさんに教えておきてぇことが、あってよ。旧・佐渡海産の父っつあん、つまり、あんたの祖父さんと火野屋の銀次郎さんは、ベニズワイ蟹の甲羅蒸しに新潟の本醸造を燗で入れて、混ぜて飲んでたってえ、粋な話よ」
言うが早いか、伝兵衛は佐渡の手から甲羅蒸しを取ると、畏まっている誠司から湯気の残るお銚子を奪った。そして、甲羅蒸しになみなみと酒を注ぎ、佐渡の顔の前に差し出した。
「この飲み方、うちの祖父さんの癖だべ。それを、火野屋の銀次郎もやってたとは……」
受け取りながら、佐渡が甲羅蒸しに口をつけた。見守るあすかと龍二が「どうなるの?」
と口を揃えた時、ひび割れた甲羅の隙間から酒が洩れた。
「あっ、もったいねえ」と誠司が素っ頓狂な声を発すると、伝兵衛が言った。
「そのひびを、あんたの祖父さんはいつも指で押さえて飲んでただろ。新潟から築地に来た時ゃ、それをこぼさねえように、火野屋の銀次郎さんも指で押さえながら、二人で回し飲みしたんだよう。だからよう、俺が言いてえこたぁ、分かるだろ」
伝兵衛の分厚い両手が、微動もしない佐渡の背中と丸まっている銀平の背中を叩いた。
頷く銀平の手が洩れているひび割れを押さえると、佐渡はひと息吐いて甲羅酒に口をつけた。張り詰めた空気をほどくように、太郎がもう一杯のベニズワイ蟹を手にした。
「葵の親方。この飲み方、うちでやらせて頂きやす。龍ちゃん、俺とどうだい!」
「太郎さんとなんて、願ってもないすよ」
と龍二はあすかを気遣いながら答えた。
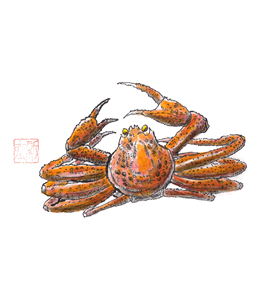
テーブル席からも甲羅酒が注文されると、伝兵衛が緊張している誠司に
「どうでぇ、やっちゃばの若けぇの。わしと、甲羅酒をやるか」
と肩を叩いた。
「めっ、めっそうもねえ! バチが当たりまさぁ……となりゃ、俺のお相手は」
誠司があからさまに鼻の下を伸ばして、あすかを見つめた。
ゾッとした顔のあすかに誠司が近づくと、太郎の腕が首根っこへ伸びた。
「おめえは甲羅酒より、銀平に叱られるコラ酒が似合ってんだよ!」
爆笑する佐渡と銀平の手のひらが、甲羅酒を大事そうに持っていた。
