隅田川を抜ける秋の風が、冷えた夜気を都心に運んでいた。上野公園の周りは、金木犀の甘い香りに満ちている。
ポンバル太郎の通りにも同じ匂いが漂い、肌寒さにスーツの肩をすくめるビジネスマンをほっと和ませていた。すっかり衣替えした男たちの中、目立っているのは、いまだにTシャツ姿の火野銀平である。
「へっ、ヘェックシュン! こんちくしょう! やけに冷えるじゃねえか」
独りごちた銀平がクシャミした勢いで扉を開けると、枡の鳴子が暴れた。
そのけたたましさに、口数少なく背中を丸めていた店内の客たちがいっせいに振り向いた。なぜか、寒くなって燗酒を飲む時は、誰もがその姿勢になる。
ただ、年中燗酒の平 仁兵衛だけは、いつもと変わらずカウンター席で背筋をしゃんと伸ばしていた。
久しぶりに隣から平へ酌をしている菱田祥一が、銀平に飽きれ顔で言った。
「銀平さん、まだ半袖かよ。粋がる歳じゃないだろ、四十前のオヤジなんだからさ。風邪の抵抗力だって、落ちてるよ」
「てやんでぇ。築地の現場じゃ、まだまだ汗だくよう。それによう、豊洲移転が先送りになっちまったもんでテンテコ舞いだ。風邪なんて、引いてるヒマはねえや……へっ、へっ、ヘックション!」
銀平の負け惜しみが鼻水とともに飛び出すと、テーブル席の男たちが「お、おわ! きっ、きたねえな!」と盃を手で隠しながらのけぞった。
すると、カウンターの隅を占めている小さな客たちの一人が声を発した。
「素直じゃないねぇ。オヤジの上に、頑固が付いてら。銀平さん、もう、いい歳になってきた証拠だよ」
箸を振りながら剣がイジると、両脇に座る同級生らしき少年たちもクスリと笑って、手元の料理を口へ運んだ。三人が食べているのはサンマの塩焼きに雉の釜飯、そして、湯気の立った鯛のアラ汁で、どうやら剣が同級生を夕餉に招いたらしい。
「やい、剣。おめえ最近、背丈が伸びて、俺に迫ってきたからって、生意気な口をきいてんじゃねえぞ。そっちの少年たちも、さっさと飯食って、家へ帰ぇれ! 父ちゃん、母ちゃんを心配させんじゃねえ!」
銀平が剃った頭に血管を浮かせて凄むと、友人の一人は青ざめた。だが、もう一人の少年は銀平へ視線を釘づけて、口を半開きにしていた。
「まったく、築地のオヤジって、古くさいんだよ。修一君、清太郎君、気にしないで、ゆっくり食べてってよ……あっ! 何なら、さっき見たアンコウを、父ちゃんに頼んで小鍋にしてもらおうか」
剣が言ったのは、開店前の厨房で三人が目にした平べったいアンコウだった。
太郎が手にするグロテスクなアンコウを目の当たりにした修一は後ずさりしたが、清太郎は「なんだ、小さいべ」と呟いた。わけ知り顔だが、どこか寂しげな清太郎が、太郎は気になった。
修一と清太郎を気遣う剣に銀平は、大人げなく、また、ちょっかいを出した。
「太郎さん一人じゃアンコウの吊るし切りはできねえから、俺がさばくのを手伝うんだよ。だけど、お前たちに食わすのは、もったいねえや。お子ちゃまに、俺が目利きした宮城沖のアンコウの味が分かるはずがねえ」
うつむいたままの修一が、「剣ちゃん、俺、帰るわ。ごちそうさま」と膳の半分も箸を付けずに店を出て行った。
「あっ、待って!」と制する剣を、振り返りもしなかった。
素っ気ない修一の態度に、銀平が
「まったく、最近のガキは躾がなってねえ! ご馳走になった飯を残すなんて、バチが当たらぁ」
と冷蔵ケースから宮城の純米酒を取り出しながら、追い打ちをかけた。菱田は「しい! もう、よしなよ」と、唇に指を立てながら銀平を隣に座らせた。
だが、今にも泣き出しそうな剣は声を震わせて銀平を罵った。
「な、何だよ、銀平さん! 小学生を脅すなんて、最低なオヤジだよ! それに修一君も清太郎君も、東日本の震災のせいで4年前に宮城の塩釜から東京へ引っ越したばかりなんだ。親だって、亡くしてんだ。もっと優しくするのが、まともな大人のすることだろ!」
剣の甲高い声が水を撒いたように店内を静かにすると、太郎のため息が厨房から聞こえた。気まずげな菱田の盃を置く音が、銀平の言葉を誘った。
「あっ……いや、そいつぁ、すまねえ」
口を濁す銀平に、しょうがないといった顔の太郎が「さっさと、吊るし切りを手伝えよ」と助け船を出した。
所在なさげに厨房へ入る銀平は居残っている清太郎に「坊主、悪かったな……許してくれ」 と詫び、武骨な手で頭をさすった。
その途端、清太郎の丸い瞳から大粒の涙がこぼれ、嗚咽が洩れた。
「ああっ! 泣かしたちゃった。ただでさえ銀平さんの風体はおっかないのに、手を出すんじゃないよ!」
うろたえる銀平の手を、剣が払った。だが、清太郎は首を横に振った。
「ち、ちがうんだ。俺、何だか、嬉しくなっちゃって……銀平さんって、津波で死んじゃった父さんに似てんだ。飲んでる宮城のお酒も、同じだよ。それに……父さん、アンコウの吊るし切りが上手だった」
突然、問わず語る清太郎に、剣が目をしばたたいた。ふだん無口な清太郎とは思えない、興奮した口調だった。
清太郎の両親は、塩釜で民宿を営んでいた。それは剣も聞いていたが、父親が小さな漁船を持ち、自分で獲った魚を調理していたとは知らなかった。
「それで、あのアンコウは小さいってわけか」
太郎がほほ笑みながら近寄ると、清太郎は「ごめんなさい、生意気言って」と頭を下げた。 ようすを覗うテーブル席の客たちが、鼻先を赤くしていた。
声を失くしていた銀平が、拳を握りしめて「俺は、大馬鹿野郎だ!」とつぶやき、剃った頭を自分で殴ろうとした。その拳を、菱田がはっしとつかんで言った。
「悪いと思うなら、今夜は、亡くなった父親代わりになってやりなよ」
平もドギマギしている銀平へ目尻をほころばせ、二度、頷いた。
「えっ……俺は、どうすりゃ、いいんでぇ」
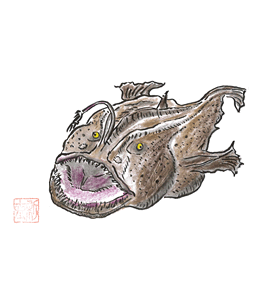 「簡単じゃねえか。アンコウの吊るし切りを見せて、後は二人で鍋をつつくだけだ。お前は、宮城の純米酒を飲みながらな」
「簡単じゃねえか。アンコウの吊るし切りを見せて、後は二人で鍋をつつくだけだ。お前は、宮城の純米酒を飲みながらな」
素直な銀平に苦笑する太郎が、早く厨房へ来いと顎を振った。
平が銀平の手にする宮城の純米酒を盃に注いで、太郎へアンコウ鍋を注文した。
「私のおごりにしてくださいね。テーブルのお客さんにも、お出ししてくれませんか。今夜はちょっぴり寒いから、あったかい話と鍋が、みんな嬉しいですねぇ」
テーブルの客が返した「ご馳走さまです」の言葉は、鼻づまっていた。
厨房でアンコウを吊るした銀平が鼻を啜り上げて、清太郎を振り返った。
「父さんみてえな、うまい鍋にしてやっからよう!」
コクリと頷いた清太郎の瞳が、銀平の背中をまっすぐに見つめていた。
