気温19℃の関西出張から東京駅へ帰ったビジネスマンたちは、新幹線ホームに着くなり、予想だにしなかった都心の花冷えに肩をすくめた。駅ビル内の「黒塀横丁」の居酒屋では、桜前線の北上が酒の肴になっている。
夕刻に上京した中之島哲男もポンバル太郎に着くやいなや、大阪城公園や桜ノ宮にほころぶソメイヨシノのスマホ写真を、先客の平 仁兵衛に自慢した。
これ見よがしな中之島に店内の客たちは飽きれたが、カウンターの隅に座るロイドメガネの白髪男は、無精鬚を撫でつつ何度も横顔を凝視していた。
出がけの陽気のせいで、気の早い中之島は春物のコットンジャケット姿。カウンター席へ座るなり、東京の肌寒さにクシャミを連発していた。
「ううむ。どこぞの別嬪さんが、わしの噂をしとるなぁ。春や春! ウキウキしまんなぁ」
上機嫌な中之島を、平の隣で搾りたて大吟醸の香りに耽る高野あすかが茶化した。
「オッちゃん、アホ言うてんと、この丹波の大吟醸、めっちゃええ匂いやから飲んでみいな」
おかしなイントネーションのあすかの関西弁へ、厨房から明石鯛の昆布じめを手にして現れた太郎が吉本ギャグばりにズッコケると、店内の客たちに大ウケした。
だが、拍手の中でカウンター席の男だけは
「ダボがぁ。きしょくの悪い関西弁は、やめんかい!」
とドスのきいた声で凄んだ。ダボとは、アホと同じ意味だが、兵庫県の方言である。
男の彫り深い目元に、あすかは思わず視線を外した。ところが男の目は、あすかの前に置かれた大吟醸の一升瓶を睨んでいた。
あすかをかばおうとする平が作り笑いを返している間、中之島は微動だにせず男を見つめていた。いや、正確には、男が手にしている自前の平たい盃をであった。瓦けに似た盃は、底が赤かった。
「平白磁に、朱色の蛇の目模様……お前、まさか」
中之島の鼻っ柱が、見る間に赤らんだ。と同時に、オシャレした太い体躯がふらついた。
椅子から崩れてカウンターへしがみつく中之島の手首を、太郎がとっさに握りしめた。間一髪、転倒はまぬがれたが、中之島の息は荒かった。
中之島のようすに、太郎だけでなく、平とあすかも、男との尋常ならざる関係を直感した。しかし、ひと言も口に出せない三人の前で、男は「やっぱり、哲ちゃんか。偶然すぎるやないか」と冷めた口調で平白磁の盃を飲み干した。
その独特の浅い盃を使って、男は七尺の冷酒を五回の酌で飲んでいた。それは飲むでもなく、利くでもなく、酒の素性を探るようなしつこい味わい方だった。太郎もうすうす、業界のうるさ型と察していた。
空気が張り詰めるカウンターに、朱色の蛇の目がなおさら怪しく映っていた。
あすかに支えられて座り直す中之島が、神妙な表情で男に訊ねた。
「25年間、どこに雲隠れしてたんや……味見酒(あじみざけ)の辰夫こと、柳沢辰夫。それにしても髪も鬚も真っ白けになって、若き天才と呼ばれた面影もないな」
中之島の表情は悲しげだが、声音には安堵したような響きがあった。
「ふっ、味見酒か。そのあだ名も、もう忘れてもうた。今は、バカ舌の辰夫に落ちぶれてるわ」
うそぶく柳沢は、丹波の大吟醸を注げとばかり太郎へ顎を振り、平白磁を差し出した。
しぼりたて生原酒の大吟醸は黄金色で、朱色の蛇の目がオレンジ色に変わった。トクトクと一升瓶が音を立てる中、中之島は無言だった。
ためらい顔の平とあすかに代わって、酒を注いだ太郎が口を開いた。
「どうして、朱色の蛇の目なんですか?」
「俺は、視覚に障害があってな。青い蛇の目より、こっちの方が自分には合うねん」
柳沢の瞳がふっと寂しげな光を帯びた時、中之島が問わず語った。
「それを作ったんは、わしの妹のきみ子や。こいつは、義理の弟。きみ子の婿さんでな。昔、大阪の料理界でブイブイ言わしとった男や。それに丹波の生まれ育ちやから、その大吟醸には目がない」
中之島は柳沢の隣に席を移しながらも、顔を背けて語り続けた。柳沢も咎めることなく、黙って盃を嘗めていた。
かつて、お互いに新進気鋭の料理人として、中之島は「キタの哲」、柳沢は「ミナミの辰」と大阪の健啖家の人気を二分するほどだった。日本酒への造詣もお互いにしのぎを削り、ついには全国の利き酒コンテストで大阪代表の座を競うほどになった。
その矢先、柳沢は忽然と姿を消した。辰夫ときみ子は、まさに夫婦善哉。女遊びや借金もないオシドリ夫婦だけに、中之島には青天の霹靂だった。
行列のできる店は、柳沢がいなくなると灯が消えたように寂れた。その二年後、憔悴したきみ子は心臓発作で亡くなったと、中之島はカウンターの上で両拳を握りしめた。
赤裸々な打ち明け話に、店内が水を打ったように静まった。
平白磁を啜った柳沢が、酒に濡れた鼻髭を指でぬぐいながら言った。
「哲っちゃん。俺の気弱な性格は、まだ直ってないわ。けど、この盃だけは、捨てられへんかった……いつか、きみ子に謝ろうと思うて、後生大事に持ってたけど……すまん」
指の震えがおさまった中之島は空になった盃を奪うと、怒りを鎮めるかのように酒をゆっくり注いだ。
「わしはあの利き酒コンテストの前に、きみ子に会うてた。お前を勝たせるために、手加減しようと思うてな。けど、きみ子は『兄ちゃん、情けは人のためならず。あの人のヤワな性根を治すためにも、真っ向勝負してや』と突っぱねた。脆弱なお前を変えるきみ子の手段の一つが、朱の蛇の目を入れたこの白磁の盃やった」
中之島は、飲み干した平白磁を柳沢の前に滑らせた。
周囲の予想に反して、柳沢は反論もせず、深く頷いて酒を注いだ。その目元に懺悔の気持ちを感じたあすがが声を発しかけると、平は肩に手を置いて制した。もう少し待てと、目で伝えていた。
盃を干した柳沢は、朱色の蛇の目を指でなぞりながら語った。
「きみ子は色覚に劣る俺のために、ちょっとずつ酒を利けるこの平白磁を作ってくれた。けどなぁ、俺の体の問題はそれだけやなかった……この舌、見てみい。食べ物の味が薄うなって、しまいには口の中に何もないのに、いつも苦い味がする。あのコンテストの前に突発した、一生治らへん味覚障害やった」
柳沢の伸ばした舌は、平たちが目を疑うほど茶色く変色していた。
周りの反応を確かめた柳沢は中之島の顔を探るように見返したが、いっこうに動じていなかった。
「辰夫。わしが知らんと思うたら、大まちがいや。わしに教えてくれたんは、お前がその病気を打ち明けもせんかった、きみ子本人や。お前は気づいてなかったやろが、その舌が治るように、あいつはお百度参りまでして願掛けした。お前の味覚の衰えを、あいつは全部お見通しやった。けどなあ、負け犬になるかならんかは、気弱なお前自身との勝負やった。きみ子はそこに賭けたくて、わしの画策も拒否した。けど、お前は結局、逃げた。きみ子にも自分にも優しすぎたんや」
言葉を失くしたままの柳沢へ、中之島が相棒にしている手提げバッグの底から古びた布を取り出した。差し出したのは何の変哲もない黄ばんだ木綿だったが、柳沢の指先が開くと刺繍が施してあった。
“一生、あんたの目と舌になってあげる”
今度は、愕然とする柳沢の指先が震えていた。
「その盃を包んでた木綿。平白磁をつかんだまま先走ったお前が、忘れていった包み布や。わしも、この木綿は捨てられへんでな。ずっと鞄の中に持ってたんや。もし、これを先に見てたら、お前、逃げたりできへんかったやろ」
悔しさとも諦めともつかないため息が、中之島の口から洩れた。同時に、崩れた柳沢の嗚咽が客席に響いた。
店内の誰もが口をつぐんだが、あすかは辛抱できずに声を発した。
「でも、中之島さん。生きて逢えただけで、いいじゃないですか。たった一人の、義弟さんでしょ。やっと平白磁と木綿が一緒になれたのは、きみ子さんの導きにちがいないもの」
あすかは、東日本大震災の罹災者。正味の言葉に、中之島は我に返った。
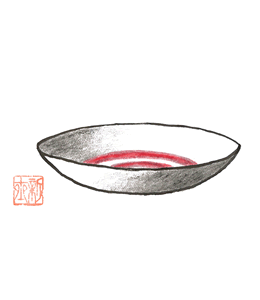
「優しすぎる亭主でも、いいじゃないですか……ご兄弟なんですから、きみ子さんの代わりを中之島さんがしてあげれば、いかがですかねぇ。もはや二人とも、似た者同士の古参酒匠でしょ」
だんまりを通していた平が、ゆるやかに笑った。
「ちげえねえ。そういや、中之島の師匠。大阪の店で助っ人を捜してたでしょ。まさに柳沢さんなら、打ってつけじゃねえですか」
ここぞとばかりに太郎が続けると、中之島と柳沢が「う、うむ」と顔を見合わせた。
ためらっている柳沢の手から中之島は平白磁を取って、木綿で包んだ。
「まあ、オッサン二人の割烹も、おもろいかもしれんな……辰夫、いっちょ、やってみいへんか」
「おおきに、哲ちゃん……いや、兄貴」
柳沢の瞳からこぼれたしずくが、盃を包んだ木綿の刺繍を濡らしていた。
