千鳥ヶ淵にしだれる桜の枝が、こころなしか薄墨色に色づいていた。
皇居の濠端を歩く人たちの瞳に万朶の花が揺れるのは、二週間後のようである。
日暮れになっても、ここ数日に予想されていた春一番はまだ吹かず、ヤキモキしているのはポンバル太郎の客たちも同じだった。長引く寒の戻りに、小鍋料理やおでんの注文が好調で、カウンター席の右近隆二は大根と鯨のサエズリ(舌)ばかり注文している。
その隣で備長炭を熾した七輪と山菜鍋を前にする平 仁兵衛は赤い頬をほころばせ、太郎へ山廃純米酒のお燗を頼んだ。そして、小鍋の山ウドをうまそうに食べると、湯気の向こうへ視線を送った。
「春の足音は、ちゃんと聞こえますねぇ。太郎さん、あの錫漆の酒器を、使わせてもらえませんかねぇ」
日頃の平らしからぬ猫なで声に、右隣の手越マリが顔を覗き込んだ。平が見つめる厨房の棚には、朱色の地肌に桜吹雪の絵柄をほどこした盃が一つ、その後ろには同じ朱色と藍色の漆を織り交ぜた徳利が控えていた。どちらも、地金は錫である。
つまり、錫の表面に漆絵を描いた豪華な酒器だった。
「そう言うたら、あの錫器は誰も使うとらんね。太郎ちゃんが客に出すのを、あたしは一度も見とらんばい。なしてかね?」
名器の趣きが漂う盃と徳利に、マリは自分にも一度使わせろと言わんばかり唇を太郎へ突き出した。マリの声音にテーブル席の客たちも錫器へ目を凝らしたが、龍二は伏し目がちに答えた。
「マリさんは、もっぱら冷酒派だから必要ないでしょ。それに、あんな高価な錫器なんて、晴れの日の燗酒にしか似合わないっすよ」
龍二はマリだけでなく、平へも聞こえよがしに声を高くした。
その理由は、ポンバル太郎へ通い始めた頃、火野銀平から
「あの錫の酒器も、亡くなったハルちゃんの形見の一つだ」
と聞かされていたからだった。
朱と藍のツートーンの徳利なら、2色の盃があるはずである。しかし朱色の盃しか置いてないのは、太郎が藍色の盃をマイ猪口として大事に保管しているにちがいない……あの錫漆は、夫婦の酒器……そう語った銀平の憶測と同様、龍二や高野あすかも錫漆の酒器のことに触れようとしなかった。
むろん平とてそう察しているはずなのに、鈍感なマリならまだしも、今しがたの無理強いに龍二は驚いた。
ただ気になったのは、日頃は目立たない位置にある錫漆がいくぶん前に置かれ、磨かれているように輝いていることだった。
マリをはぐらかした龍二はしばらく錫漆を見つめていたが、はっと我に返ると、柔和な平の表情がこちらを覗き込んでいた。
「今夜の錫漆の光り方は、まるで誰かに使われるのを待ちわびているかのようでしょう……あの酒器や太郎さんの気持ちを思う皆さんの内心と、私も一緒です。でも、ずっとタブーを守ってきたじゃないですか。だから、私が口火を切ってみたんですよ。太郎さん、ペアの藍色の盃も、ぜひ、見せてもらえませんかねぇ」
平は龍二の心境を図星で見抜くと、厨房の太郎の背中へ声を投げかけた。まだ酔ってもない平の口調はゆるりとしていながら、真剣だった。
カウンター席は沈黙し、マリの固唾を飲む音が聞こえた。
「平先生、実は持ってないんですよ。ハル子が、若い男性にあげちまったんです。あいつが亡くなった時、もう錫器の箱の中に藍の盃はなかったんです」
カウンターに並ぶ面々が、唖然として声を失くした。少々のことでは動じない平でさえ、右手から箸を落とした。
「ええ! 夫婦の酒器じゃなかね? どげんしたとね!? ハルちゃんが不倫しよったと?」
鼻息を荒げるマリを、思わず龍二が「しぃ! 声がデカいよ!」と諌めた。平までもが目を丸くすると、太郎は苦笑しながら答えた。
「そうじゃねえよ。ハル子の性格で、若い蔵人を頑張らせようとしてやったことだ。ハル子が生きてる頃に聞いた話じゃ、宮城県から来た19歳の瀬川って若僧で、うちへ燗上がりのする酒を試して欲しいと持ち込んだらしい。その日、俺は出かけていて、ハル子はその酒の欠点や出来の悪さを厳しく指摘した。瀬川君は繊細な男で、しおれるようにため息しか返さなかった。そこで、ハル子はあの錫漆を差し出して、『悔しかったら、この錫漆にふさわしい燗の酒を造ってみなさいよ』とハッパをかけたんだと。まったく、あいつらしいや」
結果、瀬川は、必ず錫漆の名器で飲むにふさわしい燗向けの酒を造ってリベンジすると約束し、ハル子はその日まで預けておくと藍色の盃を手渡した。
そう語る太郎へ、店内の客たちが耳を傾けていた。
「そげんこつじゃ、藍の盃が戻るのはいつになるか分からんばい」
しかめっ面するマリに、龍二がもう一度、棚の錫漆を見つめながら言った。
「でも、太郎さん……やけに今日は、あの酒器が光ってるんですけど」
太郎は頷いて、ひと呼吸すると
「3月11日の夜、ハル子が夢枕に立ってね」
とつぶやいた。
常連たちは動じなかったが、新顔らしき客たちは一瞬、蒼ざめて
「東日本大震災の日だ」
と口走った。
「あいつ、両手に錫漆の藍の盃と一升瓶を持っててよ。瀬川君にあげたはずの盃をどうしてお前が持ってるんだよと夢の中で俺が訊いても、ハル子は笑うだけでさ……その翌日、うちの電話が鳴った。かけてきたのは、瀬川茂吉。瀬川君の父親だった。瀬川君自身は東日本大震災で津波に呑まれ、亡くなってたそうだ」
瀬川の父・茂吉は、ハル子からもらった盃を返しに行きたいと太郎へ伝えた。そして、息子は志半ばで逝ったが、その仲間たちが造り直した燗向けの酒を、錫漆の盃で味わってみて欲しいと頼んだ。だが、ハル子が病没したと知った茂吉は、電話の向こうで絶句した。
無言の茂吉に、太郎は夢枕に立ったハル子の話をして、待っているからと繰り返した。
「でも、そのまま電話は切れちまった……それでも来てくれねえかと思って、錫漆を磨いてみたんだが」
太郎のため息に、客席の誰もが肩を落とした。その空気を和らげるように、平が口を開いた。
「無粋な電話をしてしまった……茂吉さんは後悔したんでしょうねぇ。でも、私は思いますよ。太郎さんの不思議な夢は、瀬川君や錫漆の酒器、燗酒の虫の知らせというよりも、もっと大きな東日本大震災のことを忘れてないかと私たちに教えているんじゃないですかねぇ。ハル子さんは、そういう肝っ玉の太い女傑でしたから」
平の言葉尻が強まると、龍二とマリは深い相槌を打った。テーブル席からは脅えた表情が消え、「そうだよな、復興はこれからだよ」とグラスを合わせながら口にした。
どこかほっとして錫漆の酒器を見つめた太郎が
「そうだ……思い出したよ。その夢の最後に、銀平の野郎が出やがった。ハル子と同じ一升瓶を持ってんだよ」
と独りごちた時、玄関の鳴子が音を立てた。
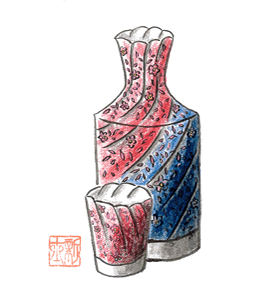
「太郎さん、そこで道を尋ねられちまってよ。ポンバル太郎をご指名で、瀬川さんってんだ。一升瓶を持ち込みたいそうでぇ! いいだろ!」
火野銀平が、白髪まじりの男を連れていた。男のはにかんだ赤い顔に、太郎だけでなく、客たちも瀬川茂吉だと直感した。
いつもの能天気な銀平だったが、今夜ばかりは、ハル子の夢先案内役に誰もが拍手した。犬猿の仲のマリなど、目頭を潤ませている。
「まったく……錫漆なんて、似合わねえ奴なのになぁ」
けなしながらも満面をほころばせる太郎に、銀平が小首をどぎまぎとした。
「な、なんでぇ? 新しい客を連れて来たってのによう。ハルちゃんなら、もっと喜んでくれたぜぇ」
ぼやく銀平へ、棚の錫漆がキラリと光ったように思えた。
