夕刻からの秋雨で都内はグッと冷え込み、新橋や渋谷の居酒屋では鍋料理が人気を呼んでいる。トマトスープやカレースープといった変わり種の鍋メニューを、若いグループが囲んでいた。
ポンバル太郎でも客からのリクエストで、小鍋料理を始めた。小さな素焼きの七輪に銅鍋を乗せ、あっさりとしたカツオダシで野菜や魚介類を食べる上品な寄せ鍋である。薬味は柚子とアサツキだけで、太郎があくまで正統派の鍋しかやらないのは、日本酒の旨味と楽しんでもらうためだ。
食材の味を引き出す本枯れ節のダシがすこぶる好評で、連日、売り切れ状態。今夜も午後10時半を過ぎ、客足が引けた店内には柚子の残り香が漂っていた。太郎は、厨房で山盛りの小鍋を洗っている。
テーブル席の七輪のかたづけを火野銀平が手伝っていると、フラリと独り客がやって来た。閉店まで残り20分のタイミングに、思わず銀平は表情をゆがめた。
「お客さん、11時には閉めちまうけど、かまいませんか?」
ぶっきらぼうな銀平の物言いに三十歳前後とおぼしき男は立ち止まったが、その視線は厨房の中を探っている。野暮ったいブルゾン姿と右手に提げる四合瓶らしき包みに、早合点した銀平が口を尖らせた。
「ひょっとして、あんた酒屋かい? こんな時分にやって来ても商談にならねえぜ」
「……いえ、酒屋じゃなくて、酒蔵で働いています。与和瀬ハル子さんを訪ねて来ました」
男の声が人気のない店内に響くと、太郎の水洗いする音が止まった。銀平も、亡くなったハル子を訪ねた男に、一瞬、言葉を失くした。
厨房から太郎が現れると、男の顔は戸惑いと緊張を綯い交ぜにした。
「ハル子はいませんけど、どんなご用件ですか?」
ハル子の名を呼び捨てにする太郎に、男がハッと表情を変えた。そして、一升瓶をカウンターへ置くと、襟を正して一礼した。
「御主人の太郎さん……ですね。初めまして。私、石川県の蔵元で酒造りをしている、辛坊 雄太郎と言います。ハル子さんとお目にかかったのは8年前で、当時は静岡県の蔵元で追い回しをやってました。その頃、ハル子さんと約束した酒がようやくできたので、お持ちしたのですが……ただ、ずいぶん前のことなので、ハル子さんは私のことを憶えていないかも知れません」
辛坊が口にした追い回しとは、見習い蔵人のことである。
太郎は小鍋を拭く手を止めて、小さく「辛坊……」とつぶやいた。律儀な辛坊に、銀平は今しがたの態度を消してカウンターの座席を勧めた。
「とすれば、ハルちゃんの性分からして、新人だった辛坊さんに説教でも食らわしたのかい」
銀平の愛想言葉に、辛坊は席に座りながらブルゾンの内ポケットからビニール袋を取り出した。透けて見えるのは真っ二つに折れたガラスの棒で、下半分は試験管のような形だった。古びたガラスは、いささか茶色がかっていた。
「……それって、浮秤(ふひょう)じゃないか。これがハル子と関係あるのかい?」
太郎は腕組みをして、店の神棚を見上げた。その視線の先にあるハル子の写真に、辛坊が息を呑んだ。
「えっ!? もしかして、ハル子さんは?」
「ええ、4年ほど前に逝っちまってね。遠路を来てもらったのに、申し訳ない……せっかくだから聞かせてもらえませんか、ハル子との縁や浮秤のこと」
閉店前ながら冷酒グラスをカウンターに置く太郎の目元が、辛坊に四合瓶の包みを開けろと伝えていた。しばしの間、茫然自失だった辛坊は、おもむろに包み紙を開いて語り始めた。現れたのは、レッテルの貼っていない酒だった。
「山廃仕込みの純米酒です。日本酒度は+9と高めで、コクがありながらキレも持たせ、熱燗に向いています。ただ、ハル子さんと出逢った頃の私は、真逆の酒を造りたかったんです。日本酒度-3ぐらいの甘い酒でした。これからは若い人たちに好まれる甘口が主流になると思い込んで、生意気にも先輩たちへ食ってかかってました。それでも認めてもらえず、悔しまぎれに、この浮秤を叩き割ってしまった。しかも、蔵を見学されていたお客様のハル子さんの前でした」
日本酒度を測る浮秤の中には、水銀や鉛が入っている。割れると有害物質が飛び散る危険性もあり
「御得意先の前で何たる醜態だ、恥を知れ!」
と蔵元は辛坊を叱りつけた。
ハル子は、口角泡を飛ばす蔵元を諌めつつ
「今どきの若い子にしちゃ、大した度胸じゃないですか……だけど、大事な商売道具を粗末にするのは、名前のわりに辛抱が足りないなぁ」
と辛坊を茶化した。
そしてハル子は蔵元に断りを入れ、何を思ったのか、辛坊と二人きりで昼食を共にした。
型にはまらない辛坊の物言いや、目指している甘い酒造りに、ハル子は黙って耳を傾けた。ひとしきり辛坊が論じると、ハル子は態度を豹変させた。
「今のあなたじゃ、どんなお酒を目指しても評価されないわ。辛坊さんに足りないのは、技術や経験じゃない。同じ志を持って酒を造ろうとしている仲間への尊敬や心遣いね……あの年季の入った浮秤。値段だって高価だけど、もっと価値があるのは、あなたの先輩やこの蔵を育てた職人たちの汗や心が詰まっている道具でしょ。それを腹立ちまぎれに壊すなんて、酒の神様の恐れを知らない不届き者だよ」
辛坊は滾々と説教され、次に逢う時には、酒だけでなく、人となりも醸して欲しい。先達を敬う仕事をしろとハル子から念を押された。
それでも辛坊は、聞き入れなかった。
辛坊の居場所は徐々に狭くなり、ハル子の諭した通り、浮秤の事件から仲間たちに白眼視された。
孤立した辛坊は3年目に静岡の蔵元から去り、実家のある金沢へ戻ったと言った。
「酒造りは、もう諦めようと思いました。どこに行っても、こんな自分じゃ通用しないと落ち込んでいた時、辞めた蔵元から荷物が届きました。それが、この割れた浮秤でした」
荷物を開けた辛坊は、蔵元を去ってまでこんな仕打ちをされることに愕然とした。だが、そうではなかった。
送り主は蔵元だが、中に入っていた一通の手紙はハル子から差し出されていた。
「この浮秤から逃げては、ダメよ。あなたは、この壊れた浮秤の重みを乗り越えてこそ、いい酒造りができる。そうでなきゃ、どんな世界で、どんな仕事についても、ダメだよ」
初めて逢ったあの日、ハル子はすでにこうなると察して、浮秤を残すよう蔵元へ頼んでいた。その心遣いを知った時、ようやく自分を真っ新にする覚悟が生まれたと、辛坊はもう一度、神棚の写真を見上げた。
太郎は辛坊の視線を追わず、苦々しさとも諦めの気持ちともつかない長いため息を吐いた。
静まる店内の窓ガラスを、強まった雨脚が叩いた。会話をひと区切りさせた辛坊が、四合瓶の封を開けた。
ポン! と心地よい音の余韻が、銀平の口を開かせた。
「ハルちゃんらしいや……いつも、てめえはそっちのけで、人の事ばかり気にかけてよ」
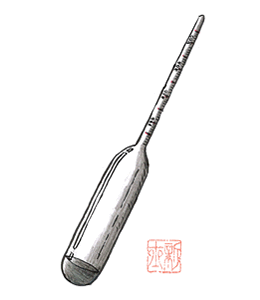
四合瓶の酒の香りが、カウンター席に広がった。甘い華やかなものではなく、しっかりとした山廃らしい風味だと銀平は感じた。
その時、太郎がおもむろに戸袋から茶封筒を取り出し、辛坊の前に置いた。“辛抱用”と筆書きされていた。
呆気にとられる辛坊に、太郎は得心した笑みを浮かべた。
「亡くなった後、ハル子の荷物から見つけたんだよ。今まで、俺も気づかなかった。この“辛抱用”って、辛坊さん用の意味なんだな。あんたに散々説教しときながら、字を間違えてやがる。そそっかしいたら、ありゃしねえや」
その言葉に辛坊の震える指先が封筒を開くと、真新しい浮秤が入っていた。
辛坊の両肩が小刻みに揺れると
「ようやく一人前ね。おめでとう!」
ハル子の声音をまねた銀平が、いたずらっぽく笑った。
振り返った辛坊の瞳から、とめどない涙があふれていた。
