東北各地から錦繍の便りが届くと、ようやく神宮外苑の銀杏並木は黄金色を帯び始めていた。夕刻の冷えた風に、ビジネスマンやOLたちが襟をすくめている。
ポンバル太郎の通りでは、軒下の空っぽになったツバメの巣が冬の近さを伝えていた。
「やけに冷える夜だぜぇ。こりゃ、まずは熱燗だ!」
火野銀平が、剃り立ての頭を革ジャンへ亀のように縮めながらやって来た。その表情はカウンター越しの湯気を見るなり、ニンマリとした。
「おい剣、仏頂面して何やってんだよ……あっ、お燗番か。こりゃ、いいや。おめえ、昔の丁稚小僧みてえだぜ」
湯気の中に、眉をしかめた剣の表情が見え隠れしていた。御仕着せの半被には、お燗をつけている秋田酒の銘柄が抜かれている。剣の手元を覗き込むと、南部鉄の茶釜に白磁のお銚子が湯煎されていた。
亡くなったハル子が大事にしていた“燗どうこ”代わりの茶釜である。
銀平の目線に気づいたカウンター席の平 仁兵衛が、黒い釜の肌を瞳に映してつぶやいた。
「南部鉄器でお燗をつけると、不思議に味が柔らかくなる。ハル子さんの口癖でしたねぇ」
平の手にする盃の薄い湯気が、ゆっくりとした口調を包んだ。
まるで時代小説に描かれているようなシーンに、隣席のジョージは見入っていた。
「日本酒は世界でも珍しい、温めて飲む酒ですね。ニューヨークでも、“ホットサケ”は人気です……でも、私は日本に来てから、お燗酒を飲む人をあまり見かけません。冷酒派が多いですね」
ジョージの問わず語りにも、ふてくされた剣は返事せず、右手で温度計を弄んでいる。それを見とがめた太郎が、茶釜の湯を指先で確かめた。
「ちゃんと湯煎を見てねえと、熱くなっちまうだろ! 中途半端なお燗番をやるんじゃねえ!」
いつにない太郎の強い語気に、剣が頬をふくらました。カウンターの真ん中に座った銀平はテーブル席の女性グループを一瞥して、剣をひやかした。
「はは~ん。おめえ、今日はお燗番で、お姉ちゃんたちにチヤホヤしてもらえねえからイジケてんだろ?」
「ち、ちがわぁ! あの客さんたちが好きな無濾過生原酒の仕入れを、父ちゃんが止めちゃったんだよ。だから、腹が立ってんの」
いっぱしの口を利くようになった剣が、上気した顔で冷蔵ケースを見つめた。確かに、ケースに並ぶ無濾過生原酒の瓶はわずかである。しかも消えた銘酒は、売れ行きのいい甘口の酒ばかりだった。
剣のボヤキが聞こえたのか、テーブル席の女性たちは気まずげにうつむいた。
太郎が長いため息を吐いて、湯煎の中から白磁のお銚子をつまみ上げた。
「まったく。図体ばっかり、でっかくなりやがって……親の心、子しらずだぜ。俺はむげに無濾過生原酒を減らしてんじゃねえ。うちの日本酒には、季節感や風情ってのがなきゃいけねえ。だから一年中、無濾過生原酒ばかりってのはダメなんだよ。秋は、お燗酒の季節だ。あったけえ酒で、夏バテした五臓六腑を癒すってのも日本酒ならではだ。そいつを忘れねぇように、お前にお燗番をやらしてるんだよ!」
その言葉を熱心にメモするジョージの横で、平が空っぽになったお銚子を太郎と交換した。
「剣君、お燗番って大事な仕事なんですよ。私が子どもの頃は、親戚が集まる正月やお盆の酒席に必ずお燗番がいました。たいていは、その家の娘がやるんです。それはね、女性の方が温度に敏感でデリケートだからです。もちろん、若い娘さんがお燗の番をしてるだけでも美味しく感じますしねぇ」
テーブル席を気づかって愛想笑いを浮かべる平は、いささか鼻の下が伸びて見えた。その横顔を、高野あすかが冷やかした。
「あら、平 先生。よければ、テーブル席の面々に、お酌を頼みましょうかぁ」
いつの間にか現れたあすかは、テーブル席の女性たちと挨拶を交わしている。顔見知りらしい一人がお燗番のことを口にすると、あすかも剣に諭した。
「私も大学生の頃、実家にいらしたお客様へお燗番をしたのよ。酒蔵のお燗番って、単に温度を見るだけじゃないの。今のように冷温貯蔵がちゃんとできる設備がなかったから、お酒によって新しい、古いがあった。風味が変わるし、酸味も出るから、お酒の状態を確かめて、一番適した美味しく飲める温度に燗をつけたの」
あすかの解説は、料理の味噌や醤油の味つけの濃淡によっても、お燗の温度を変える話しにまで及んだ。取り巻く女性たちが「さすが、蔵元の娘ねぇ」とあすかに感心すると、いつしか剣も惹き込まれ、真顔になって温度計をお銚子に刺した。やはり酒匠の息子である。
太郎はあすかの助け舟に目顔で礼を返したが、銀平は気に入らないようすで
「けっ! 江戸っ子は、めっぽう熱っちいのをつけてくれといやぁ、通じるんでぇ!」
と、剣にお銚子をよこせとばかりに顎をふった。
その時、玄関の鳴子が音を立てて、しゃがれた声が響いた。
「お待たせしたねぇ、あすかちゃん! おっ、剣坊! 今夜はお燗番かい? イカしてるじゃないの」
久しぶりに聞こえたのは、屋形船の老女将である松子の声だった。どうやら、松子を囲んでの女子会のようである。
甥っこの銀平は苦虫をつぶした顔になったが、松子は鼻眼鏡の中からジロリと睨みを効かせただけで、若い頃にやったお燗番の思い出を口にした。屋形船が流行った昭和三十年代、娘盛りだった松子は毎晩のように船座敷のお燗番に立ったと懐かしんだ。
「お燗番てぇのはねぇ、常連さんの好みの温度や味を覚えてなきゃいけない。だから、いつも手先の感覚を大事にしてたの。それにねぇ、客席に目を光らせてると、今日は常連さんの飲むペースが遅いなぁとか、注文が少ないなぁって気づくんだよ。そうするとさぁ、お客さんに体調が悪いっの?って、声がけするんだ。そんな気配りも、喜ばれたもんさ。だから、あれこれ機転の効く娘がお燗番をしなきゃ、ダメなのよぉ」
松子が皺深い口元にしなを作ると、聴き入っていたあすかと女性客たちが口をそろえた。
「あっ! だから、お燗番の娘 イコール 看板娘!」
松子は溜飲を下げるかのように、和服の前袷をポンと叩いた。その粋なしぐさに平が目尻をほころばせ、盃を飲み干した。
銀平は、げんなりした顔で言った。
「けっ! 遥か昔の、化石みてえな看板娘だろうがよ」
「何だってぇ! やい、銀平! お前みたいに気の利かない奴に、お燗番なんてできないさ。それより明日も築地は早いんだから、とっとと帰りな。はい、あんたは、ちがう意味の看板だよ!」
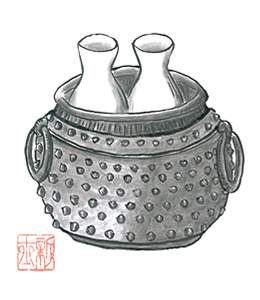
松子は銀平に勘定書きを押しつけると、飲みさしのお銚子を取り上げた。
「何てことしやがる、このババア! ええい、剣! 早く、俺にお燗をつけろ!」
すると、剣があ・うんの呼吸で湯煎しているお銚子の首をつまんで手渡した。しかし、その口元は笑いを噛み殺している。
「うあっちち! ばっか野郎、こんなに熱いの、飲めっかよう!」
「だって、江戸っ子は、めっぽう熱っちいのをつけるんでしょう」
とぼける剣に銀平が歯噛みすると、松子がダメ押しをした。
「だから、あんたはもう、お看板なの!」
銀平の困り顔が、お燗酒の白い湯気と客たちの笑い声に囲まれていた。
