篠つく菜種梅雨が、都内の桜を散らせている。
千鳥ヶ淵や市ヶ谷の神田川添いには、ソメイヨシノの名残りを惜しむ人波が続いていた。だが大半は中国からの観光客で、満開の八重桜の下がやけにかまびすしい。
曇り空を引きずるかのように、ポンバル太郎に座った火野銀平も沈んだ顔である。カウンターの上には、魚の入ったらしきビニール袋が置いてある。
夕方から強まった雨脚のせいか、ほかの客は誰もいなかった。
いつになく灘の上撰を飛び切り燗で注文した銀平に、お銚子の首をつまむ太郎が言った。
「飛び切り燗なんて、珍しいじゃねえか? 春風邪でも引いちまったか」
「いや……風邪じゃねえんだけど。ちょいとばかし、胸の奥が冷えちまってよ。太郎さん、魚善の次郎さんが癌で、余命三ヶ月てんだ」
太郎の注ぐお銚子の白い湯気が、ふいに乱れた。
「な、なんだって! あの元気者の親爺さんが……いつ、分かったんだよ?」
顔を見合わせる二人は、まばたきひとつしない。
魚善は火野屋とともに太郎が仕入れている築地の魚屋で、そもそも銀平の紹介で知り合った。火野屋は先々代の頃から魚善を師と仰ぎ、魚の目利きや品定めの腕を仕込まれた関係である。社長で今年61歳の次郎は、銀平が慕う兄貴分だった。
「半月前ってんだ。だから次郎さんが大好きな酒を、今晩は飲みたくなってよ。あの人、夏でも熱い酒が好きなんだ。今は、ドクターストップかかっちまって飲めねえ。今日、病院へ見舞いに行ったらよ、『俺の代わりに、上撰、飲んでおいてくれよ。冥途のみやげに、あのバカ息子が作る肝あえを、もう一度だけ食いたかった』て笑ってたよ」
盃に受けた熱い酒を、銀平は諦めきれないといった顔で一気飲みした。
太郎が思い出したように言った。
「息子って、翔太君のことか。確か2年前に、次郎さんの口利きで入った銀座の寿司屋を飛び出したんだろ。ギャンブルにのめり込んで、借金を作っちまったって聞いたが。今、どうしてんだよ?」
「内緒だけど、荻窪の小さな居酒屋で働いてる。次郎さんの面子をつぶしちまったから、今さら築地にゃ近寄れねえ。魚屋育ちで目利きも腕もいいんだが人の意見を聞かねえし、競馬競艇にうつつを抜かしやがったと寿司屋の板長は悔しがってたよ……次郎さんも翔太は勘当したなんて意地を張ってるけど、本当は逢いたいはずなんでぇ。男手ひとつで育てた、一人息子でよ。寿司屋で修業させて、いずれは魚善を継がせるつもりだったんだ」
銀平のため息が、お燗された上撰の匂いも吐き出した。
太郎が翔太を知ったのは、彼が魚善を手伝っていた調理師学校生の頃。弱冠22歳の翔太を銀平は弟のように可愛がり、一度だけポンバル太郎へ連れて来た。自慢げな銀平が太郎に頼んで魚をさばかせると、確かに出刃包丁や柳刃の使い方に慣れていた。酒は一滴も飲めない翔太だったが、銀平の肴に“カワハギの刺身の肝あえ”を作ったのを憶えている。
次郎の晩酌用に新鮮なカワハギが魚善へ入ったら家でこしらえるのだと、翔太は胸を張って答えていた。ただ、太郎からの肝あえの助言には耳を貸さなかった。
銀平もその時を回想しているのだろう。二人の間に、しばし沈黙が漂った。
「だからお前、こんな時間にカワハギを持って来たのか。次郎さんの代わりに、上撰の燗酒とカワハギの肝あえってわけか……まあ、翔太君が作った肝あえはちょいと苦くて、塩っぱかったがな」
気をそらせようと太郎がカワハギの入った袋を手にした時、玄関の鳴子が小さな音を立てた。
客の気配に、銀平はようやく重い空気が消せるとふり向いた。途端に、目をみはって叫んだ。
「お、お前! 翔太!」
「銀平さん、すみません。太郎さん、お久しぶりです。たぶん、ポンバル太郎にいるんじゃないかと思って」
細身で長身のジャケット姿の若者が、申し訳なさげに立っていた。
ギャンブルに溺れて苦労を重ねたせいか、二年前に逢った時より翔太はやつれて見え、短い髪も白い物がまじっている。
気を取り直した銀平が、腕組みをして訊いた。その表情は険しさを増した。
「お前、まだ博打をやってんのか。次郎さんには、逢ったのかよ」
「賭け事は、キレイさっぱり止めました。ついさっきまで、病院にいました。親父に土下座して親不孝を謝りました。でも『とっとと帰れ!』とベッドで背中を向けられて。看護婦さんから銀平さんが来てたと聞いたもんで、矢も楯もたまらずここへ……不義理を許してください」
独酌を傾ける銀平は、背中を向けたままで言った。
「俺が許しても、次郎さんは、まだお前を許しちゃいねえんだろ。じゃあ、おめえはここにゃ座れねえぜ。どうせ、酒は飲めねんだ」
銀平が隣の席を一瞥して吐き下すと、カウンターへ近づく翔太の足が止まった。
「……そうですね。虫が良すぎますよね。俺、やっぱり帰ります」
翔太がうなだれた時、銀平は肩を震わせながらカウンターを叩いた。声を発しない銀平の前で、太郎が口を開いた。
「翔太君。それじゃ二年前のあんたと同じじゃねえか。いつまでも勝手に解釈してねえで、もっと素直に、しかもしつこく相手の話しを聞くんだよ。そのこらえ性のなさが、あんたをギャンブルに走らせたんじゃねえのかな。銀平の答えを、俺が代弁してやるよ。今夜のあんたがここにいて許されるのは、この厨房の中なんだ」
太郎が型のいいカワハギを袋から取り出し、俎板に置いた。銀平のもたげた顔は、見る間に紅潮した。その後ろで、翔太が茫然としていた。
「太郎さん、すまねえ。このバカ野郎! ぼうっと突っ立ってねえで、早く肝あえを作るんだよ。ただし! 太郎さんに味の秘訣をキッチリ教えてもらうんだ。次郎さんに認めてもらえる、味つけをよ!」
銀平が翔太の襟首をつかんで、厨房に放り込んだ。
「はっ、はい! 太郎さん、お願いします!」
答える翔太の顔に赤味が差すと、太郎はカワハギの皮を剥かせた。活きのいいカワハギは、シュルシュルといい音を発して裸になった。
「因果じゃねえが、カワハギってきれいに皮が剥げるだろ。だから、別名“ばくち魚”てんだよ。つまり身ぐるみすべて、剥がされるってわけだ」
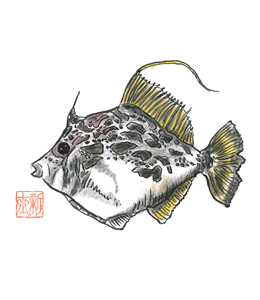
苦笑する太郎と銀平の前で、翔太は脇目もふらずカワハギを出刃でさばいた。そして赤い肝を柳刃で叩くと、太郎が灘の上撰を翔太へ渡した。
「あんたの肝あえに足りない味は、これなんだよ。築地で鉄火肌の次郎さんは汗っかきだから、塩辛い肴が好きだろ。だから、以前に食ったあんたの肝あえは塩味が強かった。それに肝の叩き方が雑だから、苦みも多い。それを旨く仕上げるなら、この上撰の風味を隠し味にすることだ」
キレのいい上撰の旨味を生かす太郎の助言に、翔太は深くうなずいた。
病院へ持参する重箱を太郎が用意すると、銀平が肝あえを味見して頷いた。
「次郎さんは、決してうまいとは言わねえだろう。おめえの、これからの人生のためによ。翔太、博打はこの先も御法度だ。だけど、この賭けだけは、しくじるんじゃねえぜ!」
肝あえのすり鉢に上撰を注ぐ翔太の瞳が、涙に潤んでいた。
