めっきり陽は長くなり、公会堂からの6時のサイレンが流れる中、通りには家路を急ぐ人たちの影が背伸びしていた。
ぬるい風に揺れる公園のキリシマツツジも、気持ちよさげに満開している。
早い時間のマチコは客待ち状態で、カウンター席では、松村の開いているスポーツ誌が小窓からの夕陽に染まっていた。その誌面には、カウンターの中の真知子も目を細めている。
「いよいよワールドカップか。また渋谷のフットボールカフェとか、大変な人出になりそうだねえ。」
昨夜の全日本代表エキジビッションマッチの記事を読み終えた松村がバサリと新聞をたたむと、真知子が「あっ、もう! 読んでたのに~」と眉をしかめた。
「えっ? あっ、ワリイ、ワリイ」
松村が新聞をもう一度開こうとした時、格子戸がカタカタと鳴って、日焼けしたスポーツ刈りの男の顔が覗いた。
「あのう……飯だけでも、かまへんですか?」
男の厚ぼったい唇が、遠慮気味に関西弁を発した。
「は~い、かまへんよ♪」
真知子が津田仕込みのイントネーションで答えると、松村が「おっ! 関西の人?」と嬉しげに振り向いた。
「えっ……ええ、まあ」
松村と同じ年頃と思える男は、はっとした顔で言葉を濁すと、そそくさと奥のテーブルへ歩き、真知子たちに背を向けて座った。
「あら、関西にしちゃ愛想がないわね」
つぶやく真知子に、松村は「だよね~、でも……あの雰囲気、どこかで見たような感じなんだなぁ」
カジュアルな服装の男の太い首回りと広い肩を、松村はしげしげと見つめた。
真知子が注文を聞きに行くと、男は鯖の煮つけ、ドンブリ飯に赤だしを頼んだ。
ひと揃えを運んだ真知子は「はい、これオマケね。よかったら、召し上がれ」とタコの軟らか煮の小鉢を置いた。
「すんません……うわ、ごっついイボやな!」
男はタコの吸盤の大きさに驚きつつ、それを口に放り込んだ。
「ふ~ん、うまいタコや」
彼が箸を動かすたび、締まった胸と肩の筋肉がググッっと動いた。
「大阪の常連さんが、明石から送ってくれたの。もうすぐやって来るわ」と真知子が答えたとたん、ガラリと戸が開いて津田が現われた。
「真っちゃ~ん。ええもん、持ってきたで。お~! 和也君もおったか、ちょうどええがな~。ほれ、和歌山のめはり寿司や」
津田が手提げ袋から取り出したのは、ラップに包んだ緑色の丸い塊だった。
「あ~、それ大好きなの! ほら、またオマケが増えたわよ、ラッキーね!」
真知子がほほ笑むと、青年はふっと顔を曇らせた。
「あら、ダメなの? めはり寿司?」
「え、いや……食べます」
その声に、松村が「ハッキリしねえなあ。嫌なら無理しなくていいじゃん。俺がもらうよ」と口を挟んだ。
真知子が津田にお燗酒を出す間も、松村はチラチラと男の後ろ姿を見ていた。津田はその横で、松村のスポーツ誌のワールドカップ特集に目を落としつつ盃を手にした。
「そういや、ワールドカップのメンバーが決まったなぁ。まあ、運・不運もあるけど、出られへん選手の分までレギュラーはとことん楽しむこっちゃ」
「でも、今回は3度目の正直で、頑張ってもらわなきゃ。ドーハの悲劇から、もう13年。やっぱ、頑張れ!ニッポンすよ」
「いや、まずは楽しむこっちゃ。気負いすぎて、責任を感じ過ぎたら、うまいこといかんもんや。日本人はついついそうなる。それに応援する側も、頑張れ!ど根性!しか言わへんがな。体の闘志は燃えてても、頭は冴えてないと勝負事は勝たれへんで」
二人の話が白熱してくると、テーブル席の男が立ち上がって「おあいそ、してもらえますか」とぶっきらぼうに言った。
「あら!? せっかくなのに」
めはり寿司の皿を手にした真知子に、カウンター脇まで来た男は「すんません」と軽く頭を下げた。
すると、辛抱できなくなった松村が「あんたなぁ、ほんまに関西人か? もうちょっとノリとか、愛想とかないの?」と関西弁で詰問した。
男はぐっと息を呑むように口ごもり、沈黙した。
新聞から顔を上げて男の顔を見つめていた津田が、口を開いた。
「まあ、ええやないか……ところでお兄さん、これ、あんたちゃう?」
津田がスポーツ誌に載っている13年前の日本代表の写真を指さした。
そこにはベンチ組も含めた大勢の選手が並び、隅っこの控えらしき選手は確かに目前の男に似ていた。
男は「あっ……」と言ったきり、顔を伏せてしまった。
「へっ? ちょ、ちょっと見せてよ」
松村は津田から新聞を奪い取ると、その写真と男をしきりに見比べた。
「そ、そうだよ! ボンバー浪速のボランチだった尾崎だ。それで、俺の記憶に残ってたんだ。当時の代表ではベンチ組で、出るチャンスはなかった。5年前ぐらいに膝の手術をした後は故障が多くて、ボンバーでも控えになってた。確か去年……J2のどこかのチームへ移籍したはず」
興奮気味な松村の声が途切れると、尾崎は蛍光灯を見上げて、ふうっと溜め息をついた。そして、テーブル席へ腰を下ろすと問わず語りした。
「そこも先月で自由契約……引退っちゅうわけですわ。昨日、国立競技場へ行ったんです。……選手らの姿を見てて、俺、あの時ピッチに立たれへんかったことがまだ悔しいんですわ。けど、もう膝は限界や。さっき、お客さんが言うた通りで、あの頃の俺は代表レギュラーになられへん不満と焦りから、闇雲に無茶な練習をして、あかんようになった気がします。でも、ようやって来たやないかちゅう自分と、ほんまにこれで終ってしまうんやちゅう自分が、まだ心の中で綱引きしてますねん」
尾崎の手のひらが、両方の膝をぎゅっと握り締めていた。
「さよか……尾崎はん、引退後は?」
津田が徳利と盃を手にしつつ、尾崎に訊ねた。
「まだ、具体的には。スポーツメーカーから営業でって声かかってますけど、商売は無理やと思います。後は、J2を目指している和歌山のサッカー協会から、ユースチームの監督候補に挙げてもろてます。もちろん、それだけでは食われへんから、副業もせなあかん。けど……もう、サッカーの仕事はせんでもええかと。何とのう、今の気分を引きずりそうですから」
しばしの沈黙が、店内に漂った。
尾崎のテーブルに座る津田は、真知子に盃をもう一つと目で伝えた。
津田が「どうや?」と徳利を傾けると、「すんません。今日はそんな気分では」と尾崎が返した。
とたんに「おい!」と声がして、ヒュッと何かがテーブル席へ飛んだ。
尾崎はすばやい身のこなしで反応し、それをヘディングで受けるとピタリと額に止めて、右手で取った。
ラップに包まれた塊は、松村の投げためはり寿司だった。
「あんた、それ好物だったよな。思い出したよ、昔サッカー雑誌の記事でプロフィール読んだ時に、そう書いてあった。尾崎選手の出身地は和歌山だった。好きな物なのに、どうして素直に好きと言わないんだ。今だってそうだろ、無意識に体が反応してたじゃない。サッカー好きなままでいいじゃないか。誰にだって、どんな人生にだって、運とか器のサイズてのがあるんだよ。それに俺たちサラリーマンには、リストラや解雇がざらにあんだよ。だけど、俺たちはいつまでも過去を恨んだり、悔やんだりはしない。そんなことしたって、いい明日は来ないよ」
珍しく酔っていない松村の声が、マチコに響いた。
尾崎は、めはり寿司をじっと見つめていた。
「それがサッカーボールに見えるんか、ピッチの色に見えるかは分からへんが、第二の人生でも、あんさんにしかできへんポジションがあるはずや。和歌山のサッカーの仕事もええかもなあ。まあ、ゆっくりと、楽しんで考えてみるこっちゃ」
津田がもう一度徳利を傾けると尾崎は「はい」と答え、今度は盃をぐっと飲み干した。そして、ほうっと満足げに息を吐くと、めはり寿司をひと口食べて「こいつのおかげで、目が覚めました」と笑った。
「そやけど、今日の和也君の言葉には、目をみはったなあ。ほんま、めはり寿司やで!」
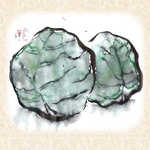 そう言ってテーブル席でおいでおいでする津田に、松村は胸を反らして立ち上がった。
そう言ってテーブル席でおいでおいでする津田に、松村は胸を反らして立ち上がった。
「まっ! 二流のサラリーマンでも、一流のスポーツマンより打たれ強いってことっすよ~」
すると、めはり寿司を頬ばる真知子が、すかさずツッコんだ。
「いつもは、目をつぶりたくなるぐらい三流なのにねえ」
4人の笑い声に誘われて、客たちが一人また一人とマチコの暖簾をくぐっていた。
