「東京も蒸し暑うなっとる。いよいよ、梅雨入りやな」
カウンターに腰掛けた津田は小ぶりの扇子を開いて、マチコの小窓からどんよりと曇る空を見上げた。
そう言いながらも「健康のためには、何はさておき、こいつや」と、いつものぬる燗を傾けている。
時計は午後4時を回ったばかりだったが、少し早めに着きそうだと連絡してきた津田のために、真知子は赤ちょうちんを提げた。
津田が厨房の真知子に声をかけようとした途端、ふいに激しく降り始めた雨が、包丁と俎板の音をかき消した。
「おっ、降ってきよった。こらぁ、ごっついぞ」
戸口から跳ね込む雨しぶきに、津田が格子戸を閉めようと立ち上がった。
その出会い頭に、二人の若い男が慌ててマチコへ飛び込んで来た。
「ちっくしょう、びしょ濡れだあ」
短い髪の男はノーネクタイで、白いワイシャツに肌が透けるほど濡れていた。
「あの、すみません。店、もう開けてますか?」
もう一人のTシャツに茶髪の男が、落ち着かない視線で店内を見渡しながら真知子に訊ねた。どちらも、25、6歳ぐらいに見える。
「……えっ、ええ。お料理はもう少し時間がかかるけど、お酒ならどうぞ」
一瞬ためらう真知子と黙りこむ津田の目が、短髪の男の肩口に止まっていた。
肌に張り付いたワイシャツは、青い筋彫りを映し出していた。
「あっ! じ、じゃあ、奥の席にします。ビールを2本下さい。健ちゃん、あっちへ座ろうぜ」
茶髪の男は、健と呼ぶ連れの肩に手を回し、刺青を隠すようにしてテーブル席へ座った。
真知子は、二人にビールと乾いたタオルを運んだ。うつむく茶髪の男の前で、健が「すまねえな、女将さん」とウィンクをした。真知子はニッコリとほほ笑んで、厨房に戻った。
カウンター席に戻った津田の耳に、ビールを注ぎ合う二人の声が聞こえた。
「なあ、純一。ここの女将、いい女だなあ。久しぶりに甘い匂いがしたぜ」
「健ちゃん! 声がデカイよ。それより、これからどうすんだよ? 仕事を探すにしても、今は3年前よりもっと不景気で、まともな奴でも働き口は無いよ」
「分かってるよ。心配するな、何とかなる」
健が人差し指をくの字に曲げて、ニヤリとした。
「はぁ、もういい加減、足を洗えよ」
純一という男の溜息が、人気のない店内に響いた。しかし、津田はそ知らぬ顔でタバコを燻らせていた。
「相変わらず、うるせえ奴だなぁ。純一、今日は迎えに来てくれて、嬉しかった。けどな、しばらく俺を放っといてくんねえか。とりあえず、金は借りてく。おい、早く出せよ」
その声に、真知子は一瞬、厨房から二人のようすをうかがった。
健は、無口になった純一から茶色の封筒を受け取ると、ズボンの尻ポケットにねじ込んだ。そして「じゃあな、また連絡する」と肩を叩き、暖簾をくぐって行った。
健が走り去ると、降りしきる雨音が、一人残った純一を包んでいた。
「お兄ちゃん、よかったら、一緒に飲まへんか?」
腕を組んだままの純一の前に、徳利と盃を持った津田が立っていた。
「あっ……俺、もう帰るから」
「まあ、一杯ぐらい、よろしやないか」
徳利を手渡された純一は、「はあ、じゃあ……少しだけ」と座り直した。
「あんさん、よっぽど、人がええんやなあ」と、津田が酌をした。その言葉に純一は「えっ?」と返しつつ、あどけなさの残る顔を赤らめた。
「ところで、さっきの健さんちゅう人、臭い飯を食うてきはったな」
「ぶっ! ゲホッ、ゲホッ。あんた、どうして知ってんだよ?」
純一は喉を詰まらせ、むせ返った。
「そら、あんなおっきな溜息吐いて、それらしい話しをしてたら、だいたいの察しはつきますわ。けど、いらんお節介のようですが、わしの勘では、あの人また塀の向こうに行きまっせ。さっきのお金、アブク銭にならんかったらええけどなぁ」
津田はゆっくりとタバコを取り出すと、端をトントンと机で叩きながら言った。
「……俺も、それは分かってんだ。でも、健ちゃんは、俺のせいで、ああなっちまった。だから、キツイことは言えないんだ。スリの常習犯で、もう5回も捕まってる。最初は、中学の時だった。」
純一は黙りこんだが、いきなり津田の徳利を奪ったかと思うと、酒をグラスに満たした。そして一気に飲み干し、健と自身の生い立ちを喋り始めた。
健と純一は、横須賀の下町に育った近所の幼なじみだった。
どちらも一人っ子だったが、健は母を、純一は父を早くに亡くしていた。お互いの親は深夜まで仕事を掛け持ちし、二人は兄弟のようにして育った。だが、彼らが中学2年になった年、純一の母親が過労で倒れた。
医療費どころか、純一は毎日の食事すら欠くありさまだった。
そんな窮状を、健が放っておけるはずがなかった。
生真面目で弱気な純一にはできない、万引き、置き引きに始まり、ついには電車内のスリにまで犯行は及んだ。
実際、中学を卒業するまで、純一の口過ごしは、そんな健の悪事に頼っていた。
「お前は黙ってろと。もし捕まってバレても、絶対、お前は関係ないからって、念押しされ続けた。でも、お互い、いい年になって、働き始めてからも、健ちゃんはスリが癖になってしまってた」
「刑務所から出てきて、なんべん働いても、あかん。そやろ?」
津田のゆっくりとした声に、純一はコクリと頷いた。そして、酔った赤い目で、財布から一枚の古ぼけた写真を取り出した。
「これ、小学校の頃の俺たちです。この頃が、一番仲良くて、楽しかった」
純一の目頭が、少し潤んでいた。
肩を組む二人の少年の写真を、白い指がそっと取り上げた。
「……純一君、だったわね。こんな色褪せた思い出は、今、あなたには必要ないんじゃないかな。あなたたちの人生は、まだこれからじゃないの。だったら、もう一度健ちゃんと、きれいな色の写真を撮らなきゃ」
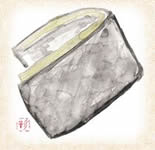 それを柔和な面持ちで見ていた津田が、口を開いた。
それを柔和な面持ちで見ていた津田が、口を開いた。
「純一君、今からスリをしといで。ただし、これは正義のピックポケットや。健ちゃん、まだそないに遠くへは行ってへんやろ。彼のポケットから、さっきの封筒、スっといで。それで、もういっぺん、ここへ連れて戻っておいで。それから、一緒に飲もやないか。今度は、ほんまに大事なことを、あんたの手で、健ちゃんの心のポケットに入れ直してあげるんや」
「……女将さん、おじさん」
純一の手にする写真に、小さなしずくが落ちた。
気がつくと雨は上がり、雲間からこぼれる夕陽が、駆けて行く純一の背中を照らしていた。
