ふくらみ始めた桜のつぼみを、小さな居酒屋マチコの赤い灯が彩っている。
十年間のOL生活に終止符を打ち、この店を始めてから二度目の春。ようやくと、割烹前掛けも板についてきた真知子だった。
料理の仕込みや段取り、客あしらいもまったくの自己流だったが、今では常連客が両手の指を越えるまでになった。棚に並ぶ地酒のラベルも、少し色あせたのもあれば、ご新規客がキープした真新しいものまで、ずいぶんと増えている。
左端の瓶はちょうど一年になるが、酒の主の名前は書かれていない。
マチコの開店の日に、最後まで座っていた老齢の男の酒だった。
男の白髪混じりの相貌と物静かな雰囲気は、人気の無くなった店内に似合っていた。
「女将さん。看板になる前に、ちょっとだけワガママを言うて、ええですかのう」
きつい訛りの男は、真知子に「もう一つ、盃を」と頼み、カウンターの左隣に置いた。
注いだ熱燗の淡い湯気に、男は、かすかな声でつぶやいていた。
酔い過ぎたのかしら、酒癖が悪いのかしらと、真知子は不安になる気持ちをおさえつつ、十一時を指す時計を気にしていた。
しばらくして、男は、なごり惜しそうに腰を上げ、真知子に礼を述べた。
「遅うまで、ありがとうさん。お陰さんで、息子とええ酒が飲めましたわ」
「えっ、あの……私、酔ってらしたのかと」
「わしの息子は、今日で二十歳になりますけん。今、生きとったらですが」
皺深い手には、一人の青年のスナップ写真が握られていた。優しげな笑顔が、男のまなじりと似通 っていた。
男は、ひと月前に四国から東京へ単身赴任したばかりだった。馴染みの店も無く、開店したばかりのこの店なら、一見さんでも無理を聞いてもらえるかと思ったらしい。
「開店のお祝いの日に、無粋なことをしましたのう」と何度も詫びながら、男は名も告げず帰って行った。
「あんな酒なんて、味も変わっちゃって飲めたもんじゃねえよ。どうせ来やしねえんだから、料理酒にでも使っちまいなよ」
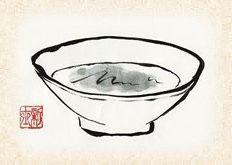 常連客はそう言うが、真知子は酒の味よりも、もっと大切なものを残しておきたかった。
常連客はそう言うが、真知子は酒の味よりも、もっと大切なものを残しておきたかった。
「いつかきっと、あの人が暖簾をくぐる日、息子さんの名と一緒に……」
そんな温かい赤ちょうちんにできればと思ったのが、一年前の今夜だった。
小窓から覗く満月に、男の素朴な笑みが揺れていた。
感慨深げに酒瓶へ手を伸ばす真知子の背中に、「こんばんは」と四国訛りが響いていた。
