
酔心一筋39年!柔らかなる水の本質を知り尽くす、職人の真骨頂
三原市内から清流・沼田川を眺めつつ、車でひた走ること30分。たわわに実った稲穂の彼方に、15,000石の美酒を醸し出す白亜の工場が現れます。
醉心山根本店を支えるこの沼田東工場は、昭和42年(1967)に完成しました。そして、その2年前から伝統の軟水仕込みを習い始めたのが、現在、工場長(杜氏)を任されている平 暉重(ひら てるしげ)氏です。
「19歳から醉心山根本店に勤めましたが、当時は季節労働、徒弟制度の時代でした。今年で39年目になりますが、思い出しますに、厳しく辛かった修行がつい昨日のようですね。成人の日に『実家に帰ってもいいでしょうか?』と先輩にお伺いを立てたのですが、仕込みの真っ最中でしたので、1日だけという条件で許可してもらったことを憶えています」
浅黒い顔ではにかむ平 工場長は、昭和19年(1944)生まれ。出身は岡山県高梁市で、いわゆる備中杜氏になります。農家の長男であったため、高校卒業と同時に家業を継ぎ、冬場の農閑期の出稼ぎのため醉心山根本店へやって来ました。
当時の醉心山根本店の蔵人は、ほとんどが備中出身者でした。同郷のよしみとは言え、歯に衣着せぬ直言は当たり前。仕事だけに止まらず挨拶から箸の上げ下げまで、徹底的にしごかれたそうです。
寒い冬の夜には、住み込み部屋でまんじりともせず、故郷の家族を想う日もありました。
しかし、そんな経験ができたからこそ今があると、平 工場長は満足げな表情を覗かせます。そのイブシ銀のような容貌が、筆者を惹きつけます。
醉心生え抜きの平 工場長は、歴代4名の杜氏の下で働いてきました。つまりは各人ごとの技を順次叩き込まれ、体の隅々まで醉心の酒造りが染み込んでいるわけです。
今年で杜氏10年目を迎えた平 工場長に、醉心の特長を語ってもらいました。
「飲み飽きしない、素直に旨い酒ですね。旨いと言っても甘くはなく、少し辛さもある。そして、麹米と掛け米に良質の山田錦をふんだんに使うことでしょう。だから、新酒でも良し、秋上がりでも良し。四季を通じて味と喉ごしが最高なのです。料理との相性も抜群で、現代的な脂っこい料理にも合いますから、若い方に好評です。濃醇過ぎるとコッテリした料理には合いにくいのですが、醉心はキリッと辛口でもある。それは、軟水仕込みのお陰なのです」
さすがに、醉心一筋39年。自信たっぷりの答えを聴いているうちに、こちらは唾まで湧いてきました。




さて、超軟水仕込みの麹造りについて、その秘訣を訊ねてみましょう。
「麹の出来が、極端に若いとダメです。軟水は醗酵を活発化する力が弱いので、旺盛な麹が求められます。ですから、当社では室に積む時間を幾分長くして、腰の強い麹を造ります。超軟水仕込みは通常の硬水系よりも10日も長くかけて、おだやかにゆっくりと醗酵させますから、麹も長時間働ける丈夫なものが必要になるのです」
沼田東工場には円盤型の製麹機が2機並んでいますが、これを効率良く“引き込み”と“盛り込み”に活用することで、どちらもしっかりとしたツキハゼの麹が生まれます。むろん、切り返し、仲仕事、仕舞い仕事はすべて麹蓋を使った手作業で、醉心の繊細な味わいが頷けます。
しかし、それも洗米、浸漬、蒸米など、原料処理段階の成功があってこそと、平 工場長は眉を引き締めます。
酵母については、一般の吟醸酵母や協会酵母を中心に採用しています。昨年の全国新酒鑑評会でも話題になった「広島吟醸酵母」の酒も手がけていますが、これは香りが高く、アルコール発酵が弱まりやすい酵母なのだそうです。
「アルコール発酵をしなければ酵母が働かず、つまりモロミは不健全になりやすい。そうなると香りもおかしくなって、味もクドくなる。しかし、アルコールを出さないようにして、醗酵を進めるのが広島吟醸酵母のコツですから、なかなかに難しいのです」
いずれにしても吟醸造りの原則は、酵母の活性を抑えつつ、低温でゆっくりと完成まで辿り着くこと。その上、超軟水の仕込みとあって、平 工場長も「本当に難しいですよ」と 問わず語るのです。


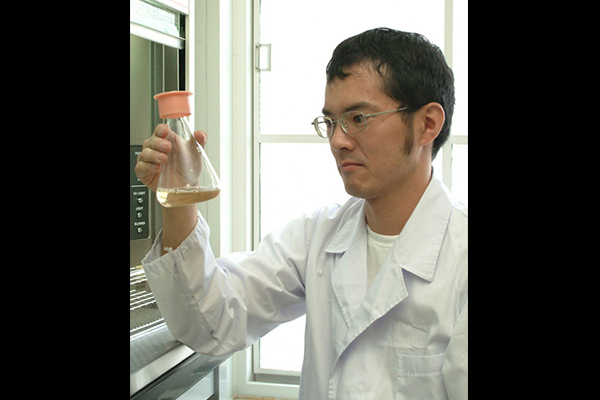
「酒米についてですが、当社の山田錦は兵庫県三田産の良質な米を特約で購入しています。昭和30年(1955)頃から先々代社長が精力的に山田錦に取り組まれ、以来、仕入れ先と入魂な関係をつないでいます。また、ようやく地元米の八反や千本錦の人気も高まってきましたが、こちらも早い時期から取り組んでいました」
ちなみに千本錦は、山田錦と広島県産の中生新千本(なかてしんせんぼん)を掛け合わせた地元好適米。これを使った“ブナのしずく”も好評ですと、平 工場長は頬をゆるませます。
ところが、ここ数年は入荷する米の具合が変化していて、腐心を重ねているそうです。
「まず、昔の米は天日干しで乾かしましたが、今はほとんどが機械設備による強制乾燥です。致し方ないことですが、当然、米は傷みやすくなります。また、天候や自然環境の変化で酒米そのものが変わっています。猛暑が続くと高温障害によって玄米の胴割れが多くなります。割れてしまうと削りにくくなりますし、吸水・浸漬にも細心の注意が必要になります。逆に、昨年のように冷害になると、米は削りやすいのですが、脆くて溶け過ぎるきらいがあります。ですから、その年の米の出来具合を早い時期から把握して、原料処理の工夫を検討しておくことが肝心です」
平 工場長としては、今年の中国地方は猛暑だけでなく台風に数回直撃されたため、特に気になるところですが、最新の情報では「出来栄えは、今ひとつ芳しくない」とのこと。
山田錦の諸白(もろはく)にこだわる醉心山根本店としては、農家出身で米作りに精通してきた平 工場長の経験・眼力に頼るところが大きいようです。



それでは、いよいよ真打ち登場! 超軟水“ブナのめぐみ”を紹介しましょう。
取材スタッフはしばし沼田東工場を離れ、ブナのめぐみのプロジェクトリーダーである山根 雄一 常務の案内で北西へ車で30分。そこかしこに原風景を残す加茂郡福富町を車窓に過ごし、鬱蒼とした山道を登ると、急勾配の斜面に造られた更地に2本の井戸と水神様の社が祀られていました。
「この奥はブナの原生林になっています。尾根と尾根の谷間なので、伏流水が合流し水圧が上がっています。
しかし、地下水脈は1メートル違っただけで水質が変わりますから、ここを掘り当てるまでは、期待と落胆の連続でした。水源の探索は地質学者や井戸の専門家にも加わってもらい、全部で8本掘りました。1本当たり約200万円を費やしまして、これを見つけてなければ、まさにすべてが水の泡になりました」
そんなジョークを言う雄一 常務の背後には、無垢透明なせせらぎが流れていました。この水も硬度14~15の軟水で、耳を澄ませて見ると微かに金属音を感じます。超軟水の流れは、そんな響きを奏でるそうです。
ところで、この“ブナのめぐみ”は11tトレーラーを使い、平 工場長が待つ沼田東工場まで運ばれています。
「この水を使えば酒の出来栄えがキレイで、味わいがきめ細くなりますね。?き酒をした際、後味が残らずスッと消えていくような、上品な味わいの酒。“女酒”と言う表現が、ピタリと当てはまります。まあ、切り替えて5年目だからこそ笑っていられますが、当初は不安と心労の連続でした」
水を替えることは、まったく新しい酒を一から造り直すのと同じであると、平 工場長は言います。ただ、この“ブナのしずく”は超軟水でありながら、ある程度の醗酵促進力を持っていることを実感したそうです。



それでは、これらの好条件を生かす人材の育成について、最後に訊いてみたいと思います。
沼田東工場はすでに社員制(年間雇用)に移行し、平 工場長以下8名の蔵人、5名のパートタイマーで仕込みを担当。蔵人の2名は30歳そこそこながら、平 工場長の双肩を担っています。
「現代っ子の彼らは、私が経験したような徒弟制度とは無縁ですし、大学や専門学校などを卒業し、技術者として入社しています。しかし私は、我々は職人であることを忘れてはならないと、常に口酸っぱく教えています。職人とは、最高の物を創ることに全力を注ぐことが使命であり、自分のなすべきこと、任されたことは、すべて責任を持って完結しなければならないと厳命しています。そして、いくら技術が発達し体制が変わっても、基本的な上下関係や人の和、チームの連帯感を理解できなければ、職人としては失格です」
とは言うものの、最近、平 工場長は若いリーダーにハッとさせられることが多いと言います。次の段取りに移る前に、「おやっさんっ! こうせにゃ、いけんのじゃないですか?」 と突っ込まれてドギマギし、その実、彼らの成長に胸を熱くすることがあるそうです。
平工場長の心配をよそに、若手社員はその背中をしっかりと見つめ、醉心の職人魂を受け継いでいるのでしょう。
そんな平 工場長へ、花道を飾るまでにやり遂げたい夢は? と訊いてみれば「若い人を惹きつける日本酒を造り出したいですね。ありふれた酒でなく、斬新でありながら日本酒の本筋を守っている酒です。例えば純米でありながら超辛口、スキッと爽やかな喉ごしがあって焼酎感覚に近いのですが、旨味もある。そんな個性的な酒を造りたい」と、まだまだ意欲的な答えが返ってきました。
インタビューを終え、沼田東工場から仰ぎ見れば、遥かな先には“ブナのしずく”の湧く鷹ノ巣山。目の当たりにする黄金色の稲並みが、間近に始まる醉心の旨い酒造りを約束しているようでした。








