
福生の人、町、暮らしのコミュニティーであり続ける、十八代の名門・石川家
おそらくは、400年前の姿をそのままに留めているであろう広大な蔵屋敷。蔵元の石川家に入る長屋門は風格と気品に満ち、紅梅を映す佇まいには幽玄さも漂っています。
そんな最初の感動もさながら、約3000坪の敷地を見学するにつれ、真綿に包まれるような温かい空気を感じるのです。静寂に満ちた木立の中では野鳥がさえずり、今しがたまでの街の雑踏が別世界のようです。
ひとたび石川酒造に足を踏み入れれば、誰もが心癒され、憧憬を描き、物想いに耽ることでしょう。“本物”が持つ有機的な空気がここにはある……しばし、筆者は歩を止めて感動に浸りました。
「お陰様で、皆様から同じような感想を頂いています。それは、当家が数百年の昔から地元の方々の集まるコミュニティーの役割を果たしていたからだと思います。石川酒造には大小さまざまな土蔵がありますが、これらは演出的に改修したり、配置したものではありません。本来、人が集まり、酒を飲み、語り合うという必然性、生活目的の中で生み出された空間なのです」
散策の余韻に耽る取材スタッフを白壁の社屋で迎えてくれたのが、十八代目当主・石川 彌八郎(いしかわ やはちろう)社長です。
「遠祖の頃より、当家は熊川村の名主として地域の方々とともに暮らしてきました。そんな絆を、現在までずっと大切にしています」と付け加える石川 社長。十八代にわたる長き歴史ですが、その要点を紐解いてもらいましょう。




「当家に残る古文書に、天明2年(1782)の“御用御鮎世話役起立答書”と言うものがあります。これは、多摩川で獲った鮎を徳川家の将軍へ献上する“御用”を賜った時のものです。当時の主は石川 亀三郎(いしかわかめさぶろう)となっており、襲名は弥八郎(やはちろう)で、現在もこれを継承しています。また代々の当主は、多摩川の氾濫対策、治水工事の責任者としての御用も委ねられていました」
石川 社長によると、江戸期の熊川村界隈には50軒から100軒単位の集落が20ヶ所ほど存在し、それぞれに名主が置かれていたそうです。それを統括する名主総代、いわゆる大庄屋が石川家でした。
熊川村は江戸幕府の天領(直轄地)であったため、総代の石川家はお上の意向を各名主たちに指導し、郡代などの幕吏に対しては、村を代表する長として報告、申請する立場にありました。
この大役は「庭場(にわば)」と呼ばれ、いわゆる、福生一円を取り仕切る肝煎り庄屋だったわけです。その一方で、石川家は地元産の石灰の売買や質屋などを営み、商人としての側面も備えていきました。


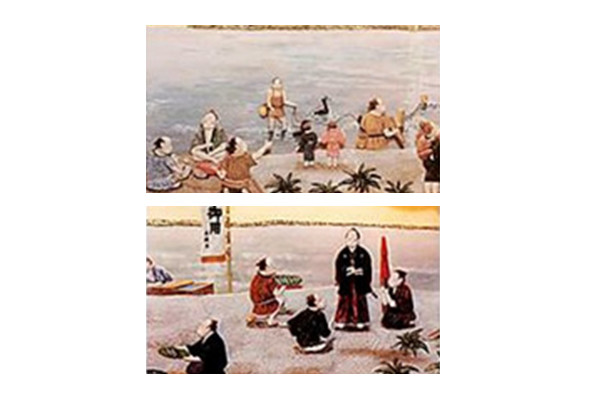

文久3年(1863)十三代目当主の石川 和吉(いしかわわきち)が、酒造業を始めます。彼は文化10年(1813)の生まれで、近隣の上川原村の指田家より養子縁組した人物でした。
名主役だけでなく商才に長けた和吉は、青梅産の縞の取引きも手がけました。さらに、余剰米を使用した酒造りを開始。ここに、現在の石川酒造の母体が創業したのです。
和吉の時代もそうですが、石川家の先祖は、その頃から地域内のさまざま人間関係を構築していたようです。現在、福生市には石川酒造を含め3つの蔵元がありますが、これらは古くから縁戚関係で結ばれているのです。
ここで、賓客訪問を受けた石川 社長とバトンタッチして登場されたのが、十七代目当主の石川 弥八郎(いしかわやはちろう)会長です。
「実は、当家の酒造りが始まったことは、多摩川と深い関わりがあるのです。現在の多摩川堤の基礎が出来上がったのは嘉永年間(1848~1854)でして、これによって熊川村の農作物の生産性は飛躍的に向上したわけです。年貢米さえ納めれば、残りは蓄え、これを使用して酒造りを始めたのです」
“多摩自慢”の銘柄には、そんな感謝も込めているのですよと微笑む石川 会長。その表情は、和吉の肖像とよく似ています。


創業時の蔵は、多摩川を挟んで対岸の小川村(現在のあきる野市)にありました。
その理由は、蛇行する流れによって土砂の堆積する小川村は土地が肥え、古くから稲作が盛んで酒蔵も栄えていたのですが、幕末になってその一つである森田酒造が廃業し、蔵を貸し出したためでした。
酒の銘柄は「八重桜(やえざくら)」で、この名は森田酒造の「八重菊(やえぎく)」と姉妹関係にありました。
その後、明治14年(1881)には、現在の地へ蔵を新築します。当主は十四代目の千代蔵(ちよぞう)、和吉の甥に当たる人物でした。
彼は熊川村に恵みをもたらした「熊川分水(くまがわぶんすい)」の整備に貢献しました。村をめぐる用水は、家々の洗濯などの生活用水として使われ、さらには米を搗く水車を回していました。千代蔵の功績は、現在も石川酒造内に引き込まれている清流に偲ばれます。
また、先見の明を持っていた千代蔵は、ビール醸造にも着手しています。
明治21年(1888)頃、横浜などの外国人居留地では人口が増え、ビールやワインの需要が高まっていました。
そこで石川酒造は「日本麦酒」の名称でドイツ式ラガービールを製造、横浜、東京方面へ出荷をしました。
しかし、キャップの欠陥によって瓶が破裂しやすく、やむなく継続を断念。2年後には、製造装置を売却しています。ちなみに、日本麦酒の商標(ラベル)には太陽の絵が(旭日)が描かれていました。これは、大阪の日の出ビールに売却しましたが、明治25年(1892)旭ビール(現在のアサヒビール)と商標権をめぐる訴訟も起こりました。
そして、ビール事業を中止してから111年後の平成10年(1998)、石川酒造は地ビール「多摩の恵」を生み出し、2年後のジャパン ビアグランプリ2000では、みごと金賞を受賞したのです。
以来、地元のビールファンを魅了し、蔵を改造したビアレストラン「福生のビール小屋」は、常連客や観光客、横田基地のアメリカ軍人やそのファミリーなどで連日盛況となっています。
1世紀を経た快挙に、おそらく千代蔵も空の上で祝杯を上げていることでしょう。





明治末頃の酒造業製造石高の番付けによると、石川酒造は2,551石。すでに、千石酒屋以上に成長していたことが分かります。
また、代々の当主は俳諧など芸術への造詣を深め、多くの文人墨客、画家と交流していました。彼らは、しばしば石川家に逗留したようです。
そうは言いながらも、当時の酒造りは、いずこの蔵元も発酵管理に不安を抱え、些細な失敗から品質を悪化させていました。石川酒造も例外ではなく、井戸水を何度も替え、醸造技術を練り直しながら、酒質向上に腐心していたようです。
と言うのも、大正8年(1919)銘柄「八重桜」を「八重梅」に変更してますが、これは、前年の腐造によって「八重桜」が台無しになったためでした。贔屓客からは、手の平を返したように「腐り酒」と揶揄され、結果として師匠である森田酒造の伝統にも泥を塗ることになったのです。
この汚名を返上すべく、生涯を賭して品質向上に努めたのが、十六代目当主・石川 真作(いしかわしんさく)でした。明治39年(1906)生まれの真作が石川家の身代を継いだ頃、時代は軍国化へ傾き、税制は酒造業をさらに圧迫していましたが、真作は「八重梅」を超える美酒を追求し、昭和8年(1933)には石川酒造の最高級酒として「多満自慢」を造り出しました。
また、昭和20年代は米の配給難や企業統制を乗り越えながら、日本酒業界へ多大な貢献を果たし、彼の功績を讃えて(財)日本醸造協会は「石川 弥八郎 賞」を設置しています。



そして高度経済成長期を迎え、昭和34年(1959)に現会長の十七代目・石川 弥八郎が登壇します。石川 会長は、福生市長を3期12年務めた人物でもあります。
昭和40年代、関東の市場にも灘・伏見メーカーの酒が普及しましたが、石川酒造の「多満自慢」は地元ファンに根強い人気があり、武蔵野から神奈川県にかけては絶大な人気を誇りました。また、昭和50年代から60年代の地酒ブーム期も左顧右眄することなく、堅実かつひたむきな経営を重ねています。
その要因は、石川 会長のこだわる地元密着主義にあります。
「私が家業に入った頃、東京には24軒ぐらいの蔵元がありました。それぞれが、生活必需品としての地酒屋でしたね。つまり、私どもは代々、福生の方々に欠かせないものを商っていたわけです。そして、当家そのものも地元の方々に無くてはならない存在でした。これを、本筋から外しちゃいけないと思います。戦後に横田基地が完成して、アメリカ兵の方々が福生に暮らすようになり、当社にも軍の方々やそのご家族がいらしゃるようになりました。酒を通じたさまざまな友情、文化の交流が生まれる中、日本人もアメリカ人も同じ地域に暮らす市民であり、もっと石川酒造の価値を多角的に見ることが大事だと感じ始めたのです」
この会長の言葉を具体的に推進したのが、子息の石川 彌八郎社長です。
現在、酒蔵の中にある旬の料理・蕎麦と多満自慢を楽しめる「雑蔵」、地ビール・日本酒とイタリアン料理「福生のビール小屋」は、福生市民とアメリカの人々で賑わっています。
さらに石川 社長は個性的なセンスを発揮し、蔵の中で日本酒を楽しみながらのピアノコンサートや美術展など、魅力的なアミューズメント空間を演出しています。
今なお、福生の人々を支え、潤し、コミュニティーであり続ける石川酒造。
温もりのある風景と歴史ロマン、そして“暮らしの中の幸せ”も醸し出す本物の地酒屋に、またいつか訪れてみたいものです。









