永代橋を霞ませる隅田川の流れに、観光用の屋形船が三艘ほど浮かんでいる。夏日を想わせる昼下がりの川風にはかすかに潮の匂いも混じって、新川公園のベンチに座る高野あすかと太郎の鼻先をくすぐった。
日本橋の卸問屋へ生貯蔵酒などの涼酒の試飲会に招かれた太郎は、偶然、会場で取材をしていたあすかと鉢合わせ、そのままポンバル太郎へ向かう途中だった。
「ここって、よくドラマの撮影に使われるの。永代橋がキレイだし。中央大橋やリバーシティ21の夜景もステキなんですよ。だから、デートスポットとしても人気なの。どうせなら、夜に太郎さんと来たかったなぁ」
利き酒が過ぎたのか、あすかの頬はほんのり赤らんでいる。口元にうっすらと笑みを浮かべる太郎に、少し酔っているあすかがしなを作って話しかけようとした時、しゃがれた声がした。
「昔、この辺りにはたくさん伝馬船が行き来していたんだ。お米や塩、お味噌やお醤油、それに東京湾で獲れた魚を船に積んだり、下ろしたりして、お江戸の町中に運んだのさ」
川岸の手すりにもたれかかる老齢の男が、水面にかがよう陽射しを眺めていた。カジュアルなチノパンツとチェックの半袖シャツが上品な横顔に似合っていた。その横で、孫とおぼしき女の子が何度も頷いていた。ジーンズにTシャツの容姿から、剣と同い歳ぐらいの小学生と見えた。
「お祖父ちゃんの好きなお酒も、そうだったんでしょ? 私、図書館の歴史の本で見たよ。お酒って、昔は関西から船で運んで来たんだよね。確か……下り酒だった」
「うむ! さすが絵里、歴女って自負するだけのことはあるなぁ」
ロマンスグレーの頭を七三分けした祖父が満面の笑みを見せると、孫娘は視線を注いでいる太郎とあすかへ自慢げに胸を張った。すると突然、あすかが拍手して言った。
「その船、樽廻船って言ってね。一年で百万個のお酒の樽を運んだの。昔の江戸の人たちって、たくさん飲んだのよね」
酔ったあすかの勢いに、太郎は苦笑しながら祖父に小さく会釈をした。祖父は柔和な顔で頷き返し、太郎たちに近寄る絵里へ目じりをほころばせた。
「へぇ! そうなの。じゃあ、樽廻船って何度も江戸と大坂を往復したんだね」
人見知りしないたちなのか、絵里はあすかの顔をマジマジと見つめ
「おばさんも、お酒好きでしょ。まだお昼なのに赤くなってるし、ちょっと匂うよ」
とたしなめた。
「おっ、お、おばさん!? ちょ、ちょっと、お姉さんじゃないの? でも、小学生からすれば、やっぱ、おばさんかぁ……」
真顔になって赤面したと思いきや、落ち込むあすかに太郎が腹を抱えて笑った。その声を、陽だまりに温もった風が川下へ運んで行った。
「こりゃ、あすかも形無しだな。まあ確かに、昼間っから隅田川べりで酒の匂いさせてりゃ、お姉さんじゃねえや。でも、お嬢ちゃんは歴史ツウだねぇ。おじさんにも何か教えてもらえないかな?」
太郎はなにげなく話しかけながら、亡きハル子の言葉を思い出していた。それは、知り合った頃、隅田川のほとりを歩きながらハル子が口にした言葉だった。
「私、子どもの頃から日本史が好きでさ。小学校の頃、同級生の男の子を歴史クイズでやりこめちゃって、女のくせに生意気だってイジメられたこともあった。たいていの女の子って、年表とか憶えるのが嫌いなの。だけど、私はおもしろくってたまらなかった。日本酒を好きになったのも、お酒の歴史と伝統を知ったからだよ」
ハル子の子どもっぽい笑顔の記憶が、ふと絵里の表情に重なった。そして、息子の剣が日本酒に深く興味を持っているのは、まちがいなくハル子の血と今さらながら思った。
「じゃあ、新酒番船(しんしゅばんせん)って知ってる?」
絵里の甲高い声が太郎の追想を止めると、あすかが余裕の表情で答えた。
「もちろん。毎年の新酒ができる頃、どの船が一番に江戸へ着くか競争するの」
「ああん! じゃあ、船は江戸のどこに着いたでしょう?」
「品川沖ね、今の品川は都心だけど、昔はあそこから南がすぐ海だったの」
立て続けに問いかける絵里に、あすかは負けん気を覗かせながら答えた。
大人げないあすかだったが、太郎はふと、日本酒のライターになった彼女もきっと幼い頃から歴史好きだったのだろうと察した。
「まぁ、この人は蔵元の血筋なので詳しくって」
あすかを凝視している祖父に、太郎は愛想笑いを投げた。
途端に、祖父が声を発した。
「ほほう! そうでしたか。実は、私の先祖も江戸で造り酒屋をしていました。ですから、隅田川とは御縁があるんです。そのせいですかね、孫がやたらと江戸の歴史にハマってましてね」
祖父は太郎に歩み寄ると、新川のほとりのビル群を指さしながら、かつてはなまこ壁の土蔵が軒を連ねていて、その一画に先祖の営む酒蔵があったと言った。地回りの酒なので、人気の高かった灘酒が底をつくと、自分たちの酒の出番だったらしい。ただ、その頃の江戸は水事情が悪く、さほどうまい酒は造れなかったようだと自嘲した。
太郎は祖父の語りを聴きながら、不思議にもつながった人の縁に気持ちが高ぶった。ハル子がこの場にいたなら、快哉を叫ぶにちがいないと思った。
「ねえ、お祖父ちゃん! 隅田川の花火って昔からあったんでしょ? この川べりにも、すごい数の見物人がいたんだろうな」
あすかの横に座り込んでしまった絵里が、祖父に訊ねた。二人の問答は、隅田川の花火に及んでいるようだった。
「花火って、江戸の人たちの生き方と同じなんだって。パッとみごとに咲いて、スッと静かに消えちゃう。それが、江戸っ子の粋なのね。私、桜も花火もやっぱり隅田川でなきゃダメなんだろうなって思うの」
その最後のフレーズもまた、ハル子が口にした言葉だった。
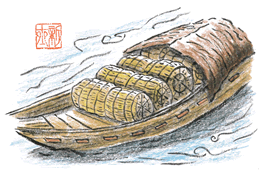 「私も、隅田川が大好き! ねぇ、お祖父ちゃんもでしょ?」
「私も、隅田川が大好き! ねぇ、お祖父ちゃんもでしょ?」
「ああ! もちろんだ。じゃあ絵里、そろそろ帰ろうか」
あすかとひとしきりしゃべった絵里は、祖父の元へ走り戻った。そして、太郎たちに手を振りながら、暮れなずむ隅田川べりを歩いて行った。
心地よさげに二人へ両手を振るあすかを目にしながら、太郎は胸の中でハル子につぶやいた。
「……俺も、隅田川が好きだよ」
