ポンバル太郎へやって来る客たちのほとんどが、扉を開けた途端、目尻をほころばせていた。彼らの視線は、テーブル席とカウンターの隅に飾られた花瓶に向けられた。
花瓶に咲くほのかに紅い桃の花を、同じような顔色になったほろ酔いの手越マリが頬杖を突いて見つめている。その隣で、太郎からお銚子を受け取った平 仁兵衛が純米酒の盃を傾けながらつぶやいた。
「雛祭りか、もうすぐ春ですなぁ。マリさんが活けられたこの桃の花に、また花瓶の色合いもいいですねぇ」
「先生、その通りたい。私が太郎ちゃんに桃の花ば活けちゃろうと思うたのは、その花瓶が理由やけん。何とも言えん澄んだ桃色ば、しとると」
マリの答えを耳にしたテーブル席の客たちも、冷酒グラスを持つ手を止めて目の前に置かれたガラスの花瓶を見つめた。店内のダウンライトを透かせて薄紅色の光彩を放つ花瓶はそこかしこに波打ったような文様を浮かべていて、手造りの吹きガラスと思えた。
「太郎さん、どこで手に入れたのかな。陶器とガラスは窯の火を使う焼き物同士ですから、いささか気になります。このガラスの独特の肌合いや凹凸はわざとこしらえたのでなく、火の力を素直に生かしている。何の変哲もなく見えて、実は奥深い技ありの品ですな」
平が前のめりになって花瓶に目を凝らしながら、太郎に訊いた。
「実は、あの真知子さんが……」と太郎が口にしかけた時、玄関の鳴子が音を立てたかと思うと、大きなくしゃみが聞こえた。客たちがいっせいに振り返ると、右手に風呂敷包みをぶら提げた男が息を弾ませて立っていた。
白髪混じりのショートカットの頭に、水色のダウンジャケットが似合っていた。男は口を開きかけて、また、くしゃみを繰り返した。
「しっ、失礼しました! 私、加瀬俊一と申します」
どこかしら天然っぽい男に、テーブル席の客たちは顔を見合わせて吹き出した。
しかし平は、確かに山出しの匂いは少しするものの、加瀬の目鼻立ちや容姿に育ちの良さを感じていた。それは、銀座のママの眼力で人品骨柄を見抜くマリも同じだった。
赤面する加瀬に、太郎がおじぎしながらカウンター席へ誘った。
「お待ちしてました。今、加瀬さんの花瓶の噂をしていたところですよ。だから、くしゃみが出たでしょ?」
「はっ!? あの……気に入らなければ、壊してくださって結構ですから。駄作と思ったなら、お許しください」
ぶっきらぼうな、それでいて正直な加瀬の言い分に、平とマリが太郎に問いただすような顔を向けた。
「加瀬さんが創ったこの花瓶は、昨年末にマチコの女将さんから譲ってもらったんです。私も、この色合いやしつらえに惹き込まれましてね。それで加瀬さんを紹介してもらって、今夜はある物を注文してたのです」
加瀬は、自分をマチコの常連と知った平とマリに素性を話し、長野県の僻村でガラス工房を開いてもう十年になると語った。訥々としながらも気骨を覗かせる表情に、平たちは加瀬の人となりを納得した。
「それで、お願いした四合瓶はできましたか?」
風呂敷に目をやる太郎に、加瀬の顔つきが引きしまった。
「はい。じゃあ、さっそく……気に入ってもらえれば幸いですが。与和瀬さんからテーマにいただきました“歴史と物語のあるガラス瓶”を創りました」
加瀬がほどいた風呂敷包みから青紫の四合瓶が現れると平はまばたきを忘れ、マリがため息をもらし、テーブル席の客たちからも声が上がった。それは表面を薄くカットした文様がバカラのクリスタルガラス風で、瓶底を異常に盛り上げた中に何かを仕込んであった。
「むう、これは桃山時代のギヤマン瓶ではないですか。信長が愛用したワイン瓶に、このような物がありましたな」
「底に隠してるのは、ひっくり返した盃か。なるほど、こいつはおもしれえ!」
感嘆する平と太郎にほだされて、今度はマリが前のめりになって瓶を覗き込んだ。裏底にはめ込まれているのは、カットガラスの盃だった。
「さすがに、よくご存知ですね。吹きガラスの技術は安土桃山時代から日本に入りましたが、徳川の時代にはキリスト教の禁止にともない南蛮人の仕業として嫌われました。しかし、信長はさすがに西洋かぶれで異能の人物、こんな巧妙でユニークな瓶を考えたのです」
加瀬の解説に店内が静まると、艶やかな輝きと紫色を移ろわせる四合瓶に目を細めながら平が口を開いた。
「確かに、ギヤマンは陶器や磁器の窯元にも敵視されましたからねぇ。明治時代になって近代化したものの、ガラス瓶が世の中に流通したのは大正時代です。でも思うに、この素敵な瓶を現代の日本酒に使えば、文化の普及と販売促進にもつながるんじゃないですかな」
加瀬の熱い言葉を平が補足すると、テーブル席の客の一人が質問を投げかけた。
「でも日本酒の瓶って、リサイクルしてるって聞きましたけど?」
「ええ、一升瓶はそうですね。瓶専門の回収会社から蔵元が買い取って、瓶を洗い、ラベルを取り除き、殺菌消毒してから再利用していますよ。茶色の瓶はほとんど、そうなっています。しかし、耐久性はありませんから、熱処理を繰り返していると割れてしまうんです。ただ四合瓶はほとんど廃棄され、ペットに砕いてから瓶に再生します」
かつて老舗ガラス器メーカーの跡取りだった加瀬だけに、明解に即答した。
これには平も知見がなかったようで、腕組みをしながら頷いた。その隣では、ギヤマン瓶に惚れ込んだらしいマリが、しつこく瓶底のガラス盃を外しては入れている。
「ふうむ、そうですか。ところで、太郎さんはどうしてこのギヤマン瓶のような、歴史と物語のある瓶の制作をお願いしたのかな?」
「そう来ると思ってましたよ」
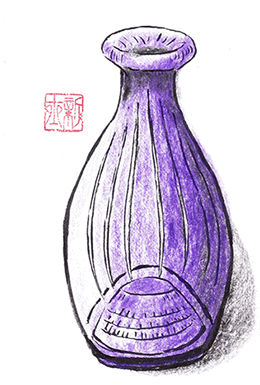
平の質問に答える太郎は、冷蔵ケースの奥に並ぶ一升瓶を数本取り出した。それは、数年前に製造された純米大吟醸や純米吟醸の瓶で、ほんの少しずつ酒が残っていた。
「すべて、私が冷温で残しておいた極上の美酒です。これをブレンドして一つの瓶に入れ、さらに冷蔵熟成させてからお客様の誕生日や記念日に祝い酒として飲んでもらおうと考えたのです。それにふさわしい、日本酒ロマンを味わえる瓶が欲しかったんですよ。お客様それぞれが刻んだ人生は、手造りの酒のように千差万別。ならば、手造りの瓶でお祝いの酒をお出しするのがポンバル太郎の流儀です」
その言葉にテーブル席の客たちが笑顔で拍手を送ると、マリが卒然として声を発した。
「太郎ちゃん! その祝い酒の企画、うちの手毬にも使わせてもらうばい。加瀬さん、私もギヤマン瓶を注文したいから、今夜は銀座の店に一緒に来なっせい」
しかし、昂ぶるマリの熊本弁に加瀬は動じるでもなく、呆気にとられたようなその顔に太郎が訊ねた。
「どうしました? 加瀬さん」
「あっ……実は私、今日が誕生日なんですよ。あまりに偶然過ぎて、ビックリしてます」
ドギマギとして答える加瀬に、平が盃を一気に飲み干し、喜びを露わにした。
「な、なんと! そりゃあ、おめでとう。いやいや、愉快ですなぁ。じゃあ太郎さん。さっそく瓶にブレンド酒を仕込んで、加瀬さんに乾杯しようじゃないですか」
「そうたい。せっかく知り合えたけん、もっと加瀬さんの人生を語って欲しかと」
平とマリの声に、さまざまな美酒が青紫のギヤマン瓶に注がれた。
ポンバル太郎オリジナルのブレンド酒の波紋に、加瀬の笑顔が揺れていた。
