東大寺のお水取りを迎えた関西では梅の蕾がほころび始めたと、テレビで報道されていた。このところ、東京も昼下がりには春の陽だまりを感じるものの、夜の帳が降りると“寒の戻り”がまたやって来る。
「う~、熱燗! 熱燗! 熱燗が飲みてぇ~」
ダウンジャケットの肩をすくめ、厚いウールのマフラーで鼻から口をすっぽり覆った銀平が、やけっぱち気味にポンバル太郎の扉を開けた。カミソリで剃り上げた頭には、うっすらと湯気が立っている。
そんな夜気の冷たさに鼻が通ったせいか、銀平はクンクンと匂いを嗅ぐ音を発した。
「おっ! 酸っぱい匂いだな? しかも、甘い感じ。太郎さん、また妙な酒を仕入れたんじゃねえか?」
眉をしかめる銀平が甘酸っぱい匂いの元をたどると、カウンター席の真ん中に右近龍二が座っていた。
冬でも冷酒を好む龍二が今夜はほのかな湯気を昇らせる二合徳利を手にし、その隣に座る中之島哲男へ酌をしている。
「銀平ちゃんの恰好、頭隠して尻隠さずやがな。ニット帽をかぶるとかして、その禿げ頭をどないかしいや。青光りするのを見てるだけで、こっちが寒うなるがな」
たしなめる中之島の赤らんだ頬と銀平の青剃り頭は対照的で、テーブル席の客たちの笑いを誘った。
「うるせえなぁ。これが俺のトレードマークなんだから、いいじゃねえすか! そんなことより龍二、珍しいじゃねえか。お前が飲む燗酒ってのは、どんな味なんだよ?」
手元を覗き込むと銀平の読み通り、その甘酸っぱい香りは龍二と中之島の盃から漂っていた。
「う~む、この酒って、ヒネてんじゃねえか?」
「いえ、この甘酸っぱいような香りこそが“菩提(ぼだい)もと”の特徴ですよ」
龍二の答えに中之島はその通りといった表情で頷き、盃を飲み干した。
しかし、銀平は一瞬口ごもると、バツが悪そうに龍二へ訊いた。
「その……菩提もとって、何だよ? もとってことは、新しい酒母が開発されたのかよ」
鼻の頭をかきながら訊く銀平に龍二と中之島が顔を見合わせると、太郎がため息を吐いて言った。
「お前、ちったあ日本酒の勉強をしろよ。菩提もとってのは、鎌倉時代に広がった僧坊酒の酒母だよ。別名、南都諸白(なんともろはく)って酒、知らねえのかよ?」
「ええっと、諸白ってのは麹米と掛け米の両方を精米してるってこったろ。でも、南都ってのは?」
江戸っ子の銀平だけに馴染みがないのかと、中之島がおもむろに口を開いた。
「奈良のこっちゃがな。南の都は、いわゆる平城京のことや。つまり、当時の奈良にはお寺さんがぎょうさんあって、そこの坊さんが酒を造ってた。だから、僧坊酒ちゅう名前が付いたわけや」
中之島は南都諸白の酒の発祥の地は奈良にある名刹の正暦寺(しょうりゃくじ)で、今でも菩提もとを仕込む神事が催されていると付け加えた。
「でもよ。昔は、坊さんが酒を飲むのを禁止してたじゃねすか。だから、般若湯(はんにゃとう)なんて隠語まで、できたわけだろう。それなのに、どうして寺で酒造りなんすか?」
銀平が龍二の盃を奪って舐めながら、腑に落ちないという顔をして中之島に訊いた。
「表立っては、そうやなぁ。“葷酒山門に入るを許さず”なんちゅう説法も残ってる。これはニンニクやニラや酒とか、匂いの強い物を食べたり飲んだりした者は寺に入ったらあかんという意味や。けど、それは南都諸白の酒造技術が外へ漏れんように、不審者の出入りを規制するためでもあった。参拝者を装った酒造りの職人も、いてたはずや」
中之島のしゃがれ声に聞き耳を立てるテーブル席の酔客が、呂律をからめながらつぶやいた。
「な、なるほどぉ、産業スパイか。昔から技術を盗む奴らは横行してたんだなぁ」
すると、菩提もとの純米酒を燗冷ましにする龍二が、テーブル席に振り返って言った。
「その通りです、お客さん。技術なんですよ、僧坊酒が美味しかったわけは。僧侶は読み書きや算術に長けていたので、理論的に酒造りを習得できた。その証拠の一つに、奈良の興福寺に残る多聞院日記(たもんいんにっき)があります」
日本酒ロマンを掻き立てる僧坊酒の話しに昂揚してきた龍二は、店内の客たちに向かって多聞院日記を解説した。いつものように出し抜かれた銀平が、ふてくされ気味に盃を飲み干した。
それは興福寺の塔頭の多聞院で文明10年(1478)から元和4年(1618)まで三代の高僧に書き継がれた日記だった。寺の暮らしだけでなく、時勢や戦乱、果ては酒造りのことまで綴られ、室町時代末期から戦国、安土桃山時代、大坂冬の陣、夏の陣の頃までの近畿地方を知る貴重な文献だと龍二は言った。
客たちが能弁な龍二に感心すると、菩提もとの一升瓶を中之島の徳利に注ぐ太郎が口を開いた。
「当時の奈良の寺は荘園の領主とつながっていて絶大な力があった。だから金を持ってて原料の米も酒造りの道具もいい物を揃えたはずだ。だから南都諸白って酒は、今の高精米の吟醸造りみたいに上質だったわけだ」
ようやく菩提もとの酒瓶に目の色を変える客たちが、太郎に燗酒を注文した。
客たちは「確かに、癖がある味だな」とか「いったい、どんな連中が飲んでたんだろ?」などと口々に評した。
それを聞いていた中之島が、うれしげな顔で話をつないだ。
「ところが、僧坊酒は江戸時代になると衰退していったんや。南都諸白の高い技術は、京都や灘の民間の酒屋に受け継がれていったわけが、さて、そこで問題や! 銀ちゃん、そうなった原因は何やと思う?」
それに拙速に答えかける龍二を目で制した中之島は、銀平に汚名挽回のチャンスを与えた。銀平が、剃り上げた坊主頭を撫でながら答えた。
「……時代的には、戦国が終わる頃ですよね。ってことは、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康が影響してるってことか。そうか、楽市楽座もそうだけど、寺の既得権益を廃止したかったんじゃねえかな。信長なんて、石山本願寺を敵に回してたのは僧侶が持つ軍資金を恐れていたからじゃないすか。政権奪取と経済活性のため、僧坊酒を廃止したんじゃねえかな。そう考えると、何だか、今の日本も同じようなことを繰り返してる気がするなぁ」
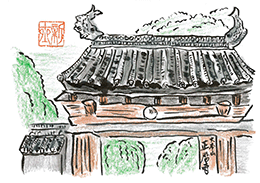
いつになく真剣な面持ちで考え込む銀平に、中之島は感心して手を叩いた。
的を得た答えに、太郎も苦笑いしながらつぶやいた。
「まったくお前は、金がからむとやたら頭の回転が速くなるな」
「へっ! 今日は頭を剃り立てだから、冴えてんだよ」
図に乗る銀平が菩提もとのおかわりを頼むと、中之島が徳利を差し出して言った。
「そうかぁ。ほなら、坊さんみたいなその頭で、いっぺん奈良の寺で酒造りを体験してみるか。もちろん、坊さん修行もあるでぇ」
「中之島の師匠、勘弁してくださいよぉ」
銀平の困り顔をやさしく見つめる客たちが、菩提もとの酒をしみじみと味わっていた。
