七色のイルミネーションが、クリスマスを祝う全国各地のリゾートで輝いている。関東ではディズニーランドを筆頭に、スカイツリーやお台場、六本木ヒルズ周辺で、光の舞いに人々が魅了されていた。肩を寄せ合う男女は、木枯らしも、どこ吹く風といった雰囲気だった。
もちろん、都内の人気飲食店は予約で満席。あぶれたカップルたちは、新小岩や下北沢といった庶民的な界隈で聖夜の晩餐を楽しんでいる。
下町にあるポンバル太郎の店内にも、そんな男女が見受けられた。
「日本酒で、クリスマスディナーか……今風で、いいわね」
ポンバル太郎のカウンター席で独酌する高野あすかが、店奥のカップルを羨むようにつぶやいた。そこへ視線を向ける横の右近龍二と、その隣に座る青砥誠司も「ああ、そうすね」と気後れしたように返事をした。
あすかを含めて、三人とも独身のシングルベルである。スパークリング大吟醸で「メリークリスマス」と物憂げに乾杯し、この後は、揃って銀座の手越マリのBar“手毬”へ繰り出すつもりだ。
一人浮かれているのは、アメリカに彼女がいるジャーナリストのジョージだけ。さっきから、スマホで長い国際電話をかけている。
店主の太郎自身は、振り返れば今年もまた、女性より美味と美酒に惹かれた1年だった。 ここ数日も、クリスマス向けの和洋折衷メニューとして七面鳥を使った日本酒に合う燻製や焼き鳥、洋風ダシの鍋料理、日本酒を使ったスィーツ作りに没頭し、無理がたたったのか、眼窩はくぼみ、クマもできている。
太郎を気遣って栄養ドリンクをこっそり手渡す息子の剣が、客たちには、ほほ笑ましかった。
「ところでさ、太郎さんには悪いけど、俺、ターキーって、さほど美味しいと感じないんだよ。むしろ、国産の比内鶏やシャモでクリスマス料理を作った方が、脂や旨味がのって売れると思うんだよね」
今しがた龍二が気のない生返事をした理由がそれと分かり、あすかは酒食ジャーナリストとしてのコメントを口にした。
「まぁ、確かに日本のスーパーマーケットじゃ、炙ったターキーよりも、ブロイラーのフライドチキンの方がクリスマスは売れるのよね。日本人が食べ慣れてないってこともあるけど、七面鳥って淡白な味で、食べ応えがないの」
とは言うものの、太郎の気持ちを惹きたいあすかは、スパークリング大吟醸に“ターキーの燻製 柚子胡椒添え”をペアリングしている。BS放送や雑誌で有名な高野あすかが選んだ料理と知って、龍二の声をよそに、店内からは立て続けに同じ注文があった。
客席のオーダーを耳にした誠司が、スパークリング大吟醸のグラスを飲み干して龍二へ耳打ちした。
「悪いっすね、龍二さん。俺ぁ、七面鳥って、まったく食ったことねえから、一度食ってみやす。てぇことで、太郎さん。俺は“ターキーの焼き鳥 紫蘇とチーズ巻き”てえのを、頼みやす!」
龍二は不機嫌そうに、誠司の注文を腐した。
「まぁ、ササミに似てるから、ターキーの焼き鳥は日本酒にイケるかもな。ただなぁ、せっかくのクリスマスなのに、何で七面鳥なのか……アメリカ人の味覚が分からないよ」
腐すような龍二の言葉に、ほろ酔いで上機嫌になっているジョージが口を挟んだ。彼女との国際電話に気分上々なのか、自信満々で問わず語った。
「龍二さん、あなた勉強不足ですね。ターキーは、アメリカの建国時代を支えた食糧なのです。17世紀、ヨーロッパからアメリカへ向かった移民たちが、現地で飢えをしのぐために捕まえ食べたのがターキーでした。当初は、友好的だったインディアンからも七面鳥が与えられたそうですよ。だから、ターキーはアメリカ文化の縁起物。感謝祭やクリスマス、結婚式などの祝いの席には、欠かせません!」
いつになくキッパリとしたジョージの物言いに、龍二は返す声がない。
あすかは、ジョージへ気遣うように前言を撤回した。
「そうか。日本人にとっての鯛みたいな存在かしら……ごめんなさい、さっきのは失言でした」
その時、三人の会話に、カウンター席の隅に座る男が浅黒い頭をもたげた。ワイングラスで北海道の純米酒を飲みながら、箸につまんでいるのは鮭のはらす焼きである。肩幅があるごつい体格の男は、ワイシャツとスーツの胸を筋肉で盛り上げていた。
いささか角張った顔の男は、どちらかといえば東北の日本海側にありがちな切れ長の目元をしていた。
極端なモンゴロイド系の顔立ちで、垢抜けしない雰囲気の男に龍二が気づくと
「ターキーだけじゃないですよ。アラスカ州では、サーモンがクリスマスのメインディッシュです」
と本人が口を開いた。その声の妙なアクセントに、あすかと誠司が顔を見合わせた。太郎も東北弁でなければ関西弁でもないと、肴を盛り付ける菜箸を止めた。ただ、ジョージは真っすぐに男を凝視していた。
不審げな龍二が、
「失礼ですが、どちらのご出身ですか?」
と訊ねれば、ニンマリと笑う男は「でなり、です」と答えた。いや、そう聞こえた発音だった。やはり、男の言葉使いは不自然である。
「でなり? って、どこの市だっけ? あすかさん、取材とかで行ってない?」
龍二は、あすかだけでなく、全国の野菜市場を知っている誠司にも質問を向けた。
「知らないわねぇ……あのう、秋田とか新潟ですか?」
問いかけるあすかへ男がしたり顔を見せると同時に、ジョージは声を発した。
「アラスカ州にある、国立公園の名前でしょう? あなたは、エスキモーの方ですか? 私はデナリに旅したことがありますから、さっきのアクセントで分かります」
ジョージにコクリと頷く男の目尻は、言われてみれば、テレビ番組で目にしたアラスカの現地人に似ている。あすかや龍二たちだけでなく、テーブル席の客たちも、男の顔立ちが日本人と似ているのを理解しつつ
「なるほどね。ちょっと、ちがう雰囲気だよね」
とためつすがめつしながら囁き合った。
「デナリは、広大な森林がある国立公園ですね。東京にいらした理由は、観光ビジネスですか?」
単刀直入な質問をしながら、いきなり名刺を差し出すところは、いかにもヤンキー気質のジョージらしかった。相手の男も、カードケースをジャケットのポケットから取り出し「ケイン・佐藤です」と名乗った。
驚いたジョージが見つめる英語表記の名刺を、龍二も覗き込んで
「エスキモーなのに、日系の方って珍しいな。アラスカサーモンの水産会社か……どうりで、スモークサーモンはお得意なわけだ」
と目を丸くした。ケインは破顔一笑して
「イエス! 私の曽祖父は新潟県の村上出身で、大正時代にアラスカへ移民しています。父に聞いていたのは、村上もデナリと同じで、たくさんの鮭が川に戻って来る町です」
と冷酒グラスを掲げた。
ケインは、アラスカでも日本酒人気が高まりつつあり、気候的にHot Sake=お燗酒が人気を呼んでいると話した。ただ、スモークサーモンには通常、白ワインだから、これに冷酒を合わせて市場をつかみたい。そこで、蔵元の視察も含めて、日本にやって来たと語った。
ケインがビジネスバッグから自社のパンフレットを取り出すと、そこには森林に包まれたデナリの大河を遡る鮭の群れの写真が掲載されていた。
ジョージは、あすかが酒と食のジャーナリストであると紹介した。名乗ったあすかも、そのままケインに語りかけた。
「確かに、最近、日本に出回っている養殖物で脂ののったノルウェー産とろサーモンに、無濾過生原酒の酸味とコクは合います。でも、アラスカの天然サーモンは、それほどコッテリしてない気もしますから、ペアリングとしては淡麗系の日本酒がいいのかしら」
取り扱うスモークサーモンを味わってみなければ、専門家のあすかでも合わせやすい日本酒は分からないと、あすかはパンフレットを捲った。
ケインが惜しげに、サンプル品は築地市場の訪問で使い切って今夜は持っていないと首を横に振った時、入り口扉にぶら下がる木枡の鳴子が躍った。
「太郎さん! 上物のスモークサーモンの見本が手に入ったぜぇ! アラスカ産だがよう、日本酒にもイケるんじゃねえかと……あれぇ? あんた、今日、築地に来てたケインさんじゃねえかよ?」
禿頭を青く光らせる火野銀平の登場に、あすかと龍二が「えっ! 知り合いなの?」と声を重ねた。
「火野屋で扱うつもりなら、いいスモークサーモンだろうな」
太郎は、ケインと銀平を見比べながら戸惑っている誠司へ頷いた。
ケインが「オウ! 火野屋さん!」と声を張り上げ、玄関へ駆け寄ると、銀平は右手を差し出した。しかし、ケインは握手でなく、銀平が手にするサンプル商品を抜き取って、あすかの前に置いた。そして、味見をして酒を選んで欲しいと冷蔵ケースを指さした。
「な、何でぇ! おう、誠司! いったい、どうなってんでぇ!?」
あすかにお株を奪われた形の銀平は誠司へ八つ当たりしながら、隣へドッカと腰を下ろした。なだめる誠司が、今までのなりゆきを説明する間も、あすかは聞こえぬふうで真剣にスモークサーモンを口にした。そして、誠司に冷蔵ケースから北海道の純米吟醸をいくつか取り出してと頼んだ。
「う~む、ルイべみたいにあっさりしていないし。スモークすると北海道産の鮭より風味は濃くなるのよねぇ……ちょうどいい具合な淡麗系って、どこの地酒かしら?」
言いなりに酒瓶を取り出す誠司の頭を銀平が小突いて、あすかに文句をつけた。
「おい、おめえもプロなら、しっかり答えな! ちなみに俺なら、ケインさんの御先祖が暮らしてた村上の地酒を、まず選んでみる。悩んでる時には、ゲン担ぎが大事なんだよ」
そう言うなり冷蔵ケースから村上の銘酒を選ぶと、ケインへ一升瓶を手渡した。その酒は、銀平のお気に入りの一つである。
ただ、龍二と誠司が腑に落ちないのは、銀平が瓶の裏ラベルをケインの顔先へ近づけたことだった。次の瞬間、キョトンとしているケインの隣で漢字を読めるジョージが
「ワオ! 杜氏さんの名前は、佐藤さんだ! しかも、ケインに近いケンだ!」
と目をこすった。製造担当者の名前に、“佐藤 拳 杜氏”と表記されていた。まんざらでもない顔の銀平は、それを知っていて選んだらしい。
あすかが、銀平の機転に感心して言った。
「あら、その蔵元の社長さんと私は親しいの。だから、新潟県の下越地方に取材でよく行くんだけど、佐藤さんって苗字が多いのよね……もしかしたら、本当にケインさんの親戚だったりしてね」
冗談めかすあすかに龍二と誠司は「まさかぁ」と苦笑したが、ケインは憑かれたように、佐藤杜氏の名前を繰り返していた。
すると、銀平は真顔で言い放った。
「あすか! こういうのは、勘が大事なんでぇ! もしかじゃなくて、今すぐ、その社長へ電話して、アラスカへ移民したケインさんの御先祖のことを知らねえか、訊いてみろい! 蔵元てえのは、代々、地元の名士だから、顔も情報も広れぇじゃねえか。まったくよう、頭がいいんだか悪いんだか、どっちなんでぇ!」
口早な江戸っ子言葉を通訳するジョージにケインは耳を傾けながら、興味津々に村上の地酒をグラスに注いだ。いつもなら言い返すあすかが素直にスマホを取り出したのは、太郎が、銀平を見直したように頷いたからだった。
スマホのつながった蔵元の社長に話すあすかに、太郎たちだけでなく、テーブル席の客も声を呑み込んだ。
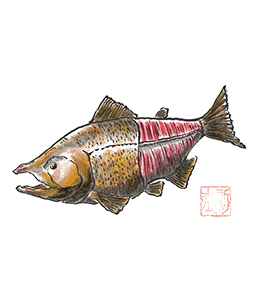 「えっ! そうなんですか!? じゃ、じゃあ、御社の佐藤 拳 杜氏の御先祖の一人が、戦前に、アラスカへ移民したのですか! ちょ、ちょっと、お待ちくださいね」
「えっ! そうなんですか!? じゃ、じゃあ、御社の佐藤 拳 杜氏の御先祖の一人が、戦前に、アラスカへ移民したのですか! ちょ、ちょっと、お待ちくださいね」
驚きを隠せないあすかの手が、いつになく震えていた。
あすかのやりとりをジョージから通訳されたケインがたどたどしい言葉使いでスマホに出ると、先方の社長の喜ぶ声が洩れ聞こえた。
途端に「どうだ、俺の勘は!」と言わんばかりに銀平が拳を上げると、店内から割れんばかりの拍手が響いた。龍二と誠司だけでなく、あすかも脱帽とばかりに拍手をした。
「うむ、香りおだやかで端麗な旨味の越後酒とスモークサーモンなら、いいペアだな。それにしても、スモークサーモンだけに、煙に巻かれたような話だが……今夜のおめえは、神ってるぜ」
つぶやく太郎が、アラスカのスモークサーモンをうまそうに口にした。
