秋の新作モードを着こなすキャリア系の女性たちが、青山通りを闊歩している。その一方で、竹下通りは原色調のギャルファッションに、ヨーロッパやアジアの若い観光客が群がっていた。
年配の外国人は、もっぱら歌舞伎座や美術館に列をなし、日本の“芸術の秋”を耽美している。とりわけ日本語の分かるマニアックなグループになると、浅草演芸場の寄席を鑑賞して、ギミックやジョークと似た落語のおもしろさに腹をよじっていた。
その高座を終えた噺家の深川亭亀吉が同業らしき壮年の男性を伴って、お気に入りのポンバル太郎のカウンター席に座っている。亀吉と陶器つながりの仲である平 仁兵衛は男と初顔合わせらしく、丁寧なお辞儀を交わすと男の素性に驚いたようすだった。
二人とも粋な江戸小紋の羽織と雪駄を履き、いかにも芸人らしい口調に、やって来る客の誰もが目を止めた。
「近頃の外国人客は、意外にダジャレを理解できるんでげすねぇ」
壮年の男は古い江戸の御座敷言葉を使って、亀吉に話しかけた。太郎から肴の鉢を受け取るしぐさが、妙に女形っぽい。
「そうなんでぇ、えん辰つぁん。中にゃ、英語に翻訳された落語集を手にしてる客もいてよ。日本人より、ネタを知ってんだ。いや、まいったねぇ」
亀吉はテレビでも目にするが、えん辰と呼ばれる男をテーブル席の男性客が誰何していると、気を回した平が言った。
「あの方は、日本で五人しか残っていない幇間(ほうかん)芸の福笑亭えん辰 師匠ですよ」
だが、二人の若い男性は不審げな顔で「幇間って、何?」と声を合わせた。落語家に比べ幇間という特殊な芸域だけに目立たないのは仕方ないが、実のところ、えん辰自身のありきたりな芸が人気の出ない原因だった。
えん辰が苦笑いをして、冷やおろしの盃に口をつけた。
「さっき亀吉師匠が言われた通り、日本人の方があちきの芸を知らねえでげすねぇ。実は、あちきの舞台でも、外国人が幇間に詳しいんですよ。ねぇ、お兄さん方。幇間てえのは男芸者のことだって、知っておいでかい?」
シナを作って解説するえん辰に、テーブル席の男たちは悪寒がしたのか、ブルッと身震いした。だが、平は興味津々で、えん辰に耳をそばだてた。
幇間の遠祖は、豊臣秀吉の家臣の曽呂利新左衛門(そろり しんざえもん)で、機知に富んだ武士だった。秀吉がご機嫌斜めになると「太閤、いかがで、太閤、いかがで」と持ち上げて喜ばせた。つまり、「太閤持ち」が「太鼓持ち」に変わったと伝わっている。
これが江戸時代には、幇間の名に変わった。「幇」は助けるという意味で、「間」は人と人の間、すなわち人間関係だ。つまり、宴会の席で接待する側とされる側の間、客同士や客と芸者の関係を盛り上げ、つなぐ遊びの助っ人なのだ。修業は、師匠について芸名をもらい、住み込みで師匠の身の回りの世話や雑用をこなしながら芸を磨く。5年ほどの修業を勤め、お礼奉公を1年してから正式な幇間となるしきたりだと、細く甲高い声で話した。
「幇間芸って、どんなのがあるんすか?」
冷酒グラスを飲み干してぶっきらぼうに訊いたテーブル席の若い男に、亀吉が不機嫌な顔になって
「おい、兄さん。“あるのでしょうか?” だろ! 日本語は正しく使わなきゃ、いけねえよ。それによ、俺たちぁ、芸で飯食ってんだ。舞台の外じゃ、手の内を見せねえ」
と突っぱねた。
気圧された若い男が恥ずかしげに頭を掻いた時、誰ともなく店内から「カッポレやってよ、カッポレ」と声が上がった。
ムッとした顔で振り返る亀吉に客席が静まると、平は張り詰める空気をほぐそうとして、お銚子を持ってえん辰に話しかけた。
「そうですねぇ。私も昔、浅草演芸場でカッポレを踊る幇間さんを観たことがあります。ピョンピョン片足で飛び跳ねる姿が、なんとも滑稽で、おかしいんですよねぇ」
だが、えん辰は相槌を打たず、盃を手にすることなく表情をこわばらせていた。気にかける平に、亀吉も「おう、えん辰。どうしたい?」と声をかけた時、玄関の鳴子が響いてトロ箱を手にした火野銀平が入って来た。後ろに、八百甚の誠司の顔も覗いている。
「カッポレ! カッポレ! って聞こえたけどよう、甘茶じゃなくて、お酒でカッポレだぜ! だけど、どうして俺が、このカッポレを持って来るのが分かったんだよ」
トロ箱を開いて太郎へ訊ねる銀平に、カウンター席の面々はポカンとしている。箱の中には、銀色に光る平べったい80センチもの魚が横たわっていた。
魚を目にして「これ、カッポレてぇのか?」と小首を傾げる亀吉に、誠司が突っ込んだ。
「今、カッポレがどうって、皆さん、言ってたじゃねえですか。カッポレってのはこの魚のあだ名で、正式にはギンガメアジでさぁ」
おそらくは、銀平の受け売りそのままの誠司に、太郎が手を打って答えた。
「ああ、そうだった。カッポレは、釣り人の世界じゃ有名だもんな。銀平が電話で言ってた、めったにお目にかかれねえ大物が駿河沖で揚がったてのは、こいつのことか。だがよう、こっちのカッポレは、こちらにいらっしゃる福笑亭えん辰 師匠の幇間芸のことだ。にしても、せっかくですから、両師匠、召し上がりませんか? カッポレの刺身は、最高の日本酒の肴ですよ」
太郎が亀吉とえん辰に勧めると、味は保証するとばかり銀平は胸を叩いた。
「あんた、築地の火野屋さんだったね。おう、えん辰つぁん。ごちになろうじゃねえか」
銀平を覚えている亀吉も、すこぶるつきにいい魚を目利きする男だと、えん辰に紹介した。
ところが、えん辰は目をつぶって拒んだ。
「すまねえ。その魚だけは、勘弁してくれ。あちきは食えねえ……カッポレは、あちきから師匠のえん五郎を奪った魚でげす」
怪訝な顔の太郎と平だけでなく、客席からも「カッポレに、命を取られたってこと?」とつぶやきが聞こえた。
黙り込むえん辰の代わりに、亀吉が口を開いた。
「亡くなった先代の福笑亭えん五郎は、噺家の中でも名うての太公望だった。今だから言えるけどよ、晩年は八丈島の船釣りに入れ込んじまって、浅草の演目に穴を開けることもあった。それがたたって、えん辰に後を託して引退しちまったんだけどよ……たけど、あのカッポレだけは個性的で、みごとな踊りだったぜ。他の幇間なんて、目じゃねえ!」
腕ぐんで感心する亀吉に、テーブル席の男たちは「どんな踊りだろ」とスマホでえん五郎の動画を探した。
すると、えん辰がため息をして、問わず語った。
「そりゃ、そうだわさ。えん五郎師匠は、カッポレを上手に踊るために、釣りキチになっちまったんだもの。カッポレの踊り方は、この大きなギンガメアジを釣り上げる時に、船の上で竿を抱えて、飛び跳ねるように必死になっているさまに似てるでしょ。だから、ギンガメアジを、カッポレって呼ぶようになったの。えん五郎は、引退しても死ぬまでずっと、カッポレ釣りしかやんなかったのよ。だから、あちきはカッポレの刺身が憎いの」
カッポレをさばき始めた太郎の向かいで悔し泣きするえん辰へ、亀吉が慰めるように酌をした。彼の女形は、幇間芸で板についたよりも、根っからの性質らしいと平たちは感じた。
話に聞き入っていた誠司が、納得のいかない表情で銀平に言った。
「てぇことは、踊りを上手くなりたくて、カッポレ釣りにのめり込んだわけでしょ。でも、カッポレの呼び名は踊りが先で、魚は後についたわけで……ええい、なんだかアベコベじゃねえですかい」
誠司の疑問を、えん五郎のカッポレ動画を見つけた客たちの大笑いする声が消した。そのようすに、銀平が得心したように答えた。
「誠司! つまらねえことを気にすんじゃねえよ。そんなこたぁ、どっちだっていい。大事なのは、えん五郎って名人が、芸のためならと船に乗り続けて、生身のカッポレ釣りから、自分流のおもしれえカッポレ踊りを大成したってことじゃねえかよ」
横にいた平にはそれが、煮え切らないえん辰への諫言のように聞こえた。
柳葉包丁で切られ、皿の絵柄が透けるほど薄造りしたカッポレの身は、太郎の手でカウンターの真ん中へ置かれた。背伸びして覗き込む客たちが、どよめいた。
それでも、えん辰は箸を持つのをためらった。
じれったい顔の銀平と誠司を察したかのように、亀吉が声を太くした。
「えん辰つぁん、あれほどのカッポレ踊りを、避けちゃ通れねえよ。おめえさんは、えん五郎の後継者なんだ。むしろ師匠は、俺のカッポレを超えてみろって、あの世で言ってんじゃねえか? 食わず嫌いじゃ、いけねえよ」
亀吉は目顔で“さっさと喰え”と、えん辰へ言っていた。
胸襟を開き合う仲の亀吉の助言に、えん辰は渋々、箸を手にした。そして、手元を震わせながらも、太郎へ「やたら大きな身だねぇ」と皮肉っぽくつぶやき、刺身を口へ運んだ。
途端にえん辰から「お、美味しいわ! これ! 美味しい!」と、誉め言葉があふれ出た。
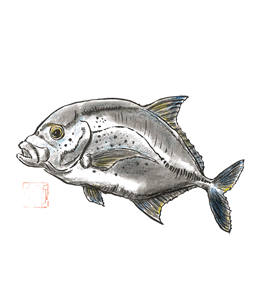 亀吉を始め、カウンター席の面々がほっと胸を撫で下ろすと、テーブル席や店内からも拍手が起こった。
亀吉を始め、カウンター席の面々がほっと胸を撫で下ろすと、テーブル席や店内からも拍手が起こった。
太郎がえん辰に、意味ありげに言った。
「ギンガメアジは大物ほど、うまいんです。こいつの小物は“メッキ”って呼ばれましてね。体の銀色はメッキみたいな光り方なんだけど、“メッキが剥げる”てえ言葉があるように、味も変わりやすい。カッポレ級じゃねえと、いけねえんです」
えん辰がハッとして、太郎を見返した。
「つまり、あちきの踊るカッポレは、まだメッキで、本物のカッポレじゃないと……その通りかもねぇ。師匠に叱られないように、私だけのカッポレを手に入れなきゃね」
ありがとうと両手を合わせるえん辰の隣で、亀吉が「えん辰つぁん、頼んだぜぇ!」とカッポレを詠い始めた。
えん辰は「じゃあ、この魚の御礼に」と銀平と誠司へ片目をつぶると、袂から豆絞りを取り出して、粋に頭へ巻いた。
トトンガトンと跳ねながら踊り出したえん辰に、初めてカッポレを目にする客たちが酔いしれていた。
