夕陽に染まる巨大な入道雲が、上空からスカイツリーを見下すように聳えていた。ゲリラ豪雨に襲われてはと、プレミアムフライデーの仕事を切り上げた丸の内のビジネスマンは足早に駅へ向かっている。
都心は蒸し暑く、先週からビヤガーデンもスタートして、帰宅する男たちは後ろ髪を引かれるかのように駅ビルのネオンを見上げては、改札を抜けていた。
ポンバル太郎の通りでも、火野銀平は八百甚の誠司を連れて、人波に逆らいながら店へ辿り着いた。どうしても今夜、太郎に食わせておかねばと意気込む魚が、銀平の右手のビニール袋に入っている。
「兄貴ぃ、この魚、本当に食えるんですかい? 夕焼けみてえに真っ赤なもんで、俺ぁ、金魚に思えてしかたねえや……ええっと、何てぇ名前でしたっけ」
袋を覗き込む誠司の目に、鮎と似た形の魚が映った。体側には、朱色の帯を引いたような模様が浮いている。
「関東じゃハヤが通称だが、学名はウグイだ。ウグイてぇ名前はよう、鵜が好んで食うから、そうなったんでぇ。まぁ、そもそも山国の蛋白源でよ、東京じゃ食わねえ川魚だから、おめえが知らなくてもしかたねえけどよ」
ポンバル太郎の扉を入りながら、銀平は話を続けた。
ウグイは春から初夏が産卵期で、オスの体には婚姻色が現れ、下っ腹が赤く染まる。高級魚の鮎に比べて安値のウグイだが、野趣あふれる苦みが日本酒に合う。だが、鮮度が持ちにくく、臭いが悪くなるのが難点。だから、千曲川の川漁師がわざわざ活かして送ってくれたこのウグイを竈で焼いてもらうのだと、カウンター越しに平 仁兵衛とその連れらしき白髪の男に対応している太郎へ聞えよがしに言った。
「ウグイ!? そいつぁ、珍しいな。俺も信州で10年前に田楽を食ったよ。ほろ苦い身に、信州味噌がピッタリ合うんだ……確か、“つけ場漁”てえのを見せてもらったぜ」
記憶を探る太郎の口から出たのは、ウグイを獲る仕掛けで、産卵時の罠である。
初耳の誠司は小首をかしげ、銀平はテーブル席で独酌している30歳前後の男が舌打ちするのを耳にした。今しがたまで存在の薄い印象だった男は、一変して苦い表情を太郎に見せた。
平から酌を受けている連れの男が、ふいに問わず語った。
「“つけ場漁”に適しているのは、ウグイが卵を産みやすい川の水の流れが比較的早い瀬ですよ。川底にきれいな石や砂利が続く場所で、大雨で川の水が増えた後は底石が洗われ、産卵も盛んになるんです。ウグイはメス1尾に対して、かなりのオスが群がるので、産卵する場所は魚影が濃い。その習性を利用して砂利や石で人工の産卵場所をつくり、そこに集まったウグイを川漁師は投網で獲る。まさに、一網打尽にするわけです」
やたら詳しい男の笑顔に銀平が「ほう!」と感心すれば、平はお銚子の動きを止めて男に訊いた。
「そう言えば、佐久田さんは千曲川の土木事務所にいらしたことがありましたよね?……ウグイは、よく召し上がったのですか?」
竈に薪をくべた太郎へウグイの入った袋を手渡しながらカウンター席へ座る銀平と誠司が、佐久田の答えに耳を澄ませた。だが、テーブル席の男は藪にらみするかのように、佐久田へ視線を止めていた。
「ええ、平さんと信州の窯元で知り合った20年近く前は、よく食べました。今じゃ、めっきりとウグイ漁は見なくなりましたが、当時は、初夏になると投網や簗(やな)で獲ったウグイを焼いて売る、掘っ建て小屋も川岸にあったんですよ」
信州などの山国では、川魚は貴重な蛋白源で、千曲川のウグイは古くから食されていた。鮎のような公儀の御用物にならない下魚なので、庶民には好都合だった。とりわけ、地元では子育てする母親の乳に栄養がつくと言われた。また、どんな餌にでも食らいつくので、数を揚げることができたと佐久田は解説した。
「へえ! 例えば、どんな餌がありますんで?」
誠司が5ミリほどに伸びた髪の毛を撫でながら訊くと、銀平が得意げに口走った。
「竹輪やソーセージをちぎった餌でも、釣れちまうんだよ!」
訳知り顔の銀平に、誠司だけでなく平も目を丸くすると、佐久田は大きく頷いて
「私は当時、古い竹竿で釣り上げるのが趣味でした……でも、今は一切やりませんし、ウグイはもう食べません」
と声音を低くした。ビニール袋から太郎が取り出した活きの良さげなウグイの赤い腹に、佐久田は悲しみとも諦めともつかないような、ため息を吐いた。
「また、どうしてですか? 食も遊びもこだわり派の佐久田さんがやめるとは、いわくがありそうですねぇ」
佐久田を忖度して黙り込む面々の中、平が訊ねると、思いがけずテーブル席から答えが返った。
「ヘボ釣り師だったから。ですよね? 佐久田 喜一さん」
突然の無礼な言葉に、銀平は男へ食ってかかった。太郎はいきなり佐久田をフルネームで呼んだ男に気を取られ、銀平を制するのを忘れている。
「何だぁ、この野郎! ヘボ釣り師てなぁ、誰に言ってやんでぇ!」
「あっ、兄貴ぃ。落ち着きやしょう! この人は、佐久田さんを知ってるみてえだ」
頭に血が上った銀平を諫める誠司の声に、平もゆっくりと頷き、表情の一変している佐久田と男を交互に見比べた。
「そ、そうだ……私は確かに、ヘボ釣り師だった。長野では、蜂の子をヘボと呼びます。ウグイを釣る餌にヘボを使うのが、ヘボ釣り師です。とにかく良く釣れて、釣果が上がった。そして私は、ウグイ釣りの名人と競うほどの腕になった……君の父親、真田 源次郎さんとね。大きくなったな、雄太郎君。面影が残っているよ。また、逢えるとはね。お父上が亡くなって、もう22年になるか」
流暢な口ぶりだった佐久田と別人のように途切れる会話からは、心の乱れが読み取れた。それを聞き流すかのように、真田は吐き下した。
「俺の親父も、同じ穴のムジナだよ。ウグイに憑かれちまって、あんたから勝負を受けて、水量の増えた千曲川で練習してる内に、早瀬に足を取られて溺れちまった……親父が死んだ日から、ガキだった俺もウグイを食うのはやめたよ」
二人の間柄を察した銀平の鼻息が、一気に静まった。誠司も口元をへの字にしたまま、黙りこくった。
息苦しい佐久田と真田の空気を破ったのは、玄関の鳴子の音だった。
「太郎さん、お土産を持って来ましたよ。一昨日から、長野の佐久市に行ってましてね。地元で人気の燗酒向きの本醸造です。これ、川魚にピッタリらしいんですが、いい肴ってありますか?」
右手でトランクを引き、左手に一升瓶をぶら提げている右近隆二へ、銀平が雄叫びを上げた。
「で、でかしたぁぜ、龍二! おめえ、最高だぁ!」
弾かれたように抱きつく銀平と誠司に
「わ、わあ! 酒の瓶が割れちゃいますよ!」
と龍二がカウンターへ置くと、その銘柄に佐久田と真田が声を重ねた。
「佐久錦……ウグイと飲む酒だ」
お互いに視線を合わせたまま、外さない。かつて、佐久田も真田の父も愛してやまなかった長野の地酒だった。
遠い記憶を振り返っている二人の間に、竈で熾した炭火が爆ぜた。
太郎が手にするウグイに櫛を打ちながら、龍二に目顔で燗酒をつけろと命じた。ひと目でウグイと見抜いた龍二は
「その赤い腹、初夏の四万十川でも人気なんですよ」
と太郎へ親指を立てた。
太郎の焼く香ばしいウグイの匂いと、龍二がつける熱燗の香りに、佐久田と真田の喉が唾を呑んだ。
「お二人とも、素直じゃありませんねぇ。真田さん、いつまでも意地を張ってウグイを食べないなんて、お父上が喜ぶとは思えませんがねぇ。それに佐久田さんも、真田源次郎さんは好敵手だったのでしょう。ならば、もう一度、あなたはヘボ釣り師に戻るべきですよ」
平の言葉を追いかけるように、焼き上がったウグイが佐久田の鼻先へ煙を漂わせた。
ためらいながらも手を伸ばした佐久田は、ウグイを見つめている真田に話しかけた。
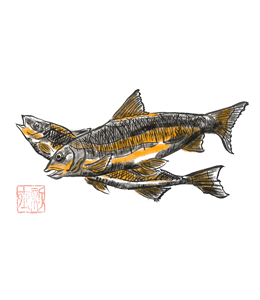 「君のお父さんから、言われたことがある。源次郎さんの体も血も、ウグイを食べて育ったおかげだと。そして、君を育てたお母さんの乳もそうだ。だから、ずっとウグイを忘れて欲しくないと……君に許してもらえるなら、私はもう一度、ヘボ漁師になってみせるよ」
「君のお父さんから、言われたことがある。源次郎さんの体も血も、ウグイを食べて育ったおかげだと。そして、君を育てたお母さんの乳もそうだ。だから、ずっとウグイを忘れて欲しくないと……君に許してもらえるなら、私はもう一度、ヘボ漁師になってみせるよ」
ひと口噛んだウグイの串焼きを、佐久田が真田に差し出した。ピッタリのタイミングで龍二の熱燗が仕上がると、今度は真田から
「千曲川に全部流して、忘れることにします」
と酌をした。
銀平が、佐久錦の燗酒を平へ注ぎながら訊いた。
「平先生、二人がウグイを口にしたがっているの、お見通しだったんですかい?」
「いやいや、マグレですよ。まあ、ヘボ釣り師じゃなくて、私はヤボな焼き物師ですからねぇ。イチかバチか、引っかけ釣りをしてみました」
それに答えるかのように、また竈の薪が爆ぜた。
