白南風も待たずに、真夏めいた強い陽光が丸の内のオフィス街に射していた。
焼けた路面の照り返しに、OLたちはハンカチで頬を隠している。ビルのサインボードの紫外線予報も、真っ赤に変わっていた。
そんな日の夕刻、ポンバル太郎でカウンター席に座る火野銀平の剃った頭は日に焼けた上に、酒が回って赤くなっている。真っ白な火野屋のロゴ入りTシャツと好対照だった。
「おい、龍二。キュンと冷えた生貯蔵酒に、江戸前のスズキの洗いたぁ、もう夏だねぇ!」
隣で頬をほんのりと朱色にしている右近龍二の肴は、火野屋が納めた旬のスズキである。
薬味の刻みミョウガを手にする太郎も、龍二に向かって頷いた。
「1mオーバーのみごとな大物だ。脂のノリが良すぎて、洗うのに手間取っちまったよ」
片身でも冷蔵ケースに入り切らなかった大スズキは、太郎の出刃包丁で6つの切り身に分けられていた。能登育ちで、スズキを食べ慣れないと敬遠する平 仁兵衛も、分厚い身に視線を奪われている。
「東京の目と鼻の先で、こんな立派なスズキが獲れるのですねぇ」
「産卵前のこの季節、江戸川や多摩川の河口など汽水域にウジャウジャいるそうです。シーバスって呼んで、夏はスポーツ的なルアーフィッシングが盛んですよ。暴れて鈎をはずそうと“スズキのえら洗い”ってのをやるんですが、これが最高のファイトなんです」
この春から海釣りにハマっている龍二が立ち上がって竿をさばく仕草をすると、席一つ置いて座る高野あすかが
「子どもみたいに、はしゃいじゃって。龍二君、いつから釣りバカになったのよ? ちなみにスズキって、江戸時代の料理本“本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)”にも、スズキは洗いに限るって紹介されてるの。でも、新鮮で活きたスズキでなきゃダメ。ちょっとでも時間が経つと泥臭さと脂が回ってしまうのは、今も同じらしいよ」
と酒食ジャーナリストらしいウンチクを挟んだ。
あすかの話にテーブル席のビジネスマンたちは、中腰になって冷蔵ケースの切り身を覗いた。物欲しげな表情に気づいた銀平が、聞えよがしに声音を上げた。
「洗いもいいが、焼き物もめっぽううめえんだ! 白身だからよう、塩焼きよりも、味醂と醤油のたれ焼きが江戸前の食い方だぜ。泥臭さも、消えちまわぁ」
確かに、太郎の手元には壺に入った赤黒いタレと塗り刷毛が用意されている。
それはポンバル太郎を開店してからずっと注ぎ足してきた江戸前のタレで、亡きハル子が復刻させて仕込んだ深川の辛口の”かえし”である。淡白な白身魚とかえしは抜群の相性で、辛口の灘酒を好む客たちから絶大な支持があった。
銀平は、先に注文していたスズキのかえし焼きが仕上がると、香ばしい匂いに鼻先をひくつかせた。
「これ、これ! かえしの焦げた匂いも、たまんねえな」
すると、カウンター席の隅から不機嫌そうな声が聞こえた。
「大将。その切り身、目ざわりだからケースの端っこに寄せてくれませんか。俺は、スズキが大っ嫌いなんです」
小ぎれいな紺色のスーツ姿の男が、しかめっ面を覗かせていた。今しがたまで静かに盃を独酌するようすから、そんな口ぶりが出るとは思いもよらなかった。
出し抜けな声に太郎の答えが詰まると、新顔のくせに無礼な物言いとばかり銀平が顔色を変えた。隣の龍二は、いつもながらに銀平を警戒し始めた。あすかの冷静な目元が、太郎と男の表情を見比べている。
「なんだよ、あの人……」とテーブル席の客も怪訝な表情に変わり、銀平が口火を切った。
「あんたさぁ、酔っぱらっちまったのか? 料理屋の陳列ケースにアヤつけるなんてなぁ、ご法度だぜ。とっとと帰った方が、いいんじゃねえか?」
だが、男はスズキの切り身から銀平のTシャツに視線を移して、悪びれずに訊いた。
「おたく、築地の魚屋なんでしょ。だったら、オオタロウって知ってる?」
それを受けた銀平の顔が、一瞬、引き締まった。
耳慣れないオオタロウの言葉に、龍二と平は小首をかしげた。あすかはその意味を知っているのかと太郎に目顔で訊いたが、無言で首を横に振るだけだった。
銀平は酔いが覚めたような顔で、男に訊き返した。
「あんた、そのなりで魚業界の人かよ。それも古い職人じゃねえと、今どきオオタロウなんてなぁ、口にしねえよ。俺の祖父さんの時代の言葉だぜ」
太郎たちだけでなく、耳をそばだてるテーブル席の客たちも男の答えを待っていた。
「いや、俺はおたくの業界の人間じゃない。IT系だよ。だが、料理人だった俺の親父は、スズキの洗いが得意料理だった。夏が来ると、スズキ釣りにものめり込んでね。銀座の料理人の間じゃ釣りキチ島田って、あだ名もつくほどだった」
そんな父親は暴れて跳ねるスズキのえら洗いの虜だったと、島田は話を続けた。父親は、いつか超大物のオオタロウを釣ってやると子どもだった島田に豪語していた。そして25年前、東京湾の波止場で、とんでもないスズキを釣ってしまった。だが重すぎて揚がらず、逆に引っ張られて海に落ちた。溺れた父親の死体に絡みついた釣り糸の先には1mを超えるスズキ、つまり、オオタロウが掛かっていた。
水を打ったように静まる店内に、「スズキが、憎いのね」とあすかのつぶやきが聞こえた。
島田は答えず盃の純米酒を飲み干し、龍二に向かって
「あなたもシーバスにハマってるなら、気を付けた方がいい。うっかりオオタロウを釣っちまったら、大変だよ。それに、親父の左手は傷の痕だらけでさ。スズキのえらは鋭い刃物みたいで、包丁でさばく時に軍手をしても手を切りやすかった。何度も切っては治った痕が、コブみたいに盛り上がってたよ」
とため息まじりに言った。
島田の打ち明け話に口さがないはずの銀平は言い返せず、胸の内を斟酌した。
「その通りだ。今日、ここへ納めたスズキはオオタロウだよ。だから、なおさら、あんたは気にいらねえんだな。だけどよう、あんたの親父さんたちのおかげで、今じゃ、スズキ専用のゴム手袋まで開発されてんだぜ……親父さんが、そんなに惚れてたスズキなんだ。一度、食ってみたらどうなんでぇ」
切り出しにくいセリフを口にする銀平を、平が後押しした。
「私も賛成ですねぇ。スズキの洗いは、御父上の自慢料理だったのですから。島田さん、食わず嫌いなだけじゃないですかねぇ」
龍二とあすかだけでなく、テーブル席の客たちも平の勧めに相槌を打った。
「スズキの泥臭さが、苦手なんですよ! あなたたちも、さっき、そう言ってたじゃないですか!」
お節介な老爺とばかりに口元をゆがめた島田は、お銚子を盃に傾けた。その時、玄関の鳴子が響いて、聞き慣れた大阪弁が聞こえた。
「ところが、その泥臭さをすっきり消せる技がスズキをよう食べる関西にありまんねん。しかも、それは元々、江戸の料理人が流行らせたんや!」
気の早い中之島哲男は紬の作務衣に雪駄履きと、すっかり夏衣装である。
「待ってやした! 師匠」と銀平が両手を打てば、平も「真打ち登場ですねぇ」と龍二やあすかにほほ笑んだ。
憚ることなくカウンター席へ座り込む中之島哲男を、島田は迷惑げに見つめた。
「立ち聞きしてすまんなぁ。けど、島田はん。スズキの洗いを生み出したんは、江戸の料理人が考え出した、灘酒で作る“玉水”や。あんたの親父さんも、きっと使うてたはずや」
初耳な玉水の言葉に、また龍二と平は小首をかしげた。酒食ジャーナリストのあすかは思い出したのか「あっ、そうか!」と洩らして、中之島の言葉に頷いている太郎を見つめた。
島田はたじろぎながらも、腹の据わった中之島に父親と同じ料理人の匂いを感じ取った。
「玉水……って何ですか? 親父から聞いた覚えはないですよ」
店内の客たちも口々に玉水をつぶやくと、あすかが口を開いた。
「玉水は、酒と水を1:1で混ぜ合わせた物よ。日本酒のことを玉と呼んだのは、磨いた酒米が玉に見えるからなの」
そこから先を、あすかは目顔で太郎に譲った。
小さく頷いた太郎は冷蔵ケースから灘の純米酒を取り出し、ボールの中へ注ぐと、仕込み水で半分に割った。そこへ氷を入れながら、島田に言った。
「冷やした玉水でスズキの身を洗うと、泥臭さが取れて、旨味も引き出される。だから、うちも使ってるよ。もちろん教わったのは、この中之島の師匠からだ。灘の酒を使うのは、江戸時代からでね。当時は灘の辛口の風味がもてはやされて、そいつで玉水を作るってのは、江戸の料理人の粋だったのさ」
樽廻船で上方から江戸まで揺られた酒は、杉樽の香りと熟成した風味が強く、食材の臭い消しにも役立った。その玉水の名残りが、今に伝わっているんだと太郎は説いた。
理にかなった話に
「へぇ! スズキの洗いって、深いねぇ」
と客席はざわついたが、島田は呆然として、盃を持つ手を宙に止めていた。
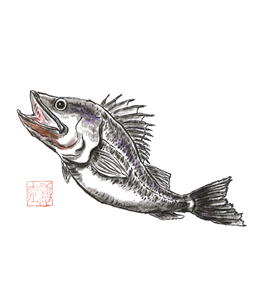 「……親父の晩酌はいつも灘の辛口の酒だった。とりわけ夏は一升瓶がいくつも、うちの台所に並んでいて……あれは、スズキの洗いに使う玉水の酒だったのか。たかがスズキ一尾に殺されちゃうような、ロクでもない親父と思ってました。それで、見るのも嫌になっていた」
「……親父の晩酌はいつも灘の辛口の酒だった。とりわけ夏は一升瓶がいくつも、うちの台所に並んでいて……あれは、スズキの洗いに使う玉水の酒だったのか。たかがスズキ一尾に殺されちゃうような、ロクでもない親父と思ってました。それで、見るのも嫌になっていた」
島田の潤んだ瞳が、スズキの切り身を見つめた。
「特に、オオタロウみたいな大物は、脂のノリもタップリやろ。洗いをする玉水には、酒がぎょうさん必要や。親父さんは、そんな丁寧な仕事をする職人だったんやなぁ」
中之島は島田の肩に優しく手を置くと、太郎へ無言で頷いた。がってん承知と、太郎が冷蔵ケースの分厚いスズキの切り身を取り出した。
龍二とあすかは灘の辛口酒を注ぎ合い、中之島と島田にも盃を回した。
「洗いの玉水にしても、焼き物のかえしにしても、スズキ料理は昔から江戸の夏の味覚だったんですねぇ」
平の嬉しげな言葉を、扉の隙間から流れる涼やかな夏の夜風が包んでいた。
