菜種梅雨が終わると、都心の緑は一気に色濃く萌えている。25℃を超える夏日のような暑さは、首都高速へ逃げ水を呼んでいた。
築地市場では、鮮度を保つためにトロ箱の冷蔵に使う氷の量が日ごとに増えている。魚の種類もイサキやマナガツオなど初夏の旬が先物で入荷し、銀座の高級鮨店や割烹の亭主は仲買人との値引き交渉に忙しい。その顔ぶれの中には、火野屋のジャンパーを着た銀平もいた。
今夜のポンバル太郎は、銀平の納めたサクラマスが売りである。
「値段は太郎さんの粘りに負けちまったがよう、こいつは山形の酒田産で60㎝の大物だぜ! 旬の最後を締めくくる、貴重品だ! どうでぇ、このプリップリの身はよう!」
太郎が柳葉包丁で厚めに切ったピンク色の刺身は、白磁の皿へ桜の花びらをかたどっている。銀平の隣で刺身をスマホ撮影しているジョージは「ファンタスティック! ワンダフル!」を連発し、目をみはった。
ネクタイをほどいて撮影に夢中のジョージを、厨房から出て来た太郎の解説はさらに刺激した。
「サクラマスは高級魚だ。今はキロ当たり、2000円前後。大きいほど値が張って、体高のあるこの“板マス”は極上品だよ。軟らかくて、すこぶる甘味がある。こいつには、山形の旨口の純米酒がピッタリだ」
テーブル席からは、注文した刺身を待っている客たちの唾を呑む音が聞こえた。
ひと足先に、サクラマスのルイベを食べ終えた平 仁兵衛は舌へ残る美味しさをぬる燗の純米酒で流し込み、ご満悦の表情で銀平へ訊ねた。
「脂がのっているのに、実にスッキリとした旨味ですねぇ。銀平さん、サクラマスは上流にいる川魚のヤマメが海に降りた物なのでしょ?」
「その通りで。こいつは、最上川を下ったヤマメでさぁ。いったん海に出たヤマメは回遊しながらでっかくなって、川へ戻る頃にゃ60㎝を超える。これを海や河口で撮ったのがサクラマスてぇ呼ぶわけで。ところが、川の中で一生を過ごすヤマメは40㎝ぐれえにしかなりやせん。どうして海派と川派に分かれるのかは、いまだ謎なんでさぁ」
トロサーモンに似た刺身を箸でつまみながら自慢げに答える銀平に、平だけでなくテーブル席の客たちも「へぇ、そうなの」と口を揃えた。
「私、もう、ダメ! 銀平さん。ひと口、もらっていいですか?」
せがんだジョージがつまみ食いするようすを、八百甚の誠司は辛抱しながら一瞥している。今夜は、歳の近そうな男とカウンター席の隅に並んでいた。だが、どうも顔色がよくない。
盃とサクラマスをつまむ箸は遅々として進まず、傍目にも太った連れの男に気を遣っているのが分かった。
見覚えがある男の顔に、平との会話を続けるふりで銀平は聞き耳を立てた。グレーのスーツ姿の男を誠司は江木と呼び、元・八百甚の先輩社員で、今は野菜や果物の流通会社に転職していた。
江木は酔いが早く、居丈高な口ぶりで冷酒グラスをあおり、サクラマスの話を受け売りにして誠司をなじった。
「ほら、サクラマスだって、海に出て成長するそうじゃないか。お前さ、もっと大きなビジネス市場でバリバリ売らなきゃ、儲からないよ。築地青物のやっちゃばなんて、所詮は魚市場のお荷物じゃねえかよ。俺が口を利いてやっからさ、うちに来いよ」
しかつめらしい顔で口説く江木に誠司は
「いやぁ……俺なんか、企業の営業マンなんて柄じゃねえし。無理っすよ」
と引き攣った笑いを返すだけで、いつになく弱腰な態度だった。
ここ数か月、八百甚は退職者が増え、仕事の負担がキツくなったと誠司がボヤくたび、銀平は「若い内の苦労は、買ってでもしろ」と諭していた。
銀平の記憶では、江木の実家は築地近くの八百屋だったが、父親の代で小さな店をたたみ、
息子の江木は当時の仕入れ先だった八百甚に縁故で就職していた。だが10年後、義理堅い社長が止めるのも聞かず流通会社へ転職したと噂に聞いていた。
誠司を引き抜く魂胆のようだが、つま先の剥げた革靴や肘の出たスーツというなりは、みすぼらしい。胡散臭そうな江木の誘い話に、銀平は気が気ではない。
「誠司の野郎……あいつに借りでもあるのか。築地にゃ築地の商いがあるてぇ、バシッと言い返してやりゃあ、いいものをよう」
鼻息が荒くなった銀平は、黄色信号の点っている状態である。ましてや、兄貴分としての面子が、誠司を口説く江木を放っておかないのは目に見えている。
平は銀平の気をそらそうと、サクラマスに話題を戻した。
「ところで、ヤマメには独特の模様がありますよね。でも、サクラマスにはない。いつの間にか、消えてしまうわけですか?」
「パーマークってんでさ。日本語じゃ幼魚斑って意味で、ケツの青いガキってことすよ。あの江木って野郎みてえにね」
平がふった話は、ヤブヘビになった。聞えよがしな銀平の皮肉に誠司が表情を曇らせると、江木は鋭い視線でやり返した。
「てやんでぇ! 築地なんて、古臭せぇことにこだわる老害オヤジばかりじゃないかよ。だから、若い者が続かねえんだよ」
途端に、平が制するのを無視して銀平が立ち上がった。
「てめえ! 上等じゃねえか。表へ出やが……」
銀平の啖呵を止めたのは、肩に乗っかった水色の四合瓶だった。その瓶を、高野あすかが手にしている。
春の新作ファッションに身を包んだあすかの登場に、店内がどよめいた。銀平と江木の諍いも、一瞬にして火が消えるほどだった。
生貯蔵酒の瓶を、あすかは呆れ顔で銀平の前に置いた。
「まったく、銀平さんって話し合いで解決できない人格なの? そんなのじゃ、築地が移転したって、ブラックイメージになっちゃうじゃないの」
あすかが銀平に直言すると、固唾を呑んでいた客たちが失笑した。それに同調するかのように江木があすかにおもねった。
「でしょう? 僕もそれが嫌いで、築地を出ちゃったんですよ。なにせ、“早朝がキツい”“匂いが臭い”“掟が厳しい”の3Kだし。品質のいい野菜やフルーツなら、僕のいる会社からネットで直接お届けできますよ」
渋い顔の誠司をよそに、やにさがった態度で名刺を差し出す江木だったが、その鼻っ柱をへし折るかのようにあすかが声音を上げた。
「君もさぁ、勘違いしてるわよ。さっきの売り言葉に買い言葉、銀平さんは年上でしょう。どんな仕事をしても、礼儀ってもんをわきまえなきゃね。それもできないようじゃ、いくら転職したって、しくじると思うけど。人生、陽の当たる場所ばかりじゃない。我慢と辛抱はつきものだよ……ね、誠司君」
歯に衣を着せない物言いに、江木は声を失った。
引っ込みがつかないままの銀平へ、平がぬる燗のお銚子を差し出して
「また、あすかさんに、イイところを持ってかれましたねぇ」
とカウンター席へ戻した。
水を打ったように静まるカウンターへ、竈で焼いた魚の匂いが漂った。太郎の手にする皿の魚は30cmほどで、体の側面には縞模様と斑点が浮いている。
「おっ! 尺ヤマメですねぇ」
「美味しそう! 私にも、焼いて欲しいな」
平とあすかの声に「尺? ワッツ?」とスマホから顔を外すジョージの横で、気を削がれた銀平が口を開いた。
「……そいつぁ、仕入れ先から特別にもらったのを、太郎さんの晩飯用にあげたヤマメじゃねえか。このサクラマスと同じ、最上川育ちだ」
「ああ、江木さんに食べてもらおうと思ってな」
所在なさげに突っ立っている江木を、太郎は誠司の隣へ座るように皿を置いた。銀平からの差し入れに躊躇したのは、江木だけでなく誠司も同じである。
「な、なんだってぇ! こんな野郎に食わすなんて、もったいねえよ」
案の定、カウンターを叩いて憤る銀平を太郎は無視して江木に言った。
「江木さん。本当はあんた、築地に帰りてぇんだろ。誠司に逢いに来たのは、引き抜きじゃなくて、やっちゃばのようすを聞き出したかったんじゃねえのか……その名刺入れ、八百甚の物だろ?」
今しがた江木があすかへ差し出した名刺のケースには、誠司のジャンパーと同じ八百甚のロゴマークが入っている。図星らしく、江木は名刺入れを握り隠した。
客たちが、江木の気持ちを斟酌するかのように押し黙ると、誠司の声がした。
「江木さん、本心なんですかい? ……だったら、俺が社長に話してみますよ。だから、もう一度……」
「今さら、そんなみっともねぇことたぁ、できねえよ!」
唇を噛む江木は財布から一万円札を取り出すとカウンターへ置いた。そして、薄汚れた鞄を手にした。
立ち去ろうとする江木の肩を、銀平がつかんだ。
「逃げるのかよ。その前に、このヤマメを食ってけ…サクラマスに負けねえくれえ、旨ぇんだ。サクラマスは広れえ日本海で、でっかくなるがよ、また育った最上川の水に帰って来るんだ。今のおめえにも、築地の水が必要なんじゃねえか?」
江木は一瞬、苦い顔で立ち止まったが、銀平の手を振りほどくと、玄関を飛び出て行った。
咄嗟に後を追いかけようとする誠司の腕を、太郎が捕まえた。
「今は、そっとしておいてやんな……あいつの血に築地の水が流れてるなら、きっと戻って来るさ」
ため息を吐く誠司へ、ジョージがスマホの画面を見せた。
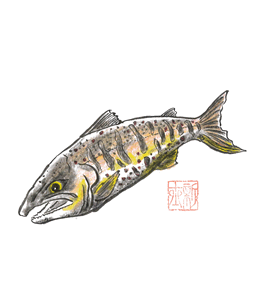 「誠司さん、この写真データを八百甚の社長さんへ見せれば、きっと江木さんを許してくれます」
「誠司さん、この写真データを八百甚の社長さんへ見せれば、きっと江木さんを許してくれます」
画面に映っているのは、江木が手にしていた八百甚の名刺入れだった。
「あ、ありがてぇ。恩に着るよ、ジョージ」
手を合わせる誠司に、平は太郎と顔を見合わせた。
「ジョージさん、やりますねぇ。江戸っ子気質が染みついてきましたねぇ」
カウンターへ忘れられたヤマメの塩焼きに、銀平がつぶやいた。
「あいつの心のパーマークは、消えちゃいねえよ」
あすかが嬉しそうに笑みを浮かべて、銀平をイジくった。
「でも、銀平さんの頭の中には、違う意味のパーマークがあるわねぇ」
「なんだとう! そりゃ、俺がバカだってことかよ!」
店内に、大笑いとヤマメを焼く匂いが満ちていた。
