ポンバル太郎のそばに立つ街路樹でアブラゼミがうるさく鳴き出すと、夕刻の通りの蒸し暑さに辟易としている通行人たちはうっとおしげに眉根を寄せ、額の汗をぬぐった。
その中を割って歩く火野銀平は、剃った頭から流れる汗をタオルで拭きながらポンバル太郎に入って行った。火野屋の黒いTシャツの背中は、抜けて乾いた汗のせいで白く塩を吹いている。
「ふう! たまんねえ暑さだぜ。太郎さん、冷えた活性酒を飲ませてよ……と、あれ? いい花の匂いがするな。どこに、あるんだ?」
その芳しい香りは日本酒の味わいを邪魔すると思えるほど甘ったるく、カウンター席に座っている高野あすかの方から漂っていた。ふだんなら強い香水をつけた銀座のホステスへ露骨に顔をしかめる太郎なのに、タンクトップ姿のあすかには、涼しい顔をして冷酒を注いでいる。
「おいおい、太郎さん。あすかは特別扱いかよ、そりゃ、ねえんじゃねえの」
とがめる銀平に太郎が口を開きかけると、先にあすかが、してやったりの顔で叫んだ。
「ほら、太郎さん! やっぱり、引っかかったでしょ。このスズランの花酵母は、かなり香りが立つのよ」
「ふ~む。ここまで強いと、料理との相性が難しくなるな」
太郎がいったん視線を外すと、無視された銀平は
「は、花酵母って、何なんだよ!?」
とカウンター越しに顔を見合わせる二人の間に割り込んだ。
声高になる銀平へあすかは唇に指を当ててから「し~」と諌め、視線を店の中へ向けた。それを追った銀平の目にはテーブル席を占める妙齢の女性客たちが映り、囲まれている一人の男性客を凝視すると、右近龍二がほほ笑んでいた。
「けっ! 龍二の野郎、鼻の下を伸ばしやがって……それにしても、女性客だけで貸し切り状態か。今夜は、どうなってんだ」
「あの人たちは、花酵母の酒を研究している全国の蔵元の女将さんたち。若い世代の日本酒ファンを増やすのに、香りの高い花酵母で一石を投じたいって、龍二さんを介して太郎さんに提案方法を相談に来たの」
花酵母はさまざまな花の蜜から分離した酵母で、東京のある大学で世界で初めて成功した研究成果として、かつて人気をさらった。ほとんどの日本酒を仕込む酵母は、酒のもろみから分離培養しているが、それらの酵母が育ちやすい環境に合う花を採取し、分離・培養することで、華やかな香りとしっかりした旨味を持つ酒を造る花酵母が誕生したとあすかは語った。
「じゃあ、バラとかもあるのかよ?」
「もちろん。ツルバラがあるわ、リンゴや洋ナシの香りに似てるよ。カーネーションの花酵母もあるの。母の日とか、女性へのプレゼント酒に使えそうでしょ!」
嬉々としてしゃべるあすかはトートバッグからデジカメを取り出すと、テーブル席に近づいて抜け目なく取材を依頼し、女将たちの撮影を始めた。
「太郎さんは、どう思ってんだよ。酒と肴の相性からすると、俺は食中酒には向いてねえと思うぜ」
カウンターに置かれたすずらん酵母の純米酒のボトルに、銀平が鼻先をクンクン鳴らしながら訊いた。
「うむ、そうかも知れねえが、シェリー酒みたいなアペリティフ(食前酒)って方法もある。和食よりも、洋食のオードブル、中華料理の冷菜にも合うんじゃねえかな」
その時、テーブル席で歓声が上がった。女将たちの持ち寄ったさまざまな花酵母の四合瓶が開けられ、華やかな香りの波が太郎と銀平の席まで広がった。とたんに銀平が、鼻の穴をヒクつかせた。
「ダメだ、クシャミが出そうになってきやがった。俺みたいな江戸前の魚屋には、こりゃ無理だな。悪いけど、今夜は退散するぜ」
銀平が鼻先をつまみながら立ち上がった時、両肩を押さえるようにして、龍二が隣に座った。
「まあまあ銀平さん、もう少し付き合ってくださいよ。確かに、花酵母は香りが突出しているので料理が難しいのですが、それを逆手にとれば、ユニークな肴になると思います。太郎さん、ちょっと厨房をお借りしたいんですが」
ワイシャツを腕まくりしながら龍二が頼むと、その自信ありげな口調に期待する太郎は、
「冷蔵庫には、白身なら房総のヒラメ、赤身なら焼津沖のメジマグロがある。どっちでも、好きに使いな」
と答えた。すると、考えた龍二はヒラメを選んで、スズラン酵母の純米酒を表面に塗り、塩コショウをした。次に長ネギのみじん切りとレモン汁、それに醤油を合わせた。
怪訝な表情でそれを見つめる銀平の前で、龍二はフライパンにオリーブオイルをしくと、ニンニクを炒めた。そして塩コショウをしたヒラメを、皮の面から焼き始めた。
香ばしさが立ち、食欲をそそられた銀平が負け惜しみに舌打ちすると、いつの間にか、両隣の席に美しい和服姿の蔵元女将が並び、龍二の腕前に見惚れていた。
「ここからです! 花酵母の酒を活かすのは」
龍二はフライパンにすずらんの酒を加え、蓋をして蒸し焼きにした。
そして蓋を取ると、上品な醤油と花酵母の香りが渾然一体となって、カウンターを包んだ。
「ヒラメの和風ポワレって、ところか。なかなか、うまそうだ」
太郎の言葉に、あすかと蔵元の女将たちも目をみはっていた。
「じゃあ、まずは銀平さんに……」
皿に盛りつけたヒラメを龍二から出されると、銀平は箸先でつまんで香りをかぎ、口に入れた。
固唾を飲むような面持ちの女将たちの前で、銀平がおもむろに訊いた。
「龍二、ヒラメを選んだわけを聞かせろ」
「日本酒は、食材の旨味を引き出す力を持っています。だから、脂ののったメジマグロだと濃厚な身の味と花酵母の酒の香りが喧嘩しそうだと思ったんです。それで淡白なヒラメにして、酒を塗って香りをつけ、旨味も引き出しておきました。先に馴染んでいることで、仕上げ前の白ワイン代わりに花酵母の酒を加えれば、香りと味わいはグッと和風になります。醤油ともからみやすいですしね」
龍二は、すずらんの純米酒を銀平のグラスに注ぎながら解説した。その香りが、ヒラメの和風ポワレの匂いをさらに包み込むようだった。
ヒラメを口に入れた太郎が、ソースを舐めながら言った。
「うむ……酵母の香りと醤油がマッチして、おもしろい! 海外の日本食ブームも含めて、これからの日本酒には新しい発想やスタイルが大切だ。若い奴らの食文化も、俺たちの世代とずいぶんちがってきてる。実際、山廃仕込みの純米酒がイタリアンやフレンチでかなり評価されてきてるのは、その表れだろうな」
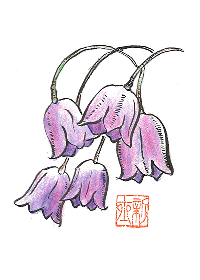
すずらんの純米酒を傾けるあすかが、満面の笑みを浮かべた。
「それとさぁ。今、この店にいる人はみんな笑顔になってるでしょ。外はあんなに暑くて嫌なんだけど、ここは花酵母のおかげで気持ちもスッキリ! おだやかになってるの。花酵母のお酒は、アロマみたいに香りで癒す魅力もあると思うの。さっきまであんなに怒ってた銀平さんも、まんまとハマッちゃったもんね」
「うっ、うるせえや! それほど、単純な男じゃねえぞ」
反論しつつも、両脇の女将たちにドギマギしている銀平を太郎が冷やかした。
「そりゃ花酵母のせいじゃなくて、両手に花だからじゃねえのか?」
今夜のポンバル太郎は、華やかな香りと声音にいつまでも満ちていた。
