桜吹雪を忘れたかのような寒の戻りが、夜雲からみぞれ混じりの雨を降らせていた。
「四月半ばなのに異常よ! ほんとに、氷河期が来てんじゃないの」
独りごちた高野あすかは、ペンだこのある指先に白い息を吐きかけながらポンバル太郎の扉を開けた。その途端、一気にぬくもりに覆われ、店に充満した人いきれと酒の匂いに気圧された。
「こっ、これがポンバル太郎?」とたじろぐあすかを、カウンターの端っこで窮屈そうに立ち飲みしている銀平が目に止めて毒づいた。
「あんた、うまく書き過ぎなんだよ! どうしてくれんだ! 俺の指定席がなくなっちまったじゃねえか」
だが、恨めしげな口調とは裏腹の笑みが銀平の口端から覗くと、取材日の「女だてらに居酒屋の取材」とたしなめられたことに、あすかは溜飲を下げる思いだった。
店内には10人を超える客がいて、カウンター席の男たちは肩をつき合わせている。その向こうの厨房では太郎が行平鍋と酒瓶を持ち替えながら、あすかの編集した居酒屋雑誌を手にする客と酒談義をしていた。
太郎の脇から豆絞りの鉢巻をしめた小学生の剣が現れては、テーブル席に料理と酒のグラスを運んでいた。手伝いをする剣の鉢巻と半被姿はなかなか堂に入って
「将来のマスター、おすすめの一杯を頼むよ」
と祖父のような客たちが目を細めていた。
活気あふれるポンバル太郎に記事の手ごたえを感じる一方で、あすかは取材した日から心待ちにしていた太郎との再会に胸を高鳴らせた。やにさがった店主には何人も出逢ったが、ウンチクや詭弁を弄することがなかった太郎はあすかの理想とする酒匠だった。
「あんたかいな、太郎ちゃんの記事を書いたんは?」
太郎に見惚れるあすかの肩越しに、突然と野太い関西弁が飛んで来た。
振り返ると、白髪混じりの頭を角刈りした男が雑誌を開いていた。50歳半ばとおぼしき年波で、はなだ色の作務衣の上に綿入れ半纏をまとった昔気質な格好にあすかはどぎまぎしつつ、太郎と親しげな口ぶりの男に気持ちを引きしめた。
「あっ、はい。あの……お気に召さなかったでしょうか」
「いや、その反対や。太郎ちゃんの志をよう解かってるなあと感心しましてな。とりわけ、ここがよろしいわ」
男が開いた誌面には、太郎から引き出した酒匠の信条をあすかが表現した「造り手の素顔が見える酒」や「飲み手の本音が聴こえる酒場」の見出しが並んでいた。
「この言葉を捻り出した人は、只者やないと思うてね。どうやろ、一献付き合うてもらえまへんか。申し遅れたが、わしは中之島 哲男ちゅう者や」
問わず語る中之島は、ドングリ目に人の良さげな皺を寄せてカウンター席を見た。ちょうど勘定をすませた団体客が、帰り支度をしていた。
「えっ、あの高野って娘は、中之島の親爺さんの目に止まるほどなのかよ!」
中之島の誘いに気づいた銀平が酔いざめしたような顔でつぶやくと、太郎はカウンターからあすかに声を投げた。
「高野さん、俺の師匠だから安心しな。たまに大阪からやって来て、いい酒を教えてくれんだ。ちょいと、関西弁がえげつない時もあるけど」
「おい、誰がえげつないねん。わしは春団治と同じで、本音でしゃべるたちなんや。まあ、そんなことはどうでもええ」
カウンター席にあすかと座った中之島は、手提げ袋から緑色の四合瓶を取り出した。
間近に見る中之島の横顔が、あすかの記憶の隅でふっとうごめいた。おぼろげだが、濃い眉と長いまつ毛をどこかで見た気がした。
「この福島の酒、あんたにも?いてもらおうと思うてな。太郎ちゃんに持って来たんやけど、あんたが福島県の出身やから飲ませたいそうや。わしが2年間、冷蔵で熟成させた純米大吟醸や」
酒のレッテルには「蔵娘(くらむすめ)」の銘柄が、秀麗な文字で揮毫されていた。
中之島が開栓して冷酒グラスに注ぐと、2年冷蔵させただけあって華やかな吟醸香が柔らかく変化し、落ち着いていた。
ところが、あすかはグラスに手を伸ばすことなく、身動きひとつせずレッテルを見つめていた。
「あんた、熟成酒は嫌いか?」
怪訝な顔で中之島が訊くと、あすかの瞳から大粒の涙がこぼれた。
「な、な、なんでぇ。どうしたんだよ?」
二人のようすを横目で探っていた銀平がうろたえ、驚いた中之島は無言の太郎と目を合わせた。
「これ……私の実家のお酒です。もう蔵はありませんけど、こんな形で逢えるなんて思いもしなかった」
「な、なに! ほんまか? ほんなら、あんたは相馬の高酒造(たかしゅぞう)の……もしかして、あの小さかった娘さんか?」
あすかは無意識にこみ上げる涙をハンカチで拭いながら、遠い昔、中之島の無骨な手で頭を撫でられた感触を呼び起こしていた。小学3年生の頃、全国を行脚して酒匠の修行をしている男が実家にやって来た。それが、中之島 哲男だった。
高酒造の囲炉裏端で父と熱く酌み交わし、店先で母と談笑していた中之島の姿がようやくまぶたに浮かんだと、あすかは語った。
太郎は東日本大震災で廃業を余儀なくされた高酒造を思い出し、深いため息を吐いた。
「やっぱり、そうか。蔵元の娘さんじゃないかって気がしたんだが、あの酒蔵か……高野さん、取材の時に俺がどの銘柄を一番好きかって訊いたら、答えるのをためらったろ。悲しげな顔をして『どこの酒だって、今は大差なく美味しい』とはぐらかした。喉まで出かかっていた言葉を飲み込んでいた」
「それが、この蔵娘ちゅうわけか」
中之島の言葉に、あすかは忸怩たる思いを噛みしめるような表情でコクリと頷いた。
「ってことはよ、ハルちゃんと同じ福島生まれ、中之島の親爺さんが昵懇にしていた被災蔵元で、最期にしぼった酒がこれ。でもって、その蔵元の娘が記者としてポンバル太郎を取材したって……マジかよ、こりゃ神がかってるぜ!」
銀平のうわずった声が店内に響くと、テーブルの客たちが
「確か、その蔵元は夫婦とも亡くなったって聞いたぜ」
と声をひそめて、あすかに注目した。
「銀平、声がでかいんだよ。高野さんの気持ちを考えろ」
太郎は蔵娘に手を伸ばした銀平から瓶をひったくると、カウンターに肘を突いて両目を覆っているあすかの前に置いた。
レッテルの筆致を、中之島が太い指でなぞりながら語った。
蔵娘の銘柄は、あすかの母親がずいぶん前に書いた字だった。そして「造り手の素顔が見える酒」は、自分が若かりし頃に薫陶を受けたあすかの父親から教えられた座右の銘だと披瀝した。
涙で化粧くずれしたまま茫然とするあすかに、太郎が蔵娘をひと口含んで言った。
「確かに、ご両親の素顔が見えるようだ。高野さんの記事には、高酒造の血脈が生きてたんだな」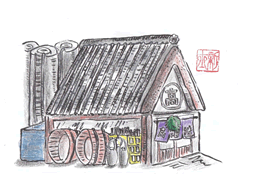 すると、おしぼりを手にした剣が満面の笑みであすかに近づいた。そのツヤツヤした髪を中之島が撫でながらつぶやいた。
すると、おしぼりを手にした剣が満面の笑みであすかに近づいた。そのツヤツヤした髪を中之島が撫でながらつぶやいた。
「剣ちゃんも、いつかお父ちゃんみたいな酒匠になった時、わしが頭を撫でたことを覚えといてや」
「うん! ところでさ。あすかさん、顔を拭いたら? 素顔の方が美人だと思うよ」
こましゃくれた剣の愛想に、どっと笑いが巻き起こった。
高野の潤んだ瞳がほころび、客たちは次々に蔵娘を注文していた。
