ゲリラ豪雨が通り過ぎた夜、渋谷や赤坂の裏通りは冠水に立ち往生するタクシーで渋滞していた。猛烈な雨足はいっこうに衰えず、出勤途中のホステスからは悲鳴が聞こえた。
ポンバル太郎には、路面のしぶきで裾をずぶ濡れにした男たちが飛び込んだ。中には上等そうな革靴の中で足を泳がせる客もいて、カウンター席の平 仁兵衛が太郎からタオルを借りて手渡した。
平に酌をしている右近龍二は、もったいなさげにつぶやいた。
「あ~あ、フェラガモがイッちゃってるよ……まぁ、この降りようじゃ、長靴でもダメか」
独り言なのに、カウンターの端っこに座る若い男が「いっそ下駄の方が、潔いですね」と相槌を打った。見慣れない顔の男は、年恰好の似た龍二にやたらと話しかけていた。
日本酒に詳しく、どことなく坊ちゃん風な印象に龍二も親しみを覚えた。すでに二合半の無濾過生原酒を飲み、自ら麻布十番で日本酒料理店を営む神田光也と名乗るほど上機嫌だった。
ふいに強い風が吹き込んで、外の雨音を響かせた。玄関扉に立っているのは渋い色の番傘に下駄ばきの老爺で、片手で紬の着物の裾を膝までたくし上げている。
まるで昭和の任侠映画から現れたような老爺だが、身なりは堂に入っていた。
「うそだろ! 今言った、まんまじゃん」
あまりのタイミングの良さと風変わりなスタイルに、光也はこらえ切れずに吹き出した。客席の蔑視に老爺は動じず、番傘の雫を軒先ではらうと、濡れた下駄の跡を床に付けながらテーブル席へ座った。そして、紬の袂から布包みを取り出した。
ほどかれた包みから青い龍を焼きつけた蕎麦猪口が現れると、「ほう~」と客たちの感心する声が聞こえた。その声につられて厨房を出た太郎に、老爺が蕎麦猪口をかざした。
「亭主。東京の上撰酒を、常温でくれねえかい」
どうやら蕎麦猪口は老爺の“マイ盃”らしく、龍二はいいセンスと頷いたが、どうしてか光也はムキになって腐した。
「蕎麦猪口で上撰だって!? 時代遅れも甚だしいや。これからの日本酒は、無濾過の生原酒ですよ。濃厚な旨味は、イタリアンやフレンチにも合いますしね……あの蕎麦猪口、薄ボケた色をしてるじゃないですか」
蕎麦猪口を持つ老爺の手が、一瞬、震えた。滑り落ちかけた蕎麦猪口をハッシとつかんだのは、別のシワ深い手だった。
「ひ、平 先生! な、ナイスキャッチ!」
思わず叫んだ龍二に、老爺の横に立つ平 仁兵衛が「ふうっ」と吐息で答えた。平は胸を撫で下ろすようなしぐさの後、しみじみと蕎麦猪口を見つめながら老爺に戻した。陶器の目利きは、平の本業である。
「これは30年前に廃業した、神田蕎麦の猪口ですねぇ……私も当時に、女将から頂いた名入りの蕎麦猪口を持ってますが、あなたのは年季がちがう。この神龍の絵柄は、神田蕎麦の創業時の意匠だった。それと、蕎麦つゆのワリシタの色が猪口にしみて、微かに匂いもしています。きっと江戸時代の逸品でしょう……これに東京の上撰を注いで飲むのは、まさに江戸っ子の粋ですねぇ……裏に彫っているのは、あなたのお名前でしょうか? 藪さん」
羨ましげな平の表情には、客席を唸らせるほどの説得力があった。太郎も龍二も老舗だった神田蕎麦の聞き憶えはあるが、今や幻となった二八蕎麦を味わったことはない。
藪と呼ばれた男は照れ臭げに、そして手探るようにして平の手から蕎麦猪口を受け取った。
「すまねぇ、旦那。あっしは、目が悪くってね。この蕎麦猪口も、もうぼんやりとしか見えねんだ。昔は、神田蕎麦で職人頭を張ってたんだが……耄碌しちまったよ」
男が藪 喜一郎と名乗ると、年配の客たちは
「知ってるよ! 昔、テレビの料理番組にも出てた蕎麦打ちの名人だ!」
とざわめいた。平も藪を思い出したのか、その腕前の凄さを太郎と龍二へ話した。何よりも神田蕎麦には昼下がりの一献を嗜む江戸っ子が集い、“板わさ”や“だし巻き”、“蕎麦がき”で酒を楽しんだ後、藪が打つ盛り蕎麦を2枚食うのがお決まりだったと説いた。
しかし、店内の客たちが舌なめずりする中、光也の顔色は蒼かった。うつむき気味で歯ぎしりする光也に気づいた龍二が、はっとして問いかけた。
「ひょっとして……神田蕎麦と光也君の苗字って、関係あるんじゃないの?」
光也の名を聞いて、藪が目を見開いた。
「ぼ、坊ちゃんですかい!? そこにいなさるのは、神田蕎麦の光也さんなのかい?」
藪が両手を伸ばしながら瞳を凝らすと、店内は水を打ったように静まった。
だが、光也は頭をもたげず答えた。
「だったら、どうなのさ。うちの親父が神田蕎麦を潰したのは、普通酒のノンベばかりを大事にしたからだよ。蕎麦を食う客だけで行列を作っていりゃ、あんなことにはなってなかったとおふくろは嘆いてた。だから、俺は蕎麦猪口で佳撰や上撰の酒をダラダラ飲む奴は嫌いなんだ! グラスで飲む無濾過生原酒こそ、最高の日本酒だよ」
突き刺すような光也の口ぶりに、藪は蕎麦猪口を胸元へ止めたまま押し黙った。
今しがた光也が藪を腐したことは誰もが腑に落ちたが、彼の意見に頷く者は少なかった。
流行の無濾過生原酒はポンバル太郎でも人気だが、それだけを愛飲する客たちはいない。そう龍二が諭そうとした時、ゆっくりと扉が開いた。外の雨はもう上がっていたが、鳴子の音は静かだった。
いつもの銀平らしからぬおとなしい登場の仕方に、かえってその場の空気は張り詰めた。
「光也さんって言ったな。あんた、祖父さんの時代のこと、何にも分かっちゃいねえな。30年前は無濾過生原酒を年中売るなんてなぁ、タブーだったんだよ。冷蔵設備も整ってない酒屋で火入れしない生酒を売るなんて、おっかなくてできねえだろ。それによう、蕎麦のワリシタってえのは、あの辛さが酒のツマミになるんでぇ。蕎麦屋じゃ、一品の肴を食って、まだ飲み足りねえから、肴の代わりにワリシタをなめるんでぇ。それが、江戸っ子だ! だからよう、ワリシタの味がしみてる蕎麦猪口で酒を飲めば、一石二鳥ってわけよう」
銀平は幼少の頃、神田蕎麦の常連だった祖父の銀次郎に連れて行かれたらしく、藪にその名前を告げた。
懐かしげな二人の横顔へ、光也が言い返した。
「そ、そんなの、しみったれた飲み方じゃないですか!」
怒り出しそうな銀平を平は笑みで制して、光也へ答えた。
「蕎麦は、気取って食べる物じゃありません。それに、上品な京料理にも、こんな話があるんです。高級なすっぽん鍋なんですけど、その店じゃ、信楽焼の土鍋を何十年も使う内に、すっぽんのダシがしみ込んで、お湯だけを沸かせても味が付くそうです。ですからねぇ、器を長年愛用するのは、日本人の食文化の一つだと思いますねぇ……そんな蕎麦猪口の魅力を、あなたはお父上から学んでいない。残念ですよねぇ、藪さん」
意味ありげな平の視線が、藪の持つ蕎麦猪口へ止まった。
「俺が飲んでみてえよ、その蕎麦猪口でよ」
と銀平がつぶやくと、藪はゆっくりと光也に蕎麦猪口を差し出した。
「憶えちゃいねえでしょうが……赤ん坊だった光也坊ちゃんの“お食い初め式”に、あっしは招かれましてね。この蕎麦猪口で、ワリシタをあなたになめてもらったんでさぁ……これは、あなたが使うべきだ。どうか、神田蕎麦の心意気と蕎麦屋が好きなノンベの気持ちを忘れずにいてくだせえ」
蕎麦猪口を差し出す藪の両手を、おずおずとする光也の両手が包んだ。蕎麦猪口を放した藪の手のひらが光也の顔かたちをまさぐると、太い指先は少しずつ光也の涙に濡れた。
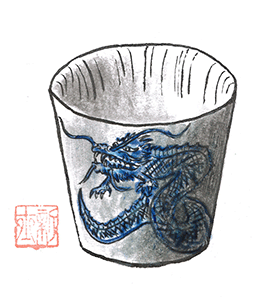
藪に抱きしめられる光也の背中へ、銀平が先輩気取りで言った。
「俺も、その内、自分の蕎麦猪口を作って酒を飲むぜ」
客たちが感心する中、太郎がイジくった。
「ほう! お前にできるかねぇ。魚を売る以外は、てんで不器用だからよう。だけど、さっきのワリシタの話は、なかなかおもしれえ」
銀平が胸を反らすと、龍二は平へ耳打ちした。
「あれ、以前、僕が教えてあげたんですけどね。まあ、憶えていただけマシか」
「うっ、うるせえぞ、龍二! 黙ってろい!」
銀平が赤面すると、涙目の藪が嬉しげに口を開いた。
「江戸っ子は、人様のウケウリが得意でさぁ」
思い当たるのか、客たちが揃って苦笑すると、ようやく光也も笑顔を覗かせた。
