明後日から開催される「伊勢志摩サミット 首脳会議」に、中部国際空港だけでなく、都内でも厳戒態勢が敷かれていた。テロ対策に東京駅や羽田空港は防弾チョッキで身を固めた警察官がそこかしこに配置され、夜になっても物々しい。
それでもテレビニュースは、「晩餐会では、ぜひ和食と日本酒を楽しみたい」と話す欧米の首脳たちを報じるなど、歓迎ムードを盛り上げていた。
ポンバル太郎のカウンター席も、今夜はいつもと様相がちがっている。
ジョージやその友人で和食修行中の料理人・フィリップのたどたどしい日本語に交じって、中国語やハングルも聞こえている。東洋系だが、明らかに日本人離れした面立ちの女性がジョージたちの隣に座って、二杯目の冷酒グラスを傾けていた。料理も、酢の物や天婦羅といった純和食を選んでいる。
彼女たちは海外のマスコミとして来日しているジョージの友人だが、モデルのようなスタイルの良さに店内の男たちは思わず目を止めた。
カウンター席で上機嫌の平が、純米酒の盃をなめながらジョージへ言った。
「こんなに国際色豊かな夜は、初めてです。ジョージさん、彼女たちは日本酒をたいそうお好きなようですね」
「ええ、二人とも明日から伊勢志摩へ入るそうで、地元の日本酒を、とても楽しみにしています。私は現地に行きませんが、要人たちのディナーのメニューに興味があります!」
そう答えるジョージの言葉を、フィリップが英訳して女性たちに伝えた。ワンレングスの髪型の女性も相槌を打ち、平へ「こんばんは。ワン・メイリ―(王 美麗)です」とお辞儀をすると、ショートカットの女性が「私は、パク・ロミ(朴 瑠美)と言います」と続いた。二人とも片言の日本語だったが、カウンターへ丁寧に両手をつく仕草に親日家らしい人となりが表れていた。
「なるほどねぇ。伊勢志摩サミットの晩餐会のメニューですか。これに載ってますかねぇ」
カウンターの隅に置かれたスポーツ新聞を広げる平に、厨房の太郎が行平鍋から立ち昇る湯気の中で答えた。
「予想できるのは、松阪牛とアワビでしょう。どっちも三重県の名物で洋風のソティにも合いますから、きっと出ますよ。伊勢海老が、微妙ですね。ロブスターやオマール海老は、欧米でも口にしてますから、珍しくないですからね。まあ、バターソティやホワイトソースに合わせる日本酒なら、濃厚な純米酒だな。お誂え向きに、中京地区にはしっかりとコクのあるタイプが多いですからね」
太郎の的を得た答えに、平だけでなく、ジョージも相槌を打った。すると、ほろ酔いのフィリップが声を上げた。
「私、伊勢海老のグラタンは、今、修行している赤坂の割烹で食べました! あれにはワインよりも、冷やした山廃純米酒がピッタリだったよ」
弾んだ声音に、平は上達しているフィリップの日本語を感じ取って、ジョージと笑顔を見合わせた。
その時、玄関の鳴子が軽快な音を立て、店内の話を耳にしていたらしい右近龍二が問わず語った。
「サミットの日本酒ですか。中京地区の地酒が出れば、いいんですけどねぇ。いわゆる、中国銘酒(ちゅうごくめいしゅ)ですよ。江戸時代、三河から伊勢にかけての地酒は灘や伏見といった上方酒に次ぐ二番手の酒として、廻船で江戸へ運ばれてました。灘酒の人気には勝てなかったけど、上方の酒が江戸で品切れする初夏になると、一気に需要が伸びたんですよ。値段も手頃だったし、キレのいい灘の辛口とちがって、濃厚なコクと辛さが合わさった中国銘酒は、味の濃い料理を好んだ北関東出身の庶民の舌にピッタリだったそうです。でも、高価な伊勢エビを酒の肴にするのは、無理だったんじゃないかな」
ウンチクを披露する龍二が冷蔵ケースから三重県の純米酒を取り出すと、ジョージに通訳された女性たちは「アメイジング!」と口をそろえて感心した。そして、ワン・メイリ―はその銘酒と伊勢海老を今夜食べてみたいとジョージへ訴え、パク・ロミはフィリップへ料理人ならどうにかしろと迫った。
困り顔のヤンキー二人に龍二と平は苦笑いを返すだけだが、太郎はニンマリと笑った。
「今夜の予約をジョージに聞いた時、そんなことになるだろうと思ってよ。銀平へ伊勢海老を注文してんだ……ほうら、噂をすればだ」
太郎が顎を振ると、今度は玄関の鳴子が暴れた。それは、火野銀平がトロ箱を担いで駆けつけた時の合図である。
「太郎さんよう、ここん所、人使いが荒くねえかぁ。築地の中を走り回って、やっと手に入れたよ。明日の朝、競りに出すのを、どうにか生け簀からお裾分けしてもらったぜ。型は小ぶりだかよう、味は保障するぜ。正真正銘、伊勢海老は本場の志摩半島産。おまけの車海老は、三河湾の天然物だ!」
いかつい風体の銀平の登場にワンとパクは一瞬ひるんだが、トロ箱の中で蠢いている胴体を縛られた数尾の伊勢海老、さらには数十尾の車海老に思わず「ワンダフル!」と叫んで、二人とも銀平に抱きついた。
「わ、わわ! 何しやがんでぇ!」
その口調と反対に銀平の顔が茹でダコのように赤面すると、店内の客たちがどっと笑った。
「なるほど! 中国銘酒には、伊勢エビよりも車エビがいいかも」
と龍二が、店内に向けて再び解説した。
「三河湾は、昔から車エビの宝庫です。名古屋のエビフライが有名なの、知ってますよね。それに江戸の立ち食い寿司の原点は、尾州・半田の早寿司。だから江戸前の車エビにも、中国銘酒は合ったってわけです」
ピシャリと跳ねるトロ箱の車海老に、平が垂涎しながら訊いた。
「ほう。名古屋のエビフライ文化が三河湾のおかげ。じゃあ、サミットの料理にも車エビは出ますかねぇ?」
「まあ、用意されるのは、トマトソースのかかった車海老のカクテルかなぁ。残念なのは、車エビの踊り食いの習慣は、アジア以外の国にはないでしょ」
龍二の答えにテーブル席の客たちが頷くと、ワンが声を発した。早口でまくしたてる英語をジョージが訳した。
「ワンさんの中国では、車海老の老酒漬けがあるそうです。“酔っぱらい海老”と呼んで、老酒、醤油、ザラメ、ネギ、生姜、陳皮、花椒、八角、唐辛子へ漬けます。それを湯でて、老酒と食べるのがベストだと言ってます」
すると、負けじとばかりにパクが、フィリップへしゃべり続けた。
フィリップはつなぎつなぎの日本語で、懸命に通訳した。
「コリアでは、生の車エビを焼酎、ニンニク、唐辛子、ショウガ、それと醤油やコチュジャンを合わせたタレに漬ける。すると、生海老の甘さと辛さがマッチして美味しい。ドライな焼酎に合わせます」
伝え終えると、フィリップは龍二に「ドゥ ユー アンダースタンド?」と不安げに確かめた。何度も頷く龍二の横で、銀平が腕組みしてつぶやいた。
「だからって、そんな酒、ここにはねえじゃねえかよ」
捨て鉢な口調の銀平の前で、太郎がトロ箱の車海老をつかみながら答えた。
「いや、いけそうな代用酒がある。ほら、冷蔵庫の隅にある、山廃純米酒の20年物の熟成酒。あれって、すごく老酒に似てただろ」
ビビンと尻尾を振った車海老に、平が舌なめずりをしながら言った。
「おお! そうでしたねぇ。あれなら、使えますねぇ」
「それに、韓国焼酎の代わりには、宮城県の超辛口の純米酒がいけますよ。+23度だから、かなり似てます」
龍二が冷蔵庫から熟成酒と超辛口の一升瓶を取り出すと、太郎は
「後は、伊勢海老だな。そいつはフィリップに任せるぜ。バターソティを、スパークリング純米吟醸とマリアージュしようじゃないか」
と厨房へ誘った。
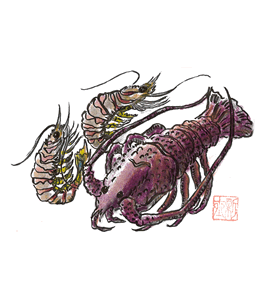
あっという間に動き出した海老料理のレシピに、銀平はポカンとしている。
「イエイ! トゥナイト イズ 海老サミット!」
とフィリップは嬉々として立ち上がり、トロ箱に手を伸ばした。ところが、そこに伊勢海老はない。ギーギーと鳴き声を上げる伊勢海老を手にしているのは、勝手にカウンターの中へ入り込んでいるワンだった。
「あんた、な、何しようてんでぇ!?」
ドギマギする銀平の前で、ワンは太郎へ大きなボールをくれと指さした。それを手にすると、太郎から熟成酒を奪って無理やり注ぎ、なんと、酔っ払いの伊勢海老を仕込もうとしていた。
暴れまくる伊勢海老が熟成酒を跳ね飛ばすと、唖然としているカウンターの面々にしぶきが飛んだ。
騒ぐカウンター席で、一人だけ冷静な平が苦笑した。
「やっぱり中国の人は常識はずれな、突拍子もないことをやりますねぇ。これじゃ、サミットも揉めるわけだ」
それに答えるかのように、伊勢海老の尻尾が大きな音を立てた。
