「淡麗辛口って、どんな味なんだろうね?」
ポンバル太郎のテーブル席に座る三人の女性が、つやつやした目元で杉板の壁に張られている限定酒メニューに声を合わせた。仕事帰りのOLらしい、カジュアルな装いだった。
手提げバッグから覗いている日本酒の入門書や、一見して二十代半ばとおぼしき若さから、まだ日本酒を飲み始めたばかりと太郎は察した。
「ちょっと、アテンドしちゃおうかなぁ」
カウンター席に座ったばかりの高野あすかは太郎と目を合わせて、彼女たちに淡麗辛口の意味を教えようと椅子から腰を浮かせた。
女性たちがあすかと談笑して新潟県の生貯蔵純米酒を注文すると、火野銀平はカウンターの隅で、ため息とも諦めともつかない声を洩らした。
「淡麗辛口が地酒の代名詞になって一斉風靡してから、もう三十年。尻の青いガキだった俺も、歳を喰うわけだなぁ。まあ、最近は女性が好きそうな香りの立つ旨口の酒が増えてるし、淡麗辛口の存在が薄れても仕方ねえや。ただ、情けねえかな、若い男がめっきり日本酒を飲まねぇ!」
駆けつけで飲んだ生原酒が急に回ってきた銀平は、先にカウンター席に座っていた見慣れない若い男へ聞こえよがしに独りごちた。
太郎は声が大きいとばかり銀平へ睨みをきかせたが、秋田の超辛口山廃仕込みの純米酒とハタハタの干物をつまんでいる若い男は、口元に薄い笑みを浮かべるだけだった。
切れ長の目元は歌舞伎役者のようで、一見やさぐれた印象を感じさせたが、あすかも銀平も、太郎が彼をやけに意識しているようすを不思議に思っていた。それが証拠に、すでに3種類の銘柄をその男に蛇の目盃で利き酒させ、酒の産地の珍味をひと口ずつ出している。
「ところで、いくつになられましたか?」
「三十歳です。もうオヤジ予備軍ですわ、太郎さん。今の淡麗辛口の話やないですけど、大阪でも飲まれる銘柄がずいぶん変わってきました。蔵元も飲み手も、世代交代してますわ」
その大阪弁の口調は、ポンバル太郎のカウンターで聴き慣れたある人物の声にうり二つだった。途端に、銀平が目を丸くして、若い男の顔をシゲシゲと覗き込んだ。
「あ~っ、おい! あんた、中之島のおやっさんの息子じゃねえか!? 十年ぐらい前に、広島の全国新酒鑑評会で俺と逢ってるだろ? 確か、名前は俺とひと文字ちがいの修平君だったな」
「はいっ、ご名答です。火野さんのことは、そのツルツル頭をよう憶えてます。今でもうちの親父から、ポンバル太郎には欠かせん、天然キャラクターと聞いてますし」
その声が聞こえるや否や、あすかが銀平を押しのけるようにして、修平の隣へ座り込んだ。
「えっ! このイケメンな方って、太郎さんの知り合いだったの!?」
「お、おいっ、俺が知り合いだってば」
とつぶやく銀平を無視してシナを作るあすかに、太郎が苦笑しながら答えた。
「イケてるのは、面構えだけじゃないぜ。秋田で蔵人を数年間経験し、今は大阪で中之島のおやっさんの後継者として酒匠と料理人の修行中だ。実は、俺がこれからテーマにする“酒肴口卒啄(しゅこうそったく)”を、すでに修平君は実践しているんだ。今日は、中之島のおやっさんが書いてくれた、この額をわざわざ大阪から持参してくれたってわけだ」
太郎は厨房の中で、酒肴口卒啄と豪快に揮毫された額を掲げた。
「酒肴口卒啄か……ちょっと、待ってね!」
記者魂に火がついたあすかはバッグから名刺と手帳を取り出すと、修平に聞き込みをしようとした。
「あの、取材はお断りですわ。僕、そんな大そうな男やないです……ただ、自分の鼻と舌と口、それと経験や直感で、今は実践しているだけです。学者やないし、駆け出しの若造やし、お話しできる理論なんかまだありません……それに今夜は僕にとって、太郎さんと話せる大切な時間なんですわ」
一瞬、水を打ったようにカウンター席が静まった。
いつもなら気まずい雰囲気に助け舟を出す太郎が、「ごもっとも」と頷いた。
「あすか! 最近、何でもかんでも傍若無人に聴き込むお前は、どうかしてるぞ。ちったぁ、反省しろい!」
銀平がここぞとばかり、あすかに冷や水を浴びせた。
その叱責で、あすかにテーブル席の女性たちが次の酒を選んで欲しいと頼む声が途切れた。無論、うろたえるあすかがそれに応える余裕はなく、黙り込んでいる。
「……どうだろ。代わりに修平君、頼んでもいいかな」
太郎が修平に片目をつむると、修平は意を得たとばかりにゆっくりと立ち上がった。そして、あすかの肩を軽く叩くと「見るだけやったら、取材やないですから」
修平は、女性たちに丁寧に挨拶して自己紹介すると、まずはそれぞれの好みの料理や味つけを話題にした。いきなり淡麗辛口を説明したあすかとはちがって、さりげなく、それぞれの出身地の味の傾向、好きな肴やツマミの話しから、個々に合いそうな酒を紹介し、その酒に合う肴や飲み方までも奨めた。
「酒肴口卒啄の意味は、親鳥が嘴(くちばし)で卵の殻をつつくと、卵の中から産まれようとする子鳥がそれに答えるという仲むつまじい関係。酒と肴はお互いの個性を引き出し、より向上させる関係が理想なんだが、酒匠とお客さんの関係も同じなんだ」
太郎が誰とはなく、おだやかな目元で語った。それは今は亡きハル子の言葉であり、あらためて、自身に言い聞かせているようでもあった。
女性たちが選んだのは富山県の淡麗辛口の純米吟醸に、肴は旬の福井の岩牡蠣と金沢のがす海老で、どちらも北陸ならではの珍味だった。
「なるほど、いい仕事するじゃねえの。やっぱり、中之島のおやっさんの子だねぇ!」
高値の岩牡蠣とがす海老を女性客へ上手に奨める修平に、それを目利きした銀平は満悦していた。
あすかは修平の表情や動きをつぶさに見ながら、その手元を止めていた。理屈ではなく、体と気持ちで何かを感じ取ろうとしていた。
すると、席に戻って来た修平があすかに耳打ちをした。
「お一人だけ、あすかさんを待ってますよ。酒肴口卒啄、やってみたらどうです? あなたには、蔵元の血が流れてるんですから」
あすかは、わざと自分にゆだねたらしい修平に驚いたが、彼の横顔にかつて幼い頃に慕った中之島哲男の笑顔がふと浮かんだ。ポンバル太郎の面々について父の哲男からつぶさに聴かされているのだろうと悟り、その親子の関係を羨ましく、嬉しく思った。
「気を遣ってくださって、どうもありがとう……でも、やっぱり私じゃなくて、修平さんの方が適切なアドバイスができると思います」
「そうやないんです……あの方、訊けば相馬の出身でした。それに、あすかさんのお家の酒を飲んでたそうです。そやから、故郷の味つけや旬の食材、郷土料理の話もできるでしょ。まさに、酒肴口卒啄やないですか」
ためらうあすかに、グラスを飲み干した銀平が、せっかちな口調で言った。
「ええぃ、じれってぇな! 行けよ。ただし、ライター根性を剥き出して、話しを急ぐんじゃねえぞ」
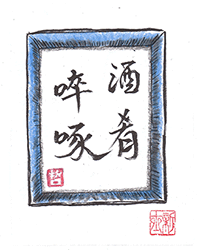
すると太郎がいつの間に炙ったのか、あすかの前に相馬名物の黒かれいの干物が置かれていた。
「お客さんは、卵の中の小鳥。優しく、慈しむんだ。……あの震災の思い出も話し合ってみてもいいんじゃないか。ライターになる前は、そんな、あすかだっただろう。それこそが、酒肴口卒啄の原点だよ」
こくりと頷きテーブル席へ向かうあすかの背中に、修平がほほ笑んだ。
「初心、忘れるべからず……僕も蔵人の頃の気持ちを、忘れたらあかんな。ポンバル太郎に来て、やっぱりよかったですわ」
「いや、俺こそ……ありがとうよ」
酒肴口卒啄の額が、太郎の両手にしっかりと握られていた。
