飛鳥山の緋寒桜が、早春のきざしを告げていた。
ずいぶん日暮れが遅くなった隅田川べりでは、ふくらみかけた梅の蕾が肩をすくめる通行人を見下ろしている。その中を、トロ箱を手に提げる火野銀平が駆けていた。
「待ってろよお、今年一番のキスだぜぇ!」
独り言ちる銀平の声に、すれちがったOLたちが顔を見合わせて吹き出した。彼女らの勘違いである。
キスはキスでも、銀平が言ったのは江戸前のシロギス。天然物の極上品を、ポンバル太郎へ届ける途中だった。
10日前、純米酒を注文した銀平がカウンター席へ座ると、隣りの手越マリは険しい面持ちでスマートフォンをいじっていた。画面が、やけに大きく見えた。
「おっ、らくらくフォンに変えたかぁ。マリさんも、老眼にゃ勝てねえなぁ」
いつもなら間髪入れずにやりかえすマリの声がない。おまけにグラスの大吟醸は注いだままで、減っていなかった。
「なんでぇ……マリさん、具合でも悪いのかよ。」
つまらなげに銀平は腰を下ろしたが、隣りの平 仁兵衛や右近龍二も黙っている。妙なムードがカウンターを包んでいた。
マリはスマホをカウンターに置き、厨房の太郎へ訊いた。
「新品ばい。まだロックは、掛かってなかねぇ。画面の背景写真が、太郎ちゃんとこの陳列ケースに入っちょったシロギスちゅうのも、なんでかねえ……それに、ここで預かっちょったら取りに来るはずたい。なのに、どげんして来んとねぇ?」
画面には、銀平の納めたシロギスが目を光らせていた。
「あの若い女性が忘れて帰って、もう5日になる。2度電話が鳴って、しかたねえから出たんだよ。電話してきた相手に、スマホを忘れて帰ったのを言おうとしてさ。そうすりゃ、あの人にも伝わるだろ。それが声もしないまま、プッツリ切れちまった……こいつは何だか、いわくつきだぜ。うす気味悪いから、そろそろ警察に届けようかと思ってさ。だけど、らくらくフォンを持つにしちゃ、あの客は若過ぎるな」
太郎の口ぶりから、銀平は常連たちが押し黙っている原因がスマホにあると知った。気になるのか、テーブル席のグループ客は首を伸ばしてスマホを見つめた。
その時、スマホが鳴って、マリが「ヒッ!」と声を洩らした。
カウンターで震えるスマホを、平や太郎も固唾を飲んで見つめた。手元へ寄って来るスマホに龍二が躊躇していると、しびれを切らした銀平が手にして受信ボタンを押した。
「もしもし! あのよう、この電話の持ち主が忘れちまったらしくてよう! こちとら、困ってんでぇ。あんた、誰だい。持ち主の知り合いかよ?」
ぶっきらぼうな銀平の物言いに、マリはまた切られると思って「この、馬鹿ッタレ!」と腐し、太郎も「あちゃ、ヤブ蛇だ」と肩を落とした。
ところが、スマホからは嬉々とした声が響いた。
「まあ、あなた、江戸っ子? その魚河岸の言葉、懐かしいわぁ……あら、私ったら、つまらないことを。実は、そのスマホは孫娘からのプレゼントなんです。でも、それを失くしたまま、翌日、パリに出張してしまったの。それで、娘に教えてもらった番号へ2度ほど掛けてみたんですけど、何だか、気後れしちゃって……でも、あなたのべらんめえを聞いて、思わず答えることができました。ありがとうございます」
上品な女性らしい声音と言葉使いだった。
赤面する銀平に、マリはスマホへ耳をすり寄せた。怪訝な顔の太郎たちへマリが聴き取った事情を説明する間も、銀平と相手の会話は続いていた。
相手は、鈴木美和と名乗った。年齢までは訊き出せないが、先日やって来た女が孫娘なら70歳頃じゃないかと太郎は思った。平も、だんだんと鼻の下が伸びる銀平に「案外、年上の女に弱いんですねぇ」と苦笑した。
「こりゃ、銀平に春が来たばい」
いたずらっぽい笑みでスマホへ耳をそばだてるマリの横で、龍二が「熟女との恋ですかぁ」と冷やかすと、銀平は「うるせえ! そんなんじゃねえ」と真顔になった。
つかの間の会話を切ると、銀平はふうっとため息を吐いて問わず語った。
「単純な忘れ物の話しかと思いきや、その孫娘、なかなか泣かせるぜ。今、話した美和さんは銀座の老舗の生まれ育ちでよ。江戸前のシロギスが大好きで、その昔、実家には築地から魚屋が届けてたらしい。去年の暮れにポンバル太郎へ来た孫娘が、うちの納めた上物のキスを食って、お祖母ちゃんを連れてこようと思ったそうだ。だけど、その直後に美和さんは具合が悪くなっちまった。それで、美和さんへスマホの写真やインターネットでポンバル太郎のようすやシロギスを見せてやろうとしたが、つい忘れちまったってわけだ」
10日後には帰国するのでポンバル太郎へスマホを取りに行かせると、銀平は美和の伝言を太郎へ伝えた。一件落着したかのように、銀平は頷きながら常連たちを見回した。
しかし、太郎の口は問いかけた。
「それで……おめえはどうするんだよ?」
「へっ? まさか、いくら俺が独身だからって、70手前の女性のお相手はよぅ」
はにかむ銀平に、太郎が長いため息を返した。
「バカ野郎、そうじゃねえよ。美和さん、キスが好きなんだから、江戸前の上物をおめえが持って来ちゃどうなんだよ。これも、人の縁ってもんだろ」
「そうそう! ひょっとすると、いっしょに来る孫娘さんと恋が芽生えたりして!」
茶化そうとする龍二へ銀平は舌打ちを返したが、表情はまんざらでもなさげに緩んだ。
銀平の駆け足は、龍二の言葉を思い出すたび速くなっていた。
ポンバル太郎の鳴子を銀平が響かせると、カウンター席で白いひさし髪を結った女性が立ち上がった。開店前のため、客は常連だけである。
皺を浮かべる色白な肌と楚々とした和服が、美和の銀座育ちを醸し出していた。
銀平の禿頭と顔つきを、老眼の美和は凝視した。
「先日は、ありがとうございました……あら、あなた、私の知ってた築地の魚屋さんによく似てらっしゃる。実家に出入りしていた、確か……火野銀次郎って方です。粋でいなせな若者で、私、惚れちゃったんですよ」
しかし、片想いだったと美和は笑った。
「ええっ! 驚いたな! そいつぁ、銀平の祖父さんだ」
声をうわずらせる太郎へ、ぬる燗の純米酒を飲み干した平が嬉しげに続けた。
「ほら、やはり御縁ですよぉ、銀平さん」
「やった! ついに、彼女をゲットだ!」
後で迎えに来る孫娘に龍二が期待すると、シロギスのトロ箱を太郎へ渡す銀平の胸も高鳴った。
塩焼きと潮汁に仕立てた江戸前のシロギスを美和が満足げに食べ終えると、玄関の鳴子が揺れた。
スーツ姿の目鼻立ちの美しい女性が、美和へ小さく手を振っていた。銀平が頭に描いたままの娘だったが、少しだけ絵面がちがったのは、イケメンな若い男と一緒だった。
「初めまして、孫の麻衣子です。このたびは、ご迷惑をおかけしてごめんなさい。その上、祖母が大好きな江戸前のシロギスまで頂けるなんて、本当にありがとうございます。うちの主人も御礼を申し上げたいと言うので、連れて参りました」
美和とよく似たうりざね顔の麻衣子へ、主人が寄り添うように頭を下げた。キスを焼く竈の備長炭が、シンとする店内に爆ぜる音を響かせた。
「だ、旦那さん……ですか。こりゃあ、わざわざ、ありがとうよ」
落胆を隠す銀平を思ってか、美和はさっと腰を上げて
「また、参ります。火野屋さんならではの、江戸前のキスを食べに」
と銀平の手を握った。ふっくらと柔らかな温かい手のひらに、なぜか銀平は赤面した。
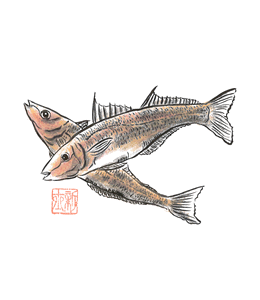
通りを去って行く美和たちを太郎が見送る間、銀平はカウンター席に座ったまま、苦笑を洩らした。
「祖父さんも俺も、美人にゃ、縁がねえってこったなぁ」
「それでも、美和さんを火野屋のシロギスで幸せにしてあげて、銀次郎さんも喜んでいますよ」
盃に酒を注いでやる平の声に、銀平は「ちげえねえ」と頷いた。その目が、祖父も自慢していたシロギスの光る体を見つめていた。
「よかよか、銀平! あたしが、あの孫娘の代わりにキスしちゃるばい!」
首根っこを引き寄せるマリに、銀平が悲鳴を上げた。
「げぇ~、それならまだ、シロギスとする方がましでぇ」
爆笑する平たちに、やって来た客たちは店内を覗きこんだ。その鼻先を、シロギスを焼く香ばしい匂いが誘っていた。
