マイナス40℃のシベリア寒気団が、節分の日本列島上空を覆っていた。
都内の夜気は凍てつき、窓を開けて豆まきをしたり、ベランダで恵方巻きにかぶりつくどころじゃない。鬼も縮こまる、冷え込みだった。
ポンバル太郎でも、中之島哲男が大阪から持って来た特製の太巻きよりも鍋料理が人気で、お燗酒の注文に剣はてんてこ舞いである。
巻き寿司を両手に構え、大口を開けて恵方の南南東を向いているのは右近龍二だけだった。
「これは大阪の今宮戎にちなんだ“恵比須巻き”ちゅう、縁起のええ太巻きでっせ!」
イマイチな売れ行きに、カウンター席でほろ酔いの中之島が声を張り上げた。徹夜して仕込んだ恵比須巻きは銀座のママ・手越マリのお気に入りだったが、今夜は風邪を引いてダウンしていた。
当てが外れた恵比須巻きを売りさばく剣に、テーブル席の女性グループは半分ずつを丸かぶりしたいと注文した。剣を手伝う龍二に、帰り際の土産に一本くれと頼む中年サラリーマンもいた。
だが、カウンター席の隅で独酌する五十がらみの男は、恵比須巻きには一瞥もくれず、冷蔵ケースのメバルに目を移しながら香川県の地酒を傾けていた。
しかめっ面でブツブツつぶやく男に、中之島の視線が止まった。
火野屋が納めた極上のメバルは、ピカピカに光っている。しかし、男はそれを凝視しながらも注文しなかった。
煮え切らない男にしびれを切らしたのか、中之島が恵比須巻きを一本、目の前に置いた。
「おっちゃん。俺は、頼んどらんぞ。太巻き寿司は、好かんけん」
男のぶっきらぼうな返事と強い訛りは、客席の注目を浴びた。厚手のダウンジャケットから覗く首筋には、日焼けの跡が濃かった。
「まあ、そう言わんと、いっぺん食べてみまい。あんたの故郷の、香川の海で獲れたアナゴも使うとるけん……あんた、瀬戸内の漁師やろ?」
男と同じさぬき弁を上手に使う中之島に、剣と龍二が顔を見合わせた。
「な、なんじゃい。漁師やったら、いかんのか?」
中之島の読みは図星だったらしく、男の顔色が変わった。鼻筋から頬へ一気に血の気がにじみ、気短かな性格を覗かせた。
「いやぁ、あかんことはない。ただ、食べたいはずのメバルを、どうして我慢しはんのかと思うてなぁ。今の季節、瀬戸内の漁師にとってメバルの煮つけは、最高の旬や。小豆島醤油と和三盆で甘く煮るのが、香川県のこだわりでっしゃろ」
堂に入った大阪弁へ戻った中之島に刺激され、店内の客たちは冷蔵ケースのメバルを覗き込み、早速、太郎へ煮つけを注文した。
男は舌打ちをして、反論した。
「東京のメバルの煮つけは、いらん! 香川県の一番うまい食い方は、ちょっと料理法がちがう。俺の家は先祖代々、網元で、冬はメバルばっかり獲ってたけんのう」
興奮した男は香川県の宇多津町出身で、三好英吾と名乗った。香川名物のうるめ鰯や近海物の白身魚を獲る漁協の幹部で、うどんチェーン店のダシに使うジャコの取引で上京していると語った。
「東京は、鰹ダシの料理ばっかりやのう。おまけに、銚子や野田の醤油で真っ黒のダシじゃ。あんな辛いダシは、俺には飲めん。あんたのメバルの煮つけも、同じようにマズいんやろ?」
メバルの煮つけは香川風の味つけに限ると言わんばかり、三好は太郎を腐した。しかし、ふと悔しげに唇を噛んだ男に、中之島は気づいていた。
その時、怒りに任せたかのように玄関の鳴子が暴れた。火野銀平が、寒さで赤くなった鼻梁をなおさら火照らせていた。
「おう、あんた! うちのメバルだけじゃなく太郎さんの味つけにも難癖つけるなんざ、聞き捨てならねえ! それなら、あんたがベタ褒めするメバル料理を、俺に食わしてみろい!」
はしご酒で酔いが回っている銀平に、太郎は「よせ!」と制した。
だが、初対面同士の売り言葉に買い言葉で、三好は立ち上がると、太郎へ「厨房を貸してくれ」と真顔で頼んだ。
断りかけた太郎の肩へ、中之島が手を置いた。ほころんだ目じりの皺が、やらせてみろと伝えていた。
太郎が、あらかじめ煮ていたメバルの鍋を開けると、三好は黒いメバルの煮つけをキッチンペーパーで巻いて、汁気を取った。さらに、厨房で見つけた竈に炭火を熾すように太郎へ頼んだ。
竈が熱を帯びて、炭火のはぜる音と薫香が店内に広がる中、太郎だけでなく、剣や銀平、店内の客たちもどうするのかと小首を傾げていた。
「よし、金網をくれ。それと天日塩だ」
竈を覗く三好の嬉しげな表情が炭火に赤く映えた時、龍二が声を発した。
「あっ! 黒メバルの焼き直しか! さぬきの伝統的な食べ方で、甘辛く煮たメバルのダシを切ってから、天然塩をまぶして、軽く焼くんですよ。ダシがしみた白身の旨みと、パリパリに焦げた皮と天日塩の旨みが合わさって最高です! 四国じゃ、土佐っぽも知ってる、香川の伝統的なごちそうですよ」
竈がプスプス音を立て、醤油と和三盆のダシに塩の焦げる香りが入り混じった。
三好が網から外した焼き直しに「うむ。こりゃ、食ってみてえな」と太郎が頷くと、銀平も思わず唾を呑み込んだ。
客席にメバルの焼き直しがふるまわれる中、三好は懐かしげな顔で太郎と銀平へ問わず語った。
「俺が子どもの頃、この食べ方は、冷えてしもたメバルの煮つけを、もっと美味しくする最高の料理法やった。けど、最近はメバルも高級魚やけん。家庭じゃ、おいそれと口にできんようになってきよった……できたら、このメバルの焼き直しを、ポンバル太郎で出してくれんかのう。魚屋の兄ちゃんは、手頃な値段でメバルを納めてくれんな。味つけダシに使うイリコや醤油、和三盆は、俺から太郎さんへ贈るけん……そっちの、大阪の大将にも、よろしゅう頼むけん」
今しがたの歪んだ表情が、三好から消えていた。
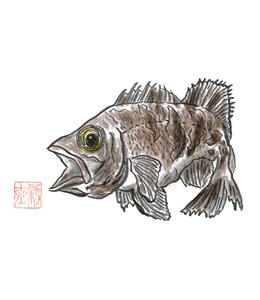
笑みを返す中之島が、ぶ厚い胸板を叩いた。
「ええでぇ。ついでに、わしの大阪の割烹でも、この献立は出させてもらうわ。香川県の地酒と一緒にな」
「そうとなりゃ! まずは一件落着ってことで、さっそく恵比須巻きを頂くぜぃ!」
メバルの身を口いっぱいに入れた銀平は、恵比須巻きにもかぶりついた。
途端に喉を詰まらせ目を白黒させると、剣が飽きれた。
「あ~あ! 銀平さんがメバルになっちゃった」
「だけどよ。こいつは焼きを入れ直しても、ちっとも美味しくならねえ!」
太郎のイジリに、節分の邪気を吹き飛ばすような笑いが巻き起こった。
