年明けの新橋や池袋の繁華街に「新酒初しぼり」の幟が並び、新年会で人気を呼んでいた。いよいよ吟醸造りの新酒も登場し、日本酒の専門店では蔵元を招いた新春イベントが催されている。
ポンバル太郎も、正月気分が抜け切らない週末に賑わっていた。
「新酒にふさわしい美味しそうな魚が揃っていますねぇ。これじゃ誰だって、気持ちがゆるんでしまいますねぇ」
さっそく元旦搾りの純米酒を味わっている平 仁兵衛が、冬の味覚がひしめく冷蔵ケースへ目を細めた。江戸前のコノシロやヒラメ、日本海のホウボウに甘エビ、北海道のヤリイカが目を光らせている。もちろん、火野銀平が届けた築地の上物である。
その一画に盛った赤い塊へ、太郎が声を高くした。
「正月明けから、ベニズワイガニの水揚げが好調なんですよ。本ズワイに比べると味は劣るらしいが、この佐渡沖で獲れた奴は身の入りがいい。甘味もたっぷりあるって、銀平のイチオシです」
姿かたちは越前ガニにそっくりだが、甲羅や足の赤さが際立っていた。今しがたカウンター席へ座った菱田祥一は、大ぶりの甲羅へ前のめりになって唾を呑み込んだ。
「へぇ! 俺はベニズワイガニって初めてですよ。これに合わせる酒は、やはり越後淡麗かな。熱燗の甲羅酒って、たまんないんだよなぁ」
菱田が興奮するのも、無理はない。彼の生まれ育った千葉の海ではズワイガニが獲れず、菱形をしたワタリガニが定番である。
菱田は東京で勤めるようになって、初めて越前ガニを食べた。ワタリガニより甘さも食感も柔らかい本ズワイガニは、すこぶるつきの冬のご馳走になった。中でも、カニミソを熱燗の酒で溶く「甲羅酒」には目がない。
舌なめずりする菱田に、太郎がベニズワイガニを広げた。
「おまえのカニ好きは、半端じゃねえからなぁ。こいつは値段も本ズワイより安いから、たらふく食っていいぜ!」
赤い花が咲いたかのようなベニズワイガニに、テーブル席の客たちも「おおっ! うまそう」と目を丸くした時、玄関の鳴子が鈍い音を響かせた。
「遅ればせですが、新年、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いします」
年明け初顔合わせの右近龍二だったが、どことなく表情が曇っている。故郷の土佐へ帰省して英気を養ったはずが、重たげな足取りでカウンター席へ近づいた。
「正月からシケた面してちゃ、福も来ないよ。ほら、このベニズワイガニを一緒に食って、元気出そうぜ」
食い気満々の菱田がおいでおいですると、平は龍二を隣の席へ誘った。
「カニはカニでも、ベニズワイガニか……いや、遠慮しときます」
龍二らしからぬ素っ気ない返事に、太郎もカニをさばく出刃包丁を止めて訊いた。
「珍しいな。龍ちゃん、ベニズワイは嫌いかよ?」
「いや、そうじゃないんです。土佐の正月で縁起物のカニを、食べそびれちゃって……それと同じように色は真っ赤なんですけど、まったくちがうんです」
龍二はスマホを開いて、丸くて赤い画像を太郎たちへ見せた。ズングリムックリの胴体に毛が生えた、赤いカニが映っていた。
「アサヒガニって言います。朝日のように赤いからそう呼びます。身は肉厚で旨味が濃く、土佐の地酒にバッチリなんですよ……毎年の暮れ、長年お付き合いしている土佐の漁師さんが正月用に獲ってくれていたのですが、体調を悪くして漁ができず、手に入らなかったんです。我が家のゲン担ぎのカニなので、その人が獲ってくれるアサヒガニを口にするまで、ほかのカニは食べないつもりです」
その漁師は、龍二の祖父の代から親交のある武市寛平。78歳の古老ながら、アサヒガニ漁一本で生きていた。武市は祖父と義兄弟を契り、40年来の間柄だったと龍二は言った。
だが、5年前に龍二の祖父が亡くなってからの武市は
「兄貴がいなくなってから、漁がうまくいかねえ。おれにとっちゃ、アサヒガニが結んでくれた、かけがえのない人だった。お前のお父さんにも、アサヒガニが縁になった兄弟分がいる。きっと、お前にも同じような人が現れるだろうよ」
と繰り返し、覇気を失っていた。
武市の獲るアサヒガニは拳ほどのサイズで、塩茹でするだけ。豪快にかぶりつきながら、常温の辛口酒とやるのがツウである。土佐の海のスープが口に広がれば、体の中でいごっその血が騒ぎ出すのだと龍二は続けた。
店内の客たちは聞き耳を立てつつ、ゴクリと喉を鳴らした。
「う~む。そうまで言われると、ベニズワイガニより魅力的だよ」
菱田の視線は、太郎の作るベニズワイガニの酢の物からスマホに移っている。
「右近家の福を支えてきたカニですか。でも、キワモノですねぇ。築地でも、入荷は難しいんじゃないですか。銀平さんに、訊いてみましょうか」
平が言った途端、玄関の鳴子が大きく響いた。
「おう! おあつらえ向きに龍二がいるじゃねえか! おめえの故郷の珍しいカニが手に入ったぜ。アサヒガニって、丸っこい奴だ。見てくれはイマイチだがよ、身が甘くって、なかなかの旨さじゃねえか。武市の爺さんって、アサヒガニ漁の名人が獲った一番食い頃のサイズだそうだ。まあ、土佐っぽの龍二にとっちゃ、珍しくもねえだろうけどよ」
銀平が両手に提げるビニール袋に、赤いアサヒガニが透けていた。話題のカニを目にした客席から、ため息が洩れた。
「た、武市の爺さんって、まさか!」
茫然とする龍二に、銀平は怪訝な顔で
「な、なんでぇ……どうかしたのかよ」
と客たちの表情を見回した。
「へぇ! こりゃ、たまげたな。それじゃあ、武市さんの具合は回復したんだ。龍二君、良かったじゃないか」
菱田は、もはやベニズワイガニには目もくれず、日本酒の冷蔵ケースから勝手に土佐の本醸造を取り出した。むろん、アサヒガニのご相伴に与る腹である。
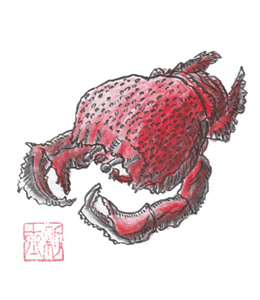
「すると、アサヒガニが取り持つ龍二君の兄弟分は、銀平さんってことになるんですかねぇ」
いたずらっぽい笑顔で、平がぬる燗の盃を飲み干した。
今しがたの不審げな表情を消した銀平は、まんざらでもなさげに鼻先を掻いた。
「平先生、もちろん龍二は俺の弟みてえなもんでさあ。今年もいろいろ、指導してやりますから」
アサヒガニを受け取った太郎が、笑いをこらえながら言った。
「何を偉そうに言ってんだか。兄弟分ってのはよ、おめえが弟で、龍ちゃんが兄貴だろ。不勉強な弟は、今年もまた兄貴から、日本酒のことを教えてもらわなきゃなぁ」
菱田と平が吹き出すと、銀平を見知ったテーブル席の客たちも肩を震わせた。
真っ赤になる銀平の顔が、丸々としたアサヒガニの甲羅のようだった。
