熱中症の注意をうながすテレビニュースが一日中報じられた夕刻、ポンバル太郎の通りは、いまだ路面に陽炎を揺らせていた。ついさっき太郎が撒いた打ち水も気休めにしかならず、一瞬で消えてしまっている。
店に入って来る客たちは肩で息をして、喉が渇き切っているようすだった。
誰もが生ビールを注文したが、ジョッキが届くまで辛抱できず
「太郎さん、まずは水を一杯!」
と汗がしみたワイシャツの襟を開きながら頼んだ。
そのせいで、今夜は蔵元から仕入れている“仕込み水”の減り具合が凄まじかった。
仕込み水は蔵元が酒造りに使っている地下水や井戸水で、太郎はお客の飲み水だけでなく煮炊き料理にも利用するため、口当たりの柔らかい無味無臭の軟水を選んでいた。それを入れた一升瓶が残り一本になり、太郎はカウンター席に座ったばかりの右近龍二に頼んで、急場しのぎにペットボトルの飲み水を買いに走らせた。
「こないに暑いと、やっぱり燗酒を飲むお客さんはおらへんなぁ」
大阪から久しぶりに顔を出した中之島哲男は、普段と同じ白磁の一合徳利で山廃純米酒傾けているが、ぬる燗ではなく常温の酒だった。肴はシメ鯖とワカメの酢味噌あえで、暑い日にはバテないよう必ず酢の物を採るという中之島のこだわりである。
ついに仕込み水の一升瓶が底を尽いてしまった時、カウンターの端っこに今しがた座った白髪混じりの男から
「北陸の辛口の純米酒で、おススメを常温でもらえませんか。それと“和らぎ水”、頼みます」
と太郎に声が投げられた。
五十代半ばとおぼしき男はゆっくりとハンカチで汗を拭いながら、カウンターの冷蔵ケースに並んでいる魚貝を覗き込んで、品定めしていた。その風貌だけでなく、男が言った和らぎ水も、酒匠の中之島と太郎の耳に心地良かった。
和らぎ水とは、日本酒を飲む時のチェイサーである。水を飲むことで口に残る肴や料理の味を洗い流し、次の一杯の酒を美味しく感じさせ、しかも翌日に酒が残らないよう体内でアルコールを薄めてくれる役目も果たす。
それをなにげなく口にした男に、太郎も中之島と同じような日本酒ツウの匂いを感じた。
太郎は、冷蔵庫から福井県産の酒造好適米“五百万石”で仕込んだ純米酒を選びながら、龍二の帰りにヤキモキしていた。だが、杉の玄関扉はいっこうに開かなかった。
「お客さん、申し訳ありません。和らぎ水が切れてしまいました。今、市販の水を買いに走ってますから、少しご辛抱頂けますか」
太郎がそう詫びて、純米酒の一升瓶を男の前に置いた。
男は銘柄を一見すると、むしろ裏レッテルに目を細めて、太郎に答えた。
「うむ……軽やかでスッキリした味になる五百万石で、日本酒度は+4……さほど辛すぎず、これがいいな。そしたら常温になるまで、あれに入れてもらえませんか。それと和らぎ水はペットボトルの水でかまわないから、同じようにあれに入れてください」
男の言葉に首をかしげる中之島が、あれと指さした先に視線を動かすと、銀色に光る塊が並んでいた。
「錫のチロリやないか……おおっ、そうか、なるほど! お客さん、あんた、錫の効果をよう解ってはりますな」
腑に落ちた中之島は感動したらしく、膝を叩いて椅子から立ち上がった。その後ろで、たった今戻ったばかりの龍二が、男の顔に驚いてペットボトルを落としかけた。
「こ、こ、近野さんじゃないですか! うわ~、お久しぶりっす! お元気ですか!?」
声が裏返るほど興奮する龍二に中之島は機先を制され、言葉を失くした。錫のチロリに手を伸ばした太郎も一瞬、唖然としている。いつも物腰の穏やかな龍二が初めて見せる、別の一面だった。
「あっ、す、すみません。太郎さん、中之島の師匠。この方は、僕が日本酒の世界に入るきっかけを作ってくださった恩人の近野さんです。ある流通企業の飲食マーケッターで、辛口の地酒が好きで、ええっと、それから……」
龍二は近野の脇へ寄り添うと、堰を切ったようにしゃべった。それを耳にしている男に、再会を驚くようすはなく、落ち着き払っていた。
「ふっ、四年ぶりか。あいかわらず、クドクドと能書きの多い奴だ。変わってないな、龍二……だけど、嬉しいよ。やっぱり、日本酒の世界に戻って来たか……じゃあ、マスター。チロリをナルハヤで頼みます」
酒の販売に通じている近野の素性を知った太郎は、手早く常温になりやすいよう錫のチロリに半分だけ純米酒を入れ、ペットボトルの水も同じように二つ目のチロリに注いだ。
それを見ていた中之島が、近野に話しかけた。
「ちょっと訊きたいんでっけど、近野さんは、いつもチロリに酒と水を入れますのか?」
「そうですねぇ。独酌の時は、ほとんどそうします。酒本来の香りと味は、常温でこそ判ると思うんです」
酒は冷やしすぎると、苦味や雑味が口の中で突出してしまう。その点で、錫のチロリは熱の伝導が速いから、冷えた酒でも室温の中にチロリで置いてやれば、すぐ常温に戻る。それに酒をまろやかにする力を持っているから、水道水でもしばらく置いていたら、同じように変化する。また燗酒だけでなく、冷酒にも錫のチロリは使える。氷水にチロリを漬ければ、酒はすぐに冷やせるのだと近野は語った。
中之島は錫の“チロリ=燗”の形にはまらない近野の考えに、感心しきりだった。太郎は近野の発想と人柄に、彼に薫陶を受けた龍二の目の付け所や勘の鋭さを得心した。
太郎から酒と和らぎ水の入ったチロリを受け取った近野は、口の中で軽やかな音を立てながら、五百万石の純米酒の香りと味わいを?いた。そして、横に座った龍二に一献を傾け、つぶやいた。
「久しぶりに、酒を批評してみろよ」
錫の盃に注がれた純米酒を龍二は、啜るように飲んだ。カウンター席で見慣れているそのしぐさが、実は、近野とそっくりだった。
その時、錫のチロリをおもしろく使う二人に、テーブル席の客から指南して欲しいと声がかかった。
龍二は得意げな笑みを近野へこぼして、テーブル席にチロリを提げて行った。
「あの……どんなふうに、彼に日本酒を教えたのですか?」
三十歳を超えてから日本酒に没頭し、酒の肴や歴史にも造詣を深めた龍二。そこへ導いた近野に、太郎は訊いてみたくなった。
近野は錫の盃を軽くゆすりながら、笑って答えた。
「主役としては目立たずに、日本酒が好きな人たちをもっと楽しませる名脇役になること。そのためには、とことん日本酒の知識と経験を重ねて、常識も非常識も含めた情報や楽しみ方を企画したり、発信できるようになること。まあ、普通の酒でもうまい酒に変える、いわば、この錫のチロリのような酒匠になってみろと言っただけです……だから、私がどうこう教えたわけじゃなく、あいつの努力と才能の結果ですよ」
謙遜する近野のまなざしが、龍二を弟のように見つめていた。
「近野はん。錫の水、ちょっと飲ませてもらえまへんか?」
ほろ酔いで顔を赤らめた中之島が、近野の横の席にユラリと移りながら白磁の盃を差し出した。近野が音もなく注ぐ水はどこかしら柔らかく、なめらかに盃の中へ流れた。
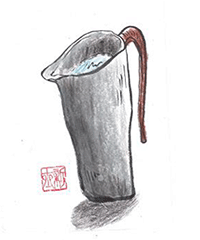
中之島はひと口含むと、目を閉じて、チロリの水を?いた。
「うむ……柔らかいな。不思議やけど、ほんまに水も美味しくするみたいや」
その声に、太郎も錫の水を味わった。口元が自然にほころぶような感触があった。
いつの間にかカウンターに戻った龍二が、錫の水を飲んで、つぶやいた。
「僕にとっては、近野さんこそ、錫のチロリです」
いぶし銀のようなチロリの色が、カウンターの上に映えていた。
