隅田川の夜の水面が、幾千もの灯りをかがよわせている。
浅草の吾妻橋のたもとから絶え間なく流れる灯篭に、今年も三千人を超える観衆が魅入っていた。その幻想的な光景を、カウンター席に座るジョージは熱く語った。
立て板に水といった口調には、英語と日本語がごちゃまぜである。テーブル席の若い客たちが苦笑しながら、ジョージを見つめている。
「わかった、わかった。おめえ、興奮しすぎだよ。日本人にとっちゃ、盆の送り火っては当たりめえの行事だったの。だけどよ、今じゃ環境汚染だ、川を汚すだのってクレームもあって、後始末が大変なんだぜ」
答える火野銀平は、毎年、築地市場を支えた先人の灯篭を隅田川に流している。昭和20年(1945)の東京大空襲で亡くなった魚匠たちの供養だが、最近の江戸っ子は情けが薄くなったとうんざり顔で冷酒グラスをあおった。
「そうですねぇ。この時期、灯篭流しをやるのは東京だけじゃないのですが、ずいぶん減ったようですねぇ。灯篭は下流に網を張って、粗大ごみとして回収するそうです」
平 仁兵衛の故郷の石川県にも観光行事として灯篭流しは残っているが、行政の経費負担は大きいだろうと話した。
クールジャパンと一概には喜べない灯篭流しの裏事情に、ジョージが頷きながらため息を吐いた。
「あすかは帰省した相馬で今年も灯篭を流したのかな……震災の供養に」
厨房から現れた太郎が、高野あすかは一週間の休暇で帰省中だと問わず語った。ジョージは、ジャーナリストとして聞きたいネタがたくさんあるのにと悔しがった。
だが銀平は、どこか翳りのある太郎の表情に気づいた。そして視線を神棚に向けながら、太郎へ訊ねた。
「太郎さんは、どこに流したんだよ? ハルちゃんの灯篭」
例年、太郎は盆の前に神棚へ小さな藁の灯篭舟を飾り、休暇をとって息子の剣と灯篭流しの旅に出る。灯篭舟を手にして亡きハル子が世話になった蔵元を訪ね、その地の川に流すのだが、もちろん回収も怠らなかった。
だが、今年は盆を迎えても神棚に藁の舟が見当たらなかった。
「……藁舟が届かなくなっちまってよ。毎年、酒樽の菰を解いて作ってくれてた老齢の蔵人さんが春に亡くなった。だから、今年はあきらめたよ」
太郎たちの灯篭流しは生前のハル子の意志を引き継ぎ、蔵元や蔵人を偲ぶことも含め、薦被りからこしらえた藁舟を使った。藁舟はハル子自身が昵懇にしていた蔵元の職人に、無理を承知で頼んでいた。
「そうか……菰樽は簡単に手に入らねえしなぁ」
悔しがる銀平は、菰さえあれば俺が作るとでも言いたげな口調だった。
「じゃあ、剣君も寂しがってますねぇ……何か、いい手立てはないもんでしょうか」
平が心配げに二階への階段を見つめた時、軽やかな足音が聞こえた。
上機嫌な気分が伝わる響きに続いて、剣の声が店内に弾けた。
「父ちゃん! どうだい! 僕が作った灯篭の舟!」
剣が手にする藁の塊に、テーブル席の客たちも瞳を凝らしていた。いびつな形ながら、しっかりと束ねられた藁に「ほう、うまいもんだ!」と感嘆が洩れた。
ジョージも「オウ! ナイス シップ!」と青い瞳を輝かせた。
「おっ、お前、いつの間に!?」
毎年流している藁舟とよく似た形に、太郎は思わず肴の器を落しかけた。平は老眼鏡を押し上げながら、奥の目を細めている。太郎譲りの剣の器用さが、藁舟の仕立てに読み取れた。
銀平が藁船に手を伸ばし、胴体に残っている酒の銘柄らしき墨残りに感心した。
「どうやって、この酒樽の菰を手に入れたんだ? バラしちまうにも、二斗ぐれえの樽酒を注文しなきゃいけねえだろ」
確かに、太郎の許しを得ずに樽酒を入手できるはずはなかった。
まじまじと藁舟を見つめる銀平の目が銘酒「蔵娘」の赤い落款に気づくと、剣が答えた。
「へへぇ、あすかさんからもらったんだよ。相馬の酒蔵は廃業したけど、実家の蔵には菰の在庫がまたいっぱい残ってるからってさ。父ちゃん、あすかさんは今年、うちの神棚に藁舟が飾ってないことを気づいたんだ」
剣は盆前になっても見えない藁舟のことをあすかに訊ねられ、頼んでいた蔵人の他界を伝えた。すると、あすかは「まかせといて!」と胸を叩き、その3日後に菰を包んだ荷物が剣に届いたのだった。
「あっ! 週初めに届いてた、あの荷物がそうか。この野郎、俺には夏休みの工作材料を小遣いで買っただとう? 誤魔化しやがったな」
拳を小さく振り上げた太郎だが、その表情は嬉しげだった。剣が藁舟で頭をかばうと、その胴体から紙切れが銀平の前にひらりと落ちた。
「な、なんでぇ、こりゃ。……けっ、あすかの奴、しょったことをしやがるぜ」
紙切れの筆字に目を細めた銀平が、太郎の前へそれを置いた。
剣 君へ
約束した菰を送ります。うちの蔵には、まだ数十枚あるから、これがなくなるまで私も毎年、相馬に帰省したお盆は藁舟を作って、灯篭を流すつもりです。
だから、剣君が大人になるまで藁船は大丈夫よ。
がんばって、剣君の手で舟を作ってみて。きっと天国のお母さんに、届くはずだから。
紙切れを横から覗いた平が、おもむろに鼻梁を赤くした。酒に酔ったせいではなかった。
太郎は剣の手から藁舟を取ると、ゆがんだ胴体や舳先を手直しながら言った。
「剣、今年の灯篭は、相馬の川に流そうか。この菰をあすかからもらったことに、母ちゃんもそうするはずだ」
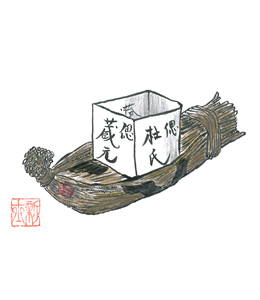
太郎の声に、銀平は目をつぶったまま頷いていた。
剣が、コクリと頷いた。
「僕もそうしようと思ってた。それにさ……」
「うん? それに何だよ?」
太郎が問い返すと、剣は神棚を見上げながら言葉を呑み込んだ。
太郎も、それ以上、訊き直さなかった。
平が二人の胸中を斟酌して、つぶやいた。
「そうなれば、あすかちゃんは太郎さんに、実家へ寄って欲しいでしょうねぇ……彼女には、ポンバル太郎は第二の我が家でしょうからねぇ」
珍しく言い切る平に、太郎の頬が紅潮した。
「今の言葉、ハルちゃんが平先生に言わせたんだろなぁ」
銀平が冷酒グラスを神棚へかざしながら、冷やかした。
藁舟の蔵娘の印形が、太郎のほころんだ目に揺れていた。
