カタカタとマチコの格子戸が開くたびに、「おめでとうございま~す」の挨拶がしきりに繰り返されている。
白い息を吐きながら暖簾をくぐる男たちの肩には、雪が積んでいた。お正月明けからの大寒波のせいで、東京は雪もよう。マチコの通りも、すっかり凍てつき、赤ちょうちんの肌はうっすらと雪化粧をしている。
客たちはおぼつかない足取りでやって来たが、きれいに髪を結い、しっとりとした加賀友禅の着物をまとった真知子に一瞬目を奪われ、ほっと表情をくつろがせた。
「ええなあ~。これぞ、日本女性やで。真っちゃんには、加賀友禅の上品な柄がよう似合うなあ」
鏡餅の置かれたカウンターでは、黒紋付をはおった津田がすでに頬を赤らめていた。その右側には新調した渋い色のスーツを着た松村が座り、津田の手にする盃に両手で酌をしている。
「プッ!2人とも何だか、おかしいわよ。時代遅れの親分、子分みたい。和也君、何をかしこまってんのよ」
真知子が、思わず2人のようすに吹き出した。
「そう言うけど……今日の津田さん、いつになく威厳があるっていうか、マジでそれっぽいんだもん。着流しならまだしも、紋付き袴に、この体格と鬚面はヤバイっすよ。ねえ、皆さん」
松村はそう言って、カウンターに座る客たちに愛想笑いをした。客たちが苦笑いする中、「あほ! カタギの善人つかまえて、何を言うか。和也君こそ、やさぐれたチンピラみたいなスーツや」と津田が冷やかした。
すると、今度は津田の右隣にいた澤井が「でも、この紋付、いい臭いがしますね。お香ですか?」と酌をした。
「おおっ!澤井ちゃん、嬉しいことを訊いてくれるやないか。着る前に、ちょっと炊いたんや。よっしゃ、何の匂いか当ててみいな! お年玉あげるでぇ」
燗酒に酔って上機嫌になってきた津田の声が、一段と大きくなった。
「えっ!えっ!お年玉!」松村が血相を変えて「え~と、え~と、白檀(びゃくだん)!」と叫んだが、津田は「残念、スカや。和也君アウト」と笑った。
澤井や宮部は「う~ん、分かんねえなぁ」と顔を見合わせ、よく見かける中年客が「伽羅(きゃら)」と答えたが、それもハズレだった。着物好きな真知子はその答えを分かっているらしく、黙ってほほ笑んでいた。
「うははは~、こらちょっと、難しすぎたかもしれんなあ」
真知子と目を合わせた津田がほくそえんでいると、カウンターの隅に座る新顔の青年が、遠慮気味に「あ、あの……ら、羅国(らこく)」とつぶやいた。
その瞬間、「あっ!」と真知子が目を丸めた。
津田は「ほう……当たったがな~。あんさん若いのに、ようご存知でんなあ」とほほえんだ。
「あっ、いえ……家で、お香売ってましたので」
そう答えるおとなしそうな青年は、客たちのまなざしに、いささか緊張した面持ちだった。
「その言葉。あんさん、京都のお人やろ?」
ニンマリと顔をほころばせる津田に続いて、「俺、彦根出身なんですよ」と酔った松村が口をはさんだ。
「そうですか。僕は下賀茂の生まれです。けど……今年からは、しばらく東京暮らしです」
青年はおだやかに答えながらも、一瞬表情を曇らせた。
それに気づいた真知子が「津田さん、お年玉はどうなったの?」と、話題を変えた。
「おっと、忘れてたわ。ところで……あんさん、お名前は?」
津田は、紋付の袂をまさぐりながら青年に近寄った。
青年は「船場と申します」と、今度ははっきりとした京言葉としなやかな物腰でおじぎをした。
「おっ……あんさん、日本舞踊もやってまんのか」
津田が見抜いたように言うと、船場は「えっ……はい、少しだけ」とポッと顔を赤らめた。
「おじぎする時の指先の合わせ方が、よろしいなあ」感心する津田だったが、「おおきに……あっ、ありがとうございます。でも、しばらくは舞えそうになくて……」と標準語に変えた船場の声は尻すぼみになった。
わけありを悟った津田は、「まあ、まずは」と袂からふくらんだお年玉袋を取り出した。
とその時、ひらりと一枚の紙切れが、紋付の袂からカウンターに舞い落ちた。
「あら?おみくじ。大吉じゃないの。津田さんらしいわねえ」と、真知子がその白い紙を手に取った。
「へっ?わし、おみくじなんか、ここ何年も買うてへんで?」
小首をかしげる津田に、おみくじを覗き込んだ宮部が「これ、ずいぶん昔のじゃないですか、昭和55年ですよ!?」と目を白黒させた。
「ふ~む、さよか。この紋付は長いこと着てないし、洗いにも出してなかったさかい、袂の底に隠れてたみたいやなあ」
不思議そうに袂を覗き込む津田、「へえ~」と目をみはる客たちをよそに、船場が愕然とした顔で立ちすくんでいた。
「船場さん、どうかしたの?」
ようすのおかしい船場に、松村が目の前で手をプラプラさせて言った。
「僕……そ、そ、その年の1月1日生まれです。それで……僕の名前は……大吉。船場大吉です」
「え!」と、津田や常連客たちが声を途切らせた。
「ってことは、船場…大吉さん? ぶっは! それって、京都人っていうよりもベタベタの大阪商人みたいじゃん、ね~皆さん。あっ、あれ?ウケない。俺、ハズしちゃった?」
一人はしゃぐ松村を、真知子が呆れ顔でたしなめた。
「あんた、ほんとに鈍感ね。船場さんの顔色見てたら、そんな冗談言えないわよ」
そして、今度は憂いを浮べる船場に、言葉をかけた。
「あの船場さん……立ち入るようだけど、胸の内にわだかまってること、打ち明けてみない? 新年なんだから、スッキリしましょうよ」
黙ってうつむく船場に、「わしも、聞きたいなあ」と津田が燗酒の徳利をそっと差し出した。
船場は、その酒をゆっくりと盃に受けた。しなやかな手の動きに、真知子や澤井は思わず見入った。
「去年の秋に、実家の香屋が廃業しまして……300年以上続いた家業やったんですが、年々厳しくなって、とうとう父の代で閉めることになりました」
船場の話によると、彼は物心ついた頃から香屋の後継ぎを自覚し、日本文化や芸事も嗜み、芸術系の大学を卒業した。しかし、家業に入って3年ほどで、こんなことになってしまった。唯一、この町にある小さな得意先が、先祖からの縁で自分を採用してくれたと訥々と語った。
「お香も、今は通販で買える時代ですし……外国産の安い製品もあるんです。けど……悔しいんですわ。ちっちゃい店でも本物の伝統を守ってきた自負が、代々ありましたよって」
船場の声が京言葉に戻ってしまうと、カウンターはしんと静まった。
津田が盃をくいっと飲み干し、口を開いた。
「大吉はん……あえて、そう呼ばせてもらうわな。あきらめんでもええ。あんさんは、まだ25歳。なんぼでも復活でける。これからは、ほんまもんの日本文化を求める人が、もっとぎょうさん出てくる。そやから、今は辛抱や。その日のために、いろんな仕事して、自分を磨いたらええのや」
それを聞きながら澤井や宮部はうんうんと頷き、「東京暮らしも慣れれば“都”だよ。特にこの町と、このマチコはね!」と親指を立てた。
「皆さん……何て言うか、ほんとにありがとうございます。あの、どうしてそないに……僕のことを」
上気した顔で、船場が言った。
真知子が、大吉のおみくじを折りたたみながら、船場に渡した。
「このおみくじは、今日、あなたが引いたんだと思うの……あなたが東京へ来たこと。そして、今日マチコへ来たことは、偶然じゃなくて必然だった。そんなふうに思えないかしら。だって、こんなステキな出会いなんて人生の中に、そうそうありゃしない。そう思わない?」
船場は震える手でおみくじを受け取りながら、津田の顔を見た。
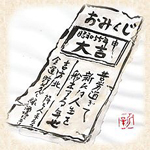 「これからは、ちょくちょく、ここへおいで。マチコのみんなと飲んでたら、きっといつか、あんさんの夢は叶うと思う。それにな、わしは大阪の船場で生まれた男や」
「これからは、ちょくちょく、ここへおいで。マチコのみんなと飲んでたら、きっといつか、あんさんの夢は叶うと思う。それにな、わしは大阪の船場で生まれた男や」
津田からの二杯目の酌を受けた船場は、目頭を光らせながら笑顔で返杯をした。
「ほんと、人間って、摩訶不思議だよねえ~」
松村が、調子よさげに声を上げた。
「でも、あんたはまったく、単純明快だもんね~」
真知子が突っ込むと、店内は、船場と常連客たちの温かい笑い声に満ちあふれていた。
