くつくつと、マチコの厨房から鍋を煮込む音が聞こえている。
窓から洩れる白い湯気は通りにほんわりと漂ったかと思うと、秋の夜風にとけこんでいた。
そのほのかな匂いに、通りを歩いて来る男たちは口々に「おっ、おでんか」と目尻をゆるめては、マチコの暖簾をくぐった。今夜はカウンター席もテーブル席も、ほぼ満員になっている。
「毎年のことながら、この季節、真っちゃんのおでんは大人気やな」
津田がお燗酒を手酌しながら、我がことのように目を細めてつぶやいた。
その横で、ダシのしみた大根を頬張り、思わず「アチチッ」と冷酒を口に流し込む松村が、ウンウンと頷いた。
「ダシの味がイイんだよ。真知子さん、野田の生醤油使ってんだろ?」
黄色い和辛子を箸でゴボウ天につけながら、澤井が訊ねた。
「ええ、ベースはね。ちょっと甘辛くって濃いお醤油よ。関西人の津田さんには、合わなくない?」
ネタ切れになりそうな大根の皮を剥きながら、真知子が言った。
「関西は薄口醤油の文化やちゅうても、“郷に入らば郷に従え”や。江戸に来たら、江戸の味を楽しむべきや。いろんな土地の味と酒を楽しむのが、ほんまもんの食ツウとちゃうか」
津田はおでんの皿を持ち上げ、ダシをすすりながら「あ~、おいし」と付け足した。
「でも、たまにいますよね。『こんな濃い味、食えるかいな』って関西人や、『こんな薄味なんてダメだ!』って、咆える関東人」と松村が言いかけた時、テーブル席で罵声が起こった。
「なんじゃい、これ! めっちゃ、辛いやんけ。こんなドン辛い味のおでん、食えるか!」
「あっ……」と松村は口を開けたまま、その方向へゆっくりと振り向いた。
奥まったテーブルに、白髪の着物姿の老人とやさぐれた風貌の五分刈り頭の男が座っていた。賑やかな店内が、一瞬にして水を撒いたように静まった。
老人は黙って目を瞑ったままタバコをふかし、若い方は眉を逆立て、厨房の真知子を睨みつけていた。
一見、古いヤクザ映画の親分子分のような二人組を、周囲の客たちは内心で嘲笑いながらも、いざこざを起こさないように目をそらしていた。
「チッ、やっぱりそういう連中か」と舌を打つ澤井に、「入って来た時から、そんな予感がしてたよ」と、宮部が顔を見合わせた。
「あんな奴ら、いつの間にいたの? まったく、たまんねえなあ」
松村は口を尖らせて、若い男を睨み返した。
「こら、聞いてるか? オバハン。ワシら、こんなもん食われへんちゅうてんねや。いったい、どないしてくれんねん!」
五分刈り男はおでんの皿を手にすると、周囲の客へこれ見よがしに声を荒立てた。
「おっ、オバハンだと!? 我らが真知子さんに向かって、そりゃ聞き捨てならねえぜ」
肩を怒らせた澤井が、冷酒グラスの酒を一気に飲み干し、椅子から腰を上げた。それを見ていた宮部も「ふぅ」と呼吸して、立ち上がろうとした。
と同時に、奥のテーブルを凝視していた津田は「まあまあ、ちょっと待ち」と澤井の肩をポンポンと叩き、席に戻らせた。
そして津田は、顔を曇らせたままの真知子に「あれは、大阪の田舎者や」とウインクして、徳利を手に二人組のテーブルへと向かった。
津田が近づいて行くと、周りの客たちは「おっ、お、お」と目を丸め、固唾を飲んで見つめた。
ニコニコと軽く会釈してやって来た津田に、若い男は「な、なんじゃい、オッサン。あんた、店の者か?」
と一瞬怯んだように声を詰まらせた。
「へっ……あいつ、津田さんにビビッってやんの」
そのようすを見ていた松村がこぼすと、心配顔の真知子が「バカッ、黙ってなさいよ」と頭を叩いた。
津田は、若い男の言い草を「まあ、そんなような者ですわ」といなし、胸を反らせてタバコをくゆらせている老人に「お久しぶりですな、恩田はん。一杯、どうでっか」と徳利を差し出した。
唐突に聞いた大阪弁に、若い男は「おっ、オッサン、大阪人か?」と戸惑いを見せ、恩田という老人は「むっ!?」と片目を開いて、津田を見返した。
途端に恩田は相好を崩し、「お、おーお、これはこれは! 津田さんやないか。奇遇やなあ。まさか東京のこんな場末で逢うとは、思わなんだ。おいヤス、もうええから静かにせえ!」
いきなり怒鳴りつける恩田に、ヤスと呼ばれた男は顔を真っ青にした。
重苦しい雰囲気をかもしていた恩田の印象は一変し、無理やりとも思える愛想笑いを振りまいて、津田の酌を受け始めた。
「けっ、場末だけは余計だよ! それにしても、いったい、何がどうなってんだよ?」
澤井がつぶやくと、「俺、聴いてこよ」と松村が立ち上がった。
「じゃあ、これを持ってって」と真知子はお燗した徳利を2本、松村に渡した。
松村がテーブル席に酒を持って行くと「おっ、ええタイミングやな。恩田はん。熱いのをグッといきまひょ」と、津田は老人に酌をした。
旧懐を温める津田と恩田の会話から、松村は恩田も大阪のミナミで割烹を営む亭主であり、東京の新しい日本料理店の見学に板前のヤスを連れて来ていることを知った。
しかし、二人の会話はどこかぎこちなく、特に恩田は津田に敵愾心を持っているかのような嫌味な雰囲気を発していた。それに、ヤスのような粗悪な板前を抱えている恩田の店が、どんな料理や酒を出しているのかと、松村は心の中で首を捻っていた。
そのままテーブル席に座ろうとする松村に、ヤスは「おい!? ワレは何をしてんねん。あっち、行っとけや」と凄んだ。
しかし松村は、「俺は、津田のおやっさんの舎弟じゃ! ここにおって、何が悪いねん」と彦根訛りの大阪弁をぶつけた。
ギョッとするヤスの前で、恩田が「おっ、あんさんも関西でっか。ほんなら分かりますやろ、このおでんの味は、私らの好みとちゃいまんな?」と松村へ確かめるように言った。
「……そうかもしれませんけど、俺はもう東京に出てきて長いですし、そんなに味の濃い、薄いにこだわっちゃいません。それに、マチコの味は、どんな人でも自然と好みになってくるんです」
松村が、恩田を否定するように答えた。
「津田さん……あんたの身内がそんなことを言うとは、嘆かわしいですなあ。それに、まさかこんな店をあんたが気に入ってるなんて。“ともしび”の看板が泣きまっせ。まあ、この程度の店に入った私もアホでしたけどな。おい、ヤス!ぼちぼち失礼しよやないか」
恩田は盃を飲み干すと、すっと立ち上がり、勝ち誇ったように津田を見下した。そして、ヤスに向かって顎を振り「行くで!」と命じた。
津田は、出て行く恩田の背中に向かって「まあ、お互いに自分の好みがありますさかいな。ところで、ああいう板前が、恩田はんのお好みでっか?」とやり返した。
恩田はふと立ち止まると、「私には、忠実な男や」と言い置き、「ツリはいらんで」と勘定をする真知子に札を渡して出て行った。
店の客たちは「へん、何だ偉そうに」とか「おととい、来やがれ」、「塩を撒いとけ、塩!」と口々に叫んだ。「ちっくしょう。……津田さん、俺、悔しいっすよ。あんなヤツ、言いたい放題にさせて」
松村が、ドンッとテーブルを叩いた。その後ろに、澤井や宮部も、何か津田に言いたげな顔で立っていた。
「あれは、マチコにはふさわしいない客や。せやから、上手に出てってもろうたんや。真っちゃん……ワシと澤井ちゃんと和也君の、3人のおでんの皿を持っといで」
津田は、澤井たちもテーブル席に手招いた。そこへ真知子が、言われたままに3つの皿を運んだ。客たちも津田のいるテーブルをじっと見つめていた。
「この3つの皿のダシ、舐めてみぃ」と言って、津田は新しい箸を松村に渡した。
松村は気だるそうに、割り箸の先をダシに浸した。
一番目の自分のダシには、何も反応もしなかったが、次の澤井のダシは「おっ、これ辛い」と気づき、最後の津田のダシでは「えっ、薄いよ……」と声を上げた。
「たぶん……このおでんのダシ味が微妙にちがうのは、真っちゃんがわしらに出す寸前に、厨房の中で、ちょっと味の工夫をしてくれてんねや。もちろん、ほかのお客さんらも同じやろ。それぞれのお客さんごとに味の好みや出身地を覚えとって、ちょっとずつダシ加減を変えてるわ……すまんなあ、真っちゃん! タネ明かしてもうたわ」
津田の言葉に、客たちは「ふへ~、すごいね」とか「え! じゃあ、俺のは州人向けだぜ」などと、お互いにダシを取り替えていた。
「さすが津田さんね……すっかりお見通しだもん、ビックリ」
真知子の笑顔に、気づいてくれたことへの嬉しさが覗いていた。
津田がタバコに火を点けて、深く吸い込んだ。
ダシを舐めながら、宮部がしみじみと言った。
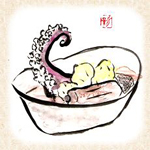 「……真知子さんのおでんは、魔法のおでんだね。俺たち、まったく気づいてないなんて、恥ずかしいよ」
「……真知子さんのおでんは、魔法のおでんだね。俺たち、まったく気づいてないなんて、恥ずかしいよ」
「ええ魔法ちゅうのは、魔法らしゅうないとこがええねん……ゆっくりと、じんわりと効いてくるもんや。その秘訣はな、“愛情”ちゅうもんや」
津田の優しげな視線が、松村たちだけでなく、全員の客を誘った。その先に、真知子が照れくさそうな顔で、おでん鍋を煮込んでいた。
